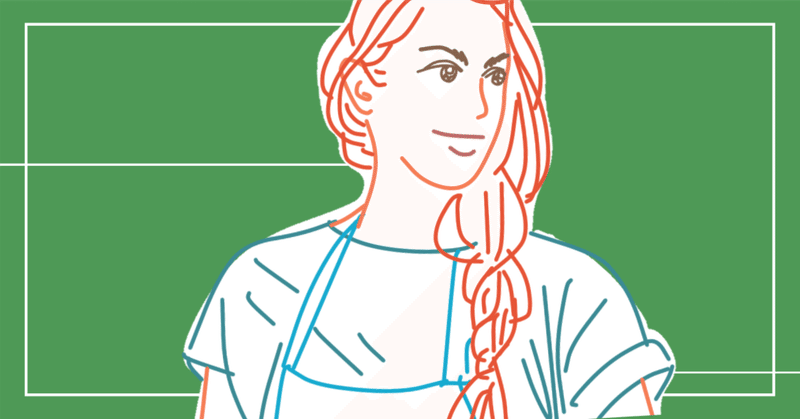
片付け屋 捨子
第1章
私の名前は、片付け屋 捨子
「片付け屋」は職業で会社名。
「社長さんが、『捨子』さんだなんて面白いですね!」
とお客様にいつも言われ、笑ってやり過ごすが、これは本名だ。
そして、社長をしている。
なぜ、こんな名前になったかは、おいおいお話しする。
会社は前社長から引き継ぎ、私の代になって2年が過ぎた。
「片付け屋」とは言わば廃品回収屋だ。
まぁ、言わば現代の「何でも屋」ところだろうか…
「片付け屋」と言う職業柄、お客様の見せたくないプライベートな所まで拝見したり、お伺いしなければならない事が多く、仕事を受けるかどうかを含め必ず下見に伺いし、直接お話を聞いてから、社長である私が判断させて頂いている。
捨てて終わり、という仕事ではない。
もう、20年近くこの仕事をしてきたが、「もの」というものは奥が深い。
その人が選び、購入し、長い年月共に過ごしてきただけに簡単ではないのだ。
私は、出来るだけその人の気持ちに寄り添うように、お手伝いさせていただきたいと思っている。
まぁ、そうは言っても色々なお客様がいるので一長一短、簡単ではないのが現状だ…
現場はさまざまで、「何でも屋」でもあることから、ワンちゃんの散歩から、孤独死されたお宅の清掃まで、多岐にわたる。
封印された想い 鍵
今回の現場は、2回目の訪問、87歳になる「徳田様」のお宅だ。
前回に引き続き、誰も使わなくなった2階和室の不用品出しと処分、併せて庭木の手入れだ。
それと••••••
今日の現場スタッフは、前回と同じく、私と20歳で働き者のマコちゃん、マコちゃんの同棲中の彼氏ヤス君の3人。
後でトラック隊が回収に来る予定だ。
マコちゃんとヤス君は会社の寮であるアパートでふたり暮らししている。
ヤス君は、マコちゃんが逆ナンしてうちの会社の引っ張り込んできたのだ。
マコちゃんの見立てはいつも正しく、ヤス君はマコちゃんに増して働きものだ。
マコちゃんの教育の賜物だとは思うけれど……
ちなみに私も入社以来そのアパート暮らしだ。
私はひとり暮らしだが……
徳田様宅への最初の訪問はひと月前、訪問介護の会社よりご紹介いただき、訪問見積もりにお伺いした時が、初めてだった。
徳田さんは脚が悪くなり、外出することが極端に少なくなったそうだが、来客がある日は、髪を小振りな髪飾りでまとめ、紅も差し小綺麗にするよう心掛けているそうだ。
初訪問の時、「お綺麗ですね」とお声かけさせていただいた際に照れながら、教えてくれた。
ご高齢ではあるけれど、品があり、少しチャーミングなところが可愛らしい。
私は、徳田さんの半分くらいの歳だが、化粧など、ほとんどしない。
そのことを徳田さんに話すと、「お綺麗なのに、勿体無いわ。」と真っ赤な高級ブランドの口紅をくれた。
脚が悪くなってからは、外出や掃除もままならないそうだ。
ご自宅は、かなり大きい日本家屋で、一人暮らし。
訪問介護に週2回来てもらって、買い物と掃除をしてもらっている。
しかし、掃除は1階だけで2階には誰も入れてないらしい。
ご自身も階段を登れなくなって、もう何年も2階にあがっていないそうだ。
終活をしたいと思っていたが、2階の整理に踏ん切りがつかずにいた。
女性の「片付け屋」がいると聞き、それならばと、当社に連絡が入ったという訳だ。
2階には和室が3部屋と、奥に洋室があるそうだが、「鍵」を無くしてしまい
そこへは入れないでいるということだった。
初回である1回目のガラ出しは、和室3部屋の家具以外のもの全てを廃棄するというご依頼だった。
和室にある机や棚は、亡くなったご主人が3人の御子様のために誂えたもので、御子様が使うかも知れないから
残しておきたいというご意向だった。
初回の作業は、布団類、本類、小物類の廃棄だけだったので、半日で終了することが出来た。
徳田さんは、ヤス君のことをひどく気に入っていて、
「一番下の息子にどことなく似ている」と、何度も涙を流したり、握手をしたりしていた。
ヤス君も明るく人懐っこいものだから、徳田さんの背中を摩り慰めていた。
ヤス君は色々なお客さんによく可愛がられる。
休みの日に、ふら〜っとご飯を食べにいくお宅が数件あるくらいだ。
(この事をマコちゃんは、よく思っていない…)
徳田さんから連絡があったのは、初回作業から10日後のことだ。
「あのね、捨子ちゃん、子供達に聞いたらね、机やなんかはもういらないって…
ごめんなさいね、もう一度来て2階を全部綺麗にしてもらえないかしら……」
「えっ、全部ですか?わかりました…… 」
「あの〜、徳田さん、奥の洋室はどうしましようか……ご主人様の書斎、鍵がないとおっしゃっていましたよね。……鍵がないと、鍵屋さんを呼んだりしなきゃなのですが……」
徳田さんは奥の洋室の話をしたがらない。
鍵をなくして入れないとだけ聞いていた。
なんとなく聞きにくかったが、奥の洋室をやるとやらないとでは、トラックや人数の見積り、鍵屋さんの手配等があるので、聞かざる得なかった。
少しドキドキしながら聞いた。
「ご主人様の書斎のものも、全部処分されるのですか?」
封印された想い 書斎
私とマコちゃんとヤス君は「徳田様」の2度目の作業のため、お屋敷の前にスタンバイしていた。
身なりチェックを行いインターフォンを鳴らす。
「キンコーン♪」
「はーい、開いていますよ」
徳田さんのか弱い声がした。なんだか嬉しそうでもあった。
「失礼しまーす」
廃棄用ビニール200枚・ダンボール100枚・掃除道具・庭木剪定のための道具と脚立などなど、大量に持ち込み玄関脇に置いた。
玄関を開けると、ぷーんといい匂いがした。
「まぁまぁ、いらっしゃい」
台所からゆっくりとした足取りで、徳田さんが出迎えてくれた。
「いい匂いっすね!カレーすか?」とヤス君が言うと
「もー!ヤス君!!」とマコちゃんに叱られた。
笑顔の徳田さんの頬が、赤らんだ。
「この前、ほら、カレーが好きって言ってたから……」
「ヘルパーさんにお願いして、材料を買ってきてもらったのよ……」
徳田さんは少し歯に噛んでそう言った。
ヤス君はいつの間に徳田さんとそんな話をしていたのか……
「味はどうかわからないけどね」
「もう何年も作っていないから……」
「ありがとうございます。では、遠慮なくお昼にいただきます!」
と、私がこの場を〆た。
「さぁ、やるよ!」
「はーい」
「では徳田様、本日は2階のお品物を全て搬出させていただき、その全て物を処分する、という事で間違いはございませんか?間違いがなければ、こちらにサインを……」
「はい、お願いします。」
迷いのない口調で徳田さんは答え、サインをした。
早速、ヤス君は庭木の剪定へ向かいマコちゃんは2階へ、一人で上がった。
2階には、前回残したお子様3人分の学習机と本棚が残っている。
当時の職人さんに 作ってもらった年代物で、私から見ても、捨てるには惜しいくらいのものだったが現代の住宅事情には、そぐわない代物だった。
マコちゃんがこれらを解体している間に、奥の洋室のことについて、徳田さんと話さなければいけなかった。
奥の洋室は鍵を無くしてしまい「もう何年も入れていない」と奥田さんは以前言っていた。
「……洋室の鍵、見つかったんですね……」
そう尋ねると、少しバツが悪そうに首を振り、
「本当は、無くしてなんかなかったの……」
私は少し驚いたが、それを抑えて
「そうだったんですね……」と答えた。
「私は足が悪くなって上へもう上がれないでしょ……本当は元気なうちに自分で片付けようと思っていたの。でも、入ることが出来なかったのよ……」
「?! なぜ?」と聞きたい気持ちを飲み込み話を続けてもらった。
徳田さんは、小さなため息をつき、
「怖かったの。怖かったのよ……今でも怖いの。こんなおばあちゃんになっても、怖いの……おかしいでしょ……」
徳田さんは80代後半になられるが、いつも小綺麗にされていて、来客時にはお化粧もされる。大きなお屋敷に住んでいて、寂しさはあるだろうけれど、何不自由なく暮らしているかのように思っていた。
徳田さんが話を続けた。
「奥の部屋は、主人の書斎だったの。普段から鍵をかけていて、本人以外は誰も入れないようにしていたわ。」
「家で仕事をすることも多かったのよ、大学の研究なんかをまとめる、とかいって
よく書斎に篭っていたわ……」
「主人が亡くなって、 ほら突然だったでしょ、だから、あっ、主人は大学に行っている時に倒れて死んじゃったんだけど……その時も、死ぬほど怖かったわ、フフッ私は生きてるんだけどね……」
自分の言っていることがおかしくて少し笑った徳田さんに、愛想笑いを返した。
封印された想い 日記
徳田さんは話を続けた。
「お葬式やら色々忙しくてね、書斎のことやら、鍵のことやら忘れていたのよ。」
「少し落ち着いた頃、大学から主人のものだという大量の段ボールが届いたの。」
「私それをどうしていいか、わからなくて……息子たちに聞いてみたんだけど、誰もいらないっていうの、捨てろって……」
「それでね、もう本当に沢山のダンボールだったもので、どうしたら良いか、途方に暮れていたの。」
「ある時ね、これは主人のものだから、主人の書斎に入れたほうがいいって考えたの!」
「でも、鍵がないのよ……」
私は不思議そうに相槌を、2回打った。
「それから、ずっと探していてね、あの人用心深い人だったから、持ち歩いてたんじゃなくて家のどこか、秘密の場所に置いているんじゃないかって……」
「そう思ったら、はっ!って気が付いたの」
「主人は外から帰って来たら1階の寝室に洋ダンスがあるんだけど、必ずそこの前で着替えるのよ。」
「それから鞄を持って2階へ上がるの。必ずよ、毎日そうだったの。」
少し興奮気味に話す徳田さんに話を、前のめりで聞いた。
「私思ったの。鍵は、洋服ダンスだって!」
「ずっと奥の方に隠しているんだろうと思って奥から探していたんだけど、なくて……探し疲れて、ふっと、ネクタイピンを置く小さい物入れがあるんだけど、そこを見たら……入ってたの、そこに、鍵が……」
「笑っちゃうわよね」
止めていた息が、一気に抜けた……
「それで、どうしたんですか?」たまらず、私は聞いた。
徳田さんは、暗い表情になり
「その鍵を使って、怖かったけど、初めて入ったの、主人の部屋に……
亡くなってからもう、半年くらい過ぎてたわ」
「鍵を開けて、扉を開いたら…………」
「主人の匂いがしたのよ……………」
「半年よ、半年も経つのに……匂いがしたのよ………………」
「もう本当に………私を残して………死んじゃって…………」
徳田さんは、呼吸を整え涙を拭った後、続きを話し出してくれた。
「部屋の中は、きちんと整理されてたわ。あの人らしい……」
「壁中本棚でね、私にはよく分からない、ほら、専門の本なんかが並んでいたわ。」
「その中にね、19何年とか書いた、本みたいなものがずらーっと並んでいたの……」
「日記だったのよそれ……」
「何十冊もあったわ。」
「その中の私達が結婚した年のを見つけたの。悪いことをしている気がして、少し気が引けたんだけど……開いてみたの。」
「あの人、あまり色々話す人じゃなかったのよ。『寡黙』っていうのかしら、そんな感じの人でね……」
「日記を開くときは、どきどきしたわ!もう死んでいない主人に『ごめんなさい』って言っちゃったわよ!」
少し笑顔になった徳田さんに、相槌を打つ。
封印された想い 匂いの秘密
亡くなったご主人の日記に、何が書かれていたのか……
私も一緒に、悪いことをしている気になったが、中身を知りたくて仕方がない、それを抑えきれなかった。
徳田さんの顔が、また少し曇った。
「毎日、びっしり書いていたわ、大学の研究のこととか、家での些細なこととか……お見合いの日に何を食べたか、まで書いていたのよ。」
「そう毎日、食べたものを書いていたの……日記の下の方に、細かく書いてたの……」
「私、料理上手くないのよ。でも、何にも言わずに食べていたわ。」
「子供たちがうちに来ないのは、私の料理が上手くないせいなのよ……」
「そんなこと……」と徳田さんを宥めた。
「主人にはね、毎日、お弁当を持たせていたの。何も言わないから、普通に食べているって思っていたんだけど……」
「あの人のお昼ご飯のところには、私の作ったお弁当じゃない食べ物の名前が書いていたのよ!」
「えっ!」私はかなり驚いた。
立派な家に住み、立派なご職業でいらしたご主人にどんな秘密があったのだろう……
息を呑んだ。
徳田さんは、唇を震わせ、
「でもね、私がわからないように、英語で書いているのよ。だから全く読めないの。住所らしきものは書いていたけど、それも英語だから読めない。もちろんお店の名前もね。」
「外食なんかは、ほとんどなかったから、私なんかは365日ずーっとご飯を作って来たのよ。」
「それなのに、お弁当は食べずに、自分は誰かと毎日、外食していたなんて……」
「お弁当は捨てていたのかしらね。それなら、いらないと言ってくれればよかったのに……」
「その方がよっぽど、よかったわ……こんなに……苦しまなくて……よかったんだから……」
「もう……あの人死んじゃって……もう聞けない……何でこんな……聞けないじゃないの……私は、どうしたら良いの……」
徳田さんの顔は怒りに震え、高揚していたが、次の瞬間には、涙に濡れていた。
ふうーっとため息をつき
「もうそれ以来、怖くて入れないの。ずっと……狭い部屋なんだけど、大学から届いたダンボールをそこに、ぎゅうぎゅうに入れてしまったら、もう二度と入れなくなる。」
「日記も見ないで済むから、知り合いに頼んで、あの部屋に全部入れてもらったの。」
「ドアを開けたら、入り口までダンボールが山積みで、捨子ちゃんたち、驚くんじゃないかしら!」
徳田さんは肩をすくめて悲しそうにほくそ笑んだ。
洋室の鍵を受け取ることができたのは、その後だ。
「おしゃべりがすぎましたね、ごめんなさい。捨子ちゃん、どうぞ、よろしくお願いしますね。」
っと私の手を握り、深々と頭を下げ、鍵を手渡してくれたのだ。
鍵を受け取りながら、
「このことを、誰かに知っていて欲しかったんだな……」
と思った。
秘密の扉
私は2階への階段を上がっている。
手には預かった洋室の鍵がある。
握りしめていたものだから、金属があたたまっていた。
2階の和室では、マコちゃんがもうほとんど机や棚など、解体していた。
流石だ。
私はこのマコちゃんの支え無くして今はない、そう心から思っている。
そのことを、酔った時にしか言えないからいつも
「シラフの時に聞きた〜い」とマコちゃんには言われる。
でも、紛れもなく真実だ。
マコちゃんが解体してくれたものをまとめ搬出しやすく毛布に包む。
室内を傷つけないためと、廃棄の後悔を軽減させるためだと前社長から教わった。
今もその教えを守っている。
毛布でまとめたものが山になってきた頃、庭木の剪定を終えたヤス君が2階へ上がってきた。
「良い匂いっすよ!もう腹へった」徳田さんが作ってくれてカレーの話である。
すかさずマコちゃんからの鋭い視線がヤス君に突き刺さり、ヤス君はおしゃべりをやめた。
「さっさと1階へ運びなさいよ」
マコ先輩の厳しいお言葉で、2階へ上がってきたばかりのヤス君は「ご苦労様」の一言も言われることなく解体したものを抱え、1階へと下がっていた。
その合間合間に、うちの裏の実権者であるマコちゃんがタブレットで作業工程をパシャパシャと撮影する。
もちろん、2階へ上がってこれない徳田様に見せるためのものだが、どの現場でも行っていることだ。
和室の机や棚の解体と毛布梱包が終わり、3人で1階へと運び出しが済んだ。
その報告を徳田さんに行った。
奥の洋室に取り掛かる。
何年も締め切った部屋に入るので、簡易的ではあるが防護服に防護メガネ高機能マスクという姿で右手に鍵を持ち、洋室のドアの前に立った。
1階へとつながる階段付近にもビニールシートで目張りをし、1階への埃やカビの侵入に備えた。
鍵を開ける。
「カチャ」
思いの外、スムーズに開いた。
ドキドキしながら引き戸を開けた。
開けた途端、そこには段ボールの壁があった。
徳田さんが言っていた、大学から送られてきた段ボールの山が、目の高さほどに積み上がっていた。
カーテンは閉められていたが、部屋の奥にある窓から光が差し込み、埃が光を受けてキラキラ舞っていた。
徳田さんの心に大きく重石のように覆いかぶさっていたのは、これなんだ……
3人は無言のままご主人様に手を合わせた。
「ん?」何かの匂いがする…
窓から吹き込む風
洋室は想像通り、段ボールで埋め尽くされ一歩も中には入る事ができない状況だ。
そして、時が止まったその部屋は息を吹き返した。
「シュッシュ」「ブォーン」
マコちゃんが軽く霧吹きをした後、業務用大型掃除機で積もった埃を吸い取る。
私が広げたビニール袋にヤス君が、なるべくそーっと段ボールを入れる。
その後、私がビニール袋の口を閉じる。
この一連の作業を、段ボールひとつひとつに行う。
ざっと、20〜30個の段ボールだ。ダンボールは、かなり重い。
大学の教授をされていたということなので、重めの書籍などが入っているのだろう…貴重なものが入っているかもしれないが、いっさい開封せず、そのまま廃棄させていただく。
床が見えてきた。
「床が腐っているかもしれない」と徳田さんは心配していたが、足で踏んでみる限り、それは無いようだ。
思っていたよりカビ臭さは少ないように感じる。
カーテンは閉まっていたが西日が差し込むため、それなりの乾燥状態を保ていあのかもしれない…と思った。
段ボールの壁がなくなり、部屋全体が見えてきた。
すかさずマコちゃんが、窓を開けて良いかとジェスチャーで聞いてきた。
さほど暑い日ではなかったが、この格好(防護服に防護メガネ高機能マスク)では蒸し風呂状態だ。
指で「OK」サインを出し、マコちゃんはつま先立ちで窓辺に行き
掃除機である程度の埃を吸った後、窓を開けた。
何年振りなのだろう…
この部屋が風を感じるのは……
マコちゃんの霧吹きのおかげで、さほど埃が舞うことはなかったが、それでもキラキラ、ふわふわなんだか幻想的だった。
その後も、マコちゃんの霧吹きと掃除機は続き、ずいぶん綺麗になった。もちろんその前後の撮影も忘れない。本当にしっかり者だ。
一旦、ビニールに入れた段ボールを2階の窓から1階へ下ろす作業に取り掛かる。
ビニールに入ったダンボールを毛布で包んだ後、紐で結び、窓に引っ掛けたハシゴから滑れせて下ろす。
ヤス君はもう、防護服を2階で脱いだ後、1階に降りて窓の下で段ボールを受け取る準備を済ませていてくれた。
幸いなことに段ボールがそんなに大きくなかったので、中々重いがなんとかやれそうだ。
段ボールを抱えて階段から下ろすことも考えたが、ビニールで包んだとは言え埃を1階へ持ち込む可能性があるということと、徳田さんが「あまり見たくないんじゃないか」とマコちゃんが言ってくれたのことで、このような作業に決まった。
2階での作業があまりに辛く、私はマコちゃんを心配して居たのだが、
「社長、ヤス君と代わってください」
とマコちゃんにサラッと言われてしまった。
マコちゃんはエスパーなのかもしれない。
私もその方が効率がいいと思ったので、その様にさせてもらった。
その後の作業は順調し進み、30個近くのダンボールを下ろし終わる頃に丁度12時になっていた。
カレー
お昼の時間になった。
丁寧に手や顔を洗わさせてもらい、食卓へ向かった。
いい匂いだ。
お腹の音が鳴らぬよう気をつけながら、準備を手伝った。
今日はこのために朝からヘルパーさんが来てくれいていた。
食卓には花が飾ってあり、ランチョンマットの上には、スプーンとフォークが行儀よく並んでいた。
グラスにはすでに水が注いていて、早速ヤス君は飲み干していた。
洋食屋さんで見る「楕円形」のカレー皿に上品にカレーライスがよそっている。人参もジャガイモも一口で食べられそうな大きさにカットしている。うちにカレーとは大違いだ。
他にもサラダとオニオンスープと唐揚げではない鶏料理が用意してあった。
「すげー、すげーこんなご馳走、初めてだ」とヤス君が大喜びするものだから、徳田さんは嬉しそうに微笑み、マコちゃんはイライラが増していった。
準備が整って、いただきますをしようと思ったら
「今日は前回に引き続き、ありがとう。捨子ちゃん、マコちゃんヤス君、本当にありがとう、助けてくれてありがとう…」
徳田さんのお話が始まったので、「待て」状態のヤス君が面白すぎたのだが、私たち3人とヘルパーさんは静かに聞いた。
「私にね、こんな大きな決断ができると思っていなかったの。みんなのお陰。これで私、いつお迎えが来てもいいわ。主人に叱られるかもしれないけれど、いいの。先に勝手に死んじゃうあの人が悪いんだから…私にこんな思いをさせて……」
ヘルパーさんが涙ぐみながら徳田さんの背中をさするのを見て、徳田さんが良い方々に支えられているような気がして、少しホッとした。
腹ペコのヤス君も涙ぐんでいて、ティッシュを徳田さんに差し出していた。
こういう所が彼の彼たる所以なんだなーと少し微笑ましく思った。
早速にカレーをいただく。
徳田さんは本当に嬉しそうだった。
マコちゃんが料理のことをあれこれ聞いていた。
「このカレー、すごい美味しい。どこのルーですか?」
「この鶏肉、初めて食べる味!」
「サラダのドレッシング、これなんですか?」すごい質問の応酬だ。
多分ヤス君の「美味しい」を言わせない為じゃないか…と心の奥で推察した。
徳田さんが驚くことを言った。
「ごめんなさいね、私が作ったんじゃないのよ。」
「私、カレー作れないの。」
「えーーーっ」
「いや、料理は上手じゃないけど作ることはできるのよ。今でも自分の分は作るの。でもカレーとかタンドリーチキンとかそういうのは作ったことがないのよ」
この鶏料理は「タンドリーチキン」ということが初めてわかった、が、それが何かは分からなかった。
「だから、ヘルパーさんに教えてもらったのよ、作り方を。でもね、一人では難しかったのね。だから昨日から来てもらって、作ってもらったのよ。」
「徳田さんも作ったじゃないですか!」とヘルパーさんが言った。優しい言葉だ。
マコちゃんがあまりに驚いた様子で
「カレー作ったことないんですか?」「徳田さんのころにはなかったの?」
と聞いた後に「あっ、なかったんですか?」と敬語で聞き直していた。
徳田さんは笑って「いいのよマコちゃん、気軽に話してもらう方が嬉しいわ。」
「カレーはね、ルーっていうの?あれ子供を育ててる頃に売ってたわ!」
「でも、私は買ったことないの。」
「うちはね、主人が日曜日に作ってくれるものだから、カレーをね、だから私は一度も作ったことがないのよ。」
「えっーーー」
「スッゲー優しい旦那さんすね。俺なんかカップラーメンしか作れないよ、なぁ!」っとヤス君がマコちゃんに言葉を振ったが、これは地雷だった。
その後、2分くらいマコちゃんのヤス君ダメダメ話と、徳田さんから聞かれた得意料理の話が続いた。
「ご主人様が作ってくれるなんて、素敵ですね。どんなカレーだったんですか?」
と私は徳田さんに聞いてみた。
すると、徳田さんは涙ぐみ、代わりにヘルパーさんが教えてくれた。
ヘルパーさんの話によると、ルーで作るカレーではなくスパイスを調合して作る本格的なインドカレーだったそう。
旦那さんは、カレー作りが趣味だったということだ。
想像もつかない。
本格的なインドカレー……
どうやって作るんだろう……
現代っ子のマコちゃんが直様スマホで調べてくれた。
「クミン・コリアンダー・カルダモン・ターメリック・ガラムマサラ・カイエンペッパーなど、数種類のスパイスをスパイスグランダーを使って押し回してすりつぶし、ダール:豆のカレー・パラックパニール:ほうれん草とチーズのカレー・バターチキン:乳製品で仕上げた濃厚なチキンカレー・ポークビンダルー:マリネした豚肉のカレー・フィッシュカレー:魚を使ったカレーなど種類も豊富に存在する」
「うわ、分かんない単語ばっかり!」
「難しそう〜、マコは普通のカレーでいいかな〜」
「マコちゃんありがとう、久しぶりに名前を聞いたわ」と徳田さんは嬉しそうにしていた。「私も全く言葉がわからなくて、全然覚えられなかったのよ。英語とかそんなの全然ダメだし、インドの言葉なんでさっぱりわからない…」そういうとマコちゃんと二人でケラケラ笑っていた。
感謝のカレーライス
ヘルパーさんは料理上手な方だそうで、普段も一緒に料理を作っているそうだ。
しかし、そのヘルパーさんも本格的なインドカレーは作ったことがないらしく、今回はルーを使わせてもらったということだった。
でも、複雑な味がする。
マコちゃんがヘルパーさんに「ルーは何か」とまた聞いた。
2・3種類を混ぜて使っているそうだ。隠し味はインスタントコーヒー。
私たちは、また驚いた。
徳田さんも驚いたそうだ。
インスタントコーヒーを入れる前と後に味見をさせてもらったそうだが、旦那さんのカレーもこんなにドロドロはしていないなが、味が複雑でコクがあるものもあったそうだ。
日本のカレーはあまり食べたことがないが、スパイスの香りが懐かしくてとても嬉しかったと言った。
「この人いろいろ入れるものだから、その度に味見させてくれるんだけど、味見だけでお腹いっぱいになったのよ」「でも、入れると味が変わるのよ、不思議ね〜」
カレーの話をする徳田さんに、元気が戻ってきたようだ。
ヤス君が「カレー好き」と聞いて、今回このようなサプライズを思いついた。ヘルパーさんに相談したところ、すごく賛成してくれて全面協力となったそう。徳田さんはサプライズをすることも初めてて、ドキドキしたりして本当に色々楽しかったそうだ。
「捨子ちゃんたちと会ってから、私、泣いたり笑ったり、忙しいわよね、ごめんなさいね。本当にこれはお礼。お礼になったかしら?」
「楽しかったのよ本当に、本当に楽しかったの。思い切ってお願いしてよかったわ」
「美奈子さん(ヘルパーさん)もありがとうね」
「みんなのお陰です、ありがとう」
ヤス君は3杯もおかわりした。もう少し食べたさそうにしていたが、マコちゃんからの無言の圧力により、叶わなかった。
笑いと涙、そして感謝のカレーライス。
ご馳走様をして、午後の作業に戻ることになった。
食器は下げさせてもらったが、ヘルパーさんが洗ってくれるということで甘えさせてもらうことにした。
食べすぎた、お腹いっぱいだ。
誰かが作ってくれたご飯って、本当に幸せな気持ちになる。
こんな風に家族でご飯が食べられるって、幸せなんだろうな〜っとぼんやり思った。
午後の作業に取り掛かる。
気持ちを切り替えて、感謝の気持ちで作業に入った。
再度防護服を着て、洋室に入る。
先ほどこの部屋に入ったときにに嗅いだ匂いは、今はない。しかし、思い当たることがあるような匂いだった。
床に置かれていたダンボールがなくなり、部屋全体がわかるようになった。部屋の中は壁一面本棚になっていて、本棚にはびっしりとしかし整然と本が並んでいた。
見回すと、机の近くの手が届きやすい棚に、19××年と書かれた革の手帳のようなものがずらっと並んでいる。
徳田さんが言っていた「日記」ってこのことだ、と瞬時に察した。
どうしたら良いものか。と考えたが、そんな暇はない。
とりあえず棚のものを持参した空の段ボールに詰め、テープ留めをして部屋の外に出す、この作業を繰り返す、今はこのことに集中しよう。
2時になると、回収のトラックがやってくる。
どうにかそれまでには、目処をつけなければ……社長としての私と徳田さんに寄り添いたい私が戦っていた。
日記
お腹いっぱい食べさせてもらったおかげで、午後の作業は捗った。
美味しかったのもそうだが、感謝の気持ちが溢れ出てくる。
あんな風に良くして貰ったことがあまりない私には、心に琴線に触れた。
「この人のために…」と素直に思えたのは、人生のうちで数えるほどしかない。
今は徳田さんの心の重石を軽くしてあげたい、そう思うと自然と気持ちが集中してあっという間に箱詰めが終わって行った。
作業は奥の本棚からスタートし、3人で箱詰めしながら段ボールが溜まってきたらそれをヤス君が部屋の外へ運ぶ。
この段ボールは当社が持参したもので、埃まみれではないので階段から下ろすことにした。2時にトラックが到着予定なので、そのスタッフも参入して一気に運び出す予定だ。
部屋の奥から棚が空になっていく。高機能マスクで呼吸が苦しいせいもあるが、3人とも今日は無口だ。
マコちゃんは机の引き出しに取り掛かった。
「社長、これどうします?」
マコちゃんが開けた引き出しには、万年筆やボールペンなど名前が彫っている高価そうなものが出てきた。
ちょうど新しい段ボールを作ったところだったので
「マコちゃんありがとう、ここに入れて」
とそれを差し出した。
マコちゃんはその高価そうなペン類を綺麗に磨き、ダンボールへ入れた。
ヤス君は背が高い。180cmくらいだったと思う。私もマコちゃんもそうでもないので(私よりマコちゃんの方が少し背が高い)棚の高いところなどは、暗黙の了解でヤス君の担当になる。
そのヤス君が日記のある棚に取り掛かろうとしていた。
背の低い棚だ。
ドサッと座り込んだ。
ははぁ〜ん、疲れたんだな!と思った。
う〜ん、日記、どうしたらいいなぁ…と、まだ悩んでいた。
どんな風に悩んでいるかというと、このまま廃棄して良いものかどうか、という事。
結論が出ないままヤス君の作業はどんどん進み日記の場所に近づいてきた。
「ちょっとまっ……」と言いかけた時
1冊の日記が棚から落ちて、あるページが開いた状態でストンと床に着地した。
個人的なものなので、私たちは見てはいけない。
社長の私が止めるのも聞かず、捨子個人は開いたページから目が離せなかった。
落ちたそれを拾い上げたのはヤス君だった。
「へー、この店、この前、行きましたよ!会社の近くっすよ!」
何事が起きたのか、よくわからなかった。
「なに?」
驚いている私をよそに、マコちゃんがヤス君に駆け寄った。
「お客さんのもの見ちゃダメじゃん!」と裏の実権を持つマコちゃんは言ったが、中身が気になったのか、自分も覗き込んでいた。
「ほら、この店、この前行ったじゃん、めっちゃうまかったよな」
「あー行った!あそこ美味しかったよね、なんか今日話してて、この店のこと思い出してたんだよね」
「俺も!」
私が呆然としていると
「ほら、会社の近くのコンビニから入ったところにあるカレー屋ですよ」
「ねぇ、あそこってインドの人とかいるから本格的なヤツだよね、『ナン』とか出てきたし…」「あれだよね、今日話してた旦那さんが作ってたカレーって」
「そうじゃん!あれさ、うまかったよな、カレーのルーがさ、たくさん出てきて、小さいヤツがさっ、どれがどれかよく分からんヤツ、はははっ」
二人のテンポ良い会話が続く。
「でも俺は、フツーのがいいわ、カレーはやっぱご飯だね!」
「あんたはなんでもご飯でしょう、お好み焼きでもパスタでも……」
「この前なんかパンとご飯食べててたんですよ!」
気まずかったのか、ヤス君は日記の他のページも開いて見ていた。
「あのー俺よく分からんのですが、これってカリー(curry)って書いてる気がするんですが……」っと私のところへ日記を持ってきた。
見てみると、次のページもその次のページもその次のページも昼食の欄はcurryの文字が入っていた。
毎日、店の名前と住所、何を食べたかが小さな文字で書いていて、細かく感想が書いているようだ。
他にも日常のことももちろん書いていて、細かなことは読まなかったが、大学でのこと、家でのこと、天気のこと、もう桜の季節だなど四季のことが書いているようだった。綺麗な文字ではないが、読みやすい細かな字だ。
日記の半分くらいは昼食にスペースを取っていた。よく分からない横文字がずらっと並んでいて、cumin・corianderなどと書かれている、これはさっきマコちゃんが教えてくれたスパイスの名前なのでは、と思った。
もちろん、朝食や夕食の内容も書いている。
ん?朝食が毎回同じ内容のようだ。
『おにぎり2個・沢庵』次のページも『おにぎり2個・沢庵』次のページも同じ…
まるでお弁当のようだと思った。
後悔
書斎の片付けは順調に進み、終わりが見えてきた。
マコちゃんはすでに、掃除に取り掛かっていた。
ヤス君は合流したトラック部隊のスタッフ達と、相変わらずすごいスピードで運び出しをしている。
私は、最後の箱詰め作業をしていたが、手が進まない……
一つは全て廃棄の契約を破ろうとしていること。
もう一つは偶然とはいえ、日記を見てしまったこと。
そして最大の原因は……
「社長、大丈夫ですか?」
マコちゃんが私の顔を覗き込む。
「あーぁ、大丈夫……」
「全然大丈夫じゃなさそうですけど!」
「あっ、日記見ちゃったの、まずかったですか?まずいですよね……」
「ごめんなさい」
「あーん、そうじゃなくて……でも、大丈夫だから……」
私の進まない手とは裏腹に、マコちゃんたちが残りの作業をさっさと終わらせてくれて、もうすでに撤収準備に取り掛かっている。
私は、名前入りの万年筆と大量の日記の入った段ボールを抱えて、一階に降りた。
足取りは決して軽くはなかったが、腹は決まっていた。
一階で徳田さんは、ヤス君と話していた。
お茶とケーキがテーブルに並んでいた。
お茶を出し終わったヘルパーさんが、帰るところだった。
「捨子ちゃん、お疲れ様。まーぁ、大変だったでしょ……」
少し涙ぐみ、杖を支えに私のところに近寄ってきた。
「じゃ徳田さん、失礼します。」ヘルパーさんが帰っていく。
近寄ってきた徳田さんが、ダンボールを持つ私を見て少し凍りついた。
全部捨てる、それはもう何も見たくないから……この約束での契約だった。
それなのに段ボールを持っている……
涙ぐんだ目から水分は一瞬でなくなり、目を見開いて私を見ている。
憎しみに似た、強い視線だ。
覚悟は決まっていた。
スタッフにはケーキを先に頂くように伝え、
私は徳田さんと奥の寝室にある洋ダンスの前に向かった。
「徳田さん、謝らなければいけません……」
「捨子ちゃん…… どうして……」
徳田さんは杖を持つ手が震えていた。悲しいような、苦しいような、怒りのような表情だった。
「私は、片付け屋です。この仕事は大変だけど、喜んでくれるお客さんがいる限り続けていくと前の社長から引き継いだ時に約束しました。」
「徳田さん、聞いてもらえますか。」
「私は片付け屋ですから、捨てるのが仕事です。」
「でも、これを捨てると、後悔が残ってしまうと思ったのです。」
「後悔が残っては、全部捨てたことにならない……そう思ったんです」
「ふふっ、捨子ちゃん……お話聞くわ。」
少し悲しそうにそう言って徳田さんは、鏡台の椅子に座った。
ダンボールを徳田さんの足元に静かに下ろした。
徳田さんは、見たくなさそうに中身を見た。
ランチの秘密
徳田さんの足元に置いたダンボールの蓋を開いた時、見たくなさそうな徳田さんの表情があった。
それと同時に見たくてしょうがない気持ちが、隠せない。
「捨子ちゃん、これが日記よ。これに私が苦しめられたこと、お話したと思うんだけど…… どうして……捨てくれなかったの?」
「他のものはどうでも良かったの、本当はそれを捨て欲しかったの!」
「あの日から、これを見た日からずっと……」
「2階に登れなくなってからもずっと……泣」
「気持ちが晴れた日はなかったのよ……」
「わからないのよ、なぜなの……」
私は聞いていた。
ただ、徳田さんの気持ちを聞いていた。
あの日記に描かれていた日々の食事の内容……ある考えがあった。
最後のダンボールを詰めていた時に纏った。
そしてそれを徳田さんに話そうと決めたのだ。
「徳田さん、聞いてください」
「徳田さんは毎日お弁当を作っていた、と言っていましたよね。」
「そうよ、毎日作っていたわ。」
「子供達が産まれてからは、大したものは作れなかったけれど……」
「ほら、言ったでしょ、私お料理、上手くないのよ。」
「徳田さん、お弁当っておにぎり2個と沢庵、ですか?」
「えっ!」っと言って徳田さんは私の目を見た。
「捨子ちゃん、どうしてそれを……」
「すみません、謝ります。箱詰めの時に日記を床に落としてしまい、中身が見えてしまいました。」
徳田さんは驚いた様子でワナワナ震えていた。
「たまたま開いたページに書いていたお店に、ヤス君とマコちゃんが行った事があるというので、話を聞きながら私も日記を見ました。ごめんなさい。」
「そのお店は、インドカレーのお店でした。」
そう伝えると徳田さんはギョッとして目を見開いた。
口を半開きにして、言葉にならない様子だ。
私は続けた。
「徳田さんが言っていたように、日記の下の方は、毎日食べたものがびっしり書かれていました。そのページも次のページも次のページもお昼ご飯は毎日、curryと書かれていました。多分、毎日カレー屋さんへ行っていたのだと思います。」
徳田さんはまだ口を半開きにしたが、我に戻って「カレー屋さん!?」と聞き返した。
「日曜の夜はあの人がカレーを作ってくれるのよ、毎週ね。それが毎回少しづつ違うの。だから私、カレーを作った事がないのよ。周りのお母さん方にそれを話した事があるんだけど、まぁそりゃ羨ましがられたわよ!」
「私たちの時代は、『男子厨房に入らず』の時代だがらね。」
「旦那さんが夕飯を作ってくれると言うだけで、『まぁ〜』って騒がれたし、それが本格カリーだっていうと、『さすが徳田さんの旦那さんは大学教授でいらっしゃるから〜』っておベッカまで言われたりしたわ。」
「でも、捨子ちゃん、お弁当は?毎日、持たせていたのよ。」
「そりゃ、おにぎりと沢庵だけになっていっちゃったけど、あの人がそれでいいって、おにぎり2個と沢庵で良いって、そう言ったのよ。」
「子供も男の子3人だから、よく食べるしね、お義母さんがいた頃はお食事はやってくださっていて、私はお米をうまく炊くことだけで良かったのよ。」
「だからお米はうまく炊けるの、家族みんな褒めてくれるくらい。」
「ふふっ、こんな話、女としては恥よね、お米しか炊けないんだから……」
「だから、捨子ちゃんたちが見た日記は、お義母さんがなくなった後、おにぎり2個と沢庵だけのお弁当になった時のものだと思うわ。」
「主人は、私がおかずが下手だから、そう言ったんだと思ってるの。」
「思えば、日曜のカレーもお義母さんが亡くなった後から始まった気がするわ。」
「なんだか、滑稽よね、何にもできない、私が何にもできないから……こんなおばあちゃんになっても……こんなに何にもできない……」
「徳田さん、ご主人は朝ごはんはどうしていたんですか?」
一番気になっていたことを聞いた。
「昔は食べていたんだけどね、『最近太ったから』って食べなくなったのよ。」
「そうね、それもお義母さんが亡くなった後からかしら……」
「『自分も健康に気を遣ったほうがいい』って言って。」
「徳田さん、わかりましたよ、ご主人の秘密が!」
「えっ!」
徳田さんはまた驚いて、今度は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。
天国からの無言の伝言①
徳田さんの顔がみるみる高揚し、心臓の音が聞こえるかのようだった。
「徳田さん…」
私は言葉を選びながら話した。
「徳田さん、ご主人は、徳田さんを本当に愛していたのですね。」
この言葉を聞き、徳田さんは小さく首を横に振り、何が起きたのか分からない、といったように呆然としていた。
私は続けた。
「ご主人がカレー屋さんに行っていたことは、本当に知らなかったんですね。」
徳田さんは頷いた。
「ご主人がお昼に食べていたカレーは、その週末に徳田さんが食べていたカレーだと思います。」
「ご主人の日記には、カレー屋さんの名前と住所、頼んだメニューだけではなく、使われている香辛料の名前や味の感想、例えば塩味が濃いとか辛味が強いとか、そう言うことが事細かに書いていました。」
「隅々まで読んだわけではないので、私の憶測ですが……」
「週末、家族にカレーを作るために、カレー屋さんに通ってカレーの研究をしていたのではないかと、私はそう感じました。そうとしか考えられませんでした。」
「実際に、ご主人の書斎には、本格的なインドカレーの本がたくさんありました。」
「これは、マコちゃんが撮ってくれた本棚の様子です。見ますか?」
と言って、タブレットを差し出した。
このタブレットは、作業前後の様子に加えて、作業途中や必要だと感じた箇所を、マコちゃんがいつも撮影してくれているものだ。
徳田さんは、タブレットを覗き込んだ。
カレーの専門書が並んだ棚と、その本を開いてカレーのレシピが書いているページの写真だ。
「この本棚、全部カレーの本でした。」
「この写真も見てください。」
そう言って私は、ご主人の机の引き出しの中を撮影した写真を徳田さんに見せた。
埃がかぶっているし、カビていたり、乾燥して粉のようになっていたりして、分かりにくいのだが、その引き出しを開けた途端、スパイスの香りがしっかりと鼻をついた。
その全てに名前が記されていて、【coriander】【turmeric】【cumin】など
スパイスの名前だと、一目見て分かった。
その引き出しには、スパイスが入った小瓶がずらりと並んでいたのだ。
マコちゃんは、「机の引き出しにカレー粉って、ありえなくないですか?」
と言ってヤス君と笑っていたが、私は、私の中で生まれたある考えの答え合わせをしているかのようだった。
「徳田さん、この瓶のようなものが分かりますか?」
徳田さんは、コクリと頷く。
「瓶の上に文字が書いているんですが、これ全部、スパイスの名前なんです。」
きょとんとした顔で徳田さんは私を見た。
「この下の引き出しには、これが入っていました。」
タブレットにはスパイスをすり潰す道具などが写っていた。
徳田さんはタブレットを指差しながら、
「これ主人が使っていたものよ!」と言いながら泣き崩れた。
「残念ながら、これらはカビていたので廃棄しました、ごめんなさい」と伝えた。
天国からの無言の伝言②
少し落ち着いた徳田さんが、私に尋ねた。
「主人がカレー屋さんで食べたカレーを日曜に家で作っていた、そこまではわかったわ、凝り性なあの人らしいと思ったわ。」
「でもね、じゃぁ、お弁当は?お弁当はどうしていたの?」捲し立てるように徳田さんが尋ねる。
「日記には、毎日の食事が記録されていました。細かく。」
「ご主人は朝食はいらない、と言っていたと聞きましたが……」
「そうよ、毎朝私、子供達のことで忙しくしていて、お義母さんが亡くなった後、朝ごはんはいらないから、弁当を作ってくれって、言われたの……だから毎朝、おにぎりを2個握って持たせていたのよ……主人がそうしてくれって……おにぎりを2個……そうしてくてって……」話しながら徳田さんは咳き込むように、咽び泣いた。
徳田さんの小さく丸くなった背中をさすりながら、私は話した。
「徳田さん、お弁当のおにぎりは、日記の中では朝食のところに書いていました。」
ギョッと、振り返り徳田さんは私を見た。
「カレー屋さんの情報の前に、『おにぎり2個沢庵』『おにぎり2個沢庵』と毎日書かれていました。」
「それを見て、お弁当は朝食だったんじゃないか、と思ったんです。」
「そして、お昼ご飯はほぼ毎日カレー屋さんに行っていたようです。」
そこまで話すと、一瞬納得して顔を上げたが、さらに疑問が浮かんだ様子で
再度、私に尋ねてきた。
「お弁当のおにぎりを朝、食べてお昼はカレー屋さんで食べてたって言うこと?じゃぁ、素直にそう言ってくれたら良かったんじゃないの?なんで、そんな嘘をつかなくちゃいけなかったの?分からないわよ……」
「徳田さんのお話を聞いかせてもらって、そしてご主人の書斎を片付けして、わかったことがあります。」
「ひとつは、ご主人は家族との食事を大切にしていたと言うこと。」
「もうひとつは、徳田さんのことをとても愛していたと言うことです。」
「捨子ちゃん、もういいわ、もうこんなの耐えられない……」
徳田さんは少し大きな声を出した。
そのことに驚いて、マコちゃんが部屋を確認に来た。
「社長、大丈夫ですか?」
「あ、ごめんなさい、ありがとう。」
「徳田さん、お伝えしたいのです。聞いてもらえないでしょうか?」
「……」答えはなかった。
「徳田さん、マコちゃんにもここにいてもらっていいですか?」
そう私が聞いた後、徳田さんはマコちゃんに手を伸ばし、部屋に招き入れた。
「どうしたんですか?」とマコちゃんが徳田さんの手をさすりながら、話を進めるよう促した。
「うん、話します。」
「徳田さんのご主人の日記に、食べたものの事を細かく書いていたね。」
「めっちゃ書いてました、びっしり書いてて読めないくらいだった。」
とマコちゃんが言った。
「あのね、徳田さんのご主人は週末にカレーを作るのが日課になってる話、聞いたでしょ。ご主人はそのためにお昼ご飯はカレー屋さん巡りをしていたんじゃ無いかと思うの。」
マコちゃんが頷く。
「徳田さんは辛いの強いですか?」と聞くと
徳田さんは首を振り「全然ダメ」と言った。
「徳田さんはご主人が作ってくれるから、カレーを作った事がなくて、今日初めて私たちに作ってくれたんですよね。」
徳田さんが頷く
「マコちゃん、今日のカレー辛かった?」
「辛くなかったです、甘口でしたよね。」とマコちゃんが答える。
「辛さは?ってヘルパーさんに聞かれたから、その話したのよ、辛いのは全然ダメだって言ったのよ、カレーって辛いの?」
「えーっ」とマコちゃんが驚いた顔で徳田さんをみた。
天国からの無言の伝言③
カレーが辛い事を知らないほどに徳田さんはご主人に……
そう思って私は笑ったのだが、
マコちゃんは徳田さんの言葉に呆気にとられたのに加え、私が笑ったのに驚いで尚のこと状況が読めず、口をあんぐり開けていた。
そこへヤス君が声を掛けてきた。
「どうしたんすか?食べ終わりましたよ」
間髪入れず、マコちゃんが
「社長がヤバイ、おかしくなった……」っと言った。
私がまた笑ったものだから、みんな、私を心配そうに見た。
私は少し泣きそうになりながら微笑んで、話し始めた。
「ごめんなさい、笑ったりして……」
「あまりに微笑ましくて……」
「徳田さんこの日記は、多分、ご主人からのラブレターですよ。」
一瞬でみんなの顔が、暗闇の猫の目のように最高に見開いて高揚したのがわかった。
「ご主人は、ラブレターと思って書いてはいないでしょうけど、ここには、徳田さんへの愛がたくさんたつさん詰まっています。」
「ご主人がカレーを作り始めた時期と、おにぎりにしてくれと言った時期は同じくらいなんですよね。」
徳田さんはうなづいた。
「それは、義理のお母さんが亡くなった時期と同じくらいなんですね。」
再度うなづく。
「ご主人はお仕事が忙しくて家のことや子育てのことなど、あまり出来なかったんじゃないですか?」
「それがどうしたっていうの?わからないわよ!!!」
徳田さんが少し上擦った声で言った。
「多分ご主人は、それが申し訳なかったんですよ。」
「義理のお母さんがいた頃は徳田さんを手伝ってくれていたので、安心して仕事に没頭できたけど、亡くなった後、苦労している徳田さんを見て、任せっきりで何もできないことを、とても申し訳なく思っていたんだと思います。」
「でも、口下手なご主人だから、それを伝えることだできなかった……」
「だから、何かできないか考えたんだと思います。」
みんな静かに聞いてくれた。
「一番大変だったのは、朝の支度じゃなかったですか?」
「そう、朝は本当に毎朝本当に大変だった……4時に起きて玄関に水を撒いて、仏様のお世話をして、朝ごはんの支度をして、子供達を起こして……ほんとうに忙しかった。私、要領が悪いから色々失敗して、本当に必死だったわ。でも、それがどうして分かるの?」
徳田さんは不思議そうに尋ねた。
「はい、多分ご主人は、まずそこを助けたかったんですよ。だから、朝ごはんはいらないと言って、徳田さんが褒められるほど上手に炊けるご飯をおにぎりにしてもらおうと、それなら負担が軽くなるんじゃないかと……そう思ったんじゃないかと思ったんです。」
マコちゃんとヤス君が目を合わせて、肩をすくめて息を飲んだ。
二人ともとろけたような、穏やかな笑顔だった。
私は続けて話した。
「カレーをご主人が作り始めたのも、深い愛情からだと思うんです。それは、食事作りの負担を軽くしてあげたいけれど思って、あれこれ考えたんじゃないかとおもうんです。でも、あからさまに普段のおかずを作っては、徳田さんを傷つけるのではないかと思って、普段家庭で作らないような専門的なものなら受け入れてくれるのではないか……その頃ちょうど、固形のカレーが流行っていたんじゃないですか?」
徳田さんは頷いて
「でも、何が入っているかわからないものは、食べないようにしていたのよ、お義母さんが……だから、あのカレーは今回初めて見たのよ、世間知らずもよっぽどよね……」
と項垂れた。
「だから旦那さんは、インドカレーにしたんだ!」
勢いよく、感のいいマコちゃんが声を上げた。
ヤス君は「なになに?」とまだわかったいないようだった。
「そう、だからよ!」
そう私が言うと、マコちゃんが徳田さんの手をとり、目を見て
「徳田さん、すごいです〜なんか羨ましい〜深いな〜あの日記はラブレターだなんて、かっこいいです!!」
徳田さんとヤス君は、まだその時点では不思議顔だった。
天国からの無言の伝言④
私は話を続けた。
「旦那さんは、一生懸命考えたんですよ。苦労している徳田さんに何がしてあげられないかと。少しでも助けになりたいと。寡黙でうまく伝えられないけど、徳田さんを助けたかった。徳田さんの負担を軽くしたかったんですよ。」
「でも、それを言うと、徳田さんがもっと無理して頑張ってしまうだろうと思ったから、何も言わず、徳田さんが気を使わない方法を考えて、朝ごはんはいらないと言っておにぎりを握ってもらって、週末に専門的なカレーを作るためにお昼はカレー屋さん巡りをしていた。」
「ただ、専門的なカレーを作るのなら毎日行く必要はなかったんだと思います。
徳田さんが食べられる、辛くないカレーを探していたんじゃないかと思うんです。
辛くなくて美味しくて、徳田さんの炊くご飯に合うカレーを……」
みんな一斉に、手を口に当てて、息を吸い込んだ。
次の瞬間、徳田さんが声を上げて泣いた。
「あぁーあなた……何で……何で……どうして……どうしてこんな……あぁー……
私が、何もできないから……あなたにもこんなに……迷惑かけて……お義母さんにも、無理をさせてしまって……本当に本当に……私は……もう……どうしたらいいの……あぁー……あぁー……」
力なく悲しげに泣く徳田さんを、マコちゃんとヤス君が支えてくれた。二人ともぐちゃぐちゃに泣いていた。
「徳田さん、ごめんなさい。辛い思いをさせましたね……」
「でも、わかって欲しいんです。ご主人もお義母さんもお子さん達も、みんな徳田さんを本当に愛していたんだと思います。」
私がそういうと、徳田さんは何度も首を横に振った。
マコちゃんが静かに口添えした。
「そうですよ、息子さんからも何回も電話ありましたよ、ねっ、社長。自分は海外にいて行くことができないからよろしくお願いしますって。」
そう言うと、ヤス君が
「それって内緒なんじゃなかったっけ?」
「えっ!」っと空気が一瞬止まったが、
「あっ、ヤス君ごめん、一応ね、『母には内緒で』で言われてたからヤス君には最初にそう言ったよね、でも、私、そうじゃない方がいいと思って、長男さんから連絡があったこと、伝えられるチャンスがあったら伝えたいって言ってみたの。」
「そうしたら、『離れていて何もできず申し訳ない、想いはあっても言葉足らずで親孝行のひとつも出来ていないんだ』とおっしゃっていたの。だからいいのよ。大丈夫。」
「なんか親子で似てますね!」とマコちゃんが言う。
「ほんとだ!」とヤス君が笑う。
みんなの顔が泣き笑いでなお一層、ぐちゃぐちゃになった。
徳田さんが少し落ち着きを取りどし、話し始めた。
「長男は私と同じ時間に起きて、玄関掃除をしてくれた。
次男は料理が上手くて、朝晩台所に一緒に立ってくれたのよ。
三男は主人に似て几帳面だったから、片付けをよくしてくれたの。」
「主人は仏様のことを毎朝してくれたわ。結局私は、たいして家事なんてしてないのね。いつもみんなに迷惑かけて、いつも誰かに頼っていた。一人じゃ何もできない……みんなに気を使わせていたのね。それすら、わからなかったわ……」
「お義母さんもね、私、体が弱くてお産も大変だったものだから、とってもよくしてくれたのよ。『綺麗なお嫁さんでしょ』って、『可愛い孫、それも男の子を3人も産んでくれただけでありがたい」って。親戚や近所の人にも、そんなふうに言って何にもできない私をいつも庇ってくれていたの。」
「これ見て、主人。」
徳田さんはご主人の写真を私たちに見せてくれた。
「仏頂面で、ずんぐりむっくりしていて、無口。最初に会った時には、機嫌が悪いのかと思ったわ。後で聞いた話だけど、何度かお見合いダメになっていたんですって。断ったのか断られたのか、わからないけれどね」
徳田さんは少し笑った。
「えー、徳田さんはご主人のどこが良かったんですか?」
とマコちゃんが聞くと
「少し笑ったのよ、あの人。」
「お見合いの時にお庭を散歩していてね、雨上がりでね、風が吹いて桜の木の下で雨の雫が私たちに落ちてきたの。キラキラって……」
「それが冷たくてね、でもとても綺麗で……私が『きゃっ』って言ったもんだから、助けてくれてね」
「その時笑ったのよ……恥ずかしそうに笑ったの……」
「私がその顔を見ていたら、照れてね、頭を掻きながら、『大丈夫ですか?』ってその時初めて声を聞いたの……」
「その声が、私の中にすーっと入ってきたような気がしたの。変でしょ。そんな感じがしたのよ……それだけ」
「すっごーい!キュンってしちゃいますね!!」
マコちゃんが言うと
ヤス君が
「徳田さんは声フェチすね!俺の声はどうっすか?」とふざけるとマコちゃんに後頭部をパシッと叩かれていた。
徳田さんが立ち上がった。
「捨子ちゃん、ありがとう、色々ごめんなさいね、許してね。この日記、今なら受け入れられると思う。ふふっ、あの人からのラブレター、死ぬまでに読み切れるかしら……もう一度あの人に出会えるような、今はそんなワクワクした気分になれたわ」
「マコちゃんもヤス君も長い時間ごめんなさい、私……本当……に……救われたわ……。本当に……みんなに助けられて……なんとか生きてこられた……」
「あーなんて幸せなんでしょう……あの人がいなくなって、ひとりぼっちで……怖くて怖くて……もうお迎えを待つだけだって思っていたのに……こんなプレゼントをいただけた。本当に、みなさん、ありがとう。捨子ちゃん、ありがとう」
こうして、徳田様の作業は完了となりました。
会社に戻る車で、なんとなく3人は無口だった。
作業報告書にマコちゃんが書いていた言葉が心に残った。
「片付けは人助けだ」
徳田家 完
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
