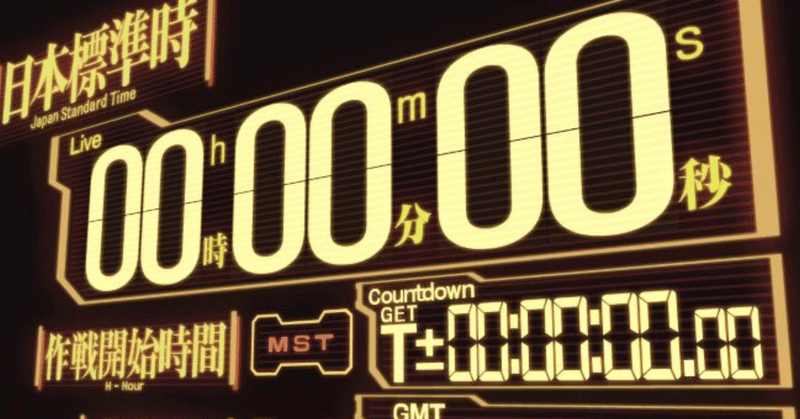
知識ゼロ、勉強未経験が予備試験一次(短答式)突破する為の作戦
みなさんどうもこんにちは😃
プーさんです!
今日は、初年度の短答受験者や、まだ一次試験未合格者に読んでいただきたいブログでございます。
私の過去の経歴、2次試験までの大雑把な勉強法は最初のブログにまとめていますので、そちらも併せて読んでいただけたら嬉しいです。
本ブログの目的
予備試験一年目で何をやったらいいかわからない人はいっぱいいると思います。世の中YouTube等でも有益な情報が得られますが、正直底辺界隈では、通用しないことも多くございます。
また、同じ教材を使っていても、使用法や慣れによってうまく身につかないこともあります。(私はめちゃくちゃ失敗しました)その経験から、戦略的に私が一年目ならこうしようと思う方法を紹介します。
予備試験短答式とは
予備試験は、言わずもがな最難関試験の一つですが、その中でも唯一皆が受けることができるのはその一次試験である、短答式試験です。短答式といっても求められる知識は幅広く、精度も高くないと受かることができません。
そのためにある程度分析する必要があります。法律科目、1教科30点、一般教養60点の270点満点で令和5年度は168点必要な試験です。
細かいデータはstady.web5さんが詳しく解析しています。私も何を行えば良いかわからない時にお世話になったサイトです。
一問の難易度で言ったらそこまでではないのですが、時間が短く呑気に解いている時間などありません。
そして、大学まで一切と言っていいほど勉強してきていない私からしたら、一般教養の60点はハンデにしかなりません。大学までの勉強量の差も痛感できる、そんな鬼畜な内容となってます😆
短答の勉強はいつからで間に合うのか、どの程度のボリュームをこなせばいけるのか、また、科目ごとに勉強と本番の戦略を立てていたので、そのことに関しても、書いていきます!!
何を使ってどうやればええんか?
まず、短答の勉強をするにあたって、入門講座や基本書等を一読していることを前提にお話しします。(内容を身につけていることまでは必要ありません)
私が使用した主に教材は短答過去問パーフェクト+基礎マスターのみです。伊藤塾ではない人は、おすすめの参考書で問題ないです。
1周目
まず最初に過去問パーフェクト一周してください。無理だったからすぐ答え見ていいですし、実力を知るために軽く解いてみてください!
その際にまだ印をつける必要はありません。
1周目から意気込んでも、そんな出来なく負担だと思うのでサラッとやっちゃうことがオススメです。
2周目
次に、全択を解き間違えたところ、わかんないところに印をつけます。この時、2択で当たるので、少しでも不安があればつけておくことをおすすめします。私はそこで適当につけすぎて印漏れが多かったため、厳しく印をつけてください笑
間違えたところが炙り出されたら、基本書の書いてあるところにマークをつけます。このことによって苦手なところが可視化されますし、本番前はこの基本書でインプットも行うので、めんどくさいですが、行ってください。
そして間違えたところの周りも含めて、もう一度インプットします。
3周目
漏れがあるかもしれないのでもう一度全択解いてください。そこで先ほどと同じ作業を行います。一度解いているのと、間違える問題数も大幅に減っていると思うので楽だと思います。
ここまで来ればある程度できていると思うので最悪このままテスト迎えてもいけます。
4周目以降
間違えた択のみを全部やります。そこで正解したら消していき、全部消すまでやります笑
テスト前
テスト前は問題を解くより、マークをつけた教科書を読んでインプットをしました。みなさん問題を解いて終わりにしてませんか?
アウトプットはこれだけ解けば十分だと思うので、あとは新しい問題に対応するためにも、確実な知識を仕込みましょう。
ここまでは、割と定番であり、最短とも言えないかもしれません。しかし、一年目はそんなものだと思ってください。論文を狙って、短答で落ちたら元も子もありません。今年周りには論文書けそうな人も短答落ちしている人を多く見かけました。
短答は年数を重ねている、40代以降の方は本当に強いですし、論文試験に多くみられました。短答はわからないところを、しらみつぶししていく作業です。面白くはないかもしれないですが、勉強に自信ない人は耐えましょう!!
科目ごとの作戦
ここからは完全に自分が行なってきた作戦です。他の人に当てはまるかは微妙ですが、ここまで作戦立ててギリギリなので自分なりの作戦は有効だと思います。

公法 憲法 行政法
公法科目は短答の中で唯一、時間が余る傾向にありました。答練でも20分ほどあまります笑
したがって急いで解く必要はなくじっくり考えます。また、択全てに正解する必要があり特殊性もあるため、精度高い知識が必要な科目です。
憲法は判例中心で問題ないです。判例さえ知ってればそこそこ解けるので、演習で間違えたら、判例をメモして、どの判例の理解が足りてないかを炙り出しましょう。
行政法だけはずっと苦手で答練でも20点越えることはありませんでした、、
原因としては、情報公開法や細かい要件、判例など2問わかるけど、残りわからないような状況が多く、点数が伸びませんでした。それなら分野別に極めたほうが伸びると思います。
本番でも12点でした、、、
特に、処分性、原告適格、訴えの利益等は論文にも役立つのでしっかり対策することをおすすめします、、、
民事系 民法 商法 民事訴訟法
民事系は1時間半あるため、わかる問題を確実に点を取る必要があります。わからない問題に時間をかけると、民訴が伸びません笑
わからない問題はとにかく、印をつけて後回しにを意識してました。
そして、民事系は択を切ることがめちゃくちゃ重要です。時間短縮にもなります。しかし、正解択を切り捨ててしまうと確実に点が取れなくなるので、実際に使っていた方法も紹介します。
まず、5問のうち、確実にあってる択、間違ってる択を2択ほど見つけます。ここで確実性が重要です。ちょっと違うかもで切っては行けません。一気に正答率が落ちます。
ポイントは先に下の選択肢を見ないで、確実にわかるものをチョイスすることです。一つでも分かったと思って下を見ると、引っ張られて正常な判断ができません。問題を見て考える隙もなく、正当できる択で確定していくことが必要です。おそらく2問で1つか2つに確実に絞られることになりますので、そこからはよりあってると思う方で確定していきます。
問題見ても一問しか確定できない程であれば、先にどんどん進んでください。時間がかかります。最後余った時間で2択or3択から頑張ります。イメージは択を減らす方がやりやすいです。あってる方はコレ!とピンとこない限り確定できませんが、間違っている方はここ違うかもでいいためです。
とにかく時間との勝負です。
民法は過去問でなんとかしました。基本難しいところは債権法や担保物件です。家族法や物権で落とさないことが重要かと思います。それ以外特に言うことないです笑
商法は最後の4問が商法と手形法なので、過去問完璧にしてれば基本落とすことはありません。量も少なく、8点取れるので絶対やった方がいいです。1番だるいのは組織系の具体的数字や文言は引っ掛かりやすいので、アバウトに覚えるのではなく、確実な知識のみを持てるように、問題に出てきそうな数字や条文を確実に理解しておくことで点数が伸びていきます。私は組織再編等はだるいので、過去問のみで間違っても仕方ないと割り切っていました。
割り切りも重要かもしれません。
民事訴訟法などの訴訟法は条文知識が多めです。過去問と条文素読でいいと思います。正直過去問で、同じ問題の焼き増しが多いので比較的解きやすいです。
刑事系 刑法 刑事訴訟法
刑事系も割と時間かつかつなので、僕は解釈問題を最後に解いていました。時間かければ解けますが、そもそも刑法はそれ以外も比較的簡単な問題多めですので、時間が余ったらくらいにしておくのが良いです。刑事訴訟法にも解釈問題があり、個人的には刑訴の方が難しい気がしています笑
得意不得意で苦手な問題を後回しにする姿勢は重要だと思います。
刑法は、想像することと論文の勉強を始めてしまうことです。一番最初に論文が書けるようになるので、短答段階から始めると短答の点数も伸びると思います。
特に総論は判例ですが、各論は要件を理解していることも重要なので、より論文の勉強が生きます!!財産に対する罪と偽造系は過去問が特に生きるのでそこは重点的にやった方がいいです。
刑事訴訟法はあまり、論文とリンクしていない感じがあるので、過去問と条文素読でいいと思います。手続の流れや条文の勉強は、やがての刑事実務に役立つので並行して勉強するのもいいかもしれません。
私は後々気づいて、後悔したので特に条文素読一番やった方がいい科目です。刑事訴訟法は条文横に何についての条文か書かれていないので、本番見つけるのはとても難しいので、本当に条文だけは読んでください!!これも失敗談です、、
一般教養
大学まで、全く勉強してきてない人にとって1番の鬼門はこの一般教養です。コレは特に作戦が重要です。
まず、英語は基本的に大学受験を経験していなかったり、英検準一級取れないレベルの人は見る必要もないと思います。まず無理です。そして、前半の世界史とかどれか一つあってるものを探す系は手掛かりがなさすぎるので解くのは厳しいです。
まずはこのYouTubeを見て、確率を高めることを意識してください。
これだけでは、まだ足りません。
一般教養の問題作成をする教授の得意分野やその都市のノーベル賞についてなど、Twitterでまとめてくれている人がいるのでその研究をしてみてください。短答直前期は、同じことの繰り返しで勉強に面白みがないので、一般教養の勉強をして3問くらい解けるようになればそれだけで10点増えるので、伸び悩む法律科目より勉強をする価値はあると思います!
短答答練との向き合い方
私は伊藤塾の短答答練をペースメーカーとして家で受けていました。論文とセットであったため、落ちたら勿体無いと思って気合い入った部分はありますが、金銭的に余裕がある人は受けた方が絶対にいいと思っています。
まず、自分の現状を知ることができます。短答は簡単のようなイメージがあったので、一度できない絶望感を味わえます。しかし、間違ったところや気づきも多く得れることもできますし、序盤は右肩上がりで点数は伸びやすいです。点数を過信することはよくないですが、伸びていく自信はつきます。
まずは答練で法律科目150点を目指しましょう。得意不得意があると思うので、それぞれの科目ごとのノルマや課題を分析する必要があります。実際答練では一度も150点行かず、最高132点でした、、
その分短答は行けるだろうという甘い考えは出てこなく、最後までやり切れました。答練できないからと言って自信をなくさないように、することも大事です。
最初できないのは当たり前で、最後にボーダーさえ越えればいいんです。短答は、やった分だけ実力がついていくと思います。勉強苦手な人はまず、一年目で受かって自信をつけ、2年目は論文に振り切ってできるようにすることも戦略だと思います。
1次受かってもいないのに2次に焦点を合わすのではなく、一歩ずつ進んでいきましょう!!
今回のブログを読んで、皆さんの戦略の足しになれたら嬉しいです。
この記事を読んで良かったらフォロー、拡散よろしくお願いします🙇♀️
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
