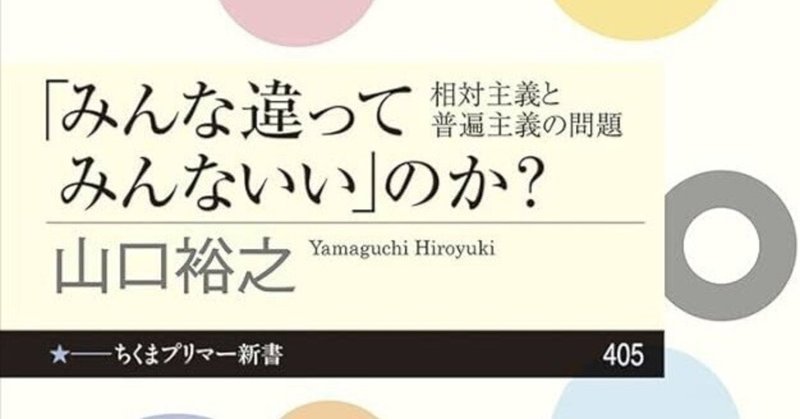
「みんな違ってみんないい」のか? - 相対主義と普遍主義の問題
今回は『「みんな違ってみんないい」のか? - 相対主義と普遍主義の問題』という本について書いてみたいと思います。
近年、グローバル化の影響もあってか、「考え方は人それぞれ」とか「何が正しいかなんて誰にも分からない」という考え方が広まっているように感じます。
このように、人や文化によって価値観や考え方は異なり、何が正しくて何が間違っているという判断はできない、という考え方を「相対主義」と言います。
僕も、自分は相対主義者だと自負しています。
その一方で、人や文化それぞれの捉え方を超えた、客観的な正しさや真理は存在するという考え方を「普遍主義」と言います。
後々、詳しく書きますが、古代哲学ではこのような考え方が主流でした。しかし、いつからか相対主義的な考え方が流布していき、人気を博していきます。
それによって、様々なところで問題が生じているのも事実です。なので、今一度、相対主義的な「人それぞれ論」を考え直そうというのが本書の内容になっています。
本書の中で印象的だったのが、
相対主義的な考え方は「正しさ」を作る努力を放棄することになる
「正しいこと」と「正しいと感じていること」は違う
「正しさ」は、その事象に関わる人間の合意によって初めて生まれる
という点でした。
今回は、その3点をメインに順を追って書いてみようと思います。
1:「人それぞれ論」がどこから生まれたか
まず、「人それぞれ」という考え方はいつ頃、どのようにして生まれたものなのでしょうか。
冒頭でも述べましたが、元々哲学のテーマは世界の真理を解明することであり、そこには普遍主義的な考え方が基盤になっていたはずです。
例えば、プラトンはあらゆる現象に共通して当てはまる普遍的なものとして「イデア」という概念を想定しました。
また、アリストテレスは諸現象の背後にある原因を究明することこそが学問だと考えていました。
例えば、これが生きていた時代は「雷」は神様が起こっている印だと考えられていましたが、彼は神のような抽象的な存在に頼ることなく観察可能で科学的な説明をあらゆる現象に求めようとしました。
もちろん、学問だけでなく西洋社会では普遍性が強調されていました。
そして、19世紀から20世紀初頭までにヨーロッパでは産業革命が起こりヨーロッパ諸国が世界中に植民地を増やしていく中、その領土をめぐってヨーロッパ諸国同士が争うようになります。
そして、20世紀初頭の第一次世界大戦をきっかけに「普遍主義」の妥当性が疑われるようになっていきます。
それと同時に「実存哲学」が普及し始めます。実存哲学はドイツのマルティン=ハイデガーを始め、ジョン=ポール=サルトルやセーレン=キルケゴール、アルベール=カミュなどの哲学者によって開拓された哲学です。
実存哲学についての説明はまた別でするとして、とりあえずここでは第一次世界大戦前後で「実存哲学」という哲学が普及したということだけ知っておいてください。
そして、時は進み、第二次世界大戦が終わった頃から元々植民地だったアジアやアフリカの国々が独立し始め、彼らの文化もヨーロッパのものと負けず劣らず素晴らしいものだという主張が強まっていきます。
この辺りから「相対主義」の片鱗が現れ始めます。
しかし、この頃はまだ構造主義や文化相対主義のように「文化それぞれ」の考え方が強かったようです。
そして、1960年頃には世界中で市民運動が活発になり、だんだんと個々人の自由や尊重を求める声が強くなっていったのです。
つまり、よく見たらそれぞれ違う個人を性別や人種、職業、階級などで勝手に縛り付けるなという考えが強くなったということです。
そして、1990年代に新自由主義ができますが、筆者はそれこそがまさに「人それぞれ」の考え方だと考えているようです。
新自由主義では、他人に迷惑をかけなければ基本的に何をしても個人の自由だと考えます。
これまで何度も自由を求めてきた人間としては当然の考えかもしれません。
確かにその考えもありますが、筆者はその考えによって、他人との関わりが避けられていくことを強く懸念しています。
なぜなら、「正しさは人それぞれ」というのは、他人同士が交わる際には通用しないからです。つまり、その考え方を誇示するためにはどこまでも一人でいる必要があります。
それでは、社会は成り行かないのです。
2:相対主義と普遍主義の関係について
僕はこの本を読むまで、相対主義と普遍主義についてふわっとした理解しかありませんでした。
なので、なんとなく相対主義と普遍主義は相反する概念だと思い込んでいました。
ここまで読まれた方もそのように感じているのではないでしょうか。(もちろんそう感じるように書いてるからというのもあるのですが。)
しかし、著者の山口さんはそのようには捉えていないようです。
なんなら、相対主義も普遍主義も、相手のことをよく理解しようとしない点において似たようなものだと述べています。
つまり、相対主義では「人それぞれ違うから」と、それ以上踏み込んで相手の考えを理解しようとしなくなります。
その一方で、普遍主義では、本来違うはずの個人をあるカテゴリーで括って同じものとして見ることで、個々人の違いに目を瞑ることになるのです。
その意味でこの二つは似ているものだと述べているのです。
そして、本書では言語学と文化人類学の研究を概観しながら、人間が「人それぞれ」というほど違っているのかについて議論しています。
本書で紹介されている細かい研究内容については割愛するので、気になる人は実際に手に取ってみてください。
それらの研究を通して考えた結果、人間はそこまで大きく違っていないというのが筆者の結論です。
例えば、ポール・エクマンは "Universal emotions" という、万国共通の7つの感情を発見しました。
また、僕たちが「これは良くない」とか「これは素晴らしい」と感じることもある程度は同じです。なので、日本で犯罪になることは大抵海外でも犯罪になります。
このように何が正しいのかを判断する「道徳感情」も文化を超えてある程度同様だということです。
当然、文化によって多少の考え方や価値観の違いは存在します。しかし、そのほとんどはお互いが理解できるレベルにとどまっています。
つまり、人間が生きていくための生物学的な機能はある程度普遍的であり、その普遍性の上に文化や個人による「人それぞれ」が成り立っている、というのが本書の主張ではないかと思っています。
3:「正しさ」はどのように作られるか
では、筆者はどのように「正しさ」を作っていくべきだと考えているのでしょうか?
本書の冒頭で、「何が正しいかなんて誰にも決められない」とか「絶対的な正しさなんて存在しない」という意見に筆者は反対しています。
その上で、その考え方では成り行かないシチュエーションがあると述べていました。
例えば、相反する意見を持った人が集まり、その中から一つの結論を導き出す必要がある際なんかがそうだと思います。
「あなたはそう思っているかもしれないけど、僕はこう思っているから」というのではダメなのです。
だから、そのような場面においては「正しさ」を作っていく必要があると筆者は述べています。
しかし、僕はどのようにしてそれが実現できるのかが読むまで想像できませんでした。
なので、読んでみてすごく納得できましたし、自分の考えを改めるべきかもしれないとすら思いました。
では、実際にどのように「正しさ」を作っていくべきだと考えられているのでしょうか。
本書を通して筆者が一貫して主張していることが、まさに「正しさは、その現象に関わる複数の人の合意を得て初めてその人たちの間で作られるもの」だということでした。
つまり、「正しさ」とは、どのように振る舞うことが道徳的に正しいのかについての共通了解だということです。
本書に出ていた例を一つ挙げてみます。
例えば、あなたが奥さんとスーパーに買い物に行ったとします。お肉を買うときにあなたは牛肉が好きだから牛肉を買おうとします。
しかし、奥さんは牛肉よりも豚肉の方が安いので、節約のためにも豚肉を買いたいと主張します。
あなたにとっては好きな牛肉を買うことが「正しい」行為かもしれませんが、奥さんにとっては節約を考えた選択をする方が「正しい」行為なのです。
ここで相反する主張が生まれたわけです。この場合、「正しさは人それぞれ」は通用しません。
なので、あなたと奥さんは話し合います。その結果、「普段は豚肉を買うことにしよう。けど、どうしても月一回は牛肉を食べたいから月末だけは牛肉を買わせてほしい」という要望に奥さんが合意したとしましょう。
その時初めて、あなたと奥さんの間で、「正しさ」が作られたことになります。
このように、正しさとは、ある出来事に関わるすべての人の共同作業によってつく荒れるものだということです。
今回は家庭内の例を取り上げましたが、これは国や社会においても同じことです。
本来社会の一員である特定の人たちの合意なしに決められたルールは不公平であり、正しいものではないということです。
僕はこれまで、このような話し合いを避けてきたように思います。
つまり、人間関係の中で相手との間に「正しさ」を作る努力をしなかったということです。
まさに筆者の言うとおり、「正しさは人それぞれ」を振り翳し、社会的生物としての責任を放棄していたように感じます。
学生の頃はそれでも良かったですが、それではいけないこともこれから出てくるかもしれません。
なので、「人それぞれ論」を都合よく振りかざすのではなく、相対主義の範囲と普遍主義の範囲をきちんと見極めて主張していこうと思いました。
4:「道徳感情」と「正しさ」を分ける必要性
ここまでで本書の骨子については紹介できたと思いますが、ここからは僕が個人的に重要だなと感じたところです。
なぜかというと、多くの人がこの二つを混同している人が多いように思うからです。
その二つというのが、道徳感情と正しさと買いてありますが、簡単にいうと、「自分が正しいと感じていること」と「実際に正しいこと」という意味です。
この二つは似ているようで実は全く別物です。ですが、実際に、自分が正しいと思っていることがあたかも誰にとっても正しいことかのように話を進める人が多いように感じます。
実際そんなことはありません。ある程度の普遍性は担保されているにしろ、やはり枝葉の部分では「人それぞれ論」になっていきます。
そこまでいくと、「何が正しいかなんて決められない」という主張が通るようになっていきます。そして、その中で誰かと関わり、その人との間で「正しさ」を作っていく際には話し合いと合意が必要なのであり、例えそれが「自分が正しいと感じていたこと」と反していたとしても、それは正しいことなのです。
5:最後に
本書は、僕がこれまでに考えていた相対主義の考え方について考え直させてくれる本でした。
また、「正しさ」を作っていく過程について、ここまで納得できたのも初めてだったかもしれません。
しかし、その一方で、人間社会において正しさを作っていくためには、話し合いや合意が必要であり、すなわちそれは他人と向き合うことが必須条件であるということを突きつけられて、少し辛くもなりました。
また、それと同時に、そんなことをしたくないから将来は社会からフェードアウトして隠居したいと言っていたことを思い出しました。
拙い文章でしたが、興味を持った方はぜひご一読ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
