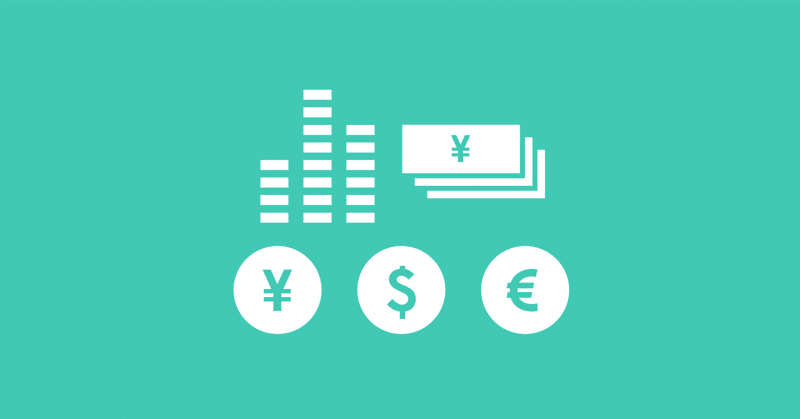
「DIE WITH ZERO」を読んで
図書館では何百人の予約待ち。
しびれを切らして父親が購入して読み終わったものが回ってきた。
この本を読み終えた父親は生前贈与の計画をはじめたらしい。
60歳を過ぎても、いいと思うものは即座に生活に取り入れるしなやかな頭を持ってるのだね、とか思う。
いったんざーっと、読んでみた。
所々気になった点に付箋を貼ったので、以下振り返りながら纏めたい。
「安全に、かつ不要な金を残さないためには、人が生きられる最長の年齢を想定すればいい」と。つまり、自分が可能な限り長寿をまっとうすることを前提に、1年当たりの消費額を決定するのだ。
言われてみればそうだと思った。
平均寿命にプラス10年としておけば十分だし、考えられるライフプランも書き出せるのであれば、年を重ねるごとに見積精度が高まっているはず。
何なら毎年ざっくり見積を繰り返すのもいいのかも。
このように、年を取ると人は金を使わなくなる。
医療費を含めてもそうなのだ、とデータを示して書かれていた。
確かに解像度の低い不安が原因で金をため込むとそんなことになるのかも。
例えば、もう85歳を超えて貯金が尽きたらその時はしょうがない、といったような腹の括り方をするのがいいかもしれない。
実際、貯金が尽きる老人は今でもそれなりにいるわけで、でも共産的なこの国は老人に手厚い。
ここ100年の人口ピラミッドを見ると、民主主義や憲法が維持される限り、この老人(票が厚い層)に手厚い方向性は変わらない。
最後の数日、数か月を生き延びるのに必要な医療費を貯めるために、人生の貴重な数年間を犠牲にしてまで働きたいと思うだろうか?
まさにその通り。
何歳かまでにお金を使い切る方針でも問題ない。
私の性格を踏まえると、それでもそれなりにお金は残ってしまうはず。
そして、仮にキャッシュがショートしてもどうにかなるのがこの国の数少ない良いところだ。
筆者が日本国籍だったらもっと主張が極端になっていただろう。
まだ健康で体力があるうちに、金を使った方がいい。
金から価値を引き出す能力は、年齢とともに低下していく
これは間違いない。
母は1人のサラリーマンとしては結構な金額を残してこの世を去ったし、父は今からの海外旅行には体力的に気が乗らないらしい(腰が耐えられないかも)。
時間は金よりもはるかに希少で有限だ。
時間をつくるために金を払う人は、収入に関係なく、人生の満足度を高めることが分かっているのだ。
異論はない。
ただ、高校生や大学生の時にもこの考えを持てるかというと話は別。
やはり、自分が金を稼ぐ側になったタイミングで、このあたりの方針も大きく変える必要がありそうだ(この辺の教育って圧倒的に不足している気がする。資産形成の教育とセットにすればいいけど、それだと金融機関がやりたがらないかな)。
あと、ちょうど今日Xで見たけど、「時間が出来事を作るのではなく、出来事が時間を作る」という一文があった。
確かに、時間という概念を自覚できるのは出来事があるときだけだ。
このあたりは出来事がありすぎて(スケジュールを埋めすぎて)、タイパの奴隷になっている人もいるので加減が大切だ。
人は終わりを意識すると、その時間を最大限に活用しようとする意欲が高まる
これも同意。
新卒で入社した会社をあと何年で退職する、と最初から線を引いていればその間に盗める技術やノウハウを必死に吸収したろうに、と思った。
純資産を「減らすポイント」を明確につくるというものだ。
これも同意。
NISAをはじめることには熱心だが、それと同じかそれ以上に大切な出口戦略を考えている日本人はどのくらいいるのか。
お金や資産を減らすという漠然とした恐怖の解像度を高めることが人生の満足度を高めるために大切。
楽天証券だと、毎月自動で商品を現金化してくれるサービスがあるし、4%ルールといったものも世の中にはある。
そういった情報を上手く取り入れて、自分だけの戦略を練る必要がある。
本自体は中盤以降失速したが、上記の内容を再考するきっかけになったので読む価値は十分あったと思う。
お父様、献本ありがとうございました。
生前贈与の議論をはじめましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
