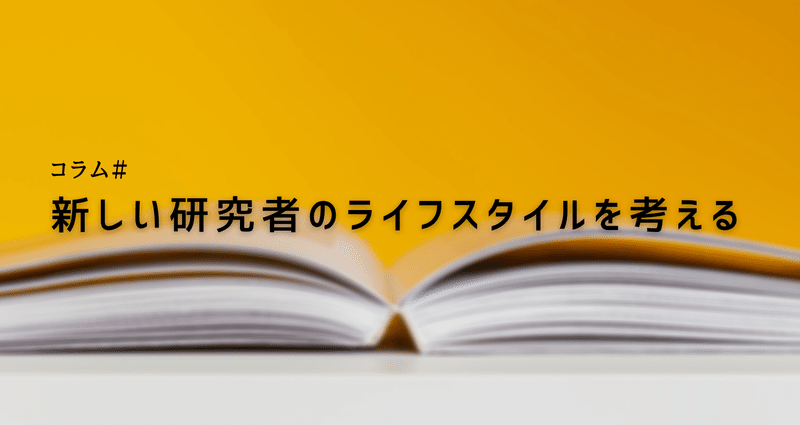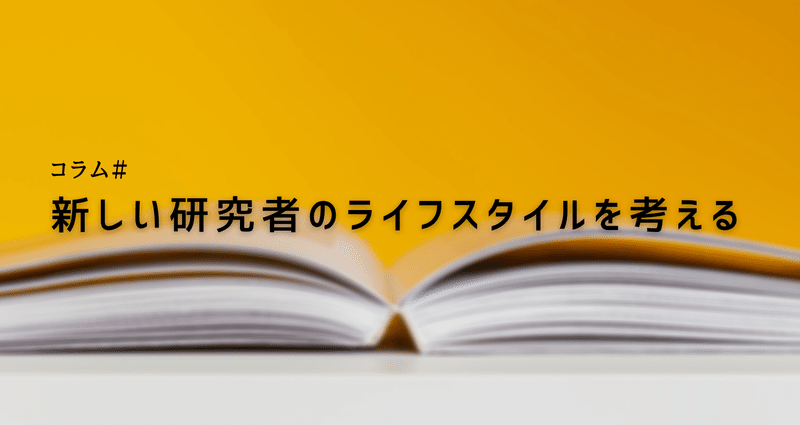コラム#6. 博士号の取りやすさ(課程博士・ラボ選び)
課程博士を無事に所定年数(修士課程を除いて通常3年)で終えられるかは、本人の能力もさることながら、学術論文必要数とラボのアクティビティーに大きく依存すると言えます。
規定年数を1年くらいなら超過してしまっても良いという方は、ざっと見積もっても400万円から1億円の損失を許容するという意味であることを理解してください。
### 1年の損失の内訳・働くのが1年遅くなる(入るはずだった1年の年収が入らず、退職金が減る。)・希望職種に就職できる可能性が50%程度減少、生涯年収