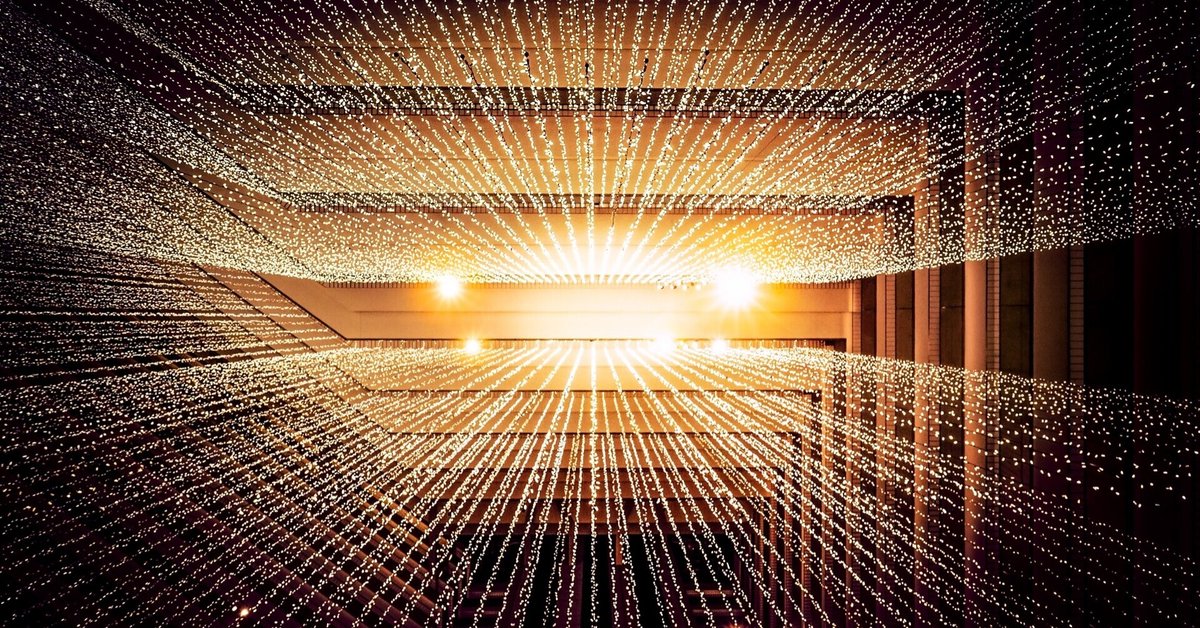
メタバース世界の存在感
NFTがメタバースと結びつくのは自然な流れなのでしょう。Facebookが社名を変更してメタバースが盛り上がる。メタバースはどこに向かうのか。
Wiredに仮想空間で活動を続けるLaTurbo Avedonの記事が掲載されていた。インタビューということだったけれど、記事はインタビュー形式ではなく、記者による所感をまとめたもののようである。
今はデジタル空間に日常までも拡張されたと思う。当初は情報を伝達するために、ネットワークが張り巡らされた。情報網の独占から情報の独占へと遷移したが、ネットワークによって繋がることの価値を疑う人は、もはや居ないだろう。
今日的な課題感を提示すると、科学、技術、経済は情報処理によって集結したが、日常の生活、人が活動する場も情報処理によって拡張され、居場所を移すと捉えても自然なことだろう。
ニコールはアヴェドンを、いまの時代のアート界を象徴する特別な存在とみなしている。さまざまな人物に扮したセルフポートレート作品で知られる写真家のシンディ・シャーマンのように、自身のアイデンティティにひねりを加える作風を採用し、それを巧みにヴァーチャル世界に持ち込んだのがアヴェドンだったのだ。
デジタルに拡張したアイデンティティを、その身体性あるいはデジタル体験を包含する。現在は、そうした世界の変化の入り口にあるのではないだろうか。
記事の中で、アヴェドンのコメントに目がいく。
ヴァーチャル空間の一部が創造よりも営利を目的としてつくられていること
フォートナイトについて言及していることと思うが、フォートナイトで運営者が目論むようなゲームの遊び方ではなく、仮想空間での過ごし方について、権利を主張したい、あるいはしているというふうに見える。
以前の発想だと、管理者が空間を把握、管理するということが通常であり、その管理下から逸脱する場合には、その空間から退場してもらうしかない。
ただ、そうした逸脱を排除していくと随分と窮屈な世界になり、ユーザーからは見捨てられるだろう。Facebookのユーザー数減少のニュースは他にも原因があるが、運営管理者だからといって神のように振る舞っていいわけではない。
運営管理者が提供するサーバーやソフトウェア、プラットフォームが正常に動作することを運用・監視するコストを誰が負担するのか。利用者のデータを知らないうちに集めて、広告を見せて、結局は利用者が負担する。こうした書き方をすると、いかにも悪の独占企業のように見えるが、利用者としても適切なサービスにマッチングしてくれていると思えば、探索コストを削減することができる。プライバシーの犠牲は必要になるけれども。
デジタル世界にも国家のようなものが起こることを予想している。
いただきましたサポートは美術館訪問や、研究のための書籍購入にあてます。
