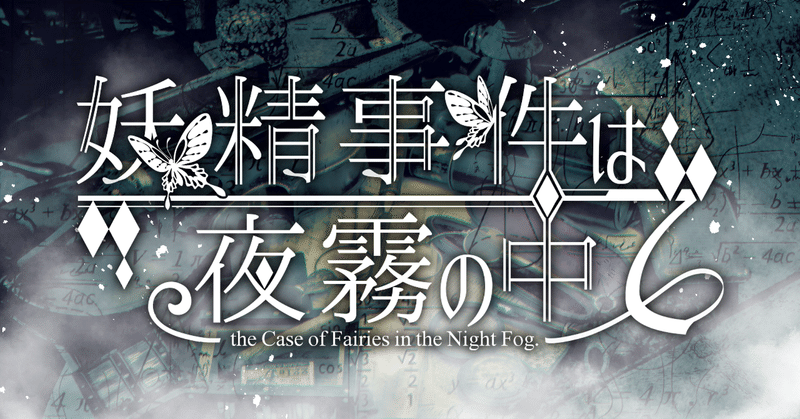
妖精事件は夜霧の中で ~【7話】【villain】悪役
【villain】悪役
彼らは物語を彩り、主役を引き立たせる重要な存在。悪役は魅力的でなければならない。
そして悪は誰にでもどこにでも存在するもの。正義よりも身近で親しく魅力的である。
意識してみなよ。ほら、今までの人生で自覚している悪を数えてごらん?
宝石都市エーデルシュタイン。またの名を犯罪都市エーデルシュタイン。
色鮮やかな輝きを放つ宝石都市とは打って変わって、裏には血と欲と憎しみが満ちている。
犯罪は数多くあり、また犯罪は常日頃から行われていた。そして、犯罪都市を作り上げ、数多の犯罪者を束ねる組織がある。
犯罪組織ヘルハウンド。
犯罪者の身元を調べると高確率で彼らは犯罪組織ヘルハウンドに所属していることがわかった。
犯罪者はなぜその組織に拘るのか?なぜ組織に加わるのか?
その答えは簡単。犯罪組織ヘルハウンド、またの名を復讐屋。
暗殺、誘拐、窃盗……その分野のプロ達が数多くの部下を連れて復讐の手伝いをしてくれる。
代償は金ではなく、残りの人生。復讐を終えたら今度は自分が誰かの復讐に手を貸し、繰り返す。
こうして犯罪組織ヘルハウンドは大規模な組織となった。
その犯罪組織が根城にしている、とある一室。ガスライトが灯る広間。
バーガンディーやボルドーなどの赤色で統一された暗い部屋。2人掛けのソファは2台あり、縁の装飾は金メッキで飾られている。
同じ金メッキの装飾をしたテーブルを両脇で囲う4人。
それぞれソファに座り、上座にある1人掛けの空のソファに、我らが主人が座ることを待つ。
「ふぁ……」
暗いマラカイトの髪にシトリンの瞳。良く言えば年季の入ったコート。悪く言えば汚らしいコートをだらし無く羽織った男はエドガー。
眠たげに目を擦りながら、あくびがを繰り返す。
手には札束を持ち、パラパラと慣れた手つきで同じ枚数を何度も何度も数えていた。
「また夜遊びであるかぁ?エドガー」
その隣に座るのはダミアン。スモーキークォーツの髪にアメジストの瞳。エドガーとは逆に豪奢なスーツを着飾っている。金の刺繍が光を反射して眩しく感じ、胡散臭さも漂う。
「昨日は監視の後暇でしたし、遊んで帰ろーと思ったんですけど〜。買った女の子が処女だったんですよね〜。高かったのに」
「処女ってだけで上玉ではないか!吾輩は好きであるぞ」
「えー?うるさいだけじゃないですかー?せっかく時間掛けて濡らしてやっているのにイヤだのなんだの……強姦よりも和姦派だから無理矢理はしませんでしたけど。途中でやめて路上に捨てればよかったなー」
あーあー。と、エドガーは首を振って肩をすくめる。
そんな残念な様子に、ダミアンも別の意味で首を振って呆れた。
「はーーー!勿体ないのう。処女は脅して犯すことこそが至高なのだぞぉ?」
「おっさん趣味悪」
「お前も歳を取ればわかる……」
「わかりたくも無いですね。……僕にとっての快楽は金を使う瞬間なので」
エドガーにとって金は命、心、人生であった。
人に値段を付けること、人を買うことが彼にとっての1番の楽しみ。そして生き甲斐。金さえあれば命も心も相手の人生だって買えるという価値観の持ち主だ。
金の使い方が派手だが、金の集め方も優秀であるため組織の金庫番を任せられている。
しかし、それはそれとして金に対しての執着は倒錯的で病的。異常だった。
エドガーはダミアンから顔を背け、避けるようにソファの手すりに寄りかかる。
なだれ込むようにそのまま横に力無く倒れ、グッタリとしたその姿勢からは、彼の育ちの悪さが見て取れた。
あくびをし、すると彼はにっこりと表情を変えて指を鳴らした。
「ま、たしかにたまにはよかったですね。半分も入っていないのに泣き喚くもんだから一気に挿れたんですけど。あは!気絶しちゃって!そこからは静かにできたからよかったですよ」
あっけからんと笑うエドガーのことを、彼の正面に座る軍人風の男が睨む。
ルビーのような赤い、赤い髪と瞳。緩く束ねられた長髪は乱れ、頭に巻かれた包帯が取れかかっている。
しかし、エドガーは気がついているのかいないのか、気にせず笑い飛ばしていた。
「……」
軍人風の男の隣で脚を組んで座るのはセシリア。妖艶で、少々下品にも思う衣装を着ている女。
彼女は手にしている扇子を広げると少し恥ずかしげに、そして興奮気味に口を開いた。
「あら、意外ですわ。エドガーに特殊性癖があったなんて」
ルベライトの髪と瞳。バーレスクのような衣装は胸元が大きく広がっており、全身過激な露出度。
「特殊性癖……って、心外です。僕はここにいる誰よりもノーマルだと思うんですけどねぇー」
わざとらしくため息を吐くエドガー。それに合わせてダミアンもまたまた呆れる。
「アブノーマルな奴ほど自分に自覚がないものだ」
ダミアンがそう言ったその時、軍人風の男が舌打ちと共に小さく、ひり潰すような声で呟いた。
「聞くに堪えない……下劣なカス共が……」
その声にダミアンが鼻で笑う。
「ほら、あいつとか」
「私をお前らと一緒にするな」
ギラついた目で嘲笑った男の方を睨む。彼の名前はフェルナンド。
イライラしているのか彼は膝に肘を付き、両手で顔を覆う。隙間から見える血のように赤い瞳の様子から、今の彼は危険だとダミアンとエドガーは悟った。
しかし、他とズレているセシリアは構わずに続ける。
「ああん。そんなことを言ってぇ……仲間なんですから、もっと友好的にはなれませんの?」
「お前らを仲間だと思ったことはない」
「まぁ酷いですこと」
そこでやっと、今の彼は最高に面倒臭い男なのだとセシリアも悟った。
「そういえば昨日はアタクシも久々に美少年をいただきましたわ。ふふ、精通前ですって!声変わりもまだのようでしたし、それはそれはぁ……鳴き声が可愛らしくてついつい……絞り過ぎて。いつの間にか死んでましたのよ。ああん、もったいない」
残念そうに。しかし口元は緩み、昨日の出来事に想いを馳せているのか愉快そうに笑っていた。
「うわ、怖いおばさんに童貞喰われて死ぬとか!ショック死だったんじゃないですか?」
「失礼ね!アタクシは若いわよ!」
エドガーの言葉に対して瞬時に返す。彼女にとって若さは宝石のようなものであり、老いは道端の石ころのようなもの。
「セシリア、その美容の秘訣は?」
ダミアンの疑問にわざとらしく首を傾げ、考える素振りをする。
うっとりとした表情で、淫らな光景を思い出しながら恍惚の笑みをこぼした。
「そぉうねぇ……毎日、美少年の赤い血と白いミルクを浴びているからかしらぁ?飲むのも塗りたくるのもツヤツヤになるんですのよ」
「僕から2メートル以内に近づかないでくださいね」
「聞くものではなかったな」
セシリアの回答は期待されたものではなかったが、内容を聞いたダミアンとエドガーは顔を引き攣らせた。
美貌を保つ為に血を浴びるという迷信は聞く。しかし、本当に効果があるのかは謎。
それと同時に若者の精子を浴びるということも。ただの彼女の嗜好の問題なのか、それとも本当に迷信を信じているのか。
前者の可能性が限り無く近い。彼女は何よりも、淫らな行為を好む。老若男女構わず抱いて抱かれているが、やはり1番の好みは美少年とのこと。
粟の匂いが漂いそうな話題を掻き消すかのように、エドガーはダミアンへと話題を切り替えた。
「ダミアンさんは良いですよね〜。ヤればヤるほどお金が貯まるんですから」
「窮地に立たされた女性は本当に脆い。すこーし優しくすれば簡単に手に入るものだからのう?」
テーブルに置かれたティーカップを手にし、口をつける。
「表では善人のフリして……」
「借金を背負う様なことをする方が悪い。騙される方が悪いのだ」
「あはっ!良いですねぇ……好きな考え方ですよ」
ダミアンは一流の美術鑑定士であり、オークショニア。
彼が本物だと言えば本物に成り、偽物だと言えば偽物に成る。彼が鑑定した物だから価値があるというもの。
一流だからこそ偽物が解り、本物が解る。
その審美眼を生かし、裏では芸術家の卵を騙して本物そっくりの贋作を描かせているとか。
彼自身も美術品のコレクターであり、狙った獲物は必ず手に入れるのが信条。
それが、物でも女でも。
「吾輩も先日惜しい女性を亡くしたのだよ」
「それはそれはご愁傷様」
その女性も、きっとコレクションの1つ。
彼のやり方は詐欺師として巧妙だった。
たった1人の、その女性がどんなに地位も家庭も、備わった技能も普通であっても、手に入れるために規模と時間と費用は厭わない。
違和感無く、忍び込み、檻へ誘う。気がついたそのときには多額の借金を背負うことになり、彼に頼らないと生きていけない状況へと変わり果てる。
「胸も尻もでかくてな、元娼婦だったのだ。そのため夜迦は申し分無かったのだが……首を吊って死んでいた」
「へぇ、勿体ないですね」
「ああ、勿体無いことをした。なんせ、あとは売れば金にはなるだろうと思うてたのに。美人薄命とはこのことだな……」
「ちょっと違うと思いますね」
はぁー。と深いため息を吐く。
その心情は決して憐れみでは無く、"もったいない"というもの。
壊れたらまた新しいモノを用意すれば良いとすぐに切り替わるが、美術品とは違い、同じ女は用意できない。
「ま、美人の死体を好む物好きもおる。そっちの界隈に買い手がいたものだから金にはなったが」
再びため息。それほどまでに手放すには惜しかったということ。
「はー。みんな人を殺しすぎですよ。こわいなぁ」
エドガーは他人事のように手をひらひらと振って苦笑った。
この場にキレイな者などいない。
それがお互いにわかるから、エドガーのその言葉の意味はふざけているように思えた。
「そういうアナタはどうなのよ」
「僕、人殺すの苦手なので。代わりにアリスが撃ち殺してくれますし?僕はなーんもしませんよ」
アリス。エドガーの部下にあたる少女。
盲目でありながらも天才的な射撃能力を持つ。例え視線が合わなくても。例え音が無くても。そこに彼女の獲物がいるのならば、決して弾からは逃れられない。
「部下といえど、幼女に任せているのは」
「悪いお兄さんね」
「なんとでも言ってくださーい。僕はこれでも止めましたよ。彼女がどーしてもって言うものですから」
エドガーは首を振ってやれやれとわざとらしい素振りをしたが、その様子を見てダミアンは忠告をするように言った。
「アリスのお兄様に気をつけるのだぞ?」
「っは!?」
その言葉にエドガーは起き上がる。自分達以外に誰もいない部屋なのはわかっているが、それでも周りを見渡して警戒をしてしまう。
アリスの兄。その存在は最凶最悪。この場にいるだれもが彼とはあまり関わりたく無いと思っている人物。
しかし、彼はこの組織で重要な立場であるため、彼を避けることはできない。
「貴様ら、今日はやけにおしゃべりだな」
頭を抱えたフェルナンドが口を開く。それまではずっと黙っていたが、彼ら3人がずっと話をしていることに少しだけ違和感があった。
「むむぅ〜?フェルナンドも混ざりたいのかぁ〜?」
「バカを言え」
「その……アレよ。あのお方がアタクシ達に話があるって」
あのお方。犯罪組織ヘルハウンドのトップ。
その人自らが改めて自分達に話があると、急遽招集があった。
「あのお方の姿を拝め、お声を聞けるだぞ?」
「いやいやいや!こっちは緊張しているんですって!」
「緊張……?」
彼らが饒舌になっていた訳は緊張からだったらしい。
あのお方といる時間が多いフェルナンドのみ、その感覚はわからないままだったが、3人にとって今日は久々に会うとのことだった。
「最後に会ったのはー……確か、2ヶ月前だったような気がするのだ。異国の行商人から買い付けた"湯呑み"は気に入ってくださるだろうか……」
「あのお方はそんな物に興味は無い」
「アタクシは3ヶ月前……イヤン!お化粧は崩れていないかしら!?」
「あのお方はそんなところを見ない」
「23万、24万、25万、26万、にじゅう……ダメだ数えられない!不安になってきた」
「貴様は黙れ」
この場に集まる4人は犯罪組織ヘルハウンドの幹部。
緊張如きで心を乱されているなんて、フェルナンドは聞いて呆れた。
「静かに待つこともできんのか貴様ら。話題も話題だ。下品極まりない……」
「おーおー出た出た。フェルナンドの堅物アピール」
「ああ言って絶対すごくムッツリですよねぇ」
「逆に、どういう癖をお持ちなのか気になりますわぁ」
フェルナンドは舌打ちをする。
しかし、その下劣な会話が途切れるのも近かった。
ガチャ……
開かれる扉。小さな少年が堂々と、優雅に、パールのような長髪を靡かせながら歩く。
「金髪に、緑眼の少女。彼はとても一途だよ。ね、フェルナンド」
「ヴィンセント様」
フレームレスの眼鏡越しに、アクアマリンの瞳。
フリルが多く使われ、高級そうなケープマントには金の刺繍が施されていた。
少年らしさがわかる、ショートパンツから伸びた脚。肉付きは成熟していない子ども。
白タイツに包まれて、それはより一層映える。
「ごめんね。待たせちゃったかな」
「とんでもございませんわ!」
「御足労、感謝致しますぞ!」
「あわわわ」
4人はソファから立ち上がり、一斉に傅く。
「お久しぶりです。ヴィンセント様」
「うん。みんな元気そうだね。……フェルナンドは1週間振りかな?」
ヴィンセント・ライサンダー。
犯罪組織ヘルハウンドの総統。しかし、その姿を知る者は組織の中でも限られている。
その理由は容姿。
小学生の男の子と同じくらいの背丈、幼さ、声変わり前の声、女の子と見間違えられても文句は言えないほどの美少年。
普通に考えておかしい。明らかに幹部4人よりも遥かに歳下である。
「君がいない1週間はとても長く感じたよ。いつもより子ども扱いが多い……。ま、当たり前なんだけどね。この姿は好きだけど、なかなか不便も多い」
トップの正体を知る者が少なければ少ないほど、足が着くリスクは低くなる。
そしてなにより、自分が所属する総統が子供だったなんて誰が想像するか。
「でも、この姿の方が得することの方が多いんだよねー。みんな警戒心が薄くなって、私に優しいんだぁ!みんなもほら!堅苦しいのは嫌いだからさ。座って?」
ヴィンセントがニコニコと笑いながら上座へ座る。脚を組む動作、白タイツがやけに官能的で、美少年好きのセシリアの視線を釘付けにした。
「ああんっ、ご褒美ぃ」
何か小さな呻き声、または嬌声か。セシリアのだだ漏れている欲望は部屋にいる全員に聞こえていた。
「今日、みんなに集まってもらったのはもちろん大事なお話があるってことなんだけども……久々にみんなの顔が見たくなってね」
そう言い、4人の顔をまじまじと眺める。最初に目が合ったダミアンへ微笑みかけると、嬉しそうに口を開いた。
「ダミアン、君は先月、大きなオークションを開いたんだってね?7カラットの妖精石を見つけたとか」
ディアマントロード達と同じく、犯罪組織ヘルハウンドもまた妖精石の回収をしている。
妖精石に秘められた力を利用するため。そして、妖精石を人の手で作るために研究をしている。
ダミアンが定期的にオークションを行うのも、妖精石の捜索と回収のため。
しかし、ダミアンは何か言い難いことがあるのか、目が泳いでいた。
「は、ははーっ!実はその……妖精石では無かったので……」
「ああ、そうなの?そっかぁ残念」
「申し訳ございません!」
ダミアンが深く頭を下げる。この場にいる中では最年長。60代後半である彼が、10代前半の男の子に頭を下げている姿なんて滑稽だった。
「ふふ、別に気にしていないよ?ただでさえ妖精石と宝石はわからないんだ。……キミのその頑張りだけで私は嬉しいよ」
「う、うううヴィンセントさま゛」
優しい顔でダミアンに話しかける姿は正に聖人そのもののようにも思える。
「セシリア」
「ハッ、ハイ!」
「今日も美しいね。久しぶりに感じるからかな?いや……ああ、そうか。化粧を変えたんだね。似合っているよ」
「はぁあんっ!ありがとうございますぅ!」
美少年の天使のような微笑みに胸を射抜かれたセシリアは絶頂と言わんばかりにガクガクと体を震わせていた。
「エドガー。やっぱり君に金庫番を任せて正解だね。去年よりもほぼ倍になっている」
「ぼ、僕に掛かればこんなの余裕ですよ」
「うん。これからもよろしくね」
余裕ぶるエドガーだったが、やはり彼の笑顔が眩しくて思わず胸を押さえる。
そしてヴィンセントの視線はフェルナンドへ向けられた。
「フェルナンド」
「はっ」
「私がいない間に妖精保護機関の研究員を捕まえたそうだね。で?なにか素敵なお茶会はできたのかな?」
「いえ。情報は何もありませんでした」
お茶会。ヴィンセントはそう例えたが、実際には拷問の話だった。
フェルナンドは幹部の中でも殺人、拷問に長けている。元軍人であるため人の殺し方と拷問には慣れており、それはもはや彼の特技だった。
しかし、彼は人を痛めつけることに悦びがある。悲鳴に心を震わせ、許しを乞う姿には胸が躍り、恐怖する顔には欲情さえした。
彼にとって殺人は天職であり、拷問は最高の娯楽。
「そう。まぁ君が楽しめたのなら良いよ。目的が無いお茶会はリラックスができて心が穏やかになるからね」
それはきっとそういう意味。
「君にとって、有意義な1週間だったみたいでよかったよ」
幼い彼は穏やかな顔で笑う。聖人のように、優しい表情は誰にとっても心が揺さぶられるモノ。
「はい!じゃあ本題に入ろうか」
ヴィンセントはパァッと明るい顔で場の雰囲気を切り替えるように手を叩いた。
「エドガーが昨日、素敵な報告をくれてね」
そう言い、ヴィンセントは紙を1枚取り出す。テーブルの上に差し出されたのは報告結果の書類だった。
「皆には試作品のデザイアを渡しただろう?これはエドガーが書いたその報告書」
エドガーの筆跡は綺麗で丁寧なもので、とてもガサツでめんどくさがりなエドガーが書いたとは思えない字。読みやすく、言葉遣いも丁寧だったが、今回はそこはどうでもよかった。
「ほら、フェルナンド。ここ」
ヴィンセントは書類に指で丸を描く。
くるりと、描かれた中の文章をフェルナンドは読んで、表情を変えた。
「こ……れは……」
「シャロンが見つかったよ」
「!!」
その途端、フェルナンドの目つきが変わる。見開き、撃たれたかのような衝撃。
「っ……は……」
息が詰まる。心臓が破裂しそうな高まりを、彼は感じていた。
「なぜ」
「ん。え……?ええっ!?」
間髪入れずに、銃声。
エドガーの頭スレスレを通過した弾は壁に小さな穴を開けていた。
憎しみを込めた眼光。ただでさえ目つきが悪く、ギョロリとした瞳はエドガーを捕らえている。
腕を伸ばし、銃を構えた手。フェルナンドは至近距離でエドガーの頭を狙っていた。
「なんで僕怒られているんですか!?あれ!?」
「うーん難しいなぁ。喜んでもらえると思ったんだけど」
おっかしーなぁ。と、銃口を向けられて命の危機に陥っているエドガーなぞ気にせず、ヴィンセントは首を傾げている。
「ね、ね。フェルナンド。エドガーだって故意で彼女を見つけた訳じゃないんだ。それに……」
そして彼は、いつものように穏やかに笑う。
「彼女はまだ私達に気付いていない。……わかるかい?」
「私が……シャロンを……」
「そういうこと!よくできました!フェルナンドは偉いねぇー」
フェルナンドは理解をすると銃を下ろして懐にしまった。
解放されたエドガーは肩を下ろし、大きな深呼吸をする。
「あ、そうそう。念のためみんなにも彼女のことを共有するよ」
そう言ってヴィンセントはシャロンの写真を取り出しテーブルへ置こうとした。が。
それを見て、フェルナンドは目にも止まらぬ速さで写真を奪い取る。
「あ」
「いけませんヴィンセント様ぁああ゛あ゛あ゛!!」
それが愛する主人であったとしても、彼の愛は止まらない。……のだろう?
「彼女を……シャロンがこんな下衆な奴らの目に触れるなんて私は……っ!私はぁああ゛あ゛!!」
1人勝手に嘆き、苦しみながらも写真はしっかりと自分の懐へと忍ばせた。
その動作を見てセシリアは興味津々にフェルナンドの身体をつつく。しかし――
「ああん。写真ぐらい見てもよろしいじゃないの?その、シャロ――ひっ!?」
「貴様がその名を口にするな」
銃口は再び、今度はセシリアへと向けられる。相手が女でも容赦無く、眉間に。
「ちょ、ちょちょちょっとぉ!ふ、ふふふ。ジョーダンよぉ〜」
冗談の通じなさ、あまりにも極端で異常だった。思わず顔が引き攣る。
彼にとって人類は自分か、ヴィンセントか、そして愛しのシャロンとその他しかいない。
「わかったよ、フェルナンド。じゃあ、キミが率先してシャロンを捕まえに……いや、取り戻してきて欲しい」
このままじゃ仲間を殺しかね無い。彼なら本当にそうする、と思ったヴィンセントは彼に命じた。
セシリアから銃を外し、懐へとしまう。ホッとしたセシリアはすぐにフェルナンドから離れた。
「承知致しました」
フェルナンドは膝をつき、深く傅く。
そして、肩を震わせながら笑い始めたのだった。
「ふ、ふふ……ククククク……ハーッハッハッハッハッハッ!!ッハァッ……!」
ゆらり。ゆっくりと立ち上がり、震える拳を握りしめる。
「ついに、ついにこのときが……!ああ、11年だ……やっと彼女に、シャロンに会える!触れる!抱ける!口付けも!最後に会ったのは5歳……ということは今はじ、じゅうろっ……!?ああっ……!?ああ、ああっ……!!」
「うわ」
フェルナンドは懐に忍ばせたシャロンの写真を見て興奮のあまり吐きそうになる。
長年、幹部を務めている4人。フェルナンドはその中でもいつも堅苦しく、他人にも自分にも厳しいストイックな殺人鬼……という印象だったが、初めて見るその表情は、大変なインパクトを与えた。
「ッハァ……ハァ、これが……大人になったシャロン!その真実だけで我が官能がっ……疼く……!つまりは初潮も来ている……だと!?シャロンと子作りがっ……?」
他の幹部3人はなんだか見てはいけないものを見たような気がして目を背ける。一方、ヴィンセントはいつものことかと言うように、ニッコリと微笑んで頷いていた。
「ク……ククク……そうか。そうか!私がいない間に立派な女になって……私のために子供を産む準備もしているとは……愛しい……!愛しすぎる!!こ、こうしてはいられん、今すぐにシャロンの純潔は私があっ!!我が精を注ぎ子を成そうではないかァッ!!」
「こらこらこらフェルナンド。だめだよ。そんなぐいぐい来られたら久しぶりのシャロンもびっくりしちゃうから。まずは……ね?少しずつ、彼女を迎える準備をしようか」
激しく興奮するフェルナンドであったが、ヴィンセントに落ち着くようにと宥められる。主人の命令と言えどすぐ熱が収まるわけがなかった。身も心も。
「あんな顔のフェルナンドさん、拷問以外で初めて見た」
「やはりおっさんが処女好きというのは常識なのだな」
「あんなにアタクシ達のことを下品だの言っておいて……どの口ですわ」
ニヤニヤ顔が止まらないフェルナンドを見て、3人は唖然とする。
同僚の意外な姿を……いや、本性を初めて見たのであった。
全話はマガジンから読めます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
