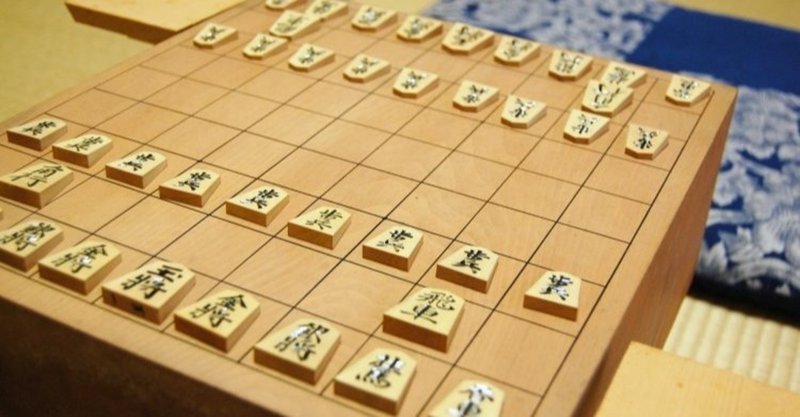
将棋における「詰み」の定義について
はじめに
詰将棋の作品に「最後の審判」という題名のものがあります。
この作品は、現行の将棋のルールに不備があるのではないかという問題提起のために作られたものです。
この作品に接して、将棋のルールについて考えました。
その結果、将棋における「詰み」をどのように定義するのが最も適切であるか、ということについて1つのアイデアを思いつきました。
それを発表しようというのがこの記事の趣旨です。
まず、「反則手」のうちいくつかのものを定義する
「詰み」を定義するためには、まず「反則手」(この手を指すと負けとなる手)のうちいくつかのものを定義する必要があると考えます。
ただし、「打ち歩詰め」はここでは定義せず、次の段階で定義することにします。
定義する必要のある「反則手」(「打ち歩詰め」以外)は次の通りです。
・2手続けて指す
・ルール上移動できない位置に駒を移動する(例えば、銀を横に移動する、他の駒を飛び越える、自分の駒がいるマスに移動する)
・成り駒を打つ(持ち駒を裏返して打つ)
・二歩
・歩、香、桂を行き先のない状態にする
・王手をされた後、玉を動かすことも、合駒 をすることも、王手をかけた相手の駒を取ることもしない
・玉を相手の駒の利きに移動する
・玉以外の駒を移動させた結果、玉が相手の駒(香、角(馬)、飛(龍))の利きにさらされるようにする
・王手をかけた結果、連続王手の千日手を成立させる
それぞれの反則手の定義は、従来運用されてきたルールにおける定義と変える必要はないので、ここで述べる必要はないと思います。
次に、「打ち歩詰め」を定義する
次に、「打ち歩詰め」を定義します。
ここまで読んでいただいた方の中には、「『打ち歩詰め』は歩を打って相手を『詰み』にすることだから、先に『詰み』を定義するべきではないのか」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「詰み」を定義するには、「打ち歩詰め」を定義する必要があるのです。
なぜかというと、相手を「打ち歩詰め」にする以外に王手を回避することができない場合は「詰み」であるという運用がなされているからです。これは詰将棋にもそういう作品がありますし、実戦でもそうだと思います(実戦でそういう例が過去にあったかどうかは知りません)。
「打ち歩詰め」より先に「詰み」を定義しようとすると、次のような状態に陥ります。
・「打ち歩詰め」を定義するためには「詰み」を定義する必要がある。
・「詰み」を定義するためには「打ち歩詰め」を定義する必要がある。
これは無限ループであって、いつまでたっても定義が完了しません。
さて、ここでは次のように打ち歩詰めを定義します。
打ち歩詰めとは、歩を打って王手をかけた結果、次に相手がどのように指してもそれが反則手(この段階では反則手に「打ち歩詰め」は含まれていない)となる状態のことをいう。
至ってシンプルです。ここでは「王手の回避うんぬん」という言葉を使う必要はないのです。なぜなら王手を回避しない手は反則手であることがすでに定義されているからです。
以上のように定義した後、これを反則手のリストに加えます。
なお、このように「打ち歩詰め」を定義してそれを反則手にすると、「最後の審判」の60手目に玉方が「5六歩」と打つことはできないことになります。よって、「最後の審判」は詰将棋として成立していることになります。
最後に、「詰み」を定義する
上のように「打ち歩詰め」を定義してそれを反則手のリストに加えてしまえば、「詰み」を定義するのは簡単です。
詰みとは、王手をかけられていて、かつ自分が次にどのように指してもそれが反則手となる状態のことをいう。
当然、ここでの反則手には「打ち歩詰め」も含まれます。
おわりに
以上述べたように「詰み」を定義することのメリットは
・シンプルである。
・ルールの不備と指摘されたものが解消される。
・これまでにおこなわれた対局の勝敗をくつがえすことはない。
・これまでに作られた詰将棋が作品として成立しているかどうかをくつがえすことはない。
ということだと思います。
何かご意見やご質問がありましたら
plainsboro.nj08536_at_gmail.com(_at_を@に変えてください)
までメールしていただければ幸いです。
参考ウェブサイト:
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
