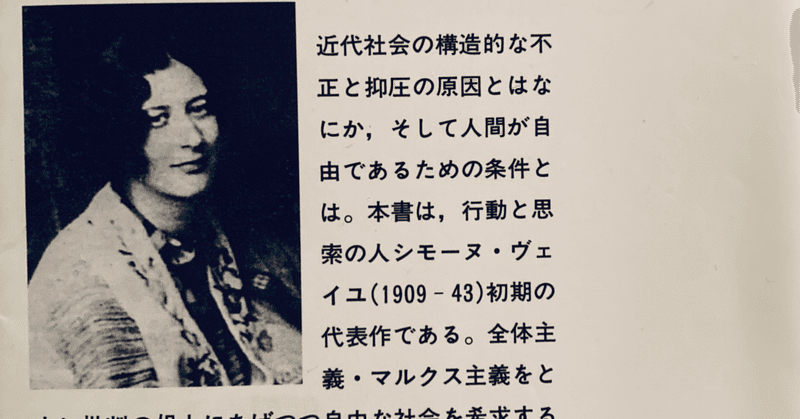
自由と社会的抑圧
"かかる道程に踏みだす人間は、まちがいなく精神的孤独と周囲の無理解を覚悟せねばならず、確実に既存秩序の敵対者からも奉仕者からも敵意を招くだろう。"1934年発刊の本書は全盛のマルクス主義の限界を指摘し、同時に台頭しつつあったファシズムにも鋭い批判を加えた著者、若干25歳で書いた先を見通した論集。
個人的には『行動と思索の人』として第二次世界大戦を駆け抜き若くして夭折した著者の本は未読であったので初めて手にとりました。
さて、そんな本書は冒頭にスピノザの『人間にかかわる事象においては、笑わず、泣かず、憤らず、ただ理解せよ』の紹介から始まり、スターリンの独裁、ナチスの台頭、ニューヨークでの株の暴落と暗雲たちこめる時代に、当時期待を寄せられていたマルクス主義を『世界同時革命の困難さ』と『生産量の際限なき増加の不確かさを根拠にしている』と非難し【ロシア革命は宗教的幻想であり失敗】とバッサリ断じつつ、あるべき自由な社会の構想を若者らしい熱情を込めながら書いているわけですが。
当時の時代的情勢を考えると【大胆かつ無謀】であったことを踏まえつつも、また荒削りであったとしても若干25歳の女性がここまで【普遍的な自由と抑圧の問題】を勇気をもって思索できるのか!とその早熟さにやはり驚かされました。
また『労働が隷従に、金銭を恩恵に思えてくるものだ』と労働者が受動的に、また結果として指導者層すら同じようになっていると現状を分析した上で『史上に例のない"全体主義的"体制が出現したとしても驚かない』との指摘は、当時のファシズム予見としても驚嘆する他ないが、アフターコロナ、withコロナの時代に【これから起きる事も予見しているように】私には感じられました。
第二次世界大戦前のマルクス批判研究の一冊として、また例え孤立しても自分の考え、生き方を貫いた女性として興味ある方にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
