
聖ニコラウスの日
引用から入ろう
近所に住んでいた貧しい三姉妹の長女が、結婚したくても出来ず、自分の身を売って妹たちとの生活を守っていることを知ったニコラウス。ニコラウスは真夜中に三姉妹の家を訪れ、屋根の上にある煙突から金貨を投げ入れました。このとき暖炉には靴下が干されており、金貨は靴下の中に入ってしまう…。も、翌朝靴下の中の金貨に気付いた長女は、この金貨が元となり、娼婦をやめ結婚できることになりました。
ニコラウスの伝説が、サンタクロースの逸話の元となった。
だから、この日をサンタクロースデーという。
聖ニコラスは姉妹の家庭を救い続け、自分が金貨を与えていることは決して口外しませんでした、また、事情を知る周囲にも黙秘をお願いしていたそう。

志賀直哉の「小僧の神様」では、寿司を食べたい仙吉に、秤り売りが、内緒で恵むという小説である。ここにニコラウスと同じような構造の”贈与”をみることができる。というのも、ことさらに秤り売りは姿を隠そうとするからだ。
ところで、モースはいわゆる贈与という社会・経済的な活動が、社会制度を活性化すると説く。
一方で、資本主義経済はいわゆる等価値なものとみなされる交換によって成り立っている。中沢新一は、この資本主義が生まれた構造をキリスト教の三位一体の構造からきていると指摘している。マックス・ウェーバーが暴いたように、富の蓄積をイタリアでうまれた複式簿記(ケネーの経済表のように)にならって図式化したものが、資本主義であり、そしてそれは、神の技を人間が実践とするプロテスタントの精神がそこにみられるというわけである。フランスやイタリアなどのカトリックでは、しかし重農主義にとどまり、イギリス、アメリカなどのプロテスタントの国で資本主義が発展したことにウェーバーの視点がある。
モースの贈与に戻ると、この資本主義の交換の仕組みが経済を回すのであるが、そのモチベーション(動機)自体は、贈与であるというのである。Take(搾取)でなくGive(贈与)であるということだが、ここで、行き詰まる。つまりは、見返りを求める贈与が経済を回す原動力であれば、その交換行為は、搾取と区別がつかなくなって動機が霧散してしまうからである。
たしかに、金は天下の周りものというけれど、資本主義の交換原理においては、コトがモノから切り離されてしまうのである。そうしないと交換可能でなくなるのである。もはや交換には動機そのものを宿していないのだ。モノに人と人とのつながりを求めたものが贈与であれば、交換はそのつながりが去勢されて、記号化しないと交換経済は成り立たなくなってしまっている。
重農主義を唱えた外科医ケネーは、血液の循環を社会活動に拡張し、交換価値に富の源泉はなく、農業というか土地がその源泉があると説いた。ここで、資本主義経済が、フィジオクラシー(重農主義)かマーカンティリズム(重商主義)のいずれかの論争が出てきて、マルクスまで受け継がれていくのである。
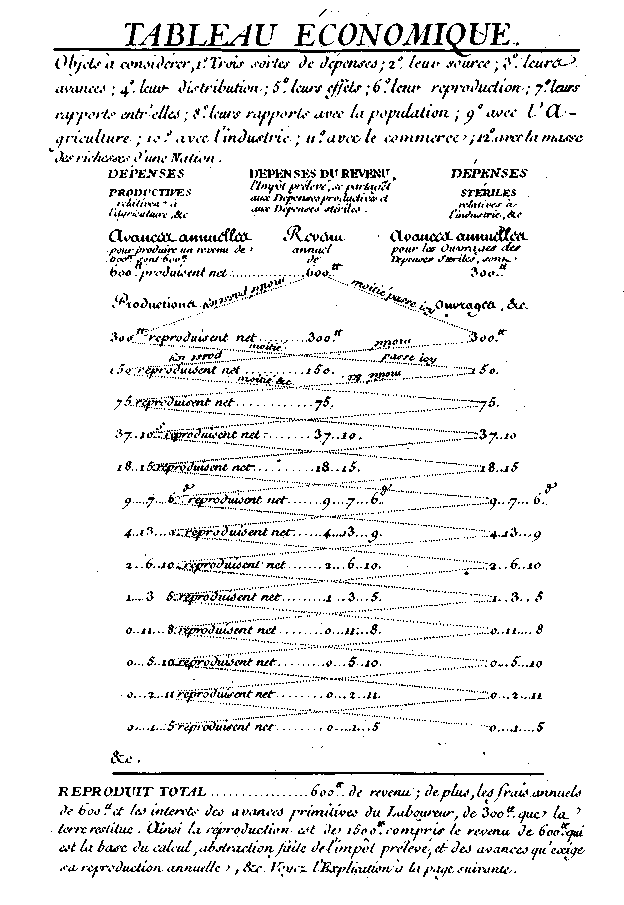
贈与か搾取かという論争はこの地平にいるかぎりは、しかし源泉が欠如している。ニコラウスや、小僧の神様のような、見返りを求めない贈与(=源泉)がないと、そもそも贈与も交換も活動できないのである。重農主義によって土地を囲い込んでも、重商主義によって植民地を支配しても、いずれは枯井戸になってしまうからである。こうした源泉には純粋贈与があるのだ。
ジャック・ラカンは、ボロメオの結び目の構造で説明して説いた。話を少しつまむと、贈与を想像界、交換が象徴界、そして純粋贈与を現実界を与えるのである。これは、三位一体の構造からでてきたことである。子である想像界と父である象徴界、そして聖霊にあたる現実界。詳しくはラカンについて語ることでこのnoteでも次第に明らかにしていこうと思う。
おそらく、人間の考えてきたアイデアの源泉となっているのが、実は富の記号化・非物質化である。富の現実から、債権化することにより、バーチャルに近づく。いわば余剰の富が富を生むということであるが、ここで、源泉に対する意識の欠如に注意しなくてはならないのである。
与えよさらば与えられん(Date et dabitur vobis.)はルカによる福音書の第6章に出てくる言葉である。私も経営の師匠からそう教わった。自分がしてほしいと思うことを、まずは、自分から人に先にするのが、サービス業の本分だというわけである。本分を間違えてテイクを考えてはいけないというのである。そして神の見えざる手が働いて、富が回り回って自分のところにやってくるというのである。
公共サービスの話か何かを、自由競争を影で支える原理にとりいれたのかしらんと思ってみたものの、しかし私はなにか構造的な欠如を感じていた。
たしかに等価交換では人は満足しない、しかしそれ以上のものを与えたとしても、富が生まれるかどうかはやはりなんとも言えない。
ニコラウスを思い出して、さらにラカンを思い出して、欠如の原因が思い当たったのである。それこそが、純粋贈与だ。大地を始めとする原初からのエネルギーとしての純粋贈与を考えないと、ピースが埋らないかったのである。
キリストが冬に生まれたとは聖書のどこにも書いてないということである。祝祭の祭りが冬に行われるのは神からの純粋贈与に対する自然の感謝ということなのかもしれない。
この純粋贈与の視点を無視すると必ずしっぺかえしをくらう。それは自然を大事にとかいう表層でなく、人間の精神そのものをもつらぬく、根源的なまなざしとならなければならない。
------------------------------------------------
<来年の宿題>
・ラカンと経済について
------------------------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
