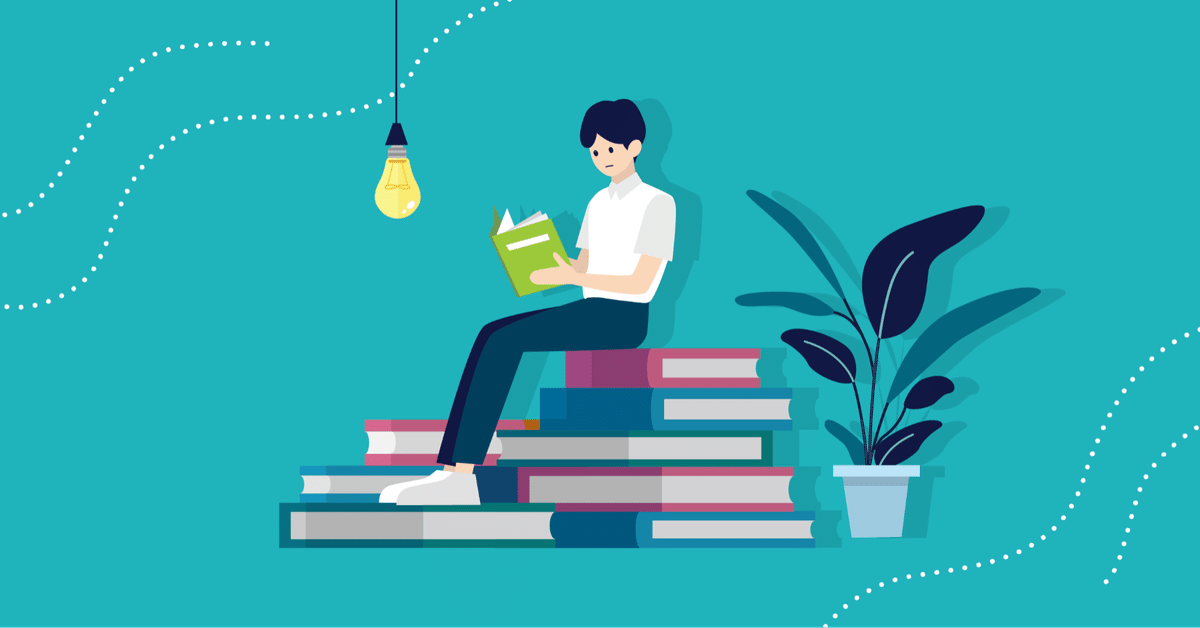
国家総合職の「教養科目」を独学3ヶ月で乗り切る話
教養の立ち位置
独学で国家総合職の専門区分を受験する上で、教養にまできちんと手を回せる人はほとんどいないと思います。僕の周りでは「教養はロト6」とか「対策するより徳をつめ」とか言われていて、流石にノータッチは厳しいながらもほとんど勉強しないのが一般的だと思います。
配点も2/15しかなく、一次試験でとるべき点数も5割ぐらいで大丈夫なので最低限のことをやるだけでいいと思います。実際僕は23/40で別にいい点数ではありませんでしたので、独学で時間もない人の最低限の対策だと思ってこの先を読んでください。
対策すべき問題
教養で出題される問題とそれに対する僕のイメージは以下の通りです。
1、国語読解:4問→一般的な大学生なら3問は正解できる
2、英語読解:7問→英語が得意なら満点、苦手な人はとても難しい
3、判断推理:7問→勉強しないと完全に無理
4、数的推理:7問→受験時代のちょいむず数学
5、資料読解:2問→たまに計算がめんどくさいが行ける
6、時事問題:3問→速攻の時事で気休めの対策
7、自然科学:3問→懐かしさに浸るが無理
8、人文科学:4問→地理は行ける、他は厳しい
9、社会科学:3問→憲法と政治は専門の知識で戦える
以上のようなイメージの中で、僕がしっかり勉強したのが判断推理と数的推理、時事問題で、読解は過去問を使って国語と英語11問を50分1セットで3年分くらいやりました。
知識問題はほぼやらない
3ヶ月で合格するには、上のリストでいう7、8、9に時間を割いている場合ではありません。ここは世界史全範囲から1問とか、物理全範囲から1問、みたいに圧倒的に勉強させる気のない出題の仕方なので、コスパが悪すぎます。
ただ全くのノータッチだったかと言えば、そうでもないです。試験の3日前から自信のある科目(地理、憲法関連、政治関連)だけ過去問集に載ってる問題を一通り(目で見て)解きました。また、思想問題もわかるときはわかりそうだったので、試験の前日に本屋さんに行ってスー過去の「人文科学」を立ち読みして、山を貼ったら本番で1問取れました。30分、1時間の勉強が意外と救ってくれます。
かける時間のイメージ
判断推理・数的推理:1日30分〜1時間、時間がある時は2時間
時事:バイトの休憩中と電車の移動中に速攻の時事を読む。トイレで日経新聞を読む。
その他:気が向いたときに1時間、他の勉強をしたくない時になんとなく1時間、という具合で過去問を解く。
専門試験と比べても「片手間でやる」というイメージですね。数的(判断推理と数的推理の総称らしい)はこのペースで3ヶ月やりました。
読解問題の対策
時間を縮めたら数的に割ける時間が増えるので、11問50分で解く練習をしました。時間をかけられないので、3年分くらいやれば十分だと思います。
こればかりは、英語が得意だったので書けることがありません。ただ解いて、解答を読むだけです。練習で解いた英語の問題はほとんど間違えなかったのですが、本番はいくつか間違えました。。得意な人ほど本番で足元救われないよう注意してください!
また、英語が苦手な人も時間がないなら「1から単語を詰めて」なんてのは辞めましょう。高校で習った英語も微妙な場合、総合職の英語の問題は相当難しく見えると思います。そのため1から英語をやるなら半年くらい時間をとるべきで、それが無理なら英語は諦めて知識問題に時間を割く方がいいかと思います。
判断推理の対策
判断推理も数的推理も、一番大事なのは「いけそうな問題だけに取り組むこと」です。総合職の数的は難しくて、苦手な僕は多分何ヶ月頑張っても得意になりません。まして3ヶ月ではやれることも限られているので、目標は5割くらいで本当に大丈夫です。
僕は最初とりあえず過去問を解こうとしたのですが、正解率3割くらいでビビりました。その後2月頃に友達からもらった畑中敦子の判断推理のうち、対応関係、順序関係、位置関係、数量推理、移動と軌跡、展開図あたりの問題を解きました。
それでも全然できず3月にスー過去を買い、対応関係、順序関係、位置関係、数量相互の関係の4テーマに絞って問題を解きました。過去問の構成を見る限り総合職は出題の半分くらいが対応関係と順序関係で、さらに1問は簡単な論理の問題が出るとわかっていたので、事実上「対応関係と順序関係だけマスターすれば合格点だ」と考えて勉強しました。
ある程度解き終わったら判断推理と数的推理の両方セットで時間を測って過去問を解きましたが、これについては後述します。
数的推理の対策
数的推理と判断推理はなんだか似ている雰囲気がありますが、実際は数的推理が数学で判断推理がパズルといった印象を抱きました。
この辺りも正直受験生時代の勉強量に左右されるものの、確率、整数、比・割合などは判断推理と比べてそれほど難しくありません。計算の仕方を間違えたら異様に時間だけ食ってしかも間違えるので、主眼としては「簡単な式を立てて簡単に解く」という感じになります。
数学といっても、出題される内容はほぼ数学1Aと中学数学です。基本は過去問を解くので十分ですが、その際は自分の解き方と解答の解き方を比べてどうすれば5分で解けるかを意識して取り組みました。

こうやってみると小難しそうですが、実際は思考の順番を追っているだけです。概念的な理解はもちろんできているので、あとは時間をかけずに場合わけの仕方や使う式を出す訓練をすればokです。このノートではどの情報から場合わけや使う式についての判断ができるのかを文字にしてまとめました。
以上のように勉強をしたら、時間を測って過去問を解きましょう。僕は読解にかける時間を50分で固定していたので、数的全体で100分くらいかけられました。
そのため演習をする際は100分使って15問中7問くらい正解するという意気込みで取り組みます。まずは全体を見て、判断推理は頻出のやつと論理問題だけまずやり、2〜3分考えて無理そうだったら諦めて数的推理で地道に計算する道を選びます。
解けなかった問題は1問ずつ5〜7分かけてもう一度解いたりしました。本番は滅多にでない分野だとか、難しすぎるものには触れません。あくまで5割取るために必要なレベルに到達すればいいと割り切って勉強しましょう。
「目標は7問でいいのか??」と疑問に思う人もいるかもしれません。結論から言えば、半分取れれば万歳です。数的で半分、読解では正解した問題が6問を超えた分を知識問題のロスに上乗せしてぎり5割を狙います。運よく知識問題で5割を超えたら全体で20点+αになるイメージです。
時事問題の対策
すきま時間で速攻の時事を読み、試験2ヶ月前からは日経新聞の学生無料サービスを使って毎日ニュースに目を通しました。速攻の時事の問題集みたいなのも買ったのですが、こちらは全然使いませんでした。
これも、速攻の時事を全部読んだら後は天に祈ることしかできないと思います。3問中1問当たればいい、2問当たったら超嬉しい、という気持ちでした。速攻の時事はあまり当たらないとも言われていたので、そんなに一生懸命は読みませんでした。一読してなんとなく入った知識が日経の記事タイトルに出てたらそれを読む、という具合で組み合わせるといいかもしれません。
長くなりましたが以上です!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
