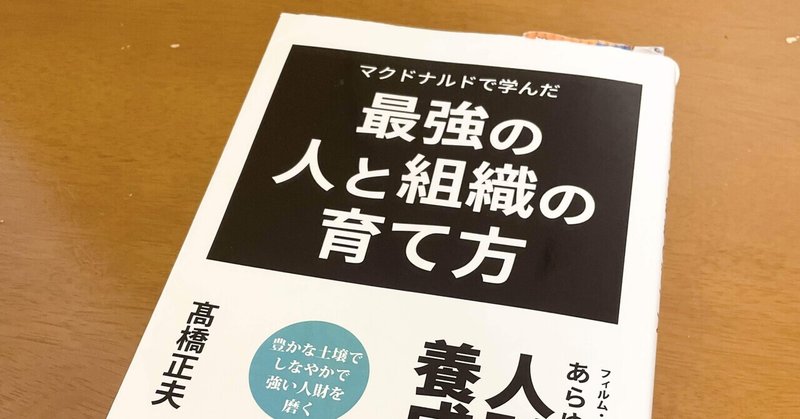
マクドナルドで学んだ最強の人と組織の育て方/高橋正夫氏
\日本マクドナルド創業時から藤田田社長と歩む/
著書「マクドナルドで学んだ最強の人と組織の育て方/高橋正夫氏」を読みました
高橋さんは1971年の日本マクドナルド創業時に入社され“銀座のユダヤ人”と自らを呼んだ伝説の経営者、藤田田社長の申し子と言える方です
本書はどちらかというと経営者ではなく「課長クラス(管理者を指す)」に向けています
組織を創る、まとめる、活かすために必要なシステムやシミュレーション、さらには人の気持ちを考えた人材育成について学べる一冊です

1流と2流の差
著書より
「マクドナルド創業者のレイ・クロップは『ラウンドを終わって帰ってきた1流のゴルファーはプレー中にうまくいかなかったことを嘆くのではなく、直ちに練習をして完璧を目指す。しかし2流のゴルファーは控室で失敗を嘆くだけ」
愚痴から成長や学びが生まれることはほぼありません。逆な全ての物事に失敗もありません。うまくいかなかったことを次に活かす思考を持っているかどうかが1流と2流の差なのだと思います
消費者に目を向けよ
著書より
「マクドナルド社の基本理念のなかで消費者に対応するには、次の3つを持たなければならない。“良心”“注意力”“差別化”つまり常に消費者に目を向けよ、と私たち自身の革新を要塞している」
ビジネスにおいて重要なことはキャッシュと顧客です。さらにはキャッシュは顧客から生まれることを考えると、顧客に目を向けると言うのは当たり前のことです。しかし多くの企業が顧客ではなく、会社や上司を見て仕事をしています。意識すべきは会社の仕組みを理解した上で、顧客に目を向け続けることです。
紅く熟すな、いつまでも青く
著書よりレイ・クロップの言葉
「As long as you are green ,you are growing as soon as are ripe,you stat to rot…
(人生はいつまでも青い気持ちを持ち続けるならば、成長し続けることができる。しかし紅く熟してしまえば、たちまち朽ちてしまうであろう)」
人は正しく評価されたいもの
著書より
「働く者にとって、従業員の業務に対する貢献度や職務の遂行度、業績、能力などを一定の基準で査定する『人事考課』ほど重要なものはない。人は誰でも“まともに評価されたい”と願っている」
会社によっては評価基準がない、上司の感覚で評価している、現場を見ていない本社が評価している、など従業員のモチベーションに悪影響を与える評価をしがちです。もちろん結果だけでなく、プロセスにおいても評価できる仕組みが必要です
文化性のないものはすぐに廃れる
著書より藤田田社長の言葉
「『文化性のないものはすぐに廃れる』ハンバーガーという新しい食文化は“簡便化”“スピード”という2要素があったため、アメリカに浸透して、アメリカの食文化となった。藤田田社長は『アメリカでも食文化となったマクドナルドが日本でも必ずや新しい“欧米化”の食文化として日本のライフスタイルになる』と確信していた」
新しい文化は「簡便化・スピード・欧米化」にあるといいます。これは当時だからと言うことではなく、今の時代にも当てはまると思います。住宅においても2020年に省エネ住宅として欧米化が進みはじめました。この3要素を意識することがビジネスの勝ちパターンになることを意識したマーケティングが重要だと学びました
優先すべきは従業員満足度から
著書より
「ダイヤモンドロール作戦:顧客満足度・従業員満足度・利益・売上占有率の4つを結んで、まるでダイヤモンドのような形に重要な意味を持たせた。売上占有率と利益は顧客満足度が高まらなければ成り立たない。顧客満足度はどこからくるか。それは従業員満足度がにほかならない。よってダイヤモンドロール作戦とは、従業員のためにお金と注意を払う作戦である」
売上至上主義や社員を駒のように扱う会社が一時的には成長しても長く続くことがない理由はここにある。お客様と同様に従業員を大切に扱うことが会社を成長させる最大のポイントであるということです。
企業は内部から崩壊する
著書より
「藤田田社長はハンバーガー無料券が一枚でも合わなければ激怒するほど、管理には厳格な人物であった。『企業は外的要因では潰れない。内部管理の甘さや、蟻の一穴から崩れる』といつも言っていた」
崩壊は小さなことの積み重ねと聞きます。これくらいいいだろう、という安易な考えが組織を汚染し、腐食していき、崩壊となります。守るべきルールは徹底し、反した場合には処罰を与える厳しさも必要なのだと思います
商売がヘタな人、上手い人
著書より
「商売のヘタな人は、社員を牛馬のごとく、こき使って儲けてやれ、などと考えるから儲からないのだ。人間の成長を心から念願し、養成してやる。そうすると不思議なことに何倍、何十倍と儲かってしまうのだ」
自分本位ではなく相手本位で考えることが何事も重要である。組織のリーダーは同様にメンバーの成長に重きを置くことで結果的には組織の成功へと繋がる
部下が認めない上司とは
管理職の職務上大切な5C
コミュニケーション:意思共有、報告、伝達
コーディネーション:調整
コンサルテーション:業務相談、助言、指導
コントロール:管理、監督、統制
カウンセリング:相談
これらにより部下の働く価値を高めることが肝心な仕事だ」
非常に厳しい話ですが納得の話です。自分が認めていない上司とは会話はしませんし、必要最低限の報告しかしません。これが部下というものです。管理職とは自らが5Cに則って部下と関わる必要があります。相手から求めるのではなく、こちらから動かなくてはなりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
