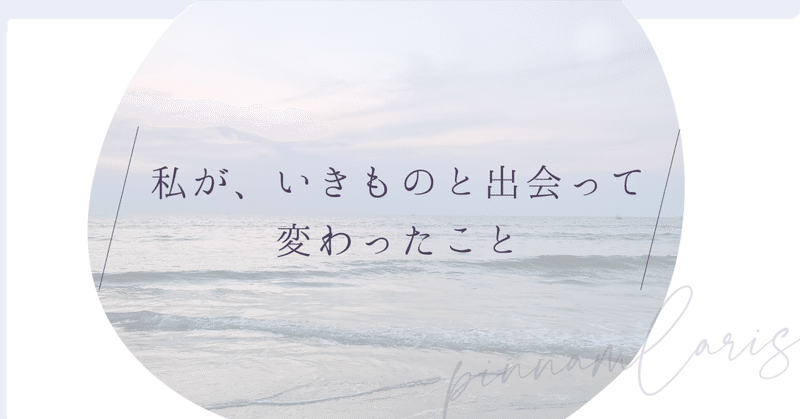
私が、いきものと出会って変わったこと
自分の人生を振り返ってみた
ここ1〜2ヶ月ほど過去を振り返る機会をいただき、恥ずかしい気持ちと新たな発見に驚く気持ちが半分ずつ。
きっかけはナリワイ助産院というプログラムでした。これまでやってきたこと、想い、強み、特性を掛け合わせて、お役立ちができるお商売を生み出すために学んでいます。
「これまでどんなことをやってきたのか?」
振り返ると、本質は小さい頃からあまり変わっていないように思います。どんくさくて泣き虫なまま、先月とうとう30歳になりました。
「30歳まで生きられたら、私は十分だなぁ」
子どもの頃の私は、夢も希望もなく、何事も最初から諦めていました。私なんかが長く生きても意味がないと思っていたのです。
夢も希望もない子どもだった
子どもの頃、世界は息苦しくて窮屈なものだと思い込んでいました。特に、同年代の子が集まる環境が苦手でした。幼稚園でも、水泳教室でも、そのままの自分ではいられなかったからです。
私の母は、子供向けのキャラクターよりも本物に触れた方がいいという教育方針でした。そのため、私が興味を持ったものは実物を見に連れて行ってくれました。
その頃の私は、近所の川沿いを歩きながら、水鳥や魚を指さして、母からいきものの名前を教えてもらうのが好きでした。いきものの他には、仏像も。母のアルバムで大きな大仏さまの写真を見つけて「行ってみたい」と言ったところ、両親に連れられて鎌倉へ。仏像の穏やかな表情と、神社仏閣の落ち着いた空気に魅入られました。その後、奈良や京都のお寺や博物館にも行くほどの熱中っぷりでした。
その反面、周りの同年代の子と趣味や話が合わないことも多々ありました。
今となっては当然だと思うのですが、
「マガモがきれいだった」
「興福寺の阿修羅像が好き」
と聞いて理解できるのは大人でも少ないと思います。また、ひとりっ子で人見知りだったこともあり、子ども同士で遊ぶことに慣れていませんでした。
みんなでままごとやごっこ遊びをするよりも、部屋でお絵描きや粘土遊びなど1人で黙々と何かやっている方が気が楽。ただ、1人きりでいる時間が長いと、周囲の大人から「友達がいないあの子は普通じゃない」と言われそうな雰囲気が漂ってきます。それはそれで両親にそのことが伝わってしまうと心配をかけるので、面倒だと思いました。
それであれば、好きなものも本心も隠して、周りの子となんら変わりないふりをするのが最適解。でも、現実はそう甘くありませんでした。
「みんな知ってるのに、なんで知らないの?」
「ほかの子ができるのに、なんでできないの?」
「普通は見れば分かるでしょ。なんでわからないの?」
「素の自分」を出してはいけない、「普通」でなくてはいけない。そう思って、そうあろうとしているのに、ボロが出てしまいます。やりたくないと言えば母に怒られるし、行きたくないと言えば父に心配をかけるし、泣けば周りのみんなから笑われる。だからといって、言い返せるほどの度胸もなく、ただ悔しくて窮屈なだけ。
この先もずっとこうなんだろうかと思うと憂鬱な気持ちでした。お姫様とか、ヒーローとか、そんな夢を持ってもどうせ自分はなれない。
「普通に生きてくことでさえ難しいのに、どうして夢なんて持てるんだ」
と思っていたのです。
小鳥を見つめ、「個」を想う
幼稚園は苦手な場所でしたが、「この園に通いたい」と自分からお願いしたのです。理由は、個人でいきものに触れる機会が多く、登園が週に1~2日であることでした。
登園日が少ないこともあり、飼っているいきものは園児が家に連れ帰ります。4歳(年少)ではジュウシマツ(小鳥)、5歳(年中)ではモルモットを当番制でお世話しました。そして、6歳(年長)では伝書鳩(ハト)をひとり1羽お世話する決まりでした。
私はすぐにジュウシマツが好きになりました。鳥類なので全身が羽で覆われ、人間にはない翼とくちばしがあり、飛ぶことができます。姿形は自分とまったく違うけれど、同じ部分もあると気づきました。
喜んだり、怒ったり、感情がなんとなくわかるのです。水や餌を新しいものに換えると、いそいそと近づいて水浴びしたり、ぱくぱくと餌を食べたり、なんだか嬉しそうに見えました。
「鳥は何も言わないけれど、言わなくても伝わることはある」
そう気づいて、いきものの心をもっと深く知りたいと思いました。
さらに惹かれたのは、個性があること。例えば、ジュウシマツは頭から尾羽まで白がベースで茶色の斑点があり、その斑点の大きさや位置が1羽1羽違います。また、鳥籠の隙間からそっと小指を入れてみると、「なんだなんだ?」と近づいてくる子もいれば、慎重に鳥籠の奥でじっと様子を伺っている子もいるので、性格も違うのだと知りました。
立派になれなくても、私のものじゃなくても
6歳(年長)になると、自分がお世話をする伝書鳩を選びました。同学年の全員で飼育小屋に入り、ハトを1人1羽捕まえます。のちに母から聞いた話によると、私は最後に残った1羽をやっとの思いで捕まえたそうです。
私がどんくさかったのがいちばんの理由ですが、ハトが嫌がることをしたくなかったのだと思います。いくら人に飼われているとはいえ、追いかけられたり、捕まえられるたりすると激しく嫌がります。飼育小屋の中で追いかける子どもと、逃げ回るハト。怯えて飼育小屋の隅にいたハトと、自分の姿を重ねて見ていました。
私のハトは、水色に黄色の水玉が描かれた足環をつけていて、とても大人しい子でした。初めて会ったときはヒナらしいふわふわした羽毛が残っていたことを覚えています。
責任感と、自分のハトだという愛着も湧いて、この子を立派な伝書鳩に育てなければと思いました。ハトの成長を見ていると、自分の未来も楽しみに思えたのです。

やがて、羽が生え揃って大人と同じ見た目になり、伝書鳩の訓練が始まりました。幼稚園の外にハトを連れていき、足に手紙をつけて放します。初めのうちは幼稚園の近くから、徐々に距離を広げていき、最終的には隣の県で放鳥しました。
放されたハトたちは自力で幼稚園まで帰ってきます。しかし、訓練の回数を重ねるごとに、1羽、また1羽と帰ってこないハトが増えていきました。
「無事に帰ってきてね、絶対だよ」
ハトを放すとき、ありったけの祈りを込める。いつもは破ってしまう母の言いつけも、きちんと守っていい子にする。そんな祈りが届くはずもなく、とうとう私のハトも行方不明になりました。
自分がお世話をしていたハトがいなくなっても、他のハトが用意されて訓練は続きます。子どもを悲しませないための配慮だと思いますが、私には「代わりはいくらでもいる」と言われているように感じて背筋がゾッとしました。
放さなければよかった。「立派な伝書鳩」じゃなくてもいいから、「私のハト」じゃなくてもいいから、生きていてくれれば、それでよかったのに……。帰れなくなったハトに申し訳なくて、何もできない自分に腹が立ちました。
このときに決めたのです。
「困っているいきものの力になりたい。もし、みんなが忘れたり見捨てたりしても、私は味方でいられる強い人になろう」
窮屈な世界のなかに
「過去の私が、いまの自分を見たらどう思うかな?」
と考えることがあります。特に大きな決断の前、小さかった頃の私が目を輝かせて喜んでくれるなら間違いないと思えるのです。
怖かった、寂しかった、息苦しかった。いきものがくれた思い出に背中を押され、この先に繫がるであろう新たなご縁に希望を託して、生きようと思ったのです。
歳を重ねて、昔と比べれば器用になって、知識もできることも少し増えました。学校や会社で化けることにも慣れたけれど、それでも傷つくこともあって、社会で生きていくのは未だに大変です。
でも、窮屈に生きてきたからこそ、わかることも、幸せもありました。川に出かけて、水鳥など野生動物を観ていると日常を忘れられます。狩りの様子や、他のいきものとの接し方を観察し、
「なるほど!こういう方法があったのか!」
と生き方を学ばせてもらう場でもあるのです。
また、趣味がきっかけで友人ができました。SNSで発信したり、イベントに行ったり、マニアックな趣味でも続けていれば意外なところでご縁は繋がっていくものなのですね。
家族や友人、いきものたち。大好きな川や海、水族館、映画や音楽、アニメなど。心の拠り所を見つけられてよかったと思います。
残りの時間は、いきものへの恩返しと、昔の私と同じように辛い思いをしている人のサポートに充てたいと考えています。いきものを軸に「個性を活かして生きていけるきっかけ」を届ける。そんなナリワイを生み出すべく、奮闘している今日この頃です。
いつも見てくださってありがとうございます!よろしければサポートいただけると嬉しいです。いただいたサポートは、いきもの作品の制作費用に使わせていただきます。
