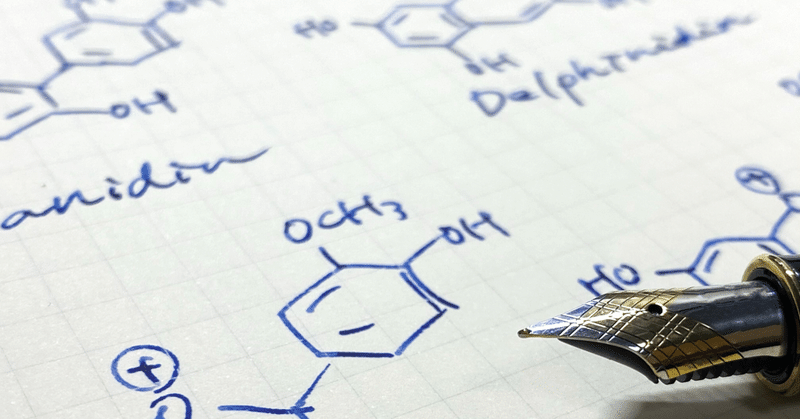
[未発表原稿]みんな何かの少数派だということ
『人生の土台となる読書』のために書いたけど使わなかった原稿です。神経学的少数派の話など。
こないだ友達と話していたら、
「本を読んで勉強するのは苦手。人から直接教えてもらったほうが頭に入る」
と言っていて、自分とは真逆だな、と思った。
僕は小さい頃からずっと学校の授業がすごく苦手で、先生の話がまったく頭に入ってこなかった。
それでも成績がよかったのは、自分で本を読んでいたからだ。授業中は先生の話を聞かずに、一人でひたすら教科書を読んでいた。自分で本を読めば理解できるのに、何のために授業というものがあるのかがわからなかった。
授業を聞くのも苦手だったし、人と話すのも苦手だった。学校の休み時間はいつも、わいわい騒いでいるクラスメイトを横目で見ながら、本を読んでいるか、机につっぷして寝ているふりをしていた。
多分僕は、聴覚によるコミュニケーションが苦手で、視覚から情報を得るほうが得意なのだ。知らないことは全部本が教えてくれたし、広い世界に自分をつなげてくれるのも本だった。だからこの本みたいなブックガイドを書いている。
大学生のときにネットを始めるまでは友達があまりいなかったのに、ネットを使うようになってから友達がたくさんできるようになったのも同じだった。会話よりも文字のほうが自分をうまく表現できる。
僕は話しているとどうもうまく頭が働かない。面白い話を次々と繰り出せる人にはずっと憧れている。
会話によるコミュニケーションが得意な人と、文字によるコミュニケーショが得意な人と、どちらが優れているというわけではない。そこには向き不向きがあるだけだ。うまくできない人は努力が足りないわけじゃない。自分に向いていない場所は避けて、向いている場所を探すのが大事なのだ。
僕はたまたま自分に向いている「本」や「文字」というやり方に巡り会えたのでうまくいっただけだ。
そういったことを昔から考えていたので、最近読んだ村中直人『ニューロダイバーシティの教科書』という本が面白かった。
ニューロダイバーシティ(neurodiversity)という言葉はneuro(脳・神経)とdiversity(多様性)という2つの言葉をつないだ合成語です。1990年後半に生まれたまだまだ新しい言葉です。
ダイバーシティというのは性別や人種や障害などについてよく使われる言葉だけど、それは脳や神経のつくりにも当てはめられる、という話だ。
この本で主に扱われるのは自閉スペクトラム(アスペルガー症候群)の話だ。だけどニューロダイバーシティというのは、自閉スペクトラムだけに限らず、あらゆる神経的な特徴について当てはまるものだ。
世の中にはしゃべるのが得意な人も本を読むのが得意な人もいる。感情の起伏が大きい人も小さい人もいるし、我慢強い人もそうでない人もいる。
それぞれの人間は違う神経を持っているのだから自分の当たり前を押し付けてはいけない、というのがニューロダイバーシティの考え方だ。
「みんな同じ」と思い込んでいると、みんなと違う人間に対する苛立ちや排除が生まれてしまうけれど、違うことを認めていれば寛容になれる。
ここから先は

曖昧日記(定期購読)
さまざまな雑記や未発表原稿などを、月4~5回くらい更新。購読すると過去の記事も基本的に全部読めます。phaの支援として購読してもらえたらう…
ꘐ
