
PORT: Performance or Theory #1 「テキスト/デザインの身体性」 | 渋革まろん
2021年10月10日(日)
第一部 17:00-18:00 / 第二部 18:00-20:00(入退室自由)
第一部 : 石塚俊×山本浩貴(いぬのせなか座)×三野新
第二部 : クロストーク
第一回目のPORTは三野新のオーガナイズで、「テキスト/デザインの身体性」をテーマに開かれた。第一部はグラフィックデザイナーの石塚俊と、いぬのせなか座の主宰で2021年に出版された三野の写真集『クバへ/クバから』の編集・デザインを手掛けた山本浩貴をゲストに招いて1時間のトークを行い、第二部ではPORTメンバーとオーディエンスに議論を開いて、デザインと身体の関係を各々の視点からさらに深掘りしていった。それでは早速、PORT#1で交わされた議論を見ていこう。
序:制作コミュニティ→デザイン→読者→社会的コミュニティ
第一部の議論は三野が投げかける「デザインは身体にどういう影響を与えるのか?」という問いから始まる。対する石塚・山本の応答はコミュニティ、アーカイブ、演出、本の流通、制作プロセス、そして環境や空間のトピックを通じてデザインの機能や社会的位置づけにあらためて光を当てた。当初は漠然としていた三野の関心も明確な焦点を結んでいき、紙面からコミュニティ、そして環境へとデザインの働きかける圏域は重層的に捉え直されることになる。
漠然と靄のかかった状態にあるアーティストの問いが次第に整理され、言語化され、問いの解像度を飛躍的に高めていく言説化のプロセスはPORTの醍醐味である。ただ、本レポートの目的は、次なる議論と実践のためにトークの内容を保存・整理しておくことなので、

の系列を仮定した上で、デザインをめぐる三野の問いかけを、以下の二方向から整理して記述していこう。
①デザインから:デザイン→読者→社会的コミュニティ

②デザインへ:制作コミュニティ→デザイン

デザインから読者へ
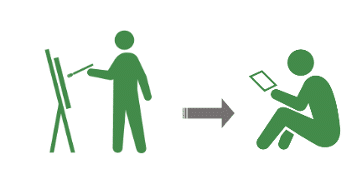
三野:スタティックな状態の本や戯曲、あるいは文字から現実の身体が動き出すことのあいだには飛躍がある。デザインはどうやってこの飛躍を生み出すのか?
トークの冒頭で、三野は「デザインが身体に与える影響」として「①デザイン→読者」の関係に言及した。三野の写真集『クバへ/クバから』のデザインを担当した山本浩貴は、同写真集の制作にあたってキャプションを何ミリずらすかも含めて三野と緻密な議論を重ねていった。筆者も足を運んだが、2021年5月に開催された本作の写真展では、その制作プロセスを公開(上演)したうえで、キャプションの位置、写真の構図で変化するレイアウトの効果、余白と写真・文字の関係などが延々と検討され、それらの差異がイメージの受容に与える影響をリアルタイムで開示する刺激的な実演が行われていた。
一方、石塚はレイアウトがもたらすイメージの効果とは別の物質的な側面、すなわち書籍の製本にわたしたちの注意を向ける。
石塚:『クバへ/クバから』はのど(本の内側)がすごく開くから片手で背を掴んで読みにくい。立ち読みができない。ただ机の上ですごくきれいに開く。だから時間をかけてゆっくり読みたくなる。
また、三野は製本と同じように、「文字」もまたデザイン的に操作可能な物質であることにも触れている。文字がのどに近すぎると本をグッと開かなければならず、とても読みにくい。しかしそのように負荷がかかることで読者の側の変な身体性が引き出される。
したがって、デザインが読者の身体に働きけるプロセスには、次の二つのレイヤーがありうることになる。
A.写真やキャプションの配置で構成されるイメージの効果
B.製本や文字の物質的な効果
後で触れるが、デザインと読者の関係は、出版および流通の制度的な側面に強く規定されている。このトークでは議論の流れが──どちらかというと──「宣伝美術」としてのデザインにうつり、デザインの物質的・イメージ的な効果に関わるトピックはあまり展開されなかった印象がある。その点はまた別途、探求・共有の余地があるかもしれない。
制作コミュニティからデザインへ
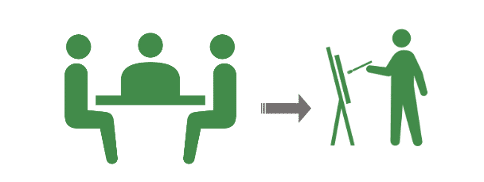
デザインと身体の関係が議論されるなかで、デザイナー自身の身体性も話題になった。②制作コミュニティ→デザインの関係である。
三野は、石塚と山本の仕事が発注されてチラシや書籍のデザインをアウトプットする一般的なデザイナーの仕事から逸脱していると説明する。三野が主宰している演劇作品を上演するカンパニー「ニカサン」 で 石塚は フライヤーのグラフィックデザインを手掛けていたが、石塚はそうしたデザインだけに留まらず、現場に出て舞台監督的な役割も担っていたり、舞台美術のサイン計画の役割も兼任していた 。また、山本は演劇の舞台に出演するようにもなっている。それはなぜなのか? 三野はここで、デザインする身体が関与するコミュニティの存在にその要因を求めようとする。
三野:ふたりの仕事はときに個人的な職能というより、コミュニティの中に入り「デザイン」を導き出すものに見える。コミュニティに身を投じることで自分自身が変わっていき、デザインせざるを得ない状況に自分自身を追い込む。そうしたデザイナーの身体性があるのではないか?
三野の立てた仮説から「制作コミュニティ→デザイナー」の枝はあまり伸びなかったが、代わりに議論は二つの方向に波及した。ひとつはコミュニティデザイン、もうひとつは動的な制作プロセスに関わる議論である。
コミュニティデザイン/流通の制約

①デザイン→読者の延長線上には読者の集合=コミュニティの存在が想定されうる。
山本:私はエディトリアルデザインが多いから、最終的にモノ=本が出来る。書き手の歴史も含め、具体的に収録される作品をかき集めて「いま」で切断して抽象化してひとつのモノ=本に変換する。そこで解釈する人、消費する人、読む人、この本を使う人達がどういう集団になっていくかを設計していくところがある。
山本は第二部で「ここに受け止めなければならない表現があるという状況を作ることがデザインの役割だと思う」と述べる。いわば本は広場に立てられた一本の杭のように人を集める。その杭にどのような装飾が施されているかで趣味や属性に応じた人々の集まりが誘発される(この杭は持ち運び式であるが) *1 。
しかし一方で、読者の知覚・身体感覚を組み直したり、デザインされた書籍/印刷物を媒介に集合が触発されるプロセスを駆動させたりするデザインの操作は、特に商業的な流通に乗せて数多くの人間が関わる場合、一定の規格に落とし込まざるをえないという事情を抱える。具体的でわかりやすいので、山本の発言を見てみよう。
山本:商業ベースであれば背にタイトルがない『クバへ/クバから』は出せない。社会の多くの人間が一冊の本に関わる場合、ルール通りじゃないと社会のあらゆる場所で細かいエラーが生じて、たくさん問い合わせが来てしまう。また、小さめの出版社なら自分たちで発送しないといけないから、判型や厚みを郵送できる2〜3センチ以内にしてくださいとなり、紙の厚みも変わる。
つまり、商業出版の書籍では流通の仕組みを無視した仕事はできない。しごく単純化すれば、デザイン→読者→社会的コミュニティの系列は、本を流通させるための経済合理的なシステムや商業的な慣習に従わなければならない。だから山本は「既存のルールをもとにそれをどういうふうに変化させて効果的に使用できるか」をデザイナーは意識せざるを得ないし、もしも逸脱的なチャレンジに踏み込む場合は、「新しいものを流通させるためにどういう仕組が必要なのか」を考えざるをえないと言うのである。
ここで【制作コミュニティ→デザイン→読者→社会的コミュニティ】の系列は、流通の制度に規定されているので、

と、書き換えることができるだろう。ちなみに、上演系芸術 *2 のなかで「流通」に自己言及するパフォーマンスはあまり見受けられないように思う。しかし上演系芸術も、チケット販売、アーティストの移動、国際的なフェスティバルマーケット、劇場のレパートリー、助成制度といった複合的な流通の制度に表現のあり方を規定されている。書籍=身体、本屋=劇場、版元=主催者などのアナロジーから流通と表現を媒介する「デザイン」の働きについて問うことも興味深い議論につながるかもしれない。
コミュニティデザイン/“あいだ”の無重力空間

前節の焦点は消費者・受容者の社会的コミュニティであるが、他方で三野は「新しいものを流通させるための仕組み」として制作者・アーティストのコミュニティに言及する。
三野:コミュニティデザイン(コミュニティのなかにおける細かいデザインの諸々)に言及するのは、僕がルール無用で生まれるデザインに興味を持つから。……ルールが決まっている商業的な流通ではなく、ルール無用のデザイン=無重力。その無重力から変な身体性が出てくる。
第二部では、
三野:今日はジャンルを前提しないゼロベースの制作について話したかったのだと思う。PORTメンバーは「身体」を最低限の前提にして、ダンス・アート・演劇・建築etc.に表現形式が枝分かれする経験を知っている。ただ、そうした(ジャンル無前提の)無重力空間で作品を作り出すのは難しいから、諸メディア・ジャンルの形式を参照していくと、だんだん既知の形式に引っ張られて似たものになっていく。でも僕は無重力空間に耐えて楽しむところから作品を考えるやり方を探求したい。
舞台芸術と写真芸術のどちらにも属さず、その“あいだ”でアート活動を継続してきた三野にとって、ジャンルのルールを前提せず、剥き出しの個として無重力空間に浮かんでいる状態は、むしろ“普通”の状態と言えるだろう。だから無重力空間の隠喩は、三野が常にそこに身を置こうとするコミュニティのあり方を的確に表現するものである。
三野:横断性の話。写真家&舞台作家の位置はジャンルの枠組みから外れる。だから作品の評価は三野個人に向けられる。「三野」がうまくやっているかどうかでしか判断できない。それがキツイと感じることもあるけど、例えば僕は「デザイナー」の肩書を持つ石塚さんと話すのではなく、石塚さん個人に話しかけていると思う。僕はこういう個人と個人の関係でクリエイションに臨む集団制作のあり方を当たり前のものにしていきたい。
肩書や職能の関係ではなく、剥き出しの個と個の関係の織り合わせからなる集団制作。当初、三野はコミュニティに関与する身体的経験からデザイナーの「デザイン」も出てくるのではないか? と仮説を立てた。そこに但し書きを加えるとしたら、そのコミュニティはあらゆる前提を括弧に入れ、諸個人の具体的な関係しか拠り所のない無重力空間と常なる緊張関係に置かれているということだ。
明示的ではないが、このトークでひとつの不和/係争点を形作っていたのは、実際に何か(組版、グラフィック、書籍、環境etc.)をデザインするときに社会的制約を引き受けざるを得ないデザイナーの立場と、それらの社会的ルールで培われてきたクライテリア/判断基準/価値判断を自然化する態度をいったんやめて、新たなクリエイションの共同性/協働性を立ち上げようとする三野の対立というか依拠する立場に起因したすれ違いである(一応、付言しておくけれども山本・石塚がひとつの価値判断に盲従しているという話ではない) *3 。
ここでは一見、社会(デザイン)と個人(アート)が対置されているように思える。決められたルール(業界・市場の)に従う職業人と、ルール無用の自由な個人の二項対立である。
しかし、三野が社会のルールから解き放たれた自由なコミュニティを望んでいるわけではなさそうだ。むしろ──三野自身がそうであるように──どのジャンルの了解からも余所者として扱われる根無し草の《個》が出会い、協働し、それぞれが持ち込んだ形式から新たに仮設的な規則を作り直していく集合的なプロセスにこそ三野の関心は向いていると思う。どこにも根を持たない常なる余所者たち、無重力な《個》と《個》が関係するような集まりを作る、そうした方法論の探求である *4 。
整理しよう。【制作コミュニティ→デザイン/クリエイション】の関係において、社会性・共同性・集合性・無重力性というクリエイションの場を規定するコミュニティのレイヤー四層を分節することができる。

だとするならば、三野が企図しているのは、集合性(C層)のデザインということになるだろう。規制の重力を働かせる社会的ルール(A層)ならびに共同性の重力──ときに同調圧力にもなるそれ──に規定されるコミュニティ(B層)と集合性(C層)との“あいだ”で、美学的・文化的・形式的・社会的諸規範との摩擦(⇅)が生じざるを得ない状況を設計し、そこでたくさん生じてしまう「細かいエラー」(⇅)の混乱・乱発をむしろクリエイションの推進力とする「コミュニティ」の方法論を練り上げること。ここで集合的コミュニティとは、無重力へと向かう力(↑)の発生で、既知の共同体から離反した人々を生み出す方法なのである *5 。
制作プロセス/作家的─集積的
【制作コミュニティ→デザイン→読者→社会的コミュニティ】の系列の下部構造にあたる流通の制約と、【制作コミュニティ→デザイン/クリエイション】を条件付けるコミュニティのレイヤー四層(社会性・共同性・集合性・無重力性)をまとめてきた。ここではさらに、集合性とクリエイションの関係に注目しよう。三野が目指す(と筆者がみなす)コミュニティの方法論は、作家=制作者の計画や構想、意図的なコントロールからの離反を含意している。
制作物は作者の意図や構想の支配下に置かれてコントロールされている。天才的な作家は因習・慣習に縛られない独自のオリジナルな創造性を発揮する。こうした作家主義的前提をわたしたちは漠然と持っている。これは0/100の制作観だ。確かに、鑑賞・観劇する立場からすれば、そこに完成品がドンと出現している感じはいつでもするだろう。しかし、三野・石塚・山本の議論は制作物を制作プロセスのなかでさまざまな要素や思考が織り込まれる、不確定なプロセスの集積として捉える見方を提示している。
石塚:宣伝美術の段階では、まだ何も決まってないわけですよね。だんだん情報が出てきて、文字組みやタイトル書体が決まり写真や絵を使って、テキストで来たものを視覚的に返していく。そうすることで、作品に最初の血が通っていく、三野くんの景色が変わる気がするんです。
石塚の発言から、美的なモノなり出来事なりを作り出す制作の営為は、瞬間の産物ではなく、時間的な幅を持つプロセスを有することがハッキリわかる。この集合的な制作プロセスを、複数人の指し手によるゲームのようにイメージしてみよう。一人の作者が制作の全体をコントロールするのではなく、ひとりが指した手に応じて、またべつのひとりが新たな手を指す。相互触発的な連鎖のプロセスにおいて、各々の指し手が決まり、その集積を──絵画・写真など物質の永遠性、演劇・ダンス・パフォーマンスなど上演の持続性のどちらに依拠するにせよ──観客/鑑賞者/オーディエンスは体験するのである。
三野がコミュニティとの関係で「デザイン」の働きを考えようとしたのは、こうした作家主義に対立する集積主義的な観点が念頭にあったからだと思われる。それは例えば次のような二項対立の系列を形成する。
作家的|集積的
───────
完結性─未完成
完了性─過渡性
必然性─偶然性
単一性─多元性
主体性─凝集性
これらの対比を現代美術、舞台芸術、パフォーマンスアート各々の歴史に照らし合わせて文脈化することもできるだろうが、筆者の手にあまるのでここではそうしたことをしない。その代わり、作家的と対立する集積的な制作手法は、どのような集まりの形式に条件付けられ、そして三野(制作者)のうちにどのような経験として現れうるのか、もう少し掘り下げてみよう。
制作プロセス/宣伝美術の効果/対価的・間人格的・集積的
集まりの形式は、集まりを秩序付けるルールの安定性─不安定性、集まる成員の匿名性─顕名性を軸とした四象限にまとめて図示することができる。

コミュニティのレイヤー四層に対応させるならば、共業=社会性、共同=共同性、集合=集合性、集積=無重力性となる。この四象限を踏まえて、集積的な制作手法が三野(制作者)に呼び起こす経験の位相を見て取るため、宣伝美術にまつわる三人のトークを参照しよう。
山本:ビジュアル来たら、「ああ来た、これだわ」と思ったりして…?
三野:めっちゃ思う。「デザイン」をテーマにしたのも、そこの変な感じがあったからなんですよ。チラシのデザインが来たときに「始まる」感じがあって。それはなんだろうと。
稽古期間の最初期にチラシのデザインが上がってきてなにかが始まる感じ、「お!」という感じに三野はなにかしらの引っ掛かりを覚えると言う。これまでの議論を踏まえるならば、この「お!」が生まれる瞬間は、発注─受注の対価的な契約関係(共業)では生まれにくく、コミュニティに身を投じる個人の──自発的な能動性を発揮したくなる──間人格的関係(共同)において生まれやすい *6 。
ふつうに言えば、顔の見える関係の方がモチベーションも上がるし、創造性も発揮しやすいという話になる *7 。だがそれだけだろうか? コミュニティのレイヤー四層を考慮に入れるならば、「お!」の瞬間は、顔の見える関係の信頼・親密性を支えるジャンル的な共同性から遊離した、不安定で不確定な《個》と《個》の集合的─集積的関係にこそ誘発されうるのではないか。それはコミュニケーションの相互触発的な連鎖反応が個々の意図を超えて思わぬ結果を導き出していくダイナミックな始まりの感覚を導くものである。
共通の前提を持たない無重力のギリギリから制作が立ち上がり始める段階を、石塚は次のように表現している。
石塚:三野くんからタイトルを借りてきて何をしたらいいのかわからないときは無重力状態だとしたら、公演に向けて重力をどこに置くのかという作業を宣伝美術を通して最初期は一緒にやるのかな。
公演のタイトルだけしかない、ほぼ何をするかわかっていない混沌とした不定形の状態が、宣伝美術のデザインを通じてビジュアル化され、漠然とした方向の予感(重力)を獲得し始める。そして三野の意図を超えた方向(重力)の発生に「お!」の感覚が惹起されるのである。
宣伝美術はそうしたひとつの効果として集積的な制作プロセスに入り込み、それを駆動させる。ただし、ここでデザインのディレクションが「重力」と表現されることに注目しておきたい。「重力」は、たとえばほぼ同義だが「方向」よりも集積的な制作観とマッチするように思えるからだ。
つまり、ここで宣伝美術のグラフィックデザインはなにかの方向を選択しているけれども、それはあくまでもひとつのマーキング=しるしづけに留まるのであり、いわば碁盤に石を置くように、「作品」の潜在的な諸可能性を含みこんだままひとつの圏域をマークする。平たく言えば、ある予感に満ちたワクワク・トキメキは膨らみながらも、制作の行方は一貫した構想に従わず、誰の手にも所有されないまま、その集積的な制作プロセスを操縦と自走のはざまでドライブさせる、と考えうるのである。
作品とは何か? 宣伝美術まで含めて作品か?
さて、これでほぼ第一部の議論をまとめられたかと思う。見てきたとおり、紙面・平面・書籍のデザインからはじまったPORTの議論は、制作プロセスに関与する制作・実践のコミュニティとそれを受容する読者/観客/鑑賞者のコミュニティの二面を通過し、制作・実践を条件付ける流通ならびにコミュニティのレイヤー四層へと議論の枝を伸ばしつつ、作家的─集積的な制作観の差異を浮かび上がらせた。二部のクロストークでもその他もろもろのトピックについて対話がなされたのだけれども、そのなかでひとつ、武本の提示した論点を取り上げよう。それは作品の境界をめぐる問いかけである。
武本:『山を見にきた』のポスターは手に取った人がどういうふうに受容して、どういうふうに公演に来てもらうかを考えて作りました。チラシを手に取ったときから公演の体験が始まると考えると、作品の境界はどこに引かれるんでしょう? 宣伝美術まで含めて作品なのでしょうか?……宣伝美術は川の流れのひとつであって、最終的に残るのは会場で見た作品だということだけれど、でもそこで残るものはなんだろう? 上演芸術はその瞬間で消滅する。最終的に物質として残るのは戯曲や宣伝美術だったりする。だとすれば、上演を作品として見るとはどういうこと?
上演系芸術の場合、「作品」の境界がどこに引かれるかは極めてあいまいである。特に武本の「作品」は、特定の時間のあいだどこかしらの環境を引き受け、それによって身体を主客未分の境界的な状態に推移させる、傍目から見ればゆっくり歩いているようにしか見えない「行為」なわけだ。そこにあるのは「作品」という境界づけられた対象というよりも、環境を引き受ける行為から生まれるある状態の発生と言ったほうが適当であり、作品と非-作品の境界は線というより、観客とのあいだに発生する(相互触発的な)濃度のグラデーションと言われたほうが飲み込みやすい。だから観客が初めて触れる宣伝美術から「作品」という状態の生成は次第に立ち上がり始めている、と考えるほうが武本的な「行為」の観点からすれば自然なのだ。
持続的な耐久性を持ち、自律的な境界を形成する「作品」の形式と、瞬間瞬間に儚く消え去り、間主観的・他律的な出来事性をもたらす「上演」の形式、両者の優位性をめぐる泥沼の対立に深入りすることはできないが、「宣伝美術まで含めて作品なのか?」という武本の問いは、作家的─集積的な制作観が対立的に捉えられる局面では、常に混乱のもとであり続けるだろう。
第二部:クロストーク/落ち穂拾い
落ち穂拾いとして、二部のトークで出た各自の発言をいくつか記録しておきたい。
◎石塚×たくみちゃん
石塚:映画/複製芸術のチラシを作ったことがあって、でもあんまりうまくいかなかった。複製芸術だから。本当にタイトル、キャストを置いて、固いフォーマットのなかで動いていて。裏面にはここの会場で上映中というスペースを空けない といけない。オーダーがどのクライアントよりも固い。それと比較すると、もともとビジュアルがないものにビジュアルを与えるのは、自由度高すぎて無重力だし、やりがいがある。
たくみ:上演芸術と複製芸術、そこでの宣伝美術は決定的に意味が違うなと。作品は何だろうとなったときに宣伝美術が重要という話は、映画のフライヤーだと起きにくいのかもしれない。舞台のフライヤーにはなにか特別なものがあるのかも。
◎奥泉理佐子
建築とデザインの共通点。このあいだ、ハラさんと「こう振り向くしかない振付」の話をした。電車に乗って、どこの駅かを確認するためにパッと振り返る。そこには「この形になるしかなかった身体」がある。前についた目、身体のかたち、その可動域から必然的に導かれるかたち。必然性だけが積み重なって生まれる身体の振付と、ある角度で上りきれば前に見える景色が限定されて、必ず「それ」を見させられるように誘導される階段の構造は似ている。モノ、壁、窓のような物質には、のっぴきならない現実性がある。でも、(標識のような)サイン計画は、もう少し親切さみたいなものがある。「→」は確かに記号の暴力を帯びているけれど、乱暴な現実のモノを整理する役割がサインにはあるなと思いました。
◎小林勇輝
こういうディスカッションのときに身体性の話になると、僕は悲しくなることがあって。だいたい演劇やダンスや俳優の話で終わってしまうから。パフォーマンスアートに辿り着くまでに時間がかかると毎回思う(笑)。いや、誰のせいでもなくて、そういう風に今につながってしまっている過去のこともあるし、これからどうしていくかの問題でそこの仕事を僕はしている。
〆切があるという話。パフォーマンスアートで僕は最初から最後まで不確実なままやっている。僕にとっての〆切はパフォーマンスが終わるとき、ずっと不確実なままやっていて、〆切という名のタイムリミットで終わる。でも自分のなかでは全部終わっていなくて、ずっと不確実なままの時間が続いている。武本君が言った「転んでも良い」とか、ある意味では失敗しても良い──失敗とは何かの話になるけれど──という前提で、そういうことの繰り返しをやっている。ダンスの振付や俳優の発語とは別の身体性がパフォーマンスにはあると改めて思いました。
◎三野新
演出は正解だと思う人がいる。でも「正解」なんて絶対ない。演出家主導の正解/不正解はヒエラルキーを作るから、パワハラ的なものの温床になっている。演出家と出演者は同じ距離であるべき。何を基準にするかというと、戯曲がある。その等距離感をどのように形作り、配置するかが演劇の上演だと思う。不確実性は演劇やダンスにもある。でもそれを隠していたり、形式だから正解あるよとか、そういうふうなフリをしているだけ。
◎ハラサオリ
「観客が求める方にいっちゃう」で思い出したのが、私はお客さんのためにやっている意識はなくて、お客さんと何をするか、どういうプロブレム・イシューを扱うかを意識している。例えば、キャンプファイヤーで火(イシュー)を囲む場を、アーティストの立場から創作している。みんなにきれいな火を見せるためにやっているわけではい。でもオーディエンスの中には「客」という言葉が含意されている。オーディエンスはカスタマーではないし、ダンスはサービスではない。でもコロナ禍では「芸術家はサービス業」という分類が可視化されていて面白い なと思った。だから、私はなるべくオーディエンスと言うけれど、「お客さん」と呼んでいるうちに「サービスとカスタマー」の関係になってしまう。アーティストとして、見る人に何を求めるのかを明確にするために、なるべく「観客」という言葉を避けるようにしている。
◎小林勇輝
僕も学部生のときは絵を描いているときが多かった。絵を描いている行為とそこで生まれる痕跡との対話が好きだった。あるとき、絵の構想や形を意図的にデザインしている自分に気づいた。そうしたデザインへの反発でパフォーマンスを始めた。自分のなかの飽きが絵の中に出てきて身体を直接的に使うようになったわけです。……でも最近は、パフォーマンスをたくさんやるなかで不確実性が失われる感覚もある。このモノと場所を使えば30分は絶対できるとか、どうなるかわかってしまう。そうするとまた未来予想図的にデザインしている自分がいることに気が付きます。グラフィックデザインとは違うけれど、僕にとって身体とデザインの関係はそういうもの。
◎三野新
デザインと身体、テキストから遠いところまで来た。デザインはすでに作られているものとしてのメタファーとしてもある。だから不確実性はアートとも聞こえる。でも、不確実性もデザインだなというところもあって、その境界も曖昧になっている。
結び
トークの最後は、三野の言葉で締めくくられた。
三野:平面のデザインの話から空間、環境、三次元的・四次元的なデザインの議論にまで拡張できたと思う。デザインがそんなに単純なものでなく、制作・演出・パフォーマンスに複雑に組み込まれている作業の一つだと意識されて面白かった。そういう感覚でデザインを考えると、良いものが生まれるんじゃないかなと思いました。
*1:コミュニティデザインに関して、石塚はなかば冗談めかして、次のように言っていた。「コミュニティデザイン、面白いですね。確かに今日、客席にも友人がいますけれど、二次会までデザインしますからね」。ただし、しごく当然だけれども、書籍のデザインは読者のコミュニティを設計する(かもしれない)間接的な働きかけであり、飲み会をデザインするような直接的な働きかけとはまた異なるだろう。
*2:煩雑になるので「舞台芸術/上演系芸術/パフォーマンスアート」の諸形式の表現を「上演系芸術」に代表させる。
*3:エディトリアルデザイン、ブックデザイン、グラフィックデザインと呼ばれる、販促やプロモーションを前提にしたデザインの場合は、①表現の作者ではない、②受け手(読者)の母数(市場)が大きい、③受け手の集団とは流通を介して間接的に関係する、といった諸々の理由で社会的ルールの拘束力が強くなる。そのため、山本は「演出」と「デザイン」を対比して、前者を「自由な感じ」と表現し、三野は「僕は演出のことを考えている」と述べる。ただトークにおける演出とデザインの関係はかなり錯綜している。近代とともに生じた演出の職能は「舞台上の諸要素──音、光、身体、言葉など──をたいていは戯曲の舞台化のために調和させる仕事」だと私は理解している。そもそもの初めから演出は戯曲(他者の表現)を立体化する空間デザインの仕事だったのではないだろうか。
*4:これを方法論的亡命と言えるだろうか? 「土地や財産を奪われ、不確かな場所に向かうように迫られ、繰り返し拒絶され、洋上もしくは無人地帯としての境界に追いやられる人々、あるいは、誰にも望まれずに国を後にする人々」のように「突然の孤立と根無し草状態」に追いやられた亡命者や難民(トリン・T・ミンハ『ここのなかの何処かへ 移住・難民・境界的出来事』、小林富久子訳、平凡社、2014年、p.70)に付与される異邦性は、三野の言う「無重力空間」における個のありかたと近似している。一方は戦争や紛争で政治的に強制されるものであり、他方は自発的なそれであるという違いを除いて。
*5:集合的なコミュニティの形成には、コミュニティの開き方を操作する技術も求められるだろう。たとえばPORTは、完全に他者に開かれているフルオープンな公共圏でも、完全に他者から閉ざされているクローズな親密圏でもない、セミオープンな親密圏として設計されている。いわば、重力(共同体)と無重力(剥き出しの個)、職能(スキル)と力能(ポテンシャル)、仕事と遊び、友達と市民、共同性と異鳴性、オープンスペースとコミュニティスペースの“あいだ”をうまく創り出しているように思う。
*6:これは感覚的によくわかる話で、時給でバイトしている限りは時給以上に働きたくないし、何らかの受注業務は時間単価に見合うかたちで業務の効率化を図るものだ。
*7:もちろんこうした個々人の自発性を高めるモチベーション管理は対価に見合わない労働を自己実現のイデオロギーで正当化する「やりがい搾取」や「ブラック労働」の問題へと直結する。自発的な取り組みとやりがい搾取を区別できるのかどうか。この問題は、活動資金が潤沢とはいえないアートコミュニティ/コレクティブ界隈においては、現在進行系の課題である。
渋革まろん
批評。「チェルフィッチュ(ズ)の系譜学」でゲンロン佐々木敦批評再生塾第三期最優秀賞を受賞。最近の論考に「『パフォーマンス・アート』というあいまいな吹き溜まりに寄せて──『STILLLIVE: CONTACTCONTRADICTION』とコロナ渦における身体の試行/思考」、「〈家族〉を夢見るのは誰?──ハラサオリの〈父〉と男装」(「Dance New Air 2020->21」webサイト)、「灯を消すな──劇場の《手前》で、あるいは?」(『悲劇喜劇』2022年03月号)などがある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
