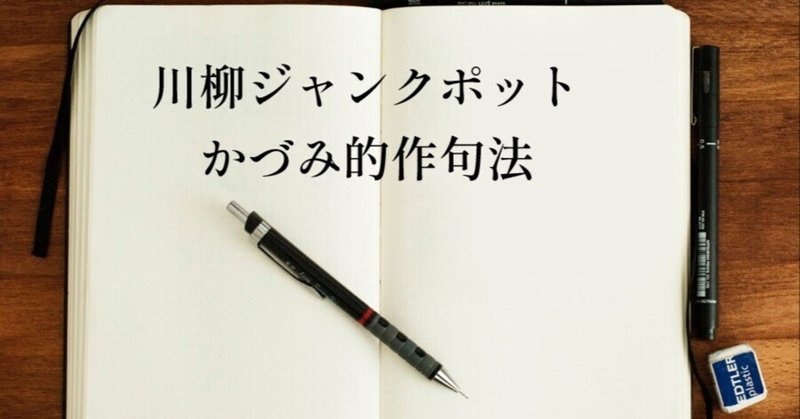
かづみ的作句法vol.4:選について
川柳句会に参加すると、投句だけではなく選をする機会もあると思います。選をすることについて、わたしが習ったことや心掛けていることなどを記します。
物理的な選の仕方
1.句箋は三本川で
紙の句箋で投句するタイプの句会での選は、基本は「三本川」で行います。すなわち左から「入選」「迷う句」「没」の三つに句箋を分けていくのです。最初は考え込まず、「絶対に入選」「絶対に没」を振り分け、少しでも迷った場合は真ん中に入れます。
入選数が決まっている場合で、一番最初に選んだ句で規定数に達していれば問題はないのですが、大抵は数が足りていないケースが多いです(わたしの場合)。その場合、「入選」と「没」は別にして、「迷う句」でもう一度三本川に振り分けて選を進めます。
2.誤字がある場合は没にする
句会での句は一字も直さずに鑑賞するのが基本です。漢字の誤用はもちろん、直筆で間違った文字を書いている句も没にします。句意がどんなに良くても、涙を飲んで没です。
3.達筆過ぎて読めない時は没にする
手書き句箋の場合、達筆過ぎて解読出来ないときも没にします。他の人に「この字読めますか?」などと訊いたりはしません。選をするときは、すべて自分の判断にて行います。特に、選の場では他の方も選に集中しています。声をかけて邪魔をしてはいけません。
4.没句は振り返らない
三本川で「没」にした句は振り返りません。選句の時間は決まっていますので、迷い出すときりがないです。そのため、ある程度の割り切りが必要です。「没」の句を拾うか拾わないかで時間を使うよりも、「迷う句」を「入選」に入れるかどうかに当てます。
5.題からの発想は広く採る
題詠の場合、作句するときはなるべく題に忠実に作ることを心掛けますが、選の時にはガチガチに捉われず広く受け入れます。自分以外の方の発想力を楽しみましょう。しかし、時々発想を広げ過ぎて題とは到底結びつかない句を出される方もいます。自分が「これは題に沿っていない」と判断したら、どんなに良い句でも没です。
6.同じワードの句は絞り込む
題詠の場合、同じワードの句が多く集まることがあります。例えば、題「黒」だと「フライパン」を使った句が多いといったことです。もちろん良い句と思えば同じワードを使っていても入選にして問題は無いのですが、わたしは句意によほどの差がある場合以外は、1句~2句くらいに絞り込みます。より多くの発想での句を採りたいと思うからです。これは、わたしの傾向で、あまり絞り込まない選者もいらっしゃいます。
7.特選句の選び方
句会にもよりますが、わたしが出てきた月刊「川柳大学」系の句会では、入選句は平抜き(規定数)+特選(1句)で選びます。特選句は単純にその日一番優れていると思った句を特選にすれば良いです。ですが、実際は「誰が読んでも納得する立派な句」を選びがちで、むしろ平抜きの止め(特選の前の句)に選者の好みが一番出るのだとか(時実新子談)。
ちなみに、わたしは特選句を迷うことはありません。三本川に分けている時に、フワっと(本当にフワっと)「自分、特選句です」と句の方で言ってくるのがわかるのです。この現象は他の方にも起こるのか確認してみたいところです。
8.披講の順番
入選句を選び終えたら、次は披講する順番に並び替えます。これも好きな順番に並べてよいのですが、メリハリを持った披講にしたいものです。
冒頭の句は、選者がどのような選をするかを宣言するようなものです。わたしは、なるべく華やかで強い句を置くようにしています(わたしの好み)。あとは、句姿が近い句は離す、体言止めを続けない、強い句の次にはしみじみした句を置く…等、入選句で物語を綴るように並べます。
選の心構え
9.誠心誠意選をする
選をする時一番大切なのは、句に誠心誠意その時の自分すべてを尽くすことです。自分が投句することのことを考えれば、その1句が作者にとってどれだけ大事なものかわかると思います。投句に対し、馬鹿にしたり嘲るような態度は絶対に許されません。
10.卑屈にならない
特に選を始めて間もない頃は、自分の選に自信が持てず「わたしなんかが選んでいいのか」と思うこともあるでしょう。しかし、そう思うこと自体が句に対して不誠実です。今日その時の自分が全力で選んだと言える選が出来れば良いのです。卑屈になるのは止めましょう
11.傲慢にならない
選者は神様ではありません。句会でただ選者であるだけです。偉くもなんともありません。「句を選んでやる」「特選に採ってやった」というような考え方は止めましょう。昔は、選者は先生と呼ばないといけないみたいなこともあったみたいですが、そんな時代錯誤な上下関係は清算していきましょう。
12.選んだ句に責任を持つ
選をするということは、自分が作句したのと同じくらいの責任を負うことだと考えます。何故、その句を選んだのかをきちんと説明できるようにしておきたいものです。もちろん理屈ではなく感覚で「この句は素晴らしい」と思って採る句もあるかと思います。その際も「なんとなく良いから」ではなく、その句を読んだときに自分がどのような感覚に陥ったかを言語化出来るといいですね。
13. 没にした句にも責任を持つ
没にした句も、出来れば何故没にしたかを訊かれた場合に答えられるようにはしておきたいものです(積極的に言う必要はありません)。投句者の中には「何故、この句を没にしたのか」と質問する人もいるでしょう(若い頃のわたしがそうでした)。その際に、「なんか嫌いだから」では納得させるのは難しいです。もし詳細な理由が見つからない時には「わたしにはわからなかった」「わたしとは相性悪かった」と言ってしまっていいと思います。そして、他の選者に投句することを勧めるといいでしょう。
14.くよくよしない
すべての句を入選句と出来ない以上、没句が出るのは仕方ありません。そして、自分が没にした句が他の方の選で入選するということも珍しくありません。また、心ない人から「この句を没にするなんて信じられない」「あんな句を入選させるなんて見る目がない」的な非難をされることもあるかもしれません。しかし、いちいちくよくよしないことです。自分は誠心誠意すべてを尽くして選をした、と胸を張って言えるなら何も恐れることはありません。ご意見はご意見として「今後の参考にします」くらいで受け止めましょう。
最後に
ざっと、思いつくまま書いてみました。なんだか「いかに没にするか」を書いた気もしますが、選は「いかに良い句を選ぶか」が基本です。ただ、心理的に他の方の句を没にするのは心苦しさを伴いますので、それを払拭する際の参考にしていただけたら幸いです。
選をするのはとても精神力を使いますが、自分が良いと思った句を「これ見て!これも!」と披露できるのはとても楽しいことです。それに、選をすることで句を読む力もついてきます。もし、句会やイベントに選者として呼ばれたら、素晴らしい体験が出来ると思って恐れずに引き受けてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
