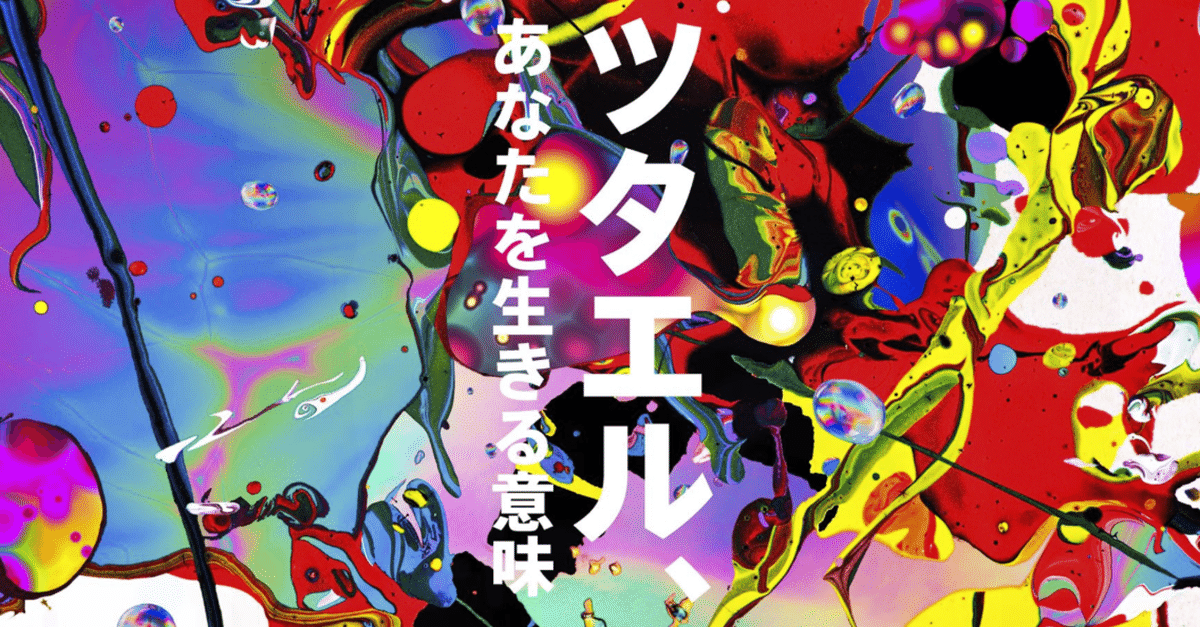
生きる意味の多様性を伝え、多くの「生きる」を肯定したくて、今日メディアを立ち上げます
こんにちは。「挑戦者の翻訳者」として事業家のあふれる想いを、理念や社名、商品名などに翻訳している大野幸子です。この仕事を通じて、これまで60社近くの想いを翻訳してきました。
この仕事をやってきた中で、自分の中に芽生えた使命があります。その使命を全うするための一つの手段として、今日メディアを立ち上げました。
ここでは、なぜメディアを立ち上げたのか、そこに込めた願いはなんなのかについてお伝えできればと思います。
私の中の憤り
私は普段、4〜5時間ほど経営者のお話を聞き、それを理念や社名、ときに商品名としてコピーライティングしてお渡しする仕事をしています。その数時間は単なるヒアリングというよりは、広く深くその方の人生にもぐり、一緒に人生を考える時間でもあります。
理念をつくるなかで彼らと向き合い、また人生の意味を共に考える中で知ったことがあります。それは生きる意味の美しさと、その多様性です。「世界の真理を探求したい」「人間の可能性の限界を見てみたい」「この世界にバランスがあってほしい」「ありったけの感情を感じ、それを表現したい」etc… そこには多様な生きる意味がありました。
その一方で、何か社会性の高い意義を掲げないと自分あるいは事業には価値がないのではないか、と苦悩する方も数多く見てきました。実際は、ご自身の軸や生きる意味に従った結果として社会の役に立ったということも多く、社会貢献は結果論という側面もあると思います。しかし社会によく出回っている「人を笑顔にする」「困っている人を助ける」「社会問題を解決する」などの王道の大義がよしとされ、それを感じられない自分には軸がないと思い込んでいる方がいます。
そういう話を、経営者ではない方からもよく聞きます。自分は、こういうことが好きだしやりたいけど、それは独りよがりかもしれない、ただの自己満足かもしれないと思い、せっかくの自分の軸になんとなく後ろめたさを感じている人が潜在的にたくさんいると感じています。
理念は外向けにお化粧された言葉。そのもっと手前にある「生きる意味」から、あなたの生きる意味に触れてほしい
本当は軸があるにも関わらず後ろめたさを感じてしまっている方に対して、あなたのその想いは立派な軸であり、生きる意味であることに気づいて欲しくて、このメディアを立ち上げました。
私の行う理念づくりは、大きく2つのステップから成り立っています。
STEP①:その方の人生に対する核(=生きる意味)をみつける
STEP②:その方の核を事業と繋げ、社会的意義と結びつける(=理念)
このステップの結果、最終的に出るのは②の結果生まれる「理念」です。それ自体が想いの結晶であり、その方の人生や会社の存在意義を描いた芸術作品だと思っています。
しかし、世の中ではその理念やビジョンという大義名分だけが出ていて、そのもう少し手前のステップ①にある「生きる意味」というものはなかなか出てきません。出てきても、かなりお化粧された(=社会性が高く脚色された)ものであり、もっとリアルな生っぽいものは表に出てきません。
その結果、多くの方が「ああいう社会性が高く、かっこいいものじゃないと自分の軸とは呼べない」といって自分の大切な生きる意味をそっとしまい込んでしまっている…。
私はその状況に対して、少しでも声をあげたくて、このメディアを立ち上げることにしました。
今回のリリースまでにこぎつけた記事は3つ=生きる意味も3つで、「多様性」なんて言うにはまだまだ全然足りないかもしれません。だけど、起業して一生懸命やっている、まだ無名かつ途上の方のリアルに触れること。そこには、既に成功した方の自伝本とは違う手触り感がある。だからこそ自分にひきつけて考えられる材料になるのではないか。そういった願いをこのメディアに込めています。
最後に
理念づくりを通じて生きる意味に触れた挑戦者のココロイキから、あなたを生きる意味に触れてほしい。その営みを通じて自らの「生きる」を肯定し、自分の心に正直に生きる人が増えて欲しい。これが「ココロイキ =ココロでイキる」をビジョンに活動する私の願いです。 どうぞ、誰かの真剣な生きる意味に触れ、ココロでイキる世界へと歩き始めるきっかけとなりますように。そんな想いを込めてこのメディアを世に送り出します。
こちらがご紹介した新メディア「挑戦者のココロイキ 」です。
もし感想などありましたら、TwitterやFacebookなどで教えてくだると大変大変嬉しいですし、出演者の方にお伝えさせていただきます。
Twitterの場合は、#ココマガ (=ココロイキマガジン)のハッシュタグをつけてくださると、見つけやすいです。
もし、理念づくりに興味がある、このメディアへの掲載に興味があるという方がいらっしゃいましたら、ページ内「掲載のお問い合わせ」からご連絡ください。みなさんのココロイキ に出会えることを楽しみにメディアの運営をやっていきます^^
まだまだ生まれたばかりのメディアを、これからどうぞよろしくお願いいたします。
twitterのフォローはこちらから
「言葉の美しさは、見ている世界の美しさ」 少しでも新しくて、美しい視点をお届けできるよう、好奇心全開で生きています。いただいたサポートは、全力好奇心の軍資金として、大切に使わせていただきます♡
