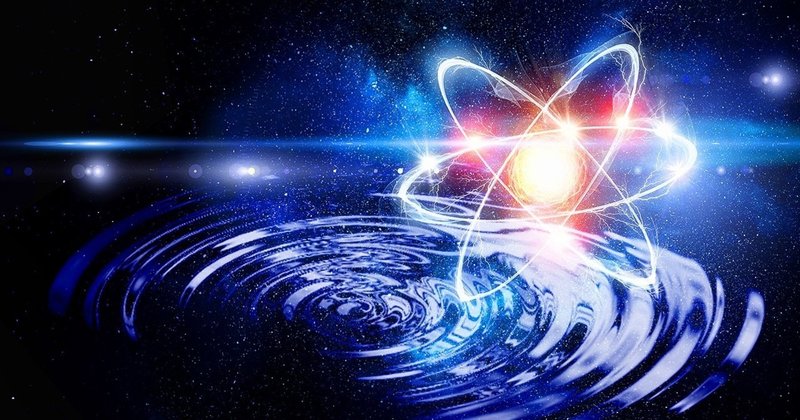
水とエーテルと量子場脳理論 Vol.1
執筆:ラボラトリオ研究員 杉山 彰
エーテルという、この悩ましい言葉
宇宙には、何か得体の知れないものが充満しており、その中に大地(地球)が浮かんでいるのだという考えは、古代ギリシャのアナクシマンドロス※1の時代(紀元前600年)頃から存在した。アナクシマンドロスは、それをアペイロン(Apeiron:形をもたない無限なるもの)と呼んだ。パルメデス※2は、無い物は考えることもできない、ゆえに空虚な空間は無いと論じた。また、デモクリトス※3は宇宙には最小単位の微分子(原子)が存在し、この原子が運動するには空虚な空間が必要で、ゆえに宇宙は、原子と空虚な空間の二要素からなり、同じ原理から成るといい、それに対し、アリストテレスは四元素説(空気、火、水、土)を認め、第五の元素としてアイテール(Aether:上方の澄んだ空気)が存在し、宇宙はアイテールで満たされているといった。このアイテールが近世においてエーテル(Ether:光が伝播するために必要だと思われた媒質)として提唱され、そしてさらに、このエーテルはコンピュータやネットワークの極めて重要な次世代ネットワーク技術の呼称としてイーサーネット(Ether・net)のイーサー(Ether:あまねく存在する)という言葉として進展したのだった。
また、このイーサーは、驚くべきことにナザレのイエスのイスラームにおける呼称でもあったのだ。キリスト教においてキリスト(救世主)として信仰の対象とされるイエスは、イスラームではイーサーと呼ばれ※4、イスラエルの子らを新しい啓示インジール(福音書)のもと導くために送られた預言者と位置付けられている。Etherという一つの単語の語源が、エーテル、イーサー、アイテール、さらにはイエス、とそれぞれ読みが異なり、意味までもが微妙に異なるようにイメージされる。現代の科学者にとって、“エーテル”という用語ほど、いとわしい言葉はなく、それは初期物理学の過去の用語の残滓であるばかりでなく、古代哲学の超現実的で霊的なニュアンスをも持っていると嘆いたのも無理のないことである。
七沢先生は、エーテルについて、言霊学の観点から水・エーテルについて独自の理論を次のように展開している。
“水が、3態(固体、液体、気体)に変化するというのは、人間の生活圏内の中で、そういうことが起こるのは水だけだということは分かっている。そして、その水が、宇宙の始まりの時から水という概念があるというか、そういう考え方が、日本の古事記の神話の天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)という、水の中の主という意味がある。神道五部書(御鎮座次第記)文献に天之水中神の由来が記述されている”
また、
“天地は一水の徳によって成り、その天地開闢の当初に所生の神が天之御中主神、または豊受皇大神と称し、外宮祭神に坐しますという。天之御中主神とは天之水中神の意にして、天地開闢当初の水気元神であり、大海中に存する一物なるが故に、この呼称があるとしている”
そしてさらに引用する。
“天之御中主神は、水中主神(みなかぬしのかみ)として、水を中心とした祭祀が神話の始まりにもなっているということが根源でもある。また、その水ということの西洋的な概念に、エーテルという言葉があるが、エーテルというのは、抽象概念というのか、宇宙が始まる時に出てきた物質というのかは定かではないが、そういうものが既にあって、そのハタラキを引き出す。それが、1つのヨーロッパ的な思考から見た時に、特に、ギリシャ的なスコラ哲学とか、色んな哲学が生まれますが、そういう一種のヘレニズムというものと、日本の古事記の神話とか、どこで融合するのかというのは、非常に大事なところになるのじゃないのかということを感じている。1つの表現としての水というもので、宇宙というものができあがってくる過程のようなものを、1つの「場」であり、「命」というものが、動かされているものが、そういうものが、我々の水というものになるのではないかと思われるが、その水というものと同時に、宇宙というものが出来上がっていく。それが、137億年の宇宙でもありますけれども、それがまた、階層性になっていく時に、どういう風に、それが、新しい概念として出てくるかということを考えることが大切なところである。いわゆる、我々が住んでいる宇宙、あるいは、大宇宙というものの中身が、結局、光というものであって、その1つの存在というものが確認できるというか、視覚表象力だけではすまない。たとえば、ダークマター(暗黒物質)というところで、光を閉じ込めるような物質があるのじゃないかということも言われているわけである。今の宇宙論と、古事記という神話の1つの捉え方というものが、今の時代でも、もういちど考えるところがでてきている。このようにして、人間の想像力が宇宙を創造していくのではないか”
と述べている。
※1:紀元前610年頃の古代ギリシャの哲学者。タレス、アナクシメネスと共にミレトス学派(イオニア学派)の代表とされる。
※2:古代ギリシャの哲学者。南イタリアの都市エレア出身、エレア派の始祖。アナクサゴラスの弟子・クセノパネスに学んだとも、ピュタゴラス学派のアメイニアス(Ameinias)に師事したとも伝えられる(出典ウィキペディア)。
※3:古代ギリシャ最大の自然哲学者。師レウキッポスの説を受けて原子論を大成。「笑う哲学者」のあだ名をもつ。彼はエレア派の「存在」に対して,不断の運動の内にあってしかも無数に存在するアトモン (「原子」「不可分割」の意) と,アトモンが運動する場としての無限の空虚を原理として立て、原子の運動と集積によって生じる物体は形と配列と位置と大きさによって異なるが、温-冷,甘-苦,柔-硬などの質的な相違は感覚的印象に基づく習慣的なものにすぎず,真実存在するものはただ原子群と空虚のみであると説いた。
※4:出典:ウィキペディア:オクスフォード・イスラーム辞典
(つづく)
・・・・・・・・・・
【杉山 彰(すぎやま あきら)プロフィール】
◎立命館大学 産業社会学部卒
1974年、(株)タイムにコピーライターとして入社。
以後(株)タイムに10年間勤務した後、杉山彰事務所を主宰。
1990年、株式会社 JCN研究所を設立
1993年、株式会社CSK関連会社
日本レジホンシステムズ(ナレッジモデリング株式会社の前身)と
マーケティング顧問契約を締結
※この時期に、七沢先生との知遇を得て、現在に至る。
1995年、松下電器産業(株)開発本部・映像音響情報研究所の
コンセプトメーカーとして顧問契約(技術支援業務契約)を締結。
2010年、株式会社 JCN研究所を休眠、現在に至る。
◎〈作成論文&レポート〉
・「マトリックス・マネージメント」
・「オープンマインド・ヒューマン・ネットワーキング」
・「コンピュータの中の日本語」
・「新・遺伝的アルゴリズム論」
・「知識社会におけるヒューマンネットワーキング経営の在り方」
・「人間と夢」 等
◎〈開発システム〉
・コンピュータにおける日本語処理機能としての
カナ漢字置換装置・JCN〈愛(ai)〉
・置換アルゴリズムの応用システム「TAO/TIME認証システム」
・TAO時計装置
◎〈出願特許〉
・「カナ漢字自動置換システム」
・「新・遺伝的アルゴリズムによる、漢字混じり文章生成装置」
・「アナログ計時とディジタル計時と絶対時間を同時共時に
計測表示できるTAO時計装置」
・「音符システムを活用した、新・中間言語アルゴリズム」
・「時間軸をキーデータとする、システム辞書の生成方法」
・「利用履歴データをID化した、新・ファイル管理システム」等
◎〈取得特許〉
「TAO時計装置」(米国特許)、
「TAO・TIME認証システム」(国際特許) 等
この記事は素晴らしい!面白い!と感じましたら、サポートをいただけますと幸いです。いただいたサポートはParoleの活動費に充てさせていただきます。
