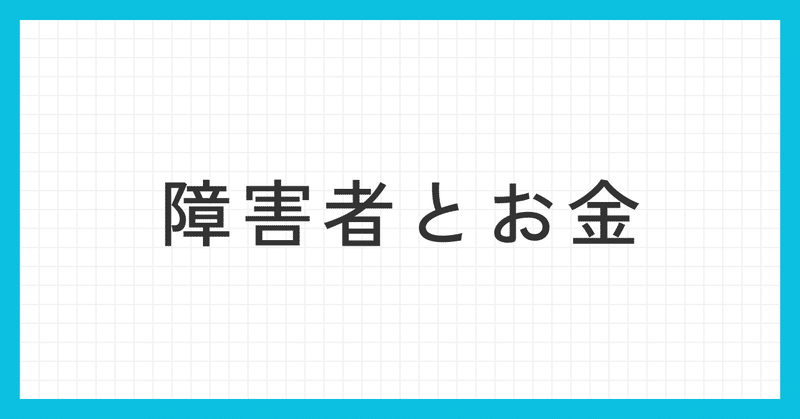
障害者とお金
私たち持続未来グループではたくさんの障害者に働いてもらっています。
また、働いてもらうだけではなく、放課後等デイサービスやグループホームの利用者さんたちと関わっています。
障害者とその家族の皆様を合わせると優に200人以上の方々と接していると、いろいろな気づきがあります。
その中で、今日はお金のことに焦点を絞ってお話します。
※私たち持続未来グループが関わる障害者のほとんどは、知的障害や発達障害のある人たちです。
■ 本人の意識
これは人それぞれですね。
そもそも貨幣価値というものを理解できない人もいます。例えば、1万円札よりも500円玉の方を欲しがる人だっています。
(でも、この1万円札よりも500円玉を欲しがる人、ウチの清掃サービスでしっかりと働いてくれています。貨幣価値を理解できる能力と就労することは無関係です)
給料が入るとすぐに使っちゃう人もいれば、ため込む人もいます。
でも、共通しているのは「稼ぎたい」という意識です。
私たちからすると当たり前のことなのですが、世間の一部では「障害者はお金ではなくやりがいが大事」とか「お金のことに頓着しない純真な障害者像」みたいな幻想を持っている方も少なくないようです。
そんな訳ありませんから。当たり前ですが障害者も普通の人間です。
■ ご家族の意識
親御さんには、「自分たちがしっかり働いて財産を残してあげないと」と考える方も多くいらっしゃいます。
私は当事者でもなければ、家族でもないので安易に「わかります」とは言いませんが、その考え方もある程度理解はできます。
一般就労と言われる最低賃金以上の給与を得られればよいのですが、そうではない働き方の場合は毎月の収入は、全国平均20,000円未満です。
この場合、障害年金(月当たり65,000円~81,000円)と合わせても、最低限の生活はできないからです。
とはいえ、過剰に財産を残そうとするのもどうかと思います。「児孫のために美田を買わず」は障害者にも当てはまることです。
■ 関わる人たちの意識
これは、特にグループホームなどの生活の場での支援者と呼ばれる人に多いと感じるのですが、とにかく無駄遣いはするなという考えです。
気持ちがわからないわけではありません。
知的障害、発達障害のある人たちの中には、明らかな無駄遣いをしたり、場合によっては詐欺まがいに引っかかることが少なくありません。
それに対して、とにかく一銭でも無駄遣いさせまいとして、自動販売機でジュースを買うことを咎めたり、エステに行くことを禁じたりする支援者が居るわけです。
それは行き過ぎだと思うのです。
基本的に、健常者がやっても咎められないことを、障害者がやったからと言って咎められるいわれはないのです。
彼ら彼女らにも無駄遣いする権利があります。
■ 資産運用の意識が希薄
最後に資産運用について。
これは本人、家族、支援者とも考えがアップデートできていないように見えます。
昨今、一般的にはNISAが話題になり、長期・分散・積立の概念が浸透してきています。
ところが、障害者の周辺ではいまだに資産運用=貯金という考えが一般的だと感じます。
投資のリスクを当事者に理解してもらうことの困難さがあり、一般でも新NISA利用率が4割弱であることも勘案すると、まだこういう状況なのは仕方ないのかもしれません。
しかし、これからのインフレ局面では、将来的な障害者の持つ資産の目減りが心配ではあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
