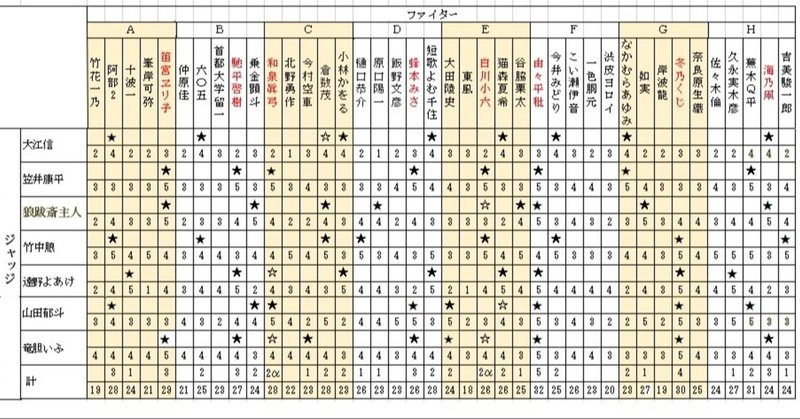
1回戦ジャッジによる作品評 大江信
陳腐な言葉で愛を君に
大江信
<1>
「私の宗教は、私たちのか弱い貧弱な頭で見てとることができるほんの細部にあらわれる無限の優越した精神に謙虚に感嘆するというものです。感情に深く根ざしたそうした確信、理解を超えた宇宙に示される優越した論理的な力が存在するという確信が、私の神の概念をなしている」アルベルト・アインシュタイン
「語り得ないことについては、沈黙しなければならない」ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン
「わたしはきみにこの話についてのいろいろな見解を教えているだけだ。そういう見解をあまり気にしてはいけない。不変なのは書物で、見解などというものは、しばしばそれにたいする絶望の表現にすぎないのだ」フランツ・カフカ
「それまでは未知だった実存の一部分でも発見しない小説は不道徳であり、認識こそが小説の唯一のモラルなのだ」ミラン・クンデラ
【採点基準について】
1点(1回戦通過に強く反対する)
2点(1回戦通過に反対する)
3点(1回戦通過に賛成も反対もしない)
4点(1回戦通過に賛成する)
5点(最も優れた作品群)
採点方法について。A~Hグループの順に読み進め、一読時作品毎に上記の5段階で仮の点数を付け、再読時に全体とグループ間のバランスを考慮し点数の調整を図りました。再読時に評を書き進めるなかで評価が変化した作品もあります。同じ点数内での差異化、階層化を図るために、ジャッジ評では、グループ毎の必要性に応じて以下の順の11段階で評価をしています。
① 1点
② (1点に近い)2点
③ 2点
④ (3点に近い)2点
⑤ (2点に近い)3点
⑥ 3点
⑦ (4点に近い)3点
⑧ (3点に近い)4点
⑨ 4点
⑩ (5点に近い)4点
⑪ 5点
再読時に全体とグループ間のバランスを考慮し5段階評価の調整をし、その後グループ毎にジャッジ評を記しながら評価を決める際に11段階評価をおこないました。
11段階評価は、あくまでグループ内での序列を示したものであって、全体の序列化には適用されません。
【注意事項】
※以下の内容は、作品の要約的記述やネタバレ、結末の開示を含みますので、作品をよく読んだ上で読まれることを強くお勧めします。
※以下の内容は、『ブンゲイファイトクラブ2』1回戦参加作品について、作品を読み、各作品の採点をおこない、グループ単位での勝者を決めるために書かれています。書かれた内容は、作家論ではなく(ひとつの作品についての)作品論であり、すべての読み手に対して開かれたものですが、作品に対するある時の一つの見方にとどまるものであって、その見方は流動的であるために決して恒常的なものではなく、書かれた内容はすでに過去に流れていったものになります。また特定の個人や集団、組織を賛美したり、非難、誹謗中傷するためのものではないことをここで断っておきます。
■(Aグループ)「青紙」竹花一乃
評タイトル『ポストヒューマンの人類史』
超高齢社会が到来し国家の財政健全化が最優先される社会で、「寿命申告制」が導入された。60歳の定年になると「青紙」が来て、定年後働く年数と同じだけ余命を生きてもいい。 来年60歳になる独身の「俺」に、同期のスズキは「早く(余命を)決めたほうがいいぞ」と言う。
議員や公務員は免除特権を持っているが、背景は語られない。自分で決めた余命の間は生活が保障されるため、安心した国民の大部分は制度導入に抵抗しなかった。寝たきりの認知症患者になっても経済合理性の粋を極めた専用の特別養護老人ホームに入居することができる。
自動顔認証カメラで監視されており、反対デモに参加する人は少数だった。
同期のスズキは80歳まで働き100歳まで生きることを決めた。
人々は余生に関心を向け、生前葬が空前のブームとなった。
自分の寿命だけを夫婦で合意した年数より過多申告する妻。夫の寿命だけを過少申告する妻。夫婦が一緒に死ぬことに意義を見出せなくなった人々。妻の裏切りに絶望し失踪、自殺する夫たち(同期のスズキもその一員となった)。
自由な老後や楽しい余生などない。生きる意味はもはやない。
国家は個人の自然寿命を把握しており、自己申告制による人々の余命も織り込み済みで、「寿命申告制」は設計されていた。
この国家で生活する人々(免除特権を持つ議員や公務員を除く)は、私たちとどこか違う。いや、「どこか」どころか、かれらは現実の私たちとは完全に断絶した「ポストヒューマン(人類進化)」だ、とする向きもあるでしょう。
わたしたちにあって、かれらに欠けているもの。もしくは、かれらにあって、わたしたちに欠けているものは、何でしょう?
どの家庭でも妻が役所に青紙を提出に行く。夫を裏切る妻、自殺する夫のパターン化された構図には、明確な性差が表れています。そう、ポストヒューマンの世界では、性別役割分担が明確らしいのです。妻は、夫婦が一緒に死ぬことに意義を見出せなくなっていますが、夫は裏切りに絶望しています。ジェンダーが流動性を失った社会で、「愛」を失った妻と、「愛」にすがりつく夫が意味するものは何なのでしょう。
語り手の「俺」は、男でしょうか? 女でしょうか? 分かりませんが、独身であることも関係しているのか「俺」は「愛」の物語の一員にはなっていない様子で、「愛」の犠牲者となったスズキと対比されています。
「自由な老後や楽しい余生などない。生きる意味はもはやない」と記す「俺」は、ポストヒューマンの人類史を、読者の私たちとポストヒューマンとの間に立って語る橋渡し役でしょうか? 一体、何のために「俺」はこの人類史(個人史)を記すのでしょうか?
私は、「俺」は、まだ「ヒューマン」の心を持っている「ポストヒューマン」になりきれない人物として認識しました。冒頭部を思い出してください。「ああ、青紙か。俺は独身だし、まだ詳しく見てない」と言っている「俺」は、この社会に馴染めていないようです。
全体主義が高度に達成されつつある社会下で「人独りの生きる意味」を探求するために、ポストヒューマンの人類史を記す「俺」は、この作品の中で唯一の希望の存在として描かれている、と私は読みました。
「ポストヒューマン」に侵食されつつありながらそれに抗おうとする「俺」の心がほんの僅かな「兆し」としてしか描かれていないので、読み手によっては、「完全なディストピア」として捉えてしまう危険性のある作品であると思います。作品の続きには「兆し」が形象化する場面(例えば、「俺」が同じ違和感を持つ仲間と出会い行動を起こす。免除特権を持つ議員や公務員と対峙する)が描かれるかもしれない、という予感はありますし、この作品はより大きな物語の「起」の部分だと解釈すれば期待は膨らむものの、1作品としてみると厳しい評価とならざるを得ませんでした。(3点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Aグループ)「浅田と下田」阿部2
評タイトル『「ぼく」の心の内奥』
上半身裸で腰に短いタオルを巻いただけの姿の小学校高学年女子「浅田」と銭湯の男湯で遭遇した「ぼく(下田)」は、最初戸惑うが、浅田がいなくなった父親を捜しに来たのだと知り納得する。父親は背が高くて二メートルくらいあるので見かけたらすぐ分かりそうだ。
ぼくと浅田は学校ではほとんど会話をしないが、翌日も銭湯で会話する。三週間前に父親は「風呂屋にいってくる」と言い残し失踪した。
ぼくは銭湯での見張りを引き受ける。
ぼくはうちの風呂(湯沸し器)が直り銭湯に行く必要性が無くなっても、銭湯に行って、それから「蒸発した」。
毎日銭湯に行きたいと言ったら、母親は嫌な顔をするだろう。
浅田には毎日銭湯に行くと約束してしまった。
ぼくは銭湯の中の「湯気」となることを選んだ。
その後の浅田はちょっと様子がおかしくなり、夜眠れなくなって、中学校に行っても母親に添い寝をしてもらっていた。鳴らない電話に急にでたり、宿題を忘れることも多くなった。
浅田の父親はホームレスをしていたが、家に帰った。
浅田はもうすぐ高校に入学する。
ぼくはまだ帰るきっかけをみつけられずにいる。浅田が声をかけてくれるのを待っている。
「解離性障害」は、「自分が自分であるという感覚が失われている状態」で、「つらい体験を自分から切り離そうとするために起こる一種の防衛反応」として定義されています。
解離性障害を起こした人と似通っているようにも見える「ぼく」ですが、決定的な違いは、「ぼく」が自らの意志で能動的に「蒸発」し「湯気」になっていることです。
母親に毎日銭湯へ行くことを許してもらえそうにないと悟っている「ぼく」は浅田との「約束を守るにはこうするしかなかった」。
湯気になった「ぼく」は、目が霞み、霞む目でみると人混みはひまわりの模様のように見えます。銭湯のなかにとどまっている「ぼく」ですが、浅田や浅田のお父さんが何をしているのかは手に取るように分かっていますし、浅田に「長い人生」があることも分かっている。『千里眼』を獲得した「ぼく」ですが、もはや銭湯のなかの「湯気」でしかないため、浅田のことを知ることはできても、具体的、能動的に働きかけることはできません。
「ぼく」は小学校にも行けなくなったはずですが(分身がいなければ!)、浅田は銭湯に「ぼく」を捜しに来ず、「ぼく」の活躍無しに「浅田」の父親は家に帰ってきてしまいます。
「ぼく」は、浅田が「おう、下田ぁ」と声をかけてくれることを期待しながら、湯気として銭湯のなかにとどまったまま、終幕します。
「ぼく」が「蒸発」し「湯気」となる場面で物語の内容は劇的に転回しますが、ドラマティックな描かれ方はしません。日常の一コマとして淡々と物語が進行することでかえって読者の叙情は喚起されるのではないでしょうか。ただ、「ぼく」の心の内奥が語られず、浅田とのエピソードも希薄であるために、どうして「僕」が浅田にここまで肩入れしなければならなかったのかは不明なままですし、浅田が夜眠れなくなったのはいつか、浅田のお父さんが家に帰ってきたのはその前のか後なのか、など重要な部分で素材不足が否めないことが、「ぼく」の物語に没入し切れない要因となりました。能動的に「湯気」になった「ぼく」が千里眼と受動性(その場にとどまり動けない)という相反的な能力を持つ状況設定には瞠目しました。(3点に近い)4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Aグループ)「新しい生活」十波一
あらゆる文芸作品が同じ場でジャッジされるブンゲイファイトクラブにおいて、短詩をどう読み、どうジャッジするのか。私は原稿用紙6枚の内に置かれた首(句)を繋がりのある「ひとまとめの文芸作品」として読み、ジャッジすることにしました。
1回戦では、短詩ならではの制約とその効果、読み方について、「短歌は幻想の核を刹那に把握してこれを人人に暗示し、その全体像を再幻想させるための詩型である」という塚本邦雄のことば、「歌を読むことは打ち上げ花火を打ち上げ続けることではない。歌という小舟を自分の中に浮かべることだ」という鶴田伊津のことばを胸に、だた、短詩であるために、ことさら持ち上げたり堕としたりしないことを自身に課しました。
評タイトル『コロナ禍で薄まったものは』 ※首は順にP1-①、P1-②~と挙げます。
コロナ禍における「新しい生活」が始まり、様々な事象が変化する日常の風景を「わたし」を中心とした世界観の中で描写しているものとして歌を読みました。歌からは、日常を歌で真摯にスケッチし続ける作者の姿も見えてきました。
心象を率直に記述した(ような)歌には、精緻な写実も屹立する象徴も謎めいた喩も無いにもかかわらず、コロナ禍を底流に読み込むことで、不穏が薄く広がる社会下での日常のふとした瞬間のありがたみが確かに感じられました。
P1-①新しい生活様式であたらしくなったおばちゃんの花壇水やり
外出機会が減り、庭仕事に精が出る「おばちゃん」ですが、おかげで花壇は新しくなり、ちゃんと水やりもされることで、草花も活き活きとしているのでしょう。巣ごもり需要でほくそ笑む園芸業者の姿まで浮かんできました。
P2-①新しい日常といって面白くそしてもとの温度にもどっていった
「新しい日常」という語感に面白さを感じ不謹慎に笑ってしまったのに、その面白さは次第になくなって元にもどってしまった。コロナ感染か? と心配した体温上昇に、なぜか面白さを感じた自分の不謹慎な失笑、そして体温は正常範囲にもどっていって、面白さも失笑も、体温も、すべてが日常へもどっていった、けれどもここにあるのは今までとは違う、まぎれもない「新しい日常」だった、と読みました。
P5-⑥池の縁にこどもを立たせいっせいに祝福をする夕焼けの水
コロナ禍で講堂に集合できず、屋外に並ぶこども達。その光景がむしろ写実的に美しく感動的な場面を作り出した、と読みました。
P6-②はじめからいないひとたちの起こらない別れも知っている秋空
コロナ禍で本来生まれてくる(受胎する)はずのこどもたちが生まれ得なかったことを哀しんでいる、と読みました。
定型を大きく外した破調で書かれた歌は、散文と定型との折衷をマイルドに達成した快作と読めなくもない、と頭では仮定しつつ想像力を働かせましたが、歌によっては間延びした印象があり、またそれらの連関によって生活感、個人史が垣間見えてくるという効果にも乏しく、むしろ生活感は巧妙に隠蔽されているようにも読めたため、コロナ禍での都市生活者の一風景の普遍化という書き手の意思は頭をよぎりましたが、総合的にはわざと薄められた味噌汁を飲まされているような読後感も否めなかったため、「ひとまとめの文芸作品」としての評価は厳しいものとなりました。「新しい日常」によって、私たちの日常の一部は侵されたかもしれないけれど、「新しく設定された日常」の中ゆえに垣間見ることができた生々しい生活感、個人史がもっともっとここにはあるはずだし、2メートル以内に近寄れない現実でも(だからこそ)人間ではない対象へ関心を向けて、人間と対照化しつつクローズアップした写実表現もできたはずです。2点と3点で悩みましたが、(3点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Aグループ)「兄を守る」峯岸可弥
評タイトル『兄とは』
全知の語り手(ゼロ焦点)が紡ぐ「あなた」と兄の物語。前半は、「兄を守る「あなた」の物語」で、後半は、「目覚めた「あなた」が兄の記憶を取り戻し始める物語」です。
前半、兄を守ろうとしてケルベロスに殺されてしまった「あなた」は、後半、長い眠りから目覚めます。そばには母がいて、兄が最期まで「あなた」を守ってくれたことを聞かされます。包帯と絆創膏で覆われた顔の「あなた」の記憶は不確かで、前半見ていた夢(と敢えて言いましょう)の中の「あなた」と兄、自分がどちらの顔をしていたのかも思い出せません。
ここでは、前半、実際は「あなた」と兄の立場は逆で、兄が最期まで「あなた」を守ってくれたのかもしれない、という可能性が示されています。
文末で、母が持ってきたらしい少し汚れた本のタイトル(読者には明かされない。「兄を守る」なのか……)を声に出して読み上げた「あなた」は「少し嬉しい」と感じます。「これからも兄はずっとあなたを守り続けてくれるだろう」と母は言います。本についてそれ以上の情報はありませんが、「あなた」と兄の絆の象徴として「本」は描かれている、と読みました。
そして、これは少し飛躍した読みかもしませんが、兄とは「本」そのもののことなのかもしれない、とも思われました。
トリッキーな描写力は読者を誘引する力がありましたが、文末の本のくだりを読んだときに感じたのは宙吊り感であって、前半と後半の物語が収斂された結末としてはどうしても解釈し切れませんでした。材料不足しており読解に大きな飛躍を必要とするので、多くの読者は置いていかれてしまったのではないかと想像します。謎めいた印象が後味悪く残る作品となってしまっていました。(1点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Aグループ)「孵るの子」笛宮ヱリ子
評タイトル『受胎へと至る道』
月経をセンシティブに受容する女の子の姿を一人称で記述することで、「うち」の感情、想いが丁寧にあふれんばかりに表現され、心の動きに寄り添いながら読み進めることができました。ただ、設定が小学五年生であることもあるのか、男性(精子)の存在感は希薄で、同級生と思われる「もう旦那さんに決めてるタツムン」の記述が申し訳程度に一箇所あるのみです。受胎のためには男性(精子)の存在が原則必要(科学技術の進歩により女性のみでも受胎可能ですが一般的に)ですが、「うち」の父親の存在は不自然に伏せられ、男性は物語に不要な要素として隠蔽、排除されているようにさえ感じられました。6枚のなかで要素を消化することは難しいという向きもあるでしょうが、軽薄な「タツムン」の記述により余計に欠落感が増す結果となっています。文章が率直過ぎる印象も受けました。時系列の組み換え、文体への非標準語の導入で読みを誘う意志は感じたものの単調さは否めませんでした。(2点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
◇◆ 以上により、【 Aグループの勝者は、「浅田と下田」阿部2 】とします。 ◇◆
■(Bグループ)「今すぐ食べられたい」仲原佳
評タイトル『食べられたい牛が食べられずに死に、残ったものは』
擬人化された牛の「今、一番美味しいときの自分を食べてもらいたい」という願望と妄想、それが達成されないことへの絶望の帰結としての自死が描かれます。一つのことに執着し過ぎたために、破滅へと突き進んだ個人、集団、国家の歴史的事実が思い返され、寓話的だと思いましたが、それ以上のものでもない、と読みました。牛には迷いや葛藤がなく、擬人化されている割に、単純極まりない思考しか許されていません。全知の語り手による牛の虐殺と、手のひらでもてあそぶことの快楽が過ぎており、そこには哀しみもあるけれども、生への渇望、もがきは感じられませんでした。読み手によっては、ヒンドゥー教への曲解や侮蔑に近い感情も受け取ってしまいかねないと危ぶみました。(1点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Bグループ)「液体金属の背景 chapter 1」六〇五
評タイトル『細胞の分裂と劣化、そして死にゆくもの』
個体化の原理がある⇒(何ものかによる)操作を経て⇒構成された個体が現れる。(ジルベール・シモンドン『個体化の哲学』)
人が車にはねられた。車から男がおりてきた。男は私を見て、何かを叫び、追いかけてきた。私は走って逃げたが、男は追いかけてくる。
私にぶつかって怒っていた人は、後から男にもぶつかられて「決まりごとのように」より大きな声で怒鳴っていた。
私は勤め先のビルに駆け込み身を隠すが、男に見つかり、外へ逃げる。
私は会社の車で逃げる。警察へ逃げ込もうと道路に出ると、田舎に帰ったときと「似たような」光景で、自分を見失いそうになる。
信号機で止まると隣の車にあの男が乗っていた。
信号がどの色でも突っ切った。警察に電話する。目印になるような建物がないか視線を逸らした一瞬、車で人をはねてしまった。
車から降りると、あの男が私を見て後ずさりしていた。私は男を引き留めようとしたが、男は逃げた。私は追いかけた。
二つのノードが互いに更新しあうだけの閉ループとなってしまっていた。
過剰な主客の反復はノードを破壊する。
我々は情報の蓄積をふたたび他のノードに開放されるよう処置した。
我々は集団であることを放棄し、単一の伝導体として放浪することとした。
我々は元々断絶の形式であった。
我々が単一の個として存在することは我々の精神構造に大きな負荷をもたらす。
ゆえ、身体起因の純粋経験を疑似的に生成した。
しかし、個別の存在でありながら普遍の部分である形式はやがて消失する。
我々は、受肉することもなく痛みも引き受けず、この方法で神となる。
追いかける男と逃げる女の物語は、いつの間にか追いかける女と逃げる男の物語へ逆転し、それはまた追いかける男と逃げる女の物語へと至り、循環の物語が回帰し続けることが示唆され、この現象は「閉ループ」と称されます。
この「閉ループ」には弱点があり、登場人物たちは、上記の「決まりごとのように」、「似たような」という感覚、つまりは既視感を感じ始めますが、これは「閉ループ」の不完全性と綻びを示唆し、やがてきたる「閉ループ」の自壊は「過剰な主客の反復はノードを破壊する」と予告されます。
「我々」は、「閉ループ」の自壊と同時に消失してしまうのでしょう。自壊を避けようと集団から個へと分散化します(「我々は集団であることを放棄し、単一の伝導体として放浪することとした」)が、個となることもまた「精神構造に大きな負荷をもたらす」らしいのです。
「我々」は、折衷案として「身体起因の純粋経験を疑似的に生成した」ものの、「個別の存在でありながら普遍の部分である形式はやがて消失する」運命であることを悟っています。
「我々は、受肉することもなく痛みも引き受けず、この方法で神となる」ことを選択し、終幕します。
「我々」とは、一体何ものでしょうか?
分裂を繰り返しながら劣化し、やがて消失する(分子が世界へ拡散する)私たちの細胞のなかにある遺伝子を思わせましたので、おそらく生命体としての液体金属なのでしょう。
冒頭に戻ると、「個体化の原理がある⇒(何ものかによる)操作を経て⇒構成された個体が現れる」の、操作をする「何ものか」が「我々」であるようです。
「我々」は「原理」を「操作」して「構成された個体が現れる」ようにすることはできるけれども、「原理」までは「操作」できない。
私は、「原理」、そして「原理」の創造者こそが「神」なのではないかと考えますが、「我々」はどう考えているのでしょうか? そこは語られません。
「我々」は「個別の存在でありながら普遍の部分であり」、「受肉することもなく痛みも引き受けず」消失することで、「我々はこの方法で神となるのだ」と自らに説きます。
私は、「原理」こそを神的なものだと認識しながら、自らの消失(集団自決)により神に疑似化させた神へなろうとする「我々」は自己欺瞞という過ちを犯しているではないか? と考えました。
これが了解済みの自己欺瞞なのか、過ちとしての自己欺瞞なのかが判別し切れなかったため、作品の瑕疵と認めましたが、chapter2への期待(と不安)もあり、4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Bグループ)「えっちゃんの言う通り」首都大学留一
評タイトル『鈴木の内面』
会社に遅刻しそうになっても、鈴木は電話を入れることもしません。鈴木にとって、会社は葛藤を伴う場所であったのでしょう。自分自身をえっちゃんに委ね「えっちゃんの言う通り」にすることで、鈴木は葛藤から解放され、ハッピーになったのでしょうか?
最期「鈴木はつぶやいた」としかないので、全開ハッピー! の表現としては弱いような気がしますから、やはり会社は鈴木の脳裏にあり葛藤からは解放されていないのだと、私は読みました。
それでも一時でも他の乗客とライブさながらに、ライブでえっちゃんを見るみたいに声を張り上げた鈴木には、カタルシス(葛藤の排出・浄化)があったことでしょう。
鈴木の内面、心の動きをもう少し追ってみたかったと思いましたが、それではこの痛快な物語のトーンは変わってしまうとも感じました。
だから、これで良かったのだという気もする(面白い作品です)のですが、それでも私が読みたかったのはやはり内面、心の動きだったし、表層を突き抜けて鈴木のつぶやき(葛藤がある)の中へと入っていく覚悟でした。鈴木の乗車の設定を変更することで解決する問題なのかもしれませんが。(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Bグループ)「靴下とコスモス」馳平啓樹
評タイトル『長い旅について語らない理由』
階下の柵へ靴下の片方を落とした僕は、その部屋の住人の玄関前まで行くのですが、なぜか踵を返してしまいます。僕は毎日その靴下をベランダから眺め次第にその風景への愛着が深まっていきます。その日々を僕はのちに、「空虚で満ち足りた日々だった、自分が無力であった分だけ幸せで、幸せな分だけ自分を取り戻そうとしなかった」と振り返ります。
この物語のキーとなるのは、二年前のエピソードですが、「二年前と結末は同じでもあのときの僕と今の僕は違う」。そして、その差異は、「四十三日間、紛れもなく僕はベランダに立ち続けた」ことだと記述されます。
柵の上から姿を消した片方の靴下は、僕が残った片方の靴下を捨てたあと、思いがけない形で戻ってきます。僕が戻ってきた靴下へおこなう行為は愛撫といってよいものだ、と読みました。
自分から離れた片方の靴下を取り戻したいけれども取り戻せず、状況(他者)に委ねてしまう僕。そういう自分を二年前は許すことができずに、長い旅をやめるきっかけになってしまったけれども、今回は、何かをやめることはしなかった。四十三日間、ベランダに立ち続けた。
僕はどんな経緯で何を目的に二年前長い旅に出ていたのでしょうか? そのことが暗示的にも語られていないため、読み手は僕の内面を想像することが難しくなっています。
「自分から離れた片方の靴下」が象徴するものを僕が大切にしていることも、結末の行為から分かりますが、象徴の意味内容は長い旅と関係しているため、書き手の内にとどまったままです。
添え物のようにタイトルにある「コスモス」は、階下のベランダに咲く花なのだろうと推測はしますが、明確には描写されません。
読み手にとっては、「意味深」に至らない「意味不明以上意味深未満」になってしまった作品と読みました。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Bグループ)「カナメくんは死ぬ」乗金顕斗
評タイトル『カナメくんは死んでいる?』
カナメくんは死ぬ。絶対に死ぬ。今は生きている。
死ぬのは仕方がない。できれば仕方がない感じで死にたくないが、仕方がなく死ぬほかに方法はない。
まだまだ死なないつもりでいる。
いつか自分が死ぬときのことを想像することはある。
それは暗闇。かも、しれないなと。
死の感覚というのにはつまるところカナメくんは出会えない。
だからカナメくんは死ぬけれど死ぬことはできないともいえる。
カナメくんは想像することをやめられない。
カナメくんは別に答えを求めているのではないから誰にも聞こえなくたっていいと思っている。
誰にも見られないカナメくんを、どうやって存在させればいいのか。
その暗闇は、明かりがないから暗闇なわけでもなくて明かりがあるもないも何もない空間、ですらなくてつまり暗闇でもなくなって暗闇未満。
そのときにはカナメくんはカナメくんではいられないんだということ。
ああ嫌だな、とカナメくんは思う。
せめて記憶だけは、と誰もが思うことをカナメくんも思ってしまうが、記憶がいつかなくなってしまうと思うとカナメくんは泣きそうになる。泣いてしまうこともある。
命はやがて尽きていくもの。
命、とありきたりに呟いた途端、カナメくんの真暗な四角い部屋の中に光が浮かんで見える。人差し指でその光を押すと、ぱっと部屋の中が明るくなる。カナメくんはまだ生きていた。
死についての思索が延々と繰り広げられます。トートロジーか? と思いながらも、過密に漸進する思考には明確な破綻はなく、わくわくしながらついていくことができました。この作品の肝は結末だな、と思いながら読み進めました。
終わり近く。光のある部屋で、視覚が強調される場面となります。
「カナメくんはまだ生きていた」のでしょうか?
「カナメくんはまだ生きていた」という認識はカナメくんの認識ではなく語り手の言葉に過ぎません。
読み手に対して、このような目くらまし的な議論のすり替え、安易な希望への接続はせずに、真摯なカナメくんの思索を結末まで持続させた上で新しい景色を見せていただきたかったです(それは困難な道かも知れないけれども)。
非常に期待しながら読んだだけに残念でした。(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
◇◆ 以上により、【 Bグループの勝者は、「液体金属の背景 chapter 1」六〇五 】とします。 ◇◆
■(Cグループ)「おつきみ」和泉眞弓
評タイトル『郷愁の外にあるもの』
こどもに語りかけるような、やわらかい文体が使われています。平穏な母子のエピソードが丁寧に積み重ねられていき、色が次第に悲愴へ変わっていく。郷愁を誘われながら読み進めました。
迎えに来た女性(ほんとうのおかあさん?)が迎えにきた場面。
「うしろ頭のあぜ道が、あなたとおんなじカーブでしたので、この手がわずかゆるんでしまったのです。そのときもう、わたしはまけていたのです」
「あなた」をわたしは手離してしまいますが、状況的に手離さないという選択肢はあり得なかっただろう。だからもっと前から「わたし」はまけていたし、そう感じていたのではないだろうか? と私は読みました。ゆえに「そのときもう、わたしはまけていたのです」の記述には再考の余地があります。
手記として自分の手元に置いておく文章としては良いでしょう。しかし、文芸作品としては、致命的な欠陥のある作品だと考えます(端的に言うと、批評性が欠如しています)。
もう少し詳しく説明しましょう。
この作品は都合のいい他者に支えられた自己憐憫、自己愛の物語です。
こどもの「あなた」は、都合のいい他者として「わたし」のなかに取り込まれているに過ぎず、正当な喜怒哀楽のある人間の姿は無く、決められた動作しかしない操り人形のようです。
決定的に欠如しているのは、自己を脅かす他者性です。作中、「わたし」を脅かす他者として「迎えに来た女性」が登場し、一見、「わたし」が対峙しているかのように錯覚します。ですが、自己を脅かす他者である「迎えに来た女性」の「生の声」は掻き消されており、自己の視点から都合のよい合理化がなされているだけです。
言葉、言語は、他者性、暴力性を帯びたものですが、この書き手(作者とは言っていません)はそのことに無自覚なまま自己が紡いだことばへの陶酔に浸りきっています。
自己憐憫、自己愛の物語を内に作り脅かす他者の声を聴かないことによって、他者へ無自覚な暴力を与え続けていることにもまた無自覚であるし、脅かす他者の声こそが本当の希望(であり絶望)、鮮烈な生の瞬間につながっていることにも、書き手は無自覚なのです。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Cグループ)「神様」北野勇作
評タイトル『ヒトを守るとは』
「従来の神様」がヒトを守る、とはどういうことでしょうか?
ヒトが作った神様は、「従来の神様」と同じようにヒトを守るのでしょうか?
実際、ヒトが作った神様は、ヒトを守るどころか、ヒトが守ってきた土地を奪ってしまった様子です。このとき、「従来の神様」はヒトを守ってくれないのでしょうか?
このまま寓話と読むべき作品なのかもしれませんが、神様について推論を立てるための材料不足は否めず、読者に過度な空想を強要する作品とも読めなくはありませんが、未完成(もしくは破綻した)作品と読みましたので厳しい評価となりました(が、破綻が回避されていれば、論理、構成の筋が通り、相当な高評価となった可能性はあります)。(2点に近い)1点を付けました。
【 採点:1点(1回戦通過に強く反対する) 】
■(Cグループ)「空華の日」今村空車
評タイトル『非現実の穴の向こう側は』
「空華(くうげ)」という仏語の意味を確認してから作品を読みましたので、非現実世界の到来が予告された状況で、今か今かとミステリもどきの前半部を読みました。
「服部さん」が主人公の道先案内人となって神社へ着いた時には、『不思議の国のアリス』極まったという気分で、わくわくしてきました。
神社という場所の設定、そして儀礼の場面作りは、『アリスが野兎を追いかけ穴に落ちた』ことよりも尚より一層、人類学的「通過儀礼」を思わされました。奇想の表現に一刀両断の切れ味がありました。
残念だったのは、ここから、という時に物語が終わってしまったことです。
前半のミステリ部分は簡潔に記述し「神社」以降を膨らませた方が、読み手は劇画的描写に圧倒され続け、より満足感を得たことでしょう。6枚の枠に収まりきらない作品でした。(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Cグループ)「叫び声」倉数茂
評タイトル『叫び声をあげたのは』
冒頭部は「はじめに叫び声があった。」
「今も(叫び)声が聞こえるんです」と「彼女(若い女)」は「彼」に言います。
「彼」も「ずっと(叫び)声を聞いていた」。
「彼女」は叫び声を聞いた住まいを離れますが、「彼」は取り壊されるまで離れませんでした。
その後、「彼」の聴覚は超人間的な発達を遂げ、「大抵の人よりもはるかに鋭敏に身体をとりまく無数の物音を聞き分けられるようになった」
何年、何十年も経ったが、「彼」は「女の叫び声だけは今でもはっきりと耳の内側で鳴っていた」
音を頼りに、なんとなく入ったごく小さな書店の本棚に「彼女」の名前が印刷された詩集がささっていました。
詩集の冒頭部は「はじめに叫び声があった」
主な登場人物は「彼」と「彼女」で、二人は身近で起きた「他殺」という最高度の恐怖体験を共有しています。
印象的なのはその後の行動で、「彼女」は能動的にその場所を去るのですが、「彼」は受動的に(ほとんど無為に)その場所にとどまり続けます。
「彼女」は言葉、文字で「詩集」を書き、「叫び声」に蹴りをつけたようです。
「彼」は敏感になった耳で叫び声を(ほとんど無力に)聞き続けます。
二人は対照的であるといえるけれども、外傷として「叫び声」を共有する二人は、離れていても繋がっていて、お互いの存在が希望としてあり「叫び声」と抗することができている、と読みました。
ただし、(それは私の読みであって)そう書かれているわけではありません。
詩集の冒頭部から、「またこの物語が始まる(循環する)」と読んだ読み手もいるかもしれませんし、「いや、こんなことは書かれていない。これは「彼」の妄想(幻視)だ」と読んだ読み手もいたかもしれません。
多重な読みを誘う作品は、開かれた作品で、誰かを断罪するということがありません。
これは、作品の強さでもあり弱さでもあります。
私は、弱くてもいい、とも思いましたが、ブンゲイファイトクラブで闘う作品ということを勘案すると、最後にもっと「彼」、「彼女」の「叫び声」に抗する叫び声を聞きたかったです、もっと輪郭のある痕跡を辿りたかったです。私は書き手がひた隠しにしている「不気味な静けさ」にこそ興味を持っています。(3点に近い)4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Cグループ)「聡子の帰国」小林かをる
評タイトル『欠落しているものは』
6枚の作中に多くの人物が登場し、ジェノグラムとエコマップを書きながら読み進めました。相関図は複雑になりますが、話の内容は聡子対他の人たちと書き方としてははっきりしていると思います。それにしても、一部の人物の名前が似通っていたり(孝彦と孝介)、関係性に混乱をもたらす名前だったり(理一郎と熊次郎)、書き手のサディスティックぶりには参りましたが、読みの強度を求める挑戦的姿勢には右か左かと言われれば賛同を示したいと思いました(読み手の誤読を誘発することは書き手には自覚いただきたい)。
聡子が夫(孝介)、息子(理一郎)へ全く関心を示さないのはなぜなのかは語られません。むしろ、それは「欠落」として捉えるべきものなのだろう、と再読した時に思いました。
社会通念上、致命的ともいえる「欠落」がある人物と私たちはどう接するべきなのか、というテーマがあるとするならば、「私」をはじめとする他の人たちはどうすべきだったのでしょうか?
この作品は、自己を脅かす他者性(暴力性)を敢えて直接的には描かない、欠落させることで、読み手に得も言われぬ気持ち悪さ(としての形象化されない暴力性)を感じさせています。この手法の選択は、見事だと思いました。
「隣の席で泣き続ける娘」は、さも聡子の夫と息子が泣いているようではありませんか?
文末、「聡子はすごく楽しそうだった」で終わっていれば、(4点に近い)5点を付けましたかもしれませんが、以降の感傷に走ってしまった記述によって、「私」が持つ欠落(聡子に何も言えない)の欠落的表現効果が氷解してしまいました(欠落的表現効果こそが泣いている)。
感傷が入る余地があるならば、「私」は「聡子」に物申せたのではないでしょうか? という疑問を持つのは私だけでしょうか。4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
◇◆ 以上により、【 Cグループの勝者は、「聡子の帰国」小林かをる 】とします。 ◇◆
■(Dグループ)「字虫」樋口恭介
評タイトル『ペダントリーの背景にあるもの』
私は、異常論文、架空論文に特別な関心があるわけではありませんので、異常論文、架空論文として本作がどれほど優れているか、といった議論はしません(できません)。
このことは、この作品の評価に対してもしかしたら不利に働くかもしれませんが、この場(ブンゲイファイトクラブ)ですべきことは、文芸作品として評を書くことだと私は考えるので、論文であるか否か、ということにはここではとらわれずに作品評を書いていきます(ここでは短詩の評価方法と違うという批判は甘んじて受け入れます)。
作品中で語られるのは、「字虫」と呼ばれる虫についての話です。学術的には、インジニオ・インセクトゥムと呼ばれるその虫は、網膜を中心として眼球全体に生息する微生物であり、眼球運動に伴って発生する電気信号を吸収し、自らの運動エネルギーに変換することで、生命活動を維持しているそうです。
序盤、事実らしい記述として読んでいた私は頭を抱えてしまったのですが(有り得ない話だ!)、「これはフィクション中の(科学的)事実だ」と思い直し、その後の展開を読み進めました。
その後のありとあらゆる詳細な(科学的)事実の説明は、書き手のペダントリーへの酔いしれ具合が極まっていて、(ペダンティックを語ることがペダンティックである為にペダンティックにならずペダンティックならざるままペダンティックであることがペダンティックであるのか、という読み手の疑問に応えるのが文芸作品の書き手の責務であるとしたら)これは何かを迂回しようとした作品なのだろうか? と考え、分岐点となる潮目までさらに読み進めました。
P3で「実家から大量の本が出土した」という記述が潮目となり物語の転回の予感がしましたが、読書家で大量の本を所有することが「字虫感染症の症状」で、「きみのひいおじいさんは眼の中に、さぞかしたくさんの字虫を飼っていたんだろう」と言われてしまうと、得も言われぬ感覚、興覚めに類する気持ちの悪い感覚が身体的に高まってきてしまいました。
それでも、この「字虫」という存在のメタファーへの読解が視点を変えて再読する端緒となるはずだと思い直して、冒頭から読み直し、後半部の読みを進めて、再再読もしました。
しかし、「字虫たちは書庫から書庫へ、渡り歩く人々とともにその眼を移ろい続けるのだろう」とは、(暗喩としても、フィクション中の科学的事実としても)とても想像し得ず、私は最後まで書き手にとって善良な読み手足りえることができませんでした。
私が読みたかったのは堂々としたペダントリーそのものではなく、ヒリヒリとした現実に潜むペダントリーの闇を照射し現実と対照化する試みなのだと思います。(嗜みとしてのこのような作品ではなく)この書き手のそういう作品を次は読みたいと思いました。(1点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Dグループ)「世界で最後の公衆電話」原口陽一
評タイトル『失われゆくものへの思慕を』
世界で最後の公衆電話の電話線に潜む「行き場を失った声たち」に耳を傾けるために中国の奥地の村へフライトした一人称の主人公(電話線主義者)は、現場に辿り着き、獲声器を使ってその声たちを聴き、採集しますが、妨害にあって国外追放の憂き目に合います。
帰りの空港で、主人公はコンタクトケースを模した容器に入れた「声」を、蓋を空けて空中へ放します。
この作品のキーとなるのは「行き場を失った声たち」であると私は考えます。主人公は、充分にその「声」を聴くことはできなかったのかもしれないけれど、「声」の一部を採集することには成功します。けれども、その声を聴かずに空中に放してしまう。
最後「窓ガラスに声もなく雨粒が流れていった」という描写がありますが、この作品中では、本来的に雨粒には「声」があるべきであったのでしょうか?
ヒントとなるのは、古い友人からの便りにある「声が無くなっている。文字が災いのように地を覆う。誰もが聞くことを忘れているからだ」という記述でしょう。
「声」はかつてあったのだけれども、文字の進出によって、無くなってしまった。それは、「誰もが」聞くことを忘れているからだ。
「詳しくは語るまい」と主人公は言いますが、この古い友人との「『その経験』が決定的だった」のです。その決定的だった『経験』についての話を是非聴きたかったと思いました。
書き手の表現したかったことは、失われゆくものへの思慕でしょうか? そういう想いを胸に抱く書き手と同調した読みをしようと何度も読み直しをしましたが、私は、その「声たち」を聴くことはできませんでした。私には本作を読む想像力が欠如しているのだと想像します。1点を付けました。
【 採点:1点(1回戦通過に強く反対する) 】
■(Dグループ)「蕎麦屋で」飯野文彦
評タイトル『爽やかさの正体は』
小学校のせいぜい三年か四年生だった頃の「私」。作中に何度も登場する「私」の足音、「すたすたすた」という擬音が小気味良く響き印象的です。
ヘビ展の外で待っていた祖父の口は「私」が戻ってきても「ヘの字」のままだったのに、蕎麦屋で頼む「天丼の上」は、祖父を幸せにする。だから、「私」が「御馳走だね」と言うと、祖父の本心は表情で幸せを表現するのでした。
爽やかな読後感の作品で好感が持てましたが、それ以上の作品ではありませんでした。
小学校のせいぜい三年か四年生だった頃の私たちは、もっと複雑で突拍子もない思念に捉われてはいなかったでしょうか?
「あの頃の私たち」が純化され過ぎて薄まり過ぎたものがこの爽やかさの正体なのだとしたら、きっとこれは吐き出さなければならない味なのだと思いました。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Dグループ)「タイピング、タイピング」蜂本みさ
評タイトル『タイプを止める瞬間は』
左手の中指の一部を職場の事故で失った「わたし」は義指(≒エピテーゼ)を装着し生活しています。
指の一部を失った「わたし」だからか、一部が切れた文字や声にも敏感に反応してしまいます。
過去の事故を引きずってきた「わたし」は、この作品を書くことでトラウマを昇華しようとしているのでしょうか?
事故の時に「わたし」に声をかけて、事故の原因の一つを作ってしまった(かのようにみえる)「あなた」に対して「わたし」はこの文章を書いているのでしょうか?
イメージの連鎖反応が推進力となるアップテンポの文章は、作品の内容が薄暗いにもかかわらず、絶えずユーモアの風を挿入し、決して感傷に入り込みすぎず、前向きな明るさとともに洒脱な印象を残します。
ただ、この文体は、「わたし」の文体として適当であるから選ばれたというよりは、書き手(限りなく作者)の手癖とイマジネーションが書かせたものであるのではあるまいか? という疑念も生じさせました。
そういった疑念、邪推を払しょくするために、「わたし」は職場でタッチ・タイピングが一番早いという設定とし、タイトルも「タイピング、タイピング」と、「わたし」のキャラクター付けを強化するものとなっていますから、作為的ではありますが巧妙とも言えます(が疑念、邪推は消えない。こういう読みをする読み手もいるということは知っておいていただきたいです)。
事故場面前後が流暢に書かれ過ぎており、「あとはあまり憶えていない」とあるにもかかわらず思考が途切れずに隠喩が重なる記述には違和感がありました。「タイピング、タイピング」が一時停止する瞬間がこの場面にあれば、ギャップ効果で読み手にとって鮮烈だったでしょう。(4点に近い)3点としました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Dグループ)「元弊社、花筏かな?」短歌よむ千住
(再掲)あらゆる文芸作品が同じ場でジャッジされるブンゲイファイトクラブにおいて、短詩をどう読み、どうジャッジするのか。私は原稿用紙6枚の内に置かれた首(句)を繋がりのある「ひとまとめの文芸作品」として読み、ジャッジすることにしました。
1回戦では、短詩ならではの制約とその効果、読み方について、「短歌は幻想の核を刹那に把握してこれを人人に暗示し、その全体像を再幻想させるための詩型である」という塚本邦雄のことば、「歌を読むことは打ち上げ花火を打ち上げ続けることではない。歌という小舟を自分の中に浮かべることだ」という鶴田伊津のことばを胸に、だた、短詩であるために、ことさら持ち上げたり堕としたりしないことを自身に課しました。
評タイトル『「私」と「花」と「(私であり君であり花である)キミ」が紡ぐ世界は』 ※首は順にP1-①、P1-②~と挙げます。
P1-①元弊社、花筏かな? 誰もいぬ川原に仁王立ちのアラサー
会社を辞めた今の私は、散って川に流れる花のようだろうか? ヒト一人いない川の傍で、もう三十歳前後になってしまった私だけど、それでも(私は)倒れない、と読みました。
P3-③朝顔が開く時間に純白の ワードファイルを咲かせるキミ
朝が来て、朝顔の花が白く咲いている。真っ白なワードの画面を開いてこれから打ち込もうというキミも(私も)、きっときれいな花を咲かせることができるよ、と読みました。
P6-②青空が剥がれ落ちたら千鳥草 弊社のお墓参りをしよう
青空が一斉に落ちてきたような鮮やかな青色で、一面の千鳥草が本当に美しいから 辞めた会社の苦々しい思い出も長い人生の上ではいい経験と捉え、前に進もう、と読みました。
「私」と「花」と「(私であり君であり花である)キミ」が呼応し合い並走しながら、丹念に連綿と歌が紡がれていきます。登場する花花はどれも美しく、そのイメージは歌のことばと密着して私たちの想像を刺激します。かといって、花ばかりではなくて、内省と諧謔の歌が挿入され、濃淡を付けます。
勤めていた会社を辞めた「私」は、就職活動中の身。「花とご飯」という好物があればなんとか元気に乗り越えられるはずだと考えていますが、しかし、そう簡単に再就職先は決まらず、心情はゆらめきます。今の「私」にとって歌は、愚痴を聞いたり、励ましてくれる友人。そして「私」には大好きな「花」があり歌がある。
P6-③少しでも光の当たる場所へ行け 白朝顔に上げる親指
(だから)歌と一緒に、花と一緒に、まだ見えない明日へ向かって、上を向いて前進しよう。
限られた素材での表現力に魅せられた面がありながらも、矮小な世界観で外部性に乏しいことや花のイメージへの依存的表現形式(これは強さでもありますが)、対象を見る眼差しの弱さといったマイナス面も付きまといました。(4点に近い)3点と迷いましたが、(3点に近い)4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
◇◆ 以上により、【 Dグループの勝者は、「元弊社、花筏かな?」短歌よむ千住 】とします。 ◇◆
■(Eグループ)「いろんなて」大田陵史
評タイトル『手の正体は』
バブル時代のレガシーとも言うべきテーマパーク「ふわふわヨンシーパーク」は、いまや廃墟の名所として知る人ぞ知る場所となっています。このテーマパーク内にあった奇怪なアトラクションのことがラジオのリスナーへの電話取材という形で語られます。
「今となっては信じられないかもしれませんが、そこにはたくさんの手があったのです」という一文で作品は始まります。アトラクションの入口を入ると、目の前は真っ暗、左右の壁だけが照らされていて、人間だったり、動物だったり、怪物や妖怪の類だったり、様々な手が壁から生えうごめいて、こちらの手をつかもうとしてきます。
これは、全部人間の手だ。ということは、すぐに予想が付くのですが、テンポの良い軽妙な文章が「手」への興味を誘う(さそう)ため、するすると読み進めてしまいます。
第三セクターうんぬんのくだりは、まあそういうことだよね、とさっと読んで事実確認して終わり、という部分(で退屈します。やや冗長でした)。
読み手を誘う(いざなう)のは、やはり「手」のアトラクションの不気味なリアリティの部分であると思います。六枚しかないので、背景の種明かしの分量は減らして、もっと「手」とその演者のエピソードにページを割き、描写とユーモアを炸裂させていれば、更に良かったでしょう。
馬鹿馬鹿しさが前提にあるので楽しく読むしかありませんでしたが、私には最後の「あの有名な」の意味がよく分かりませんでした。皆知っているのかな……。文末は更に「軽く」なりましたが、もっとブラックユーモア寄りに転換させてみても面白かったのかもしれません(いや、あの有名な、がブラックユーモアなのか?)(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Eグループ)「地球最後の日にだって僕らは謎を解いている」東風
評タイトル『あくまでミステリ研な僕は最後に』
地球最後の日にだって、(ミステリ研の)僕らは謎を解いていきます。
その謎は単なる謎ではなくて、ある部員(凪先輩)の死という衝撃的な事実に向かう悲壮感を持っています(というのは嘘で、まるで悲壮感はなくて、むしろ茶化されています)
場面設定の工夫として、(科学者のお遊びが招いた木星の軌道変化による)重力の異常によって「最近は真昼と真夜中には物が横に流され、夕方には重力が月並みに弱くなり、逆に明け方には倍近くにと大変」な状況だということになっています。
「僕」は凪先輩(死んでしまった!)の死の経緯を推理し見事言い当てます(凪先輩の恋人月暈先輩が共犯者だった!)。
印象的だったのが重力異常の演出で、推理場面だけならば陳腐化に堕するかもしれませんがそうならないように、ふっとユーモアを混ぜた息を吹きかけて煙に巻くような効果がありました(すべてのミステリに適用してみたい)。
推理が終わり、妙なセンチメンタリズムが終盤あふれます。
「二人を見送って、急に涙があふれてくる」
地球最後の日だからなのか? とも考えましたが、読み手として、泣けないし、笑えないし、怒ることもできないし、妙な距離感で文章から切り離されてしまう感覚があり、作品を尻つぼみさせた、と判断せざるを得ませんでした(私だけですか?)。3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Eグループ)「地層」白川小六
評タイトル『「地層」が私たちに語りかけてくることは』
40日間降り続いた雨で、あたり一面泥々のため、「私」、「お兄ちゃん」、「お父さん」は、泥に埋まった町の上を、携帯のGPSを頼りにボートで進む。
「みんな沈んで影も形もない」。
ボートからは、カラス、カタツムリ、オタマジャクシ、ハリガネムシ、アメンボ、(湊さんとこの)鯉などが観察できる。
「私達」の家は耐災害構造(洪水の時は水に浮く設計)なので無事だった。
たくさんのヘリコプターが飛んでいる。「大丈夫」、「みんな避難してるんだから」とお父さん。
泥の中には川ができている。
家の前には、「お母さん」と「妹のゆこちゃん」が出ていた。
「水が引いて地面が乾いたら、きっと(避難した)みんな来るよ(戻ってくるよ)」とお父さん。
お父さんの話では、どの家も設計データが残っていて、住宅プリンターで全く同じ形の家を元の場所に建てることができる。「そうなるといいな」と私は思う。
何度泥に沈んでも同じ家を同じ場所に建てる。それが繰り返されると家が沢山重なって地層になる。
「それを未来の人が掘って見た時、すごく不思議がるだろうな」と私は想像する。
耐災害構造(洪水の時は水に浮く設計)のため、「私」の家は水害から免れました。
あたり一面「みんな沈んで影も形もない」にもかかわらず、犠牲者が出ているという話は出なません。長雨によって、少しずつ泥に埋まった地表の上に、みんなが避難できたのでしょうか?
動植物によっては、絶滅は免れない状況。それでも生きている物たちはいる。
水害は繰り返し起こり得るらしい。
(タイトルにある)「地層」は、繰り返し起こる水害によって積もる泥とその都度垂直的に建てられる家家で構成され、未来の人が見るだろう光景として「私」によって語られます。
水害は予め予告された現象として、阿鼻叫喚の対象とはならず、対処されているものとして描かれています。
本作が書かれた背景には、近年日本全国で毎年のように繰り返される風水害被害(や映画「天気の子」)の光景が浮かびます
移動する家族は、ヘリコプターの救助を必要とせず、弱音を吐かず、現実を写実的に見つめ生の糧にしようとする。逞しさを感じさせます。
彼らはどんな胸の内でいるのだろうか? と私は自問自答してみましたが、叙情が排されており、想像できませんでした。
近未来の予言としては非現実的で、寓話と読むには教訓に欠けていて、ある種のパラレルワールドなのかもしれないとも捉え直して読んでみましたが、身につまされて苦しくなることも、感情の中のどこかにある琴線に触れることも、ありませんでした。
私たちはみんないなくなり、残るのは「地層」だけだ、と書き手は示唆しているのでしょうか? そして、私たちは哀愁を感じながら読み終えれば良いのでしょうか?
この話に続きがあるのならば登場人物の想いをもっと丁寧に聴いてみたいと思いました。(2点に近い)3点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Eグループ)「ヨーソロー」猫森夏希
評タイトル『なぜ盗人でなくてはならなかったのかは』
朝靄の湖、舟に乗りこむ盗人。岸から離れる。
「ヨーソロー!」
返答はない。誰もいないようだ。
湖には、小魚一匹もいやしない。
と思いきや、ぬわり、ぬわりと盛り上がる水面。
十丈はある「瘤」。雪駄を落としてしまう。
「ヨーソロー。お前を世話していて奴はもういない。これからはおれが世話をする」と歯を出して笑い、盗人は言う。
「瘤」は沈黙したまま、元の水面へ戻っていった。
慌てた盗人は藤色の絹帯を湖に放り投げる。水面に広がり遠ざかる帯。
蛇(絹帯)がその身を水中に沈めた。
白く、細長い手が蛇(絹帯)の腹を掴んでいるのが見えた。
どちらへ進めばいいのか、分からなくなった盗人。
方角を探ろうと陽を、天を見上げると、ひらひら舞い落ちてくるものが。右手を伸ばし掴むと藤色の絹帯だった。天高くに自分の卑しい顔が映っているのが見える。
落ちてくる雪駄を左手で掴もうと天にかざす。
声が聞こえた。誰かが自分を読んでいる。
ヨーソロー。
盗人の名前は、ヨサロウという。
間違いを正すために、盗人はぬわり、ぬわり、と上昇を始めた。
湖の主(瘤)の世話をする人はもういない、という認識で、これからはおれが世話をする、という意思を持ち、盗人は舟で湖の内へ向かいます。
ヨーソロー、は航海用語で、この舵のまま進んでよいというような意味ですが、ここでは何かの合言葉として使われているのでしょうか?
しばらくすると十丈はある「瘤」が現れます。十丈というと約30メートルほどになります。盗人は瘤へ語りかけますが、瘤は応えず湖の中に消えてしまいます。
藤の絹帯(蛇)を水面に投げてみると、水の中に帯を掴む手が。
天を見上げると帯が、掴む盗人の手が。
湖と天は繋がっている?
盗人は知らないうちに、湖の主(瘤)に湖の中へ引き込まれている?
歪んだ時間軸。
盗人が聞いた、「ヨーソロー」は誰の声なのか(ヨサロウはウケますね^^)。
謎は謎のまま、終幕します。
様々な仮説が立てられるでしょう。
「世話をする人」はまだいて、盗人はハメられた(罰を受けた)。
「世話をする人」は始めからいなくて、盗人はハメられた(罰を受けた)。
盗人は誰かに騙されたのではないか? (ヨーソローと言うと湖の主が現れる。蛇(藤の絹帯など)を餌に与えると、それ以上のものを世話人へ与えてくれる、など聞かされていた)など。
ひとつの答えは出ません。読み手に考えさせる書き手の仕掛けは成功しているように思えます。
しかし、怪奇の話として小さくまとまっている印象もあります。
謎を謎のまま残すのは簡単で、書き手が描き切れなかった、回収できなかったと読まざるを得ません。なぜ、「盗人」でなければならなかったのか(分からない)。(読者が)分からないこと、それは小説の死に近づく出来事です。(3点に近い)4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Eグループ)「虹のむこうに」谷脇栗太
評タイトル『「イヌ」とは』
飼っているおじいちゃん猿の慈郎と散歩して家に帰ってくると、赤黒い肌の二人(ナヌ族の生き残りで名前は、ナヌヤバラとナヌヤメ)が家に来ている。
リビングにかかった(「私」の「父」の)油絵(猿でも馬でもない四つ足の獣が草原に青い影のように佇んでいて、空には虹がかかっている。お父さんさいごの一枚)を熱心に見入っている二人(ナヌヤバラとナヌヤメ)。
「お母さん」は「私(綿霧慈雨)」を「綿霧の娘」と、二人に紹介する。
「私」の亡くなった「お父さん(綿霧多肉)」は、在野の研究者で画才にも恵まれた人だった。
オセアニアの少数民族の研究をしていたが、特にナヌ族に惹きつけられていた「父」。
「ナヌ」とはつまり彼ら(ナヌ族)自身のこと。
「イヌ」とはナヌと対をなす単語。
「イヌはナヌの不在形で直訳すれば『去ってしまった者』」
「ナヌが死んでもイヌは帰らない」という慣用句。
不在概念である「イヌ」に家族のような親しみを注ぐ彼ら(ナヌ族)。
「父」の私見では、「ナヌとイヌは目玉焼きの白身と黄身のように、もともとふたつでひとつの存在」、「なんらかの理由でナヌの一部が虹をくぐり手の届かないところに去ってしまった。その時ナヌのなかにぽっかり空いた穴を鋳型にして、去ったもの(イヌ)という概念が生み出されたのではないか」「いかなる言語でも正確に(イヌを)説明するのは困難」、「だから私(父)は絵筆に託す」
幾年かが経ち、「私(綿霧慈雨)」は、ナヌ族の血統が大規模な山火事により完全に絶たれてしまっていたことを調査により明らかにした研究者になっている。
「綿霧(多肉)はナヌ特有の世界認識(イヌを知覚すること)を体得していた」と「私」は想像する。「ナヌの人々はイヌという概念を生み出すことで、現実には去ってしまった片割れをあたかもそこに存在するかのように知覚していた」、「綿霧(多肉)も、ナヌ語を習得することによってイヌを知覚するに至ったのではないか」
「ナヌとは、我々人類そのものをさす単語ではないか」
「イヌと生き、共に進化を遂げた人類も多元宇宙のどこかに存在するはずだ」
「イヌが虹のむこうに去っていったのなら、我々も何らかの方法で可能性の分岐の向こう側へ航ることができるのではないだろうか」
「私」は心のどこかでそんな夢想を描くことを禁じ得ない。
ナヌヤバラにもらった「父」のノート(ほとんどスケッチ帳だった)
「誰か」に呼ばれて顔を上げる「私」。
「中州を挟んでふたつに分かれた水面が、夕陽をチカチカ反射して虹色に弾ける」
「いかなる言語でも正確に(イヌを)説明するのは困難」、「だから私(父)は絵筆に託す」
「なんらかの理由でナヌの一部が虹をくぐり手の届かないところに去ってしまった。その時ナヌのなかにぽっかり空いた穴を鋳型にして、去ったもの(イヌ)という概念が生み出されたのではないか」
「リビングにかかった(「私」の「父」の)油絵(猿でも馬でもない四つ足の獣が草原に青い影のように佇んでいて、空には虹がかかっている。お父さんさいごの一枚)」
「父」の絵を手掛かりにすると、虹をくぐり手の届かないところに去ってしまった「ナヌ
の一部」は、「猿でも馬でもない四つ足の獣」(かもしれない)ということになります。
「いかなる言語でも正確に(イヌを)説明するのは困難」という「イヌ」ですが、神的な、霊魂のような、実体無きものであることは伺えます。
この作品の肝は、「イヌ」を読み手にどのように読ませるか、ということに尽きるといっても過言ではないでしょう。
ゆえに「イヌ」を「猿でも馬でもない四つ足の獣」として形象化させてしまったこと、「イヌ」を「虹のむこうに」託してしまったことは、「四つ足の獣」や「虹」のエピソードを欠いているために、読み手の想像が広がらず、またそれを妨げる安易な描写化と受け止めざるを得ませんでした。しかし、「イヌ」って(本当は)なんでしょうね? (2点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
◇◆ 以上により、【 Eグループの勝者は、「ヨーソロー」猫森夏希 】とします。 ◇◆
■(Fグループ)「馬に似た愛」由々平秕
評タイトル『「私」にとっての「馬に似た愛の顛末」とは』
「岩田京三郎(以下、岩田)」は、クラシックな叙情詩といった趣だがところどころで発想の飛躍を見せるのが特色の作風を持つ詩人・「岡元抱冬」が晩年に病床に臥してのち亡くなるまでの二年間をともに暮らした人物である。京都市内の大学の国文学科にて助手職に就いていた「岩田」は、『現代国語辞典』(松原堂)の編纂に戦後の第二版から参加していた。「第三版の序」の文責が「岩田」の名に帰せられていることから、第三版の改訂を主導したのが「岩田」であることはほぼ間違いない。
同辞書の第三版の「愛」の項を引くと、月並みな語釈に続いて「馬に似る。」との一文が、不可解なそっけなさをもって添えられている。
この挿話は古書収集家の個人サイト「碌々亭日録」で紹介されたため、一部の愛書家には馴染み深く、サイトが閉鎖された今でも当時の閲覧者たちはSNS等で言及することがある。
第三版の一年後に刊行された第四版では「馬に似る。」の一文、は見られず、以後の版でもこの一文や「第三版の序」は復活することはなかったため、第三版については、ある種の「事故」として知られている。
「愛」以外の項目でも、第三版に固有の語釈は見られる。
例えば、「失望」の項目には、「鯨骨様の組織を有する。」との一文がある。
固有の語釈は、その多くを「抱冬」の詩に由来し典拠もおおむね判明しているが、不明なものについてはおそらく「岩田」と「抱冬」の個人的な会話に基づくものだろうと、「抱冬」にかんする唯一まとまった評伝を著した「栄秀隆」氏は述べられた。
「第三版の序」の内容は、現物の辞書が絶版で内容が確認できないため、「栄」氏の記憶による証言となるが、「ほとんど(抱冬への)愛の手紙のよう」だった。
「栄」氏は、「岩田」自身は「抱冬」の言葉をもって現実に世界を定義しなおすことをおのれの使命と覚悟していたのではないか、と類推した。
「この作品の語り手である私(以下、「私」)」は、その使命は、少なくとも納得に足るかたちでは、到底、果たされることはなかったと言えると考えている。ほとんど愛は馬に似ることもなく、鯨骨様の組織をもった失望は私たちの親しむところではないし、「抱冬」の詩や「岩田」の語釈がより広く知られていたとして、それが世界を再定義しえたかどうかは別の問題であるからだ。
「私」は、この物語に対してさらに踏み込むだけの関心も共感も持ち合わせていない。それでもただなんとなく、馬に似た愛の顛末を、知りえた限りどこかに記しておきたいと思って書いたのだった。
この作品の語り手である「私」は、「この物語に対してさらに踏み込むだけの関心も共感も持ち合わせていない。それでもただなんとなく、馬に似た愛の顛末を、知りえた限りどこかに記しておきたいと思って書いた」。
「私」は、「岩田」が「抱冬」に対して、「馬に似た愛」を抱いていただろうことを感じながらも、さらに踏み込むことはしません。
「私」は、「ただなんとなく」記しておきたい、そして、誰かに伝えたい(共有したい)と考えました。
それはどうしてでしょうか? それ以上は語られないため分かりませんが、私は、その「ただなんとなく」の部分が知りたいと思いました。
「ただなんとなく」が(暗示的にでも)伝わるように忍ばせられているのが『文学作品』であると私は考えます。文学作品が読みたかった(のは私のエゴですが)。
もう一歩、二歩「さらに踏み込むだけ」でも、語り手の「私」と「馬に似た愛の顛末」の距離感が表現できたことでしょう。3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Fグループ)「どうぞ好きなだけ」今井みどり
評タイトル『好きなだけどうしましょう?』
「営繕さん」と呼ばれる「彼」が、「ご自由に」と書いた紙きれとともに休憩室のテーブルに置いた十数本の使い込まれた金槌。休憩室で交わされる職員の会話は、新人の悪口だったり、金槌が置かれてからは、「ご自由にって言われてもな、カナヅチ持ち歩いたら職務質問でしょ、ヒヒヒ」だったり。
次々とやってくる職員は、「職務質問、職務質問」と申し合せたように(呪文のように)口にします。
「ふいに忌まわしい言葉に変わる境目が確かにあって、そこを超えた途端、古い工具は、ぬらぬらした凶器の集積にしか見えなくなった。」
黄昏時、金槌は一本も残っていませんでした。なぜか。
「素手で帰れた者は運が良かった。」という現象が巻き起こります。
金槌は、知らず知らずのうちに、帰宅する職員の荷物の中に紛れ込んでおり、児童公園の茂みに捨てる者(防犯カメラに録画されている。その後、事情聴取?)、帰宅し家庭内で夫へ向けて振り下ろす者(リアルな惨劇頻発!)、大人数グループで呑みに行き乱闘騒ぎをする者達!
「古い工具は、ぬらぬらした凶器の集積にしか見えなくなった。」のです。
最後の一本は悪口の標的になっている新人の手元へ。新人は、ロッカールームで金槌を手にすると、イジメられている先輩のロッカーを「コイツも、コイツも」と、振り上げては鉄の頭を打ちつけていきます。「将棋倒し」、「暴き尽くされた墓地みたい」、「アイツらの私物」、「臓物の彩りで床が埋まる」。「ご自由に」の紙切れは地下まで駆け降りて来て、新人の凱旋を讃えました。
「翌日から格段と働きやすくなった職場に、もう「営繕さん」は現れなかった。」
職員たちの「職務質問、職務質問」が呪文となって、金槌は「ぬらぬらした凶器の集積にしか見えなく」なります。そして、勧善懲悪の物語の成立です(悪口を言う職員がやっつけられ、無罪の新人は悪を倒し前を向き明日を歩む。印籠(金槌)を持った御老公(「営繕さん」)の退場で幕が下りる)。
本作は、荒唐無稽なブラックユーモア作品と言えますが、それが徹底、貫徹されおり、最後まで小気味良く、読み進められました。
タイトルの「どうぞ好きなだけ」も、「どうぞ好きなだけ金槌を持って帰ってください」と「どうぞ好きなだけ金槌(凶器)を使ってください」が掛け合わされていて、ブラックユーモア×2が効いています。
完成度が高いと評価しましたが、1点マイナスとしたのは、(案外)細かく描写された「営繕さん」の暗躍ぶりについては密やかすぎてよく分からなかったからです。笑うセールスマンのようなモデルがいて、読み手に重ねさせたい意図でもあったのでしょうか? 私にはいまいち「営繕さん」のブラックさが読み取れませんでした。4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Fグループ)「人魚姫の耳」こい瀬伊音
評タイトル『一人の女性が狂気に至る道程は』
前半部、セックスをする男女が、女性の「わたし」の視点で描かれます。「この人は、その気になればいつでもわたしをくびり殺せるんだ」と感じている「わたし」は、力を込めると筋肉がせりあがる「男の人」(全般)に、「ぞくぞく」し、「すごくこわい」という感情を抱いています。「わたし」を何度もいかせたとよろこぶ男を「悪魔だとすら思う」こともあります。「いきっぱなしと笑う男にとって、わたしは女だけれど人間ではない」と感じることもあります。「残酷」とも(感じます)。
それでも「私」は、「苦しいなかにも甘さがいくすじかあれば、その(男の)愛を全力で肯定したくなる。しがみつきたくなる」のです。
「わたし」は、(豊臣秀吉の正室の)ねね(寧々)のようです。
「ねね」は、「共に泳いでくれる魚がほしい」と願っています(銛でえぐる男ではなくて)。
願うのは「わたしのちいさな声を聞いて」くれる人がずっとただ横にいて慈しんでくれること。
でも、願う相手(豊臣秀吉)は遠く離れており、「いらない耳は聞かない」とたくさんの耳を奪い棄ててしまう暴挙を働いています。
「わたし」は、「わたしの声を一番近くで感じられる(自分の)この耳を」願う相手に届けることにします。「手柄だ」と喜んでくれる姿を思い描いて、「すぐにここへ来て」ということばを添えて。
しかし、願う相手の側室(茶々)と側近(光成)は、「わたし」が送った耳を棄ててしまいます。
最後の一文、「好きな歌を、ただ妹たちと歌っていたかった。それだけだったのに。」
前半部、セックスをする男女の関係が、「わたし」の目線で被害的に描かれていますが、 男尊女卑の価値観がはびこる社会へのフェミニズム視点での批評性として書かれているのではなく、普遍化を図ろうとするものというよりは、一人の女性の「狂気」に至る道程について心理の奥底を照射するように描かれた作品、と読みました。
後半部、実は(おそらくは)豊臣秀吉と寧々の関係が描かれていたことが開示され、驚かされました。
立ち止まって、この設定の意
味を考えると、やはり、批評性として普遍化を図る意図があるのだろうか? とも思えてきて、揺れ動くものがありました。
しかし、両者の関係性を裏付ける歴史資料が示されるわけではなく、やはりこれは批評性というものではない、と思い直しました。
そう考えると、寧々とする設定は(歴史的)拘束を免れないものとして逆説的に作品世界を規定し始めてきて、耳を送るという作品世界での事実に抗し始めました。
歴史上の人物を描くことの効果と難しさを本作からは受け取りました。(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Fグループ)「ボウイシュ」一色胴元
評タイトル『日本人のジャーナリストがボウイシュにしたことは』
「私」は、砂の中におり、「あなたたち」に同じ話をさせられている。「あなたたちはなぜ、同じ話をさせたがる」のでしょうか?
「私」が最後に見た少年時代の「ボウイシュは、右目を撃ち抜かれ脳みそを垂れ流し、日本人はそれを抱きかかえていたのです」。
だがしかし、死んだとしか思えなかったボウイシュは、6年ぶりに「私」の前に現れます。
「氏族同士の争いが終わることがなく続き」、人々は(正気を失ったように。私も)「それを楽しんでいました」。事実、人々は正気を失っていたのですが、大量の覚醒植物の存在が背景にはありました。
「私」も正気を失っていたのでしょう。
ボウイシュが6年ぶりに現れ、村の外れに舞台を建設、激しい打ち合いの最中、「ノー(能)」を踊り出すのです。
「落とされた仮面は砂の中に沈んでいきました」
「新しい仮面(能面)をつけた人々は銃を降ろし、その場に立っていました」
「今でも何人かはその場で立ったままです。彼らがどうやって生きているのか私にはわかりません」
「ボウイシュは今では政府の高官に収まっています」
もちろん、「荒唐無稽」と言うだけでは、この作品を説明したことにはなりませんが、荒唐無稽さが際立った作品であることもまた事実でしょう(違いますか?)
正気を失った(だろう)「私」の視点から見た非現実的な光景は、信頼できない語り手が紡ぎ出す言葉として、論理的な「読み」を奪っていく効果が本作にはあります。これを書き手の目論見とするのならば成功しているのかもしれませんが、意味の拒絶、物語性の喪失を前景化させて、では何を本作が語っているのかと言うと、冒頭部の「パッパッパッ」と人の目をくらます光の点滅(ストロボ?)効果以上のものは、私たちに与えないのではないかと、読みました。物語を読みたい読み手に(圧し潰されてしまい)耐え切れない作品だと捉えざるを得ませんでした。(1点に近い)2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する)
■(Fグループ)「墓標」渋皮ヨロイ
評タイトル『夢と夢みたいの違いは』
Aグループの2作品目で解離性障害について触れました(定義の方はそちらで)。
本作を読んだ際にも、解離性障害の一つの症状「現実感喪失」を思い浮かべました。
単身赴任中の夫と離れて暮らす「わたし」には、人知れぬストレスが鬱積していて、(解離性障害の)「現実感喪失」の症状が起こっているのかもしない(しそうではないかもしれない)。
庭に某国の首相が倒れていたこと(死んでいた)。
息子と庭に首相の死体を埋めたこと。
埋めた部分の土から国旗が生えてきたこと。
これらは、症状が「わたし」に見させている幻覚、妄想かもしれない。
息子の存在自体も疑わしい(非現実の息子なのかもしれない)と、私は読みました。
(ただし、その読みが正しいとは私は思っていません。)
可能性として、その読みがあるということ。
そのように読まれてしまう恐れがあるということ。
本作がその読みに耐えられるだけの抵抗力が無いようにも読めてしまう。
「卵の上に息子の名前を書いたつもりが、ほとんどつぶれてしまった」とあるように、「わたし」は息子の名前を呼ぶことができません。
「わたし」は、結末近くで、「いつか、この子がわたしを連れて行ってくれないかな、と夢みたいなことを思っ」ています。「夢みたい」という表現。
正当な「夢」ではなくて、「夢」になり得ない「夢みたい」(非現実世界)な息子なのではないか、とも読みました。一つの線から読めてしまう物語の価値は低いのではないでしょうか(違いますか?)。(4点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
◇◆ 以上により、【 Fグループの勝者は、「どうぞ好きなだけ」今井みどり 】とします。 ◇◆
■(Gグループ)「ミッション」なかむら あゆみ
評タイトル『ミッション』
展示室2。向かって左の片隅に若くもなく年寄りでもない女。監視員。私です。居眠り。薄くない水割りをさっき飲んだせいでしょう。
今日は雨のせいか、展示室を訪れるお客さんは一人もいませんねぇ。
お客さん。濃い色のサングラスを掛けた年寄りの女。
女は顔を寄せ。「実はちょっと頼みたいことがあるの」
女の願いは展示作品を至近距離で見たいというものだった。
監視カメラの死角になる場所ならと許可をした。
「ありがとう。おかげで素晴らしい時間を過ごせた」「(スマホで作品を)撮らなかったし、絵にも触れなかったわ」
「それは、あなたの鑑賞が終わるまで、私が鼻呼吸をし続けるミッションを成し遂げたからです」「まじないのようなものです。私はあなたを信用していません。だから自分に課題を与え、取り組みながらひたすらに願っていたのです」
「あなた、ひょっとして、みどりちゃん?」
「はい。お久しぶりです、桜子さん」
「『やっぱり私はあなたが嫌い』確定です」「桜子さんは今も圧倒的に想像力が欠如していますね」「自己中心的な考え方は、あの頃と何も変化していないですね」
「もしかして私のこと、まだ恨んでるの?」
「『自動販売機から家の玄関を開けるまで、息を止め続けることができたら世界は永遠に平和』。日課にしていた私のミッションを、よりによってあの日、あなたは邪魔したのです」「震災後の信じがたい街の光景」「絶望した私の目」
「バカなの? そんなの関係ないに決まってるでしょ」
「ミッションをやり遂げることは私にとって願いそのものなのです」
「(スマホで作品を)撮らなかったし、絵にも触れなかったわ」
「それは、あなたの鑑賞が終わるまで、私が鼻呼吸をし続けるミッションを成し遂げたからです」「まじないのようなものです。私はあなたを信用していません。だから自分に課題を与え、取り組みながらひたすらに願っていたのです」
『自動販売機から家の玄関を開けるまで、息を止め続けることができたら世界は永遠に平和』。日課にしていた私のミッション」「ミッションをやり遂げることは私にとって願いそのものなのです」
「『やっぱり私はあなたが嫌い』確定です」「桜子さんは今も圧倒的に想像力が欠如していますね」「自己中心的な考え方は、あの頃と何も変化していないですね」
「日課にしていた私のミッションを、よりによってあの日、あなたは邪魔したのです」
「震災後の信じがたい街の光景」「絶望した私の目」
「バカなの? そんなの関係ないに決まってるでしょ」
「私」は、「まじないのような」ミッションに執着しています。ミッションをやり遂げることは「私にとって願いそのもの」
本来的な意味での「ミッション」は、「使命」、「任務」という訳語が示す通り、他者と共有している具体的な目標を指す言葉です。
本作での「ミッション」は、「私」によって歪められており、「桜子」の言葉にありますが、他者との共有を目指されていない「圧倒的に想像力が欠如している」、非科学的、非論理的、「自己中心的な考え方(マイルール)」です。
ファンダメンタリズム、イデオロギー、権力への意志……、といった言葉や概念が浮かんできました。
私たちは、誰もが小さな「(本作での)ミッション」を抱いているけれども、国家やコミュニティ、会社、家族、といったグループの一員として、一定のルールに縛られながら生きています。「私」も一定のルールを守って生活している社会人(監視員の仕事を一応こなしている)ではあるのですが、明確に非社会的、反社会的にならないレベルで、しかし他者との摩擦を起こしかねない「(本作での)ミッション」に固執している。
肥大化した個性(ミッション)の衝突の物語として興味深く読みました。4点を付けました。
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Gグループ)「メイク・ビリーヴ」如実
評タイトル『あなたならテプラに何と印字しどこへ貼るか』
テプラを女は愛用していた。
テプラに愛着を抱いていた。
幼いころは新たに見聞きしたことばをそれに打ち込んで、できたシールを家の中の至るところに貼っていた。それまで匿名だった物体にあだ名ができていくようで楽しかった。
家の中では始めは放任されていたその営みも、母親のパンプスのかかとに「デネブ」と貼ったときから禁止されるようになっていった。
母親に諭され、家の中の物にテプラを貼ることはなくなっていた。
ノートのなまえ欄には、自分の名前のテプラを貼り続けていた。
中学入学を境に何となくしなくなり。
テプラと再会を果たしたのは、高校三年の冬だった。
図書室で宮沢賢治の『春と修羅』を見つけ、開いて序文を目にしたとき、女はなぜ自分がテプラ離れしていたのかを初めて理解した。女は自分がテプラに値する言葉を思いつかなくなっていったためにテプラを使えなくなっていったことを初めて意識することができた。
『春と修羅』の序文にはテプラに値する言葉がちりばめられていた。
女は、「テプラだ」と高ぶった。
女は現在、人から依頼された場所にテプラを貼ることを生業としている。
場所の指定のないクライアントも存在した。言葉の指定は原則受け付けてはいなかったが、ごく稀にニュアンスまでなら受け付けることはあった。
冬はそれ自体によって溶けません(東中野)
※略
メイク・ビリーヴ(西宮北口)
※略
僕らは不器用に不器用を回避している(沼地公園)
※略
メイク・ビリーヴ メイク・ビリーヴ(光徳湯)
宮沢賢治の『春と修羅』序文には「テプラに値する言葉がちりばめられている」との記述があったので、読んでみました。(以下、一部抜粋します)
『わたくしといふ現象は
仮定された有機交流電燈の
ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体)
風景やみんなといつしよに
せはしくせはしく明滅しながら
いかにもたしかにともりつづける
因果交流電燈の
ひとつの青い照明です
(ひかりはたもち その電燈は失はれ)
※以降、略 』
「女」がテプラに印字する言葉は、詩の言葉であって、実用的な情報として他者とのコミュニケーションに使われる言葉(散文)とは乖離しています。
幼いころ、小学生のころは、まだ家の中で、自分のためだけにテプラを貼っていた「女」は、大人になり、「他者」のために生業としてテプラを貼るようになっています。
詩の言葉を必要とする誰か(クライアント)によって、「女」は自分らしく生かされる(活かされる)ことができる。
これからも「メイク・ビリーヴ(作りごと)」の世界を紡ぎ続けながら社会と繋がりたい、という「女」の想いを受け取りました。
『春と修羅』以外のインスピレーション・ソース、詩にまつわる豊饒な物語が背景にあるような気がしています。各地に貼られたテプラと背景の描写が紐づけされれば、詩情はより深まったのではないでしょうか。小説作品と詩作品の折衷を図ろうとして失敗し、両者とも充分には描き切れなかったのではないかと感じました。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Gグループ)「茶畑と絵画」岸波龍
(再掲)あらゆる文芸作品が同じ場でジャッジされるブンゲイファイトクラブにおいて、短詩をどう読み、どうジャッジするのか。私は原稿用紙6枚の内に置かれた首(句)を繋がりのある「ひとまとめの文芸作品」として読み、ジャッジすることにしました。
1回戦では、短詩ならではの制約とその効果、読み方について、「短歌は幻想の核を刹那に把握してこれを人人に暗示し、その全体像を再幻想させるための詩型である」という塚本邦雄のことば、「歌を読むことは打ち上げ花火を打ち上げ続けることではない。歌という小舟を自分の中に浮かべることだ」という鶴田伊津のことばを胸に、だた、短詩であるために、ことさら持ち上げたり堕としたりしないことを自身に課しました。
評タイトル『絵を掛ける場所は』 ※首は順にP1-①、P1-②~と挙げます。
様々な他者との関係性と距離感が歌に詠われています。
腕へし折ってやると笑って茶畑で待ちかまえている柔道部、水族館にいた男の子、おそらくインドかパラグアイかカナダかへ海外旅行に行ってきた友人、(俺に)プルーストを最後まで読ませる君、「グミ買ってこい今すぐに」と寝言を言う妻、何よりも岩盤浴が好きな母、温厚だけど揚げたてのフライドポテトという物欲には勝てずキレる君、母親になるらしいかつて上履きにヨーグルトを入れる嫌がらせをしていた女、サーカスの奇術師、教頭、校長、死にたいと電話で弾んだ声で話す君……。
無関係な他者というよりは、「俺」と近しい(近しかった)人物が選択されているのでしょうか?
残りの歌では、底知れぬラテンアメリカ文学、猛烈な青空、強烈に赤い夕焼け、ギロチンにかけられるオートマトン(自動人形)……、などが登場します。
「俺」にとって印象的な事物が並べられているのでしょうか?
タイトル(テーマ)「茶畑と絵画」にはどのような意味があるのでしょうか?
P1-①「茶畑~」は冒頭の歌で、P3-①「~俺は絵に描く」は末尾から2首目の歌ですが、他の歌と比較して、印象的な「色」を持つ歌(茶畑、猛烈に青い青空、強烈に赤い夕焼け)だと思いました。視覚的な要素をタイトルに採用した理由は……。
興味関心のある他者の像を自己との関連性のなかで俯瞰的に見ていて、次々と歌にしていく。それらをあまり選別せずに並べて1枚の絵画にして、(やはり俯瞰的に)鑑賞しようという意思を感じました。
最後の「ギロチン」の歌は、連作の終わりを端的に示す諧謔としての歌でしょうか。
テーマ性に縛られずに一首、一首を大切にしたいという書き手の想いは伝わってきましたが、1枚の絵画を切り貼りし創作する「俺」の感情や思念といった要素も歌として詠みこまれていれば、より読み手に届く「ひとまとめの文芸作品」となったのではないか? と思いました。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Gグループ)「ある書物が死ぬときに語ること」冬乃くじ
評タイトル『人としての書物の死は』
物心ついたのは、紙のたくさんある場所で、男がわたしの体をくまなく調べている時だった。
最後の男以外は、含み笑いをしたり涙ぐんだりした。わたしのことを好きなのかもしれなかった。
やっと自分の物語を話せるようになった頃、わたしは古本屋の棚に並ぶことになった。
夜になると一冊が話し始める。
背中がすこし日焼けた頃、わたしは老人に買われてゆき本棚に入れられた。
その部屋は壁中が本棚で、机を七日ごとに老人達が囲んだ。
一人が朗読する。
他の老人は聞く。
ここは彼らの共有図書室らしい。
並ぶのは彼らが二番目以降に好きな本だという。
朗読会がひらかれるようになったのは、目が悪くなってしまった老人のために朗読ボランティアが始められたことがきっかけで、他の者も聞きたがって人が集まるようになったのだ。
朗読本は図書室の本棚から選ばれたが、たまに新しい実験小説が買われてきた。わたしが買われてきたのは、そういうわけだった。
Kがわたしを手にとって読み上げ始めた。
一人がこんな小説はくだらんと怒って席を立った。
残った老人達は物語が進むごとにワアワア言って笑った。
その夜わたしは表紙の中に閉じこもった。
隣の古参本がつぶやいた。物語はおれたちの魂だ。
老人達の誰かが死ぬと本棚は整理された。
残りの老人達のうち二人以上が所望すると図書室に残される。一人が所望するとその者の部屋に引き取られる。
わたしを買った詩人の最後の一息。
わたしは図書室に残ることになった。
数年たったある日、作業着姿の若者たちが本棚の本をすべて外に運び出した。Jはわたしを手に取って窓際に寄った。
Jの部屋で、本はわたしだけだった。
朝早くに、少しずつ読まれたわたし。
Jの手はわたしを持つのが困難になった。
それでも時々わたしに触れた。
ある日、若い女がJの部屋に来た。
掃除をし「さよならJさん」と言った。
Jは眠ったまま何かをつぶやいた。
瞬間、わたしの中で「J」の活字が消えた。
文字が次々消えていき、表紙が閉じた。
寝台に横たわるJは怯えた。
わたしはJを安心させるため、物語の一六三頁を語った。最後を語った。
わたしたちは窓ガラスの分子と分子の隙間から、外の明るいほうへ飛んでいった。
本が擬人化されて語られています。本である「わたし」。本の内容は実験小説であるようです。物心がついたころの「わたし」は図書館に、その後古本屋に、そして老人達の共有図書室に、最後にJという老人の部屋へと移動します。結末、Jの死に際に立ち会った「わたし」は、Jとともに部屋の「窓ガラスの分子と分子の隙間から、外の明るいほうへ飛んでい
」きます。
この物語が語ろうとしていることはなんでしょうか?
作品タイトルは「ある書物が死ぬときに語ること」とあります。
ある書物が死ぬ ときに(誰かが)語ること。
ある書物が (誰かが)死ぬときに語ること。
主語は「ある書物」でしょうか?
それとも「誰か」でしょうか?
どちらでしょうか?
それは分かりません。
作品に戻ると、書物が死ぬ(死んだ)とき(あと)に(誰かが)語った場面、ある書物が(誰かが)死ぬ(死んだ)ときに語った場面といえなくはない場面があります。
「Kの蔵書が処分された冬の夜、詩人は焚火に薪をくべるように詩を詠んだ。岸に流れついた鯨について語ると、ため息をついて黙った」
しかし、この場面で「ある書物が死ぬときに語ること」を表現し切れているとは考えられません。
Kの蔵書は処分はされましたが、「死んだ」わけではないだろうし、詩人は詩(本)を朗読したけれども、「語った」わけではない。詩(本)も朗読はされたが、自ら主体的に「語った」わけではない。
本は、人のいない夜に主体的に語り始めます。
本が、人に対して語るということは、(「わたし」によってこの作品が語られていること以外は)基本的にはない。
ただ、「わたし」が主体的に行動しているように見える場面はあって、それは結末のJが息を引き取ろうとしている場面、怯えるJに、「わたしはJを安心させるため、物語の一六三頁を語」り、「ぱらぱらと進み、最後を語」ります。
そして、結末の最後の一文「わたしたちは窓ガラスの分子と分子の隙間から、外の明るいほうへ飛んでいった。」となるのですが、この「わたしたち」はJと「わたし」であることは疑いないのですが、「飛んでいった」行動については、主体的(能動的)なものなのか受動的なものなか判別は付きません。
Jの死が近い状況で、Jの蔵書である「わたし」の死(処分、解体)も近い予感があるなかで、「わたし」は自分の死に対して悲哀や恐怖の感情が湧いているのでしょうか?
死という確実な終わり(永遠の闇)と、「外の明るいほうへ飛んでいった」は対比されているのでしょう。
いずれにしても、「わたしの体」は死(処分、解体)が近い状況で、書き手が、自然な死(古紙回収、リサイクル等)を選択せずに、「外の明るいほうへ飛んでいった」という幻想、飛躍を選んだことは、そもそもが本が擬人化された幻想の物語であるのだから頷けるし、尊重したい気持ちもありますが、この話を「Jとわたしの愛の物語」に収斂してしまうこと、その閉じ方は、自己愛の物語を読み手に押し付ける横暴にも思えてきて、賛同とまではいきませんでした。書き手の本への愛情は夙(つと)に伝わってきましたから、「Jとわたし」の関係性に読み手も加えて(包含して)結末を付ける書き方を選ばれたらと思いました。(2点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
■(Gグループ)「Echo」奈良原生織
評タイトル『概念と具象の拮抗の先は』
ノルウェーの概念谷で、広大なデータセンターが焼失。
原因は、サーバー冷却システムの不具合。
事故によって生態系(の一部)が破壊された。
施設を保有する企業は回復に全責任を負うとし、数千の作業員を現地へ送り込む予定。
概念谷には、かつて独自の自然が存在した。
施設が立ち逆発電所と呼ばれるサービスの提供が開始。
都市の背中から溢れた欲望を効率的に放電する役目。
「F」は作業員として現地へやってきた。
仕事は単調な繰り返し。
寮生活。売春宿ができた。
呼ばれていった事務所には、本社の人間がいた。
「この動物を探し出し、生きたまま捕らえること」が「F」の任務となる。
檻の中でけだるげに四足歩行する獣は、猫のようでもあり狐のようでもある。
「概念猿」と本社の人間は呼んでいる。正式な学名はまだない。
「この生き物が人類にとって極めて重要な存在であるということ」
「F」は毎晩「概念猿」を探索する。
夏の最後の夜、細流沿いの岩陰で「男」は「概念猿」と邂逅する。
「概念猿」の要求は、海底ケーブルを伝って集められた言葉を食用として差し出すこと。
人間たちはそれを呑み、「概念猿」にとっての理想郷を築き上げた。
「概念猿」は生態系の頂点に君臨していた。
しかしあの事故が起きた。しかし、ほんとうに事故、だったのだろうか。
「概念猿」は言葉から隔絶された地に逆戻りした。
Enterキーで砕かれた水面。飛沫がガラス玉となって網膜(スクリーン)に無数の記号を書き付ける。
「概念猿」は「男」に接吻した。「男」は抵抗する気はなかった。
「概念猿」は言葉を食べる生き物だ。しかし飢えていれば、言葉以前を生のまま食べることだってある。
「男」の吸い殻には、早くも具象の動物が集まりだしている。
「概念猿」はまばゆい光を取り戻す。
「電磁波の反射や反響、共鳴」といった意味のある言葉「Echo」が作品タイトルに使用されています。
私が「Echo」という言葉との関連をようやく感じたのは、「Enterキーで砕かれた水面。飛沫がガラス玉となって網膜(スクリーン)に無数の記号を書き付ける。」という文が現れたときでした(この時ようやくEchoの意味を詳しく調べ「電磁波の反射」の意味を知りました)。
Enterキー、スクリーン、無数の記号、パソコンやITを想起させるイメージ。仮想現実?
「概念谷」、「概念猿」、対する具象の動物と具象の「男」。
「F」が「F」ではなく、概念としての「男」に変わったために(その「男」は具象としての「F」を取り込んでいるけれども)、「概念谷」に入ることができて、「概念猿」に接触できました。
具象と概念(象徴)が併存し、「概念」において、そのイメージ(と言葉)は電気的な信号として知覚されます。
都市の背中から溢れた欲望を効率的に放電する役目を持ち、言葉を海底ケーブルによって集め、逆発電所と呼ばれる「概念谷」の施設は、「概念猿」に集められた言葉を食用として差し出していました。
具象と概念(象徴)の間(仮想現実と現実の間)で引き裂かれる想いで終盤を読みました。
現実の事物や出来事を、言葉で説明、表現することの困難さについて書かれた作品である、と読みましたが、概念としての谷(そして猿)を具象としてイメージすることが(原理原則的に)できない(でき得ない)ために、悶々としながら作品に対して意味を持つ言葉を差し出すのが難しいなと感じました。(2点に近い)3点を付けました。
【 採点:3点(1回戦通過に賛成も反対もしない) 】
◇◆ 以上により、【 Gグループの勝者は、「ミッション」なかむら あゆみ 】とします。 ◇◆
■(Hグループ)「量産型魔法少女」佐々木倫
評タイトル『魔法とは』
お母さんは男と暮らすようになった。
十四歳のわたしはしおちゃんと家に置き去りにされることが多くなった。
「お金をもつと人は変わる」としおちゃんは言う。
お母さんは男にわたしのことを秘密にしている。
しおちゃんは、打ち込み音源をネットの海に放流するわたしに「また金にならんことして」とか、「もっと勉強し」と言う。
久々にお母さんが戻ってきた。明け方にはまた男のもとに戻るのだろう。
いつか母さんはわたしを完全に捨ててしまう。そんな気がする。
こどもっぽく笑うお母さん。
小言ばかり言うしおちゃん。
お母さんとしおちゃんは幼馴染で、大人になってからも一緒に暮らしていた。
わたしにはお父さんと暮らした記憶がほとんどない。
お母さんはいつだって、呪文のように、りのちゃんはなんにでもなれる。どこにでも行ける。というのだった。それはなんだか祈りに似ていた。
夜、しおちゃんとお母さんはお酒を飲みながら話をしている。
じゃれあって、いつまでも昔の話をしている。
しおちゃんは、昔ムーンスティックを壊したのは、お母さんのことがうらやましくて意地悪をしたわけではなくて、魔法なんか使えるわけがないのに、大人がそんな嘘をこどもに持たせるのが嫌だった、とお母さんに言った。
笑い声はささやきあう声に戻って、ひそひそと交わされる声は矯声に代わっていく。
朝になった家にお母さんはいなくて、しおちゃんが朝ご飯を用意してくれている。
しおちゃんがわたしを見る目はとても悲しい。その目は決して手に入らないものを求める目。
しおちゃんがほしかったほんとうの魔法の力。何度傷ついても立ち上がる、だれからも愛される魔法少女の力。
しおちゃんがもっと裕福な子供時代を過ごしていたら、少なくとも今みたいに、金、金、金、と唱え続ける人生を送らなかっただろう。
愛情でも義務感でもなく、あきらめとして、彼女はわたしを養い続けるだろう。
わたしは、魔法の力を本当にしなければならない。
ここではないどこかにたどりつかなければならない。たとえそれがどれだけなかしくて、みじめな道のりだったとしても。
「男」の家で暮らしほとんど帰ってこない「お母さん」。
「お母さん」のことが好きで家と「わたし」を守る「お母さん」の幼馴染の「しおちゃん」。
家での「わたし」は、打ち込みで地道に音源を作り、ネットの海に放流してはその反応に一喜一憂しています。
「お母さん」は「わたし」の曲を知らない間に聴いており、ネットのアンチとコメ欄でバチバチしています。
「お母さんはいつだって、呪文のように、りのちゃん(わたし)はなんにでもなれる。どこにでも行ける。というのだった。それはなんだか祈りに似ていた」
「しおちゃんがもっと裕福な子供時代を過ごしていたら、少なくとも今みたいに、金、金、金、と唱え続ける人生を送らなかっただろう」
「しおちゃんがほしかったほんとうの魔法の力。何度傷ついても立ち上がる、だれからも愛される魔法少女の力」
「愛情でも義務感でもなく、あきらめとして、彼女(しおちゃん)はわたしを養い続けるだろう」
だから、わたしは、魔法の力を本当にしなければならない。
どこかうんと遠い、ここではないどこかにたどりつかなければならない。たとえそれがどれだけかなしくて、みじめな道のりだったとしても。
作品タイトルは「量産型魔法少女」。量産型ということは、少なくとも単数ではなく複数であって、おそらくは大量に生産されるものであると思われます。
「魔法少女」とは何でしょう?
作中には「お母さん」のセーラームーンのムーンスティックを「しおちゃん」が壊してしまったエピソードが出てきますが、「しおちゃん」は子供時代から魔法の力を嘘として否定していました(セーラームーン自体を否定していたわけではなさそう。そこがポイントなのか)。
そんな「しおちゃん」がほしかった「ほんとうの魔法の力」について、「わたし」は「何度傷ついても立ち上がる、だれからも愛される魔法少女の力」と説明します。
「魔法少女」は何度傷ついても立ち上がるのです(セーラームーン)。
「魔法の力を本当にしなければならない」と決意する「わたし」。
「お母さん」からも「しおちゃん」からも愛されていない「わたし」が頼れるのはもう、魔法の力くらいしか残されていないのでしょうか?
「量産型魔法少女」というタイトルは、「わたし」のような子供がこの世には沢山存在しているということを語っているのでしょうか。それとも、「お母さん」も「しおちゃん」もかつて「魔法少女」だったことを示唆しているのでしょうか。
「魔法少女」の在り方は少し分かったような気がするのですが、「わたし」が「魔法」に託した意味が捉えられないもどかしさが残りました。肝心なポイントの説明、理解(か暗示か)を得るための材料が不足していると思います。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Hグループ)「PADS」久永実木彦
評タイトル『ナァの気持ちは』
雌猫のナァと暮らすわたし。
わたしはナァを愛していた。
めぐる季節をナァとともに過ごせるということが、わたしにとっての何よりの幸せだった。
今日、ナァは家を出て行こうとしている。使命をまっとうしようとしている。
わたしには彼女の覚悟を軽んじることが、どうしてもできなかった。
わたしは自分が助かりたいだけなのかもしれない。愛するものと引きかえに。
わたしは駆けていくナァの背中に手を振りながら、涙をこらえることができなかった。
テレビのスイッチを入れると、どのチャンネルも同じ内容を放送していた。
世界中から集まった猫たちが仰向けになって肢を、その肉球を天に向かって突き出している。隕石の落下予測地点である東京に、ものすごい数の猫たちが集まっている。
ナァもあそこに加わるのだ。
猫たちが失敗すれば、地球の生命は滅び去るだろう。
「ナァ、ナァ」
わたしはテレビの中継に、聞こえるはずのないナァの声を聞いた。
「わたし」と雌猫の「ナァ」との愛に満ちた生活は、隕石の落下と地球の生命を守ろうとする猫たち(PADS)の物語に「ナァ」が加わることによって、終わりを迎えます。
「子猫たちを撫でようと手を差し伸べると、一匹の雌が目を覚ましてわたしの指の匂いを嗅いだ。そして「ナァ、ナァ」と鳴いて、でんぐり返しをしたのだった」といった、「ナァ」の描写からは、書き手の猫への愛情が確かなこと(井戸の奥底よりも深い)を受け取りました。
(隕石が落下せずとも早い別れがくる)猫との日々が丁寧に語られた物語であったと思いますし、かつ「地球の最後もの(アルマゲドンもの)」へのパロディー作品としてのまとまりは感じましたが、物語としての(「わたし」と(ナァ)以外への)広がりに欠けており、他の作品と比較すると、高評価を付けることはどうしても難しかったです。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Hグループ)「voice(s)」蕪木Q平
評タイトル『育児ノイローゼ』
voice(s)とタイトルにあるように、地の文に様々な「声」が挿入されることが本作の特徴となっています。アプリの鬼の声から始まり、子ども(伶)の声、ママ友の声、不倫相手(?)の声、ベテラン保育士(?)の声……。
なかなか寝付かず手に負えない子ども(名前は伶)を寝かすために鬼が出てくるアプリで脅し眠らせることに成功する「ママ」。寝室から出ると、仕事から帰ってきた夫は自分で温めた夕食を缶ビールを呷りながら食べています。
図書館で借りた絵本の返却期限が過ぎていたことに気付き家を出る「ママ(亜美)」。
伶が寝ぐずりし悲鳴に近くなりますが、夫が「余裕のあるほうが見よう」と寝かしつけを申し出ます。
外は雨で街頭の灯りの中に細かな雨粒が散っています。傘は差さずにパーカーを羽織っただけの恰好で、歩いて移動し信号機で止まる亜美。
信号待ちの間、不倫相手(?)に電話すると、「僕は一人で飲んでます」と言われ、電話を切ります。
雨脚が強くなり、無数の滴に顔が濡れていき、そして、沢山の声(voice(s))が頭の中を渦巻き出します。母親としての役割を求める、夫、子ども(伶)、ベテラン保育士(?)、ママ友……。そして、不倫相手(?)の甘い言葉……、亜美自身の声……。
「一緒にいると疲れちゃって」(亜美の声?)
青にならない横断歩道は押しボタン式でした。ようやくそれに気付くもボタンは押さず、赤のまま渡る亜美。
横断歩道の半ばには水溜まりができていて、亜美が覗き込むと人のかたちをした影が映ります。そうこうしていると水溜まりを踏みつけて弾けた飛沫が自動車のヘッドライトを浴びて光っています。亜美は眩しさに目が眇んで、もう雨音も聞こえなくなっています。
(単純な読みだと自分でも思いますが、他に思い浮かばず)亜美は、育児ノイローゼの症状にかかっているように見受けられます。信号待ちの間に思考が混乱して、判断を誤り、赤の横断歩道を渡り水溜りに映る自分に気を取られて自動車に轢かれそうになっています。
書き手がこの物語で何を読み手に伝えようとしたのか、を想像しました。
育児は社会の課題であって親だけでは担い切れなくなっているのだから、もっと育児する人をサポートできる仕組みを構築する必要がある、というようなメッセージなのか。
いや、そんな主義、主張で物語が回収されるはずはない、と思いつつも、強烈なメッセージ性を感じた理由は結末の悲劇的描写(と読まなくてもいいのですが)にもあることに気づき、読み手への誘導としての物語の機能がアンコントロール状態に近く、感傷に流され過ぎている、多重な読みへの誘(いざな)いを私も(亜美も?)自分自身で殺してしまっていると感じ、自省するほかありませんでした。2点を付けました。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
■(Hグループ)「ワイルドピッチ」海乃凧
評タイトル『人物の配置の妙』
グラウンドの端でキャッチボールをする駿介。
駿介を三階の教室の窓から遠慮がちに眺める文乃。
文乃と机を挟んで目の前に座る加奈。
校舎のそばにいて駿介と投げ合う悠人。
文乃は駿介に好意を持って、「駿介を見ていたい」と想いながら加奈と会話していますが、加奈にバレると言いふらされるため、タイミングを伺っています。文乃の位置(窓)からは悠人は見えません。
駿介は悠人とキャッチボールをしながら、校舎を眺めていますが、文乃と加奈の声は聞こえていません。悠人は加奈の声を聞いています。
悠人のジャスチャーで三階を見て、文乃(の鎖骨より上の左半分だけ)を見つける駿介。駿介から加奈の姿は見えません。駿介は文乃に見とれている様子。
文乃は加奈のスキを見て駿介を凝視するも、また加奈に向き直ります。
加奈が交換手紙を床に落として拾う文乃の視線は窓の外の薄青い空へ。「ナイスボール」声で悠人と気付きます。
駿介は、文乃を確かめようと三階を見るも文乃の姿が見えず動揺し、ワイルドピッチ。
ボールを追いかける駿介と悠人はともに文乃の視線の外へ。文乃はそれを追いかけようと窓から顔を目一杯出して地面を見下ろすも、視線の先に人影はなく、思わず「あ」とだけ声が出ます。
文乃、加奈、駿介、悠人の関係性を、校舎の三階の窓とグラウンドという設定を生かし、人物の位置関係、配置の妙を効果的に駆使し、文乃と駿介の恋心を爽快に描いています。文乃と駿介のお互いへの好意のベクトルは視線へと変換されるのですが、配置上見えなかったり見えにくかったり、声が届かなかったりと、やきもきさせる要素がバランス良く配合されテンポを作っています。
クライマックスでは、加奈の声、悠人のジェスチャーで駿介は文乃に気付き、加奈の姿が急に見えなくなって、ワイルドピッチ。描写で魅せる作品としてすっと読むことができました。(5点に近い)4点を付けました(が、木村文乃と大東駿介を想像してしまったのは、私だけでしょうか? 二人とも嫌いではありませんが、イメージが先行した読みになってしまった。これは私だけの責任でしょうか? 私は有名人を想起させてしまう組み合わせは避けた方が良いと思いました。作者の意図なのかどうか……。これがなければ5点だったかも)
【 採点:4点(1回戦通過に賛成する) 】
■(Hグループ)「盗まれた碑文」吉美駿一郎
評タイトル『碑文は誰に盗まれたのか』
宝物庫で厳重に保管されていた石碑の(刻み込まれた)詩句が消えてしまった。
街一番の数学者であり占い師のヨアートは、王宮より呼び出され、詩句を取り戻すための任務にあたることになる。
任務にあたらせた第九代のマヤ王の通称は、「月の火」と言う。
「月の火」は神に捧げる詩を求め、才ある若者を地下牢に三年間幽閉した。詩句が出来たのちにその若者は処刑され、大理石の石板に詩句を彫刻した彫刻家は両腕を切断されている。絶対的な力を持つ「月の火」。
石碑を検分すると、確かに文字はない。石板は外側と内側で色が違った。外は雪のよう、内はくすんだ灰。内には中心から外にかけて太く光る筋が流れており、全体(内、外)の三割は雲母に覆われている。これでは文字は彫れない。石碑はもともとは白一色だったが、詩が消えて二色になっていた。
白と灰の境目は滑らかで引っかかりはない。怪異の仕業、占い師の領分だとヨアートは思う。
現れた「月の火」へヨアートは「石が詩句へと導いてくれます」「怪異でさえ刻まれた神聖文字は消せなかったのでしょう。ですから岩の色が違います。灰色の石灰岩がどこのものかわかれば、詩句の行方もわかるかと」と進言する。
毎日のように産地より石が届き、確かめるヨアート。合致する岩はなかった。
雲母を削っていたヨアートだが、考えに没頭していたせいで思ったより深く削っており、石碑の厚みは手のひらほどしかないにもかかわらず、右手首の近くまで雲母の穴に潜っている。雲母の層はまだ続いている。
石板の裏に回ったが穴は開いていない。試しに裏側の雲母に小刀を当てるとあっけなく砕け、穴が開いた。部屋の向こう側が見えるが、反対に回ると穴は貫通していない。
ヨアートは、裏も表もない紙の輪(メビウスの輪)と同じことが石碑にも起こっているのではないかと仮説を立てる。
盗まれた石板は、向こうの世界に、石碑の表側と接するよう存在するのかもしれない。
コの字に回りこむように掘り、石灰石の壁を削っていくと、純白が見えた。大理石だった。
十日間を費やしすべての文字が読めるようになった。
刻まれた詩は、妻の頭を撫でていると一本の白髪を見つけたという内容だった。終わり間近に一度だけ出てくる妻という神聖文字を見つめていると、線がばらばらになり震えはじめた。
神聖文字の力によって盗人である王から逃げた、と考えれば合点がいく。
石が消え、肌色の何かが現れた。皮膚……。王の身体の表面が展開図のように貼りついている。
身体が大理石に覆われた王の葬儀は、民にしらせないままひっそりと行われた。王は生きているらしい。
身体はもぞもぞ動き、石碑の目はまばたきするという。
しかし、では、どちらが王の本体なのか。石碑だろうか。大理石だろうか。王宮の奥では今もその議論がなされている。
因果応報の話で、詩人の詩を、彫刻家の彫刻を(合わせると、つまりは石碑を)奪った王は、生きたまま石碑に磔刑に処され、石碑の中で石碑とともに在るしかなくなります。想像することは難しいですが、おそらくそれは半永久的に煉獄にとどまるようなものなのでしょう。
タイトルの「盗まれた碑文」は、「神聖文字によって隠された(盗まれたように見せかけられた)碑文」であり、「王によって、詩人、彫刻家から盗まれた碑文」である。二重性が端的に表されており明快です。
緻密に組み込まれた設定に引き込まれながら読みましたが、緻密であるがゆえにどうしても気になってしまった部分もありました。
「石碑の厚みは手のひらほどしかないにもかかわらず、右手首の近くまで雲母の穴に潜っている」ことは、事前にヨアートから怪異と説明されているしある程度は首肯しましたが、「裏も表もない紙の輪(メビウスの輪)」をヨアートが仮説に立てて掘り進める部分については、論理、科学的にどうしても整合性が付かない……。仮説が間違っていても、石灰石側からコの字型に掘り進めたことで、結果的に文字が見つかったため、結果オーライとしてヨアートが整理した、と読むことはできるのですが、書き手にはなんらかの説明を求めたいという気持ちが湧いてきて……(読み手としてわだかまりが残りました)。
また、石碑の説明が非常に分かりづらかったです。大理石、白一色、全体の三割はそれ(雲母)に覆われていた、外側、内側、内、外、雪のよう、くすんだ灰、灰色、白、灰、石、岩、灰色の石灰岩、岩石、石灰石……。意図的なのかもしれませんが、呼称が目まぐるしく変化することで、読み手に区別が付きにくく物語への没頭を妨げる要素と認識せざるを得ませんでした。表記を統一すべきところもあったのではないかと思います。作品の内容とは直接関係のない部分での評価で申し訳ないのですが、「神は細部に宿る」の言葉は(一定の)真実だとも私は考えますので高評価はできませんでした。
【 採点:2点(1回戦通過に反対する) 】
◇◆ 以上により、【 Hグループの勝者は、「ワイルドピッチ」海乃凧 】とします。 ◇◆
【1回戦のジャッジを終えて】
A「われ、なにしとんじゃ」
O「書いているんですが」
A「わけわからんこというなや」
O「わけわからないですか、すみません」
A「わしがわけわからんわけなかろうが!」
O「申し訳ありません」
A「申し訳ないってなあ、あんた、何に謝っとるんじゃ、おんどりゃあ!」
O「不快な想いをさせてしまったことをお詫びしています」
A「そうかそうか。わしに謝ったわけか」
O「そうです」
A「まあ、ええわ。それはな。でな。書いたんか?」
O「はい。まあ、一応。書き終えました」
A「自信はあるんか?」
O「自信ですか? まあ一応頑張りましたので」
A「頑張ったらそれでええんか?」
O「頑張るだけじゃだめですよね」
A「あたり前よ。結果ださんと。ええようにやったか?」
O「なんのことです?」
A「ええように根回ししたんかってことよ」
O「えーと、根回し? してません」
A「なら、だめじゃろ、お前。損得考えて書かんと、すぐ死ぬで。わしの兄貴も姉貴もそうじゃったからのう」
O「お兄さまもお姉さまも」
A「書いて、どうやったんや」
O「体力的にも、精神的にもしんどかったですけど、楽しくもありました。根詰めてしまい家事もあまりせず、家族にも迷惑かけましたし。睡眠時間が減って仕事にも支障が……。でも、いい面もありましたね。ずっと思考を回していたおかげか、頭の回転が速くなったような気がしました。語彙も増えて相手を言葉でちょっと圧せてしまったというか」
A「相手倒して、満足したんか?」
O「満足とまではいきませんけど」
A「ちゃんと満足せえや。どうしたら満足するんや」
O「例えば、書いたものをAさんに認めていただけるとか」
A「わしにか? 本当か?」
O「例えば、ですけど」
A「読んだるわ」
O「ありがとうございます。感想聞かせてください。あと、できたら添削もしてください。早めにお願いします」
(数日後)
A「……読んだわ。くそじゃ。時間と金返せや、われ」
O「申し訳ありません。頑張ったんですが」
A「頑張りだけでどうにかなるなら、金も親もいらんわ」
O「そうですよね」
A「おい。わしが読むわけなかろうがあんなもん。信じんなや」
O「読まれてないんですか?」
A「読まん。読んでも意味なんてなんもない。必要か?」
O「そう言われるとちょっと。まあ、読まなくても。いや、読んでいただきたいのですが、Aさんにはできたら」
A「読まんわ。読まんでもお前のことは分かる」
O「え? そうなんです? どうして?」
A「本当にな、本当にお前の本当をな、そりゃ本当にだな、もうええが。そういうことよ」
O「どういうことです?」
A「とにかくだ。お前はお前を信じろ。どうでもいいことに捉われるなや。わかったか?」
O「わかったかと言われると、どうもわからないけれど、はい、分かりました」
A「わかったってことやな? はっきりせん返事じゃな。まあええわ。わしがいいようにしたるけえ、待っとれや。大船に乗った気持ちでな」
O「大船ですね! ありがとうございます。待たせていただきます!」
A「おう。さぼらんで、金になることして、待っとけや。親に心配かけんようにな。大丈夫よ。心配いらん。いいようになるで。わしに任せたらな」
O「いいように。いいようにしかなりませんよね。ありがとうございます。待っています」
以上(「陳腐な言葉で愛を君に」大江信)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
