
「探偵とコーヒーブレイク」(再録)
2017年10月に発行したニンジャスレイヤー二次創作ファンジンの再録になります。
ガンドーさんが、シキベさんやフジキドとコーヒーを飲む短編集です。
前作めいたものはこちら ↓

1.
ぽつり。頭に何かが当たる感触にシキベは歩みを止めて顔を上げた。だが、頭上には錆びた配管もアンバランスに張り出した違法建築ビルも、塗装の剥げかけた階層天井もない。アッパーガイオンのストリートであるここでは、見上げた視界には、ただ濃い灰色の雲が広がっているだけだった。彼女の肩と頬にも何かの水滴が当たった。
これは雨だ。そう気づいたときには、空からやってくる水滴は密度と勢いを増し、周囲の人々は慌てて頭上にハンカチやカバンを掲げ、建物内へと小走りに避難し始めていた。空を見上げていたシキベのメガネに雨粒が当たり、水滴が散った。
「……ウェー」
「オイオイオイ、雨なんて聞いてねえぞ」
シキベが部分的に歪んだ視界に顔をしかめると、その隣でガンドーが呟いた。彼の厚い肩も雨に濡れはじめていた。日暮れにはまだ余裕があるはずの日差しは雨雲に遮られ、辺りは時刻に合わぬ薄暗さだ。
「とりあえず雨宿りだ」
周囲を一度見渡したガンドーは、シキベを促すと足早に何処かへ移動し始めた。シキベは慌ててついていく。覚束ない視界でも、ガンドーの大きな背中は見失うことはない。大通りから横道へ逸れ、幾度か角を曲がる。
カララン。ドアが開かれると奥ゆかしいカウベルが店内に響いた。ガンドーに続いてそのドアをくぐったシキベは、突然頭上に振り撒かれる水滴から逃げ切れたことに小さく安堵した。そこは小ぢんまりとした喫茶店だった。
コーヒーの香りの漂う店内には、同じように雨から逃げてきたと思しき入店者たちが思い思いの席に落ち着こうとしているところだった。探偵と助手も窓際のテーブル席に腰を下ろした。シキベはまずメガネの水滴を拭ってかけなおした。多少傾いている気もするがいつものことだ。
彼女は改めて店内を見回した。長い時間の中で熟した色彩であろう飴色木材のカウンターとテーブル。それぞれに合わせられたスツールとソファは落ち着いたえんじ色であり、店の一角には古めかしい振り子の時計がかかっている。
店員はコーヒーを注いでいる気難しげなマスターと物静かなウェイトレスの二人だけで、客たちの話声は低く穏やかだ。きらびやかなディスプレイの土産物屋とそれにはしゃぐ観光客の喧騒にあふれた大通りとは違う、ここだけが切り取られた時間の中にいるような、静かな店内だった。
「この店、前から知ってたんスか?」
迷いなくここへと向かったガンドーの足取りから浮かんだ疑問をシキベが口にした。
「ああ、ちょうど近くだったことを思い出してな。こないだ来たのは大分前だが、変わってねえな」
熱いオシボリで顔を拭きながらガンドーは答えた。このサービスも変わっていない。前回来た時も、突然の雨に降られた時だったことをガンドーは思い出した。慌てて店に駆け込んだ身には実際ありがたいサービスだ。
ほどなくして二杯のコーヒーが彼らの前に置かれた。無口なウェイトレスは静かにカップを置くと余計な会話を挟まずにすぐに立ち去った。暖かな湯気とともに広がる香気が彼らの鼻孔をくすぐり、口に含むと豊かで深い苦みが口中に広がった。
窓の外では雨。店内は程よい空調と静かな音楽。座り心地のいいソファ。熱く旨い上質のコーヒー。何とも贅沢な時間だ。ちらりと罪悪感がよぎるほどに。彼らはここしばらくスズキ・キヨシの捜査に追われていたし、明日もまた引き続き捜査にあたらなければならない。
だが、今日に関しては、やらねばならぬ予定はもうあらかた済んだ。もう後は事務所に帰って情報を整頓するだけだ。頭を休みなく回し続ければ、いい考えが出るってもんじゃねえ。かつて笑みを浮かべた師がそう語った時も、片手にコーヒーカップを持っていたことを彼は思い出した。あの頃は事務所でも豆からコーヒーを淹れていた。
雨が止むまで、たまの贅沢を味わうのも悪くないと、ガンドーはゆっくりとコーヒーを飲んだ。口の中に広がる深く旨い苦み。違法薬物ZBRの摂取は味覚の鈍化も伴うが、この時間には彼の体内のZBRはすでに大分薄くなっていた。そして今はまだ、追加のZBRを入れようという気にはならなかった。
このコーヒーは実際ウマイであったし、向かいの助手もウマソウにコーヒーを飲んでいた。一緒に飲み食いする奴がいる時は、自分もちゃんと味わうべきだ。そうできるときは、そうした方がいい。これもまた、遠い過去に師から教わったことの一つで、長い間忘れていたことだった。
「アー……雨に降られるのって初めてデス」
窓外を眺めていたシキベがぽろりとこぼすように呟いた。
「……そうか」
ガンドーも視線を雨の降りしきるアッパーガイオンへと向けた。瓦屋根は濡れて鈍く光り、道を歩くのは傘を持つ用意のいい者くらいだ。路上には水たまりができ、そこへ落ちた雨粒が繰り返し小さなウォータークラウンと重なり合う波紋を作っていた。
アンダーガイオンの者にとって、頭上にあるのは空ではない。己の上に広がるのは階層を区切る分厚いコンクリートの天井か、それすら隠す錆びの浮いた配管や鉄骨類だ。そこには雨も雲も太陽もない。
昼夜は人工太陽という名の照明の明暗が作るもので、上層の天井に描かれたウキヨエの雲は、排煙で色褪せながらずっと同じ場所に留まっている。そして足元に水が溜まっているときは、どこかの漏水したパイプから滲み出た液体が広がったものと相場が決まっていた。
遥か上空にいつの間にか現れた厚い雲から一面に降り注ぐ雨と、その雨が足元に描き続ける小さなさざ波の反復は、ガンドーには未だ馴染みの薄い不思議なものだった。
「幾何学模様ぽいスね。……アー……エット、あれデス、水たまりッス。雨が落ちて、水面が」
シキベの言葉にガンドーが見返すと、何を言ったのか通じなかったのかと彼女は言葉を接いで窓の外を指さした。ガンドーはシキベが同じものを見ていたことに反応したのだが。水滴が落ちた場所から広がり、互いに重なり合って模様を描く、些細で儚い円形の波だ。
「俺もそいつを見てた」
「エ?」
「水たまりだ」
「アー……そうスか」
シキベは少しばかりうれしそうに口元をほころばせた。二人は再び窓の外を眺めた。店内に流れる抑えた音量の穏やかなジャズと、店外の雨音が重なっていた。
そしてまた、ガンドーのニューロンの底から古い記憶が浮かんだ。彼が初めて雨をその目で見た日も、最初に空一面から降り注ぐ水滴に目を奪われた後、雨粒が繰り返し降り落ちる小さな水面をしばらくじっと見つめていたのだった。
(今日はなんだか色々思い出す日だな)
そう振り返ってから探偵は訂正する。
(今日は、じゃねえな)
忘れていた色々なことを思い出すようになったのは、それは二か月ほど前からだ。彼女が事務所に来てから。ままならない自分と世界に焦りと不安だけを積み重ね、一人で錆び付く日々に目に入らなくなっていたこと。
水たまりに広がる波紋がまばらになってきた。間もなくこの通り雨も止むだろう。
入店した時と同じようにドアのカウベルを鳴らして、探偵と助手は通りへ出た。路面のあちこちには水たまりがあるが、もうそこには雨は落ちていない。代わりに水面には去りつつある雨雲と空の断片が映っていた。シキベは空と水たまりを交互に見比べた後、水たまりを靴先で突っついた。小さな水面とそこに映った空が揺らいだ。
「じゃあ行くか」
ガンドーが歩き出した方向には、アンダーガイオンへと降りるリフトはない。シキベは怪訝な顔をしつつも並んで歩いた。
「帰らないんスか?」
「ちょっと寄り道してこうぜ」
西の空には既に雲はなく、辺りは少しずつ赤みを帯びた色彩に照らされていった。探偵と助手は橙色に染まり始めた建物の間を抜けていく。ガンドーは今日思い出したことがもう一つあった。
「どこ行くんスか?」
「ついてのお楽しみだ」
夕暮れへと向かう傾いた日差しは、ガイオンの街並みにも彼らにも長い影を作った。大きさのかなり違う二つの影は、人びとが家路へと向かう影と交差しながら進んだ。五重塔の作る一際長い影の中に入り、そしてまた建物と街路樹と人々の雑多な影絵と交錯していった。
探偵が向かったのは、ガイオンの西の外れの地区だった。ガイオンは格子状に張り巡らされた道路と厳しい建築規制によって、しばらく見ない場所もそう大きく風景は変わらない。あのビルの西側には、まだ同じような高さの建物はないはずだ。
果たして目的のビルとその周辺はガンドーの思ったとおりだった。彼は細い路地からビルの側面へと回った。そして躊躇わず非常階段の入口に設けられた鉄扉の上へ大きな体を登らせると、シキベへと手を差し出した。
彼女は一瞬目を丸くしてから、ガンドーの大きな手を両手で掴んだ。助手を片手で持ち上げた探偵は、彼女を鉄扉の上へ座らせると、今度は逆側へ降りて、彼女が地面へ着くのを補助する。扉を乗り越えた二人は、非常階段を昇りはじめた。
彼が何をしようとしているのか察しはじめたシキベの頬は、期待と夕日で薄らと茜色を帯びていた。非常階段の金属製の踏板を昇る、重さの違う二つの足音がリズミカルに響いた。彼らの足取りが少しずつ早くなる。
数階分を昇り、ガンドーは踊り場で足を止めた。息を弾ませたシキベがすぐ後ろから同じ場所へと立った。助手に笑顔を見せると、探偵は西の空へ顔を向けた。この場所からは、遮るもののない視界が広がっていた。彼女が見るものになんと言うのか楽しみだ。
今ちょうど、ガイオンを囲む山稜に夕日が沈もうとするところだった。
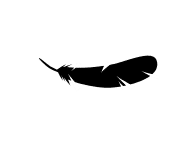
2.
ガンドーがここしばらくエントロピーの急激に低下した己の事務所へ帰ると、同居人はさらにエントロピーを下げる行為に従事しているところだった。
「もう十分きれいじゃねえか」
ハタキを手にしていてもまっすぐに背筋の伸びている男は、訝し気に家主兼雇い主兼師匠を見やると、暫時の黙考の後に省略の多すぎる彼の言わんとすることを察した。つまり、家主その他もろもろの彼にとって、事務所の清掃状況はすでに要求水準を上回っており、したがってさらに掃除をする必要はないのではないか、そのような疑念あるいは提案であろう。
「オヌシが言ったのだろう。掃除は任せたと」
「そりゃあ言ったがな。あれはゴミ出し頼むくらいの意味だぜ。生ゴミは流石に溜めこむとニオイがきついんでな」
彼の基準では掃除とはおおよそそうした意味だ。回収した郵便物の仕分けケースにきっちりと分類された手紙類を見ながらガンドーは答えた。
「他のところへ手を付けない方がよかったか?」
「いや、別にやっていけねえってことはねえ。だが、別にここまでしなくてもいいんだぜ」
支払いの遅れた家賃の督促状を見つけてガンドーは顔をしかめた。今の事務所は家賃に困るほど財政が逼迫しているわけではない。単に振り込みを忘れていたのだ。自動引き落としにすればいいのだが、かつて金策に苦労していた時の名残で、手元に家賃に回せる金があるときに自分で振り込める方を選んでしまう。家賃相当の残高があったとしても、それ以外に先に金を使うべきところは色々とあるものだ。
掃除をしていた男はハタキをかけた本棚の仕上がりを確認していた。実際几帳面な男だ。
「情報は集めるだけでなく、整理して管理してすぐに出せるようにしておけ。これもオヌシが言ったのだろう」
「そいつは頭の中の話だ」
「頭の中に限定する必要はなかろう」
ハタキから持ち替えた雑巾で窓の桟を拭き終えた男は、石鹸を泡立てて己の手を洗った。きっちり三十秒手を洗った男は、コーヒーポットの上に微妙にサイズの合わないドリッパーをセットした。ガンドーの事務所に置いてあるものはどこかしらちぐはぐなものばかりだ。
脱いだコートをソファの背に放って一服していたガンドーは紫煙を深く吸うと、火にかけたケトルを睨む男の背を眺めた。
(大分リラックスしたみてェだな)
彼がこの事務所で見習いを始めた当初は、生真面目な意気込みゆえの真剣さはともかく、長らく続いたサツバツの日々を引きずった殺気と緊張感も色濃く纏っていた。口を開くとニンジャ殺しの話を始めるこの男に、まずはゆっくり休めといったところで、黙って物思いに沈むか勤勉に返り血を浴びて帰るのが関の山であろうとガンドーは判断した。そして他愛ない、だが確実に手足を動かし時間を費やす活動をあてがった。事務所の掃除もその一つなのだが、生真面目過ぎるこの男には掃除を他愛ない行為として適当にこなすなどということはあり得ないようだった。ガンドーが同じ時間を掃除らしきものに費やした場合に片付く作業の見当を、遥かに超えたパフォーマンスを発揮していた。
この男は今後いずこかの企業や施設に変装して潜入捜査する際には、清掃員は選ばない方がいいだろう。仕事ぶりが良すぎて怪しまれるか、専任スタッフとして勧誘されるかしかねない。ともあれ、血の臭いをさせるよりは洗剤の匂いの方が大分いい。ガンドーはそう思った。整理整頓が行き届き、目に付く範囲にホコリも紙くずもない自分の事務所というものはいささか落ち着かなかったが。
先ほどまで丁寧過ぎる掃除を行い、今は微動だにせずケトルを睨み続けている男はニンジャスレイヤーだった。それは彼の名であり、彼の為すことであった。ニンジャを殺すニンジャが、ニンジャの血の臭いをさせているのは道理だ。だが、この男は、遂にニンジャスレイヤーであることをやめないとしても、ニンジャスレイヤー以外の名と、ニンジャスレイヤー以外の為すことを持ってもいい、ガンドーはそう思っていた。
彼と出会って少し経った頃、ザイバツ打倒へ向けた情報を集めながら、ニンジャスレイヤーがひたすらにザイバツのニンジャを狩っていた頃、彼が特に色濃い血の臭いを持って帰ったことがあった。持って帰った、文字通りにだ。
その日ガンドーは急ごしらえの廃ビルのアジトに籠って、UNIXに向かいながらザイバツにつながりうる情報の収集をしていた。巨大であり、そして幾重にも貼られたキョートの階層構造のベールの奥深くに隠された組織だ。かすかな断片を拾うことはできても、それらがパズルのどこのピースにあたるのか、いまだ杳として知れなかった。ガンドーは捜査の進展が感じられない作業を半日続けて焦燥と倦怠を覚え始めていた。
「フゥーッ……」
ガンドーは大きく息を吐いて手を止めた。この状態で作業を続ければ、くだらないミスからかえってザイバツの追手を引き付け、自分たちの死を招きかねない。一旦休憩をいれるべきだろう。そう判断したガンドーは椅子を立って、部屋の隅の段ボールの前にかがみこんだ。ごちゃごちゃと雑多な雑貨の詰め込まれたその箱に、確かなにか休憩向けの飲み物があったはずだ。コーヒーでも飲んで、胸ポケットのZBR煙草に新しく火をつけて。休憩とはそうしたものだ。ガンドーは箱の中へ手を伸ばした。
目的の品以外の、なぜ自分でもこんなものを詰め込んだのかはっきりしない品々の間に太い腕を入れてカフェイン含有飲料を探していたガンドーは、UNIXに向かって集中しているときには感じなかった生臭さを知覚した。
その臭いは、部屋の反対側の隅に積まれたフロシキ包みからのものであることをガンドーは知っていた。だが、あえてそちらを見る気にはならなかった。生臭さと鉄錆の混じった臭いを努めて意識しないようにしながら、ガラクタの底からチャヅツを何とか発見し、その過程でサイズの違うユノミもいくつか見つけることができた。一面に魚類を示す漢字が書き込まれたユノミや、どこかの企業キャラクターがつぶらな瞳でこちらを向きながらポーズを取ったイラストの描かれたユノミ、大きく「祝い」とだけ書かれた何らかの引き出物であろうユノミ。
入れた覚えのないコーヒーはないかと未練がましく漁ったが、入れた覚えのない子供用ザゼンは出てきても愛しい馴染みのカフェインは見当たらなかった。
「まあ、チャもカフェインには違いねェ」
こちらは発見されたコーヒーポットをキュウスの代わりにして、ガンドーがチャを淹れているときに、アジトの入り口から規則正しい足音が聞こえてきた。それと同時に、先ほどまで強いて無視していたのと同じ生臭さと鉄錆の臭いも新たにやってきた。
「どうだった」
コーヒーポットのチャにケトルの湯を注ぎながらガンドーは帰還した協力者に声をかけた。
「一人仕留めた」
その声は常と変わらぬ静かな淡々としたものだった。湯をポットに注ぎ終えたガンドーが、ザイバツ打倒へ向けて協力することになった男、ニンジャスレイヤーの方を向くと、赤黒のニンジャ装束を纏った彼は、いつものように背筋を伸ばした姿勢であり、頭巾とメンポの間から覗く目はいつものように鋭すぎる剣呑なものだった。そして知ってはいたが、片手には、切り落として間もないと思われる未だ切断面から血液の滴る生首をぶら下げていた。
部屋の隅のフロシキ包みの中身も、同じようなニンジャの生首だった。半日前に、寝起きに生首を発見したガンドーが顔をしかめて持ち帰った理由を問うと、後ほどまとめて五重塔の尖塔に刺し、ザイバツニンジャに揺さぶりをかけるのだということだった。つまり、ニンジャ生首の串団子だ。オヌシの情報探索も、少し捗るだろう。そのように言われた。確かに、現状で行き詰まりを感じていることは確かであるし、刺激には何らかの新たな反応が返ってくるものだ。そこのところはガンドーは理解したが、しかし生首の山には辟易とせざるを得なかった。
ニンジャスレイヤーはまっすぐにアジトに置いておいたニンジャ生首フロシキ包みへと向かい、それらを手に取ると、踵を返して歩き出していた。
「オイオイオイ、ちょっと待てよ」
「……どうした。何か新たな情報でも?」
ガンドーは問い返されて一瞬返答に窮した。新たな情報や捜査の進展など特にない。だが、なんとなく、このまま彼を行かせるのはいいことではないと、そう思ったのだ。ガンドーは手に持ったままのコーヒーポットを掲げて見せた。
「チャでも飲んでいけよ」
「…………」
ニンジャスレイヤーは少し眉を寄せたまま無言でガンドーを見ていた。
「アー、なんだ、その程度の時間はあるだろ?」
そう言いながら、ガンドーは彼の赤黒いニンジャ装束の色には、どの位の返り血と、彼自身の流した血も含まれているのだろうと思った。今は彼の荷物から強い血腥さが漂っているが、それがなくともこの男からは血の臭いが消えなかった。
「それは……」
「?」
口を開いて一旦切ったニンジャスレイヤーに、ガンドーは首を傾げた。
「オヌシの持つそれは、コーヒーポットではないのか、ガンドー=サン」
腑に落ちない。そうとでも言いたげな口調にガンドーは一瞬目を見開いて、そしてわずかに破顔した。確かこいつはコーヒーポットだがな、中身はチャだ。キュウスが見当たらなかったんだよ、まあいいから飲んでいけ、そのようなことを言いながら、ガンドーはニンジャスレイヤーに漢字だらけのユノミを押し付けてチャを注いだ。ニンジャスレイヤーは手にしたユノミと、ユノミを持った自分を見るガンドーを交互に見て、そして少しばかりの間立ち止まってチャを飲んだ。片手にニンジャ生首フロシキ包みをぶら下げたままチャを飲み干した男は、一つ息を吐いた。
「行ってくる」
彼はいつもの淡々とした口調で、ニンジャ生首だらけのフロシキ包みをぶら下げていずこへかと出て行った。その背中を見送ったガンドーは、ZBR煙草に火をつけて深く吸い込んだ。
それからまたしばらく経った頃に、ガンドーは彼に探偵をやらないかと提案したのだった。そう言われたニンジャ殺しの男は、その時一瞬、常に纏っていたひどく色濃いサツバツの気配を緩めたのだった。我ながら突飛な思いつきだった。あの時それは、滑稽な、冗談じみたものですらあった。冗談じみていたが、冗談ではない思いつきだった。どこまでも広がる荒野に昇る朝日を見たあの日は、実際のところさほど遠い過去というわけではないのだが、地下の穴倉たるアンダーガイオンの、さらにコンクリート壁に覆われたこの探偵事務所で、他愛ない作業を真剣にこなす男を見ていると、それらは遥かな遠い日であるように思えた。
ピィー!ピィー!
湯が沸いたことを知らせるけたたましいケトルの笛が、ガンドーの回想を遮った。
先ほどまでケトルを睨みつけていた男は、厳かな顔できっちりと適量のコーヒー豆がセットされたペーパーフィルターへ熱湯を注いでいった。湯気をまとったコーヒーの香りが広がり、事務所に染み付いたガンドーの煙草の匂いの上にたゆたった。
厳めしい顔の年下の探偵見習いはコーヒーの入ったマグカップをガンドーに差し出した。受け取りながらガンドーは小さく声を出して笑った。
「どうした」
「いやな、お前さんが俺にコーヒーを出すようになったんだなと、そう思ったんだよ」
言われた男は一瞬怪訝そうな顔をし、そして納得したように頷いた。
「……そういえば、私はオヌシからコーヒーやチャを出してもらってばかりだったか」
そう口にするこの男も、かつての日々と現状を比べているのだろうか、そんなことを考えながらガンドーは淹れたてのコーヒーを啜った。正しい手順で淹れられたコーヒーは確かにウマイものだった。
「オヌシはコーヒーポットでチャを出したこともあったな」
掘り返された同じ記憶に、ガンドーはまた笑った。
「あの時はキュウスもコーヒー豆もみつからなかったんだ、しかたねえだろ」
きちんと荷物を整頓していないから、そんなことになるのだ、生真面目な顔の男からお小言じみた話が始まり、ガンドーは頭を掻きながら几帳面にきちんと淹れられた折り目正しいコーヒーを啜った。
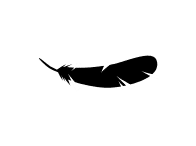
3.
暗く湿った通路の明かりは、わずかに生き残ったタングステン灯の不規則な明滅だけだった。通路の奥の薄暗闇では、どこかのパイプから滴る水音と、時折水たまりを走り抜けるバイオドブネズミの足音が聞こえていた。
不意に白色光が空間を切り裂いた。突然の明かりに驚いたバイオドブネズミたちが脅えた鳴き声を上げながら物陰へと逃げていった。
傷だらけのダスターコートを羽織った若い女がサイバーマグライトで足元から右壁面、天井、左壁面へと順に照らしていった。得体の知れない漏水で腐食したコンクリートの壁には、「アブナイ」「ケンカ」「トラベリング」といった陳腐な攻撃的グラフィティが消えかかっていた。
彼女は今この廃ビル地階エリアに通じる唯一の階段を降りてきたところだった。あたりをサイバーマグライトで照らしながら、彼女は明かりの届かない通路の奥へと眼鏡越しの視線を向けて、既にいささかしかめられていた眉根をいっそう寄せた。そしてこの薄暗く、荒れ果てて不衛生な通路の奥へと歩き始めた。
歩みを進める女は、マグライトを前方へ向けていたが、明かりに照らされた空間以外へも視線を配っていた。今の彼女の視力はこの程度の薄暗闇に明かりを必要としない。暗視モードを起動するまでもなかった。手にした鮮烈な白色光は彼女のためのものではなく、この通路の先にいるかもしれない者に彼女の存在を知らせるためのものだった。見えづらい暗い場所から手を伸ばすのは、大抵が良からぬ者だ。そうした手に暗がりの隅に押しやられた者には、誰かが来たと先に見せなければいけない。
この場所はよくない。コートを羽織った女――シキベはそう思った。こういう場所を彼女はよく知っていた。早くいかなければという衝動が小柄な背を押した。外へ、ではない、奥へ。あるはずの「巣」へ。彼女が身柄を確保しかけたところで笑いながら自殺した捕食者の、獲物の隠し場所へ。だが、彼女は隠し扉やトラップの兆候を見逃さずにいられる歩みを維持した。焦ったことで、捜査を台無しにしたかつての苦い経験を思い返しながら。そしてそれ以外の古い記憶も。彼女のいたあの場所。まともな人間は寄り付かない、顧みられない暗い場所。ここは、ほんとうによくない。
シキベは奥歯を噛み締めて、同じ歩調で捜索し続けた。一定のリズムを維持して手順を踏むことで、結局は早く、そして確実に目標へと至ることができる。焦りや省略は、かえって先入観による型にはまった思考につながる。順番に全てを見て、全てを記憶と記録にとどめて、それら全体から違和感や矛盾を探しだすのだ。ひらめきによる思考のジャンプはそれからだ。一足飛びに名推理は生まれない。
不規則な濃淡を持つ薄暗い通路に、濡れたコンクリートを踏む足音が規則的に響いた。
シキベが地階を歩きはじめてからしばらく経った頃、その上部の廃ビルの割れ窓の隙間から、奇妙な影が飛び出し、そして再び別のフロアの割れ窓から入っていった。間をおいて幾度か異なる窓からの出入りを繰り返した影は一旦上昇すると、ビルの屋上で旋回した。給水タンクの裏側を覗き込むように首を巡らせたその影は三本足を持ったカラスだった。
ビルの屋上へ着地したカラスは高さ十㎝ほどの給水タンクの下部空間を眺めて、思案するように首を傾げた。タンクの周囲をぐるりと回り、再びタンクの下部へと頭を向けた。
「ゲーッ……」
しわがれた声でぼやくように鳴いたカラスは、身を伏せて給水タンクの下部へと入り込んでいった。そしてややあってから体のあちこちに埃や蜘蛛の巣をまとわりつかせて這い出てきた。
「ゲーッ」
再びしわがれ声を漏らしたカラスは、羽にまとわりついた不快なオブジェクトたちを振り払うように翼を広げて身を震わせた。
彼は今までこのビルの上層階を探索していた。割れ窓だらけのこの建物であれば、彼は効率よく各フロアを見て回ることができる。すでにヨタモノやスカベンジャーらに荒らされていたのが幸いし、フスマや戸棚などは開け放されており、彼の嘴や爪では開錠困難な高度な電子ロックの施された不審な部屋などもなく、素早く屋内の現状を確認することができた。そして、目当てのものは見つからなかった。そして最後に残ったのがこの屋上だった。ここも空振りだ。
まだ残った汚れがないか首を巡らして自らの体を確認していたカラスは不意に顔を上げた。地階からの階段を上がってくるかすかな足音を拾ったのだ。
屋上から羽ばたいた三本足のカラスは、ちょうど廃ビルのエントランスから出てきたシキベへと近づき、いつものようにまっすぐその肩へと向かった。それが彼の定位置だ。だが、速度を緩めて肩へと降りる姿勢を取りかけたカラスは、さらに速度を落として彼女の目の前の空中でホバリングした。
シキベの着ていた、肩にパディングの入った爪痕だらけのダスターコートは、彼女が抱える大きな荷物を包んでいた。今の彼女の肩はストライプの薄いカッターシャツに覆われているだけだった。この生地ではカラスの爪には耐えられない。シキベの抱えるやや細長い形のその荷物は、ぐるりと完全にコートに包まれて中身は見えなかった。
シキベは口元をへの字に引き結んだむっつりとした表情のままカラスへと視線を向けた。
「ゲー」
ホバリングしたままカラスは問いかけるように鳴いた。シキベはかぶりを振って、抱えた荷物を見た。そして黙って歩き始めた。シキベの表情は相変わらずむっつりと、一見怒ったような、不機嫌な形を取っていた。カラスは彼女の周囲をゆっくりと回り異常はないか確認しながらも、彼女の視界から外れないように飛んだ。
子供の死体はよくない。三本足のカラスは――ガンドーは思った。特に、それを一人で見るのは。
ガチャリと音を立てて探偵事務所の入り口のロックが外された。このフスマには電子キーもついているのだが、鍵というものはこうした開錠音があった方がいいというのが、シキベの主張だった。
シキベが手に持っていた、今は何も包んでいないダスターコートを、出入口の脇にしつらえられた木製のコートハンガーに掛けていると、続いてガンドーも室内へ入ってきた。彼は強化合成皮革に覆われたソファに舞い降りると、ストレッチをするかのように首をゆっくりと左右に傾けた。
「ゲー……」
うめき声めいた声を立てながら、ガンドーは今度は広げた翼を背側へと伸ばした。
子供は死後四日というところだった。三日前に彼らが依頼を受けたときには既にもうああなっていたということだ。攫われてすぐであったろう。遺体を家に帰せた。おそらくそれは彼らにできる最大限だった。子供の両親の慟哭がガンドーの耳に残っていた。彼は過去に自分がもっと早くたどり着いていれば助かったかもしれない死体を見たこともあるし、無残な姿に成り果てて、しかし帰る家も待つ人もない死体を共同墓地に葬ったこともあった。だが、だからと言って、暗い場所で顧みられないまま殺されたことにマシもなにもない。そして世界には、こうしたクソのような出来事はあまりにもありふれている。
この体になる前は、こんな日はZBRをキメて酒を飲んで、そうしてやり過ごすものだった。一人で子供の死体を見た日にできることなどそれくらいだ。
彼が首を巡らせてシキベを見ると、先ほどまでバシャバシャと水音を立てて顔を洗っていた彼女は、戸棚を開いてインスタントコーヒーのボトルと砂糖壺を取り出すところだった。彼女はそれらを簡易キッチンのワークトップへと音を立てて置いた。次にステンレスのラックに伏せられていたままの色違いのマグカップを二つ手にすると、それも乱暴寸前の音を立てて置いた。
電気ケトルのスイッチを入れたシキベは、シンクにもたれるように両手をつくと、首をゆっくりと左右に傾けて小さい呻きを漏らした。口元はまだ引き結ばれたままだ。
ケトルがチープな電子音を響かせると、彼女は二つのマグカップにインスタントコーヒーの粉をいつもよりかなり多く入れていった。片方には大匙にたっぷりと掬った砂糖も追加された。そこへ熱湯が注がれ、ケミカルな安っぽさを伴ったコーヒーの香りが立ち上った。
シキベは挽き売りされているまともなコーヒー豆も常備していた。だが、こういう時は、コーヒーの抽出を待つことももどかしく煩わしかった。すぐに、馬鹿気たほどに濃いコーヒーが欲しい、今日はそういう日だった。
シキベは黙ってガンドーの隣に座ると、両手に持った二つのマグカップを新聞やマガジンの散らばるテーブルに置いた。ひたすら濃いだけのコーヒーと、ひたすら濃くて甘いだけのコーヒーだ。
「ゲーッ」
シキベへ向けて一声鳴くと、ガンドーは爪音を立てて強化シリコンコートの施されたテーブルに飛び移り、マグカップに嘴を差し入れてひたすら濃いだけのコーヒーを啜った。シキベは変わらぬしかめっ面のまま、ひたすら濃くて甘いだけのコーヒーを啜った。どちらもとても熱かった。
しばしの沈黙の後、シキベは大きく息を吐いた。目を閉じて、息を吸い、再びゆっくりと大きく吐く。肺呼吸の必要ない体でも、この呼吸は彼女に必要なものだ。そもそもは発声のための機能ではあるが、呼吸という動作の可能な体であって良かったと彼女は思った。
シキベは目を開くと、ガンドーが少し首をかしげて自分を見ていることに気付いた。
「……アー、大丈夫っス」
ガンドーは少しの間シキベを見て、再び嘴をマグカップに入れて濃いだけのコーヒーを啜った。シキベも再び濃くて甘いだけのコーヒーを啜った。
「ゲー」
シキベのマグカップが空になるころ、ガンドーは軽く首を上げて喉を見せると促すように鳴いた。
「……ウェー」
そこは、ガンドー自身では羽繕いしづらい場所だった。シキベは手を伸ばすと、彼の顎下から胸にかけての柔らかい羽に指を差し入れて軽く撫で、掻いた。シキベのシリコンで覆われた指先越しに、滑らかな羽根とふかふかとした羽毛の異なる感触と、鳥類の高い体温が伝わった。柔らかく暖かい手触りだ。彼女の手の動きは次第に羽繕いというよりは、むしろ両の手でわしゃわしゃと羽をかき回すようなものになっていった。
シキベの手が喉から首の後ろへ移動したので、ガンドーは彼女がやりやすいように頭を下げた。シキベの手は、今の彼の首を掴むこともできるだろうが、本来の彼の手と比べればとても小さく、指もずいぶんと細い。首と背中の境界で動いているその指は、彼に少々のこそばゆさをもたらした。
しばらく好きなように手を動かしていたシキベが改めてガンドーを見ると、首回りの羽はすっかり乱れて、質の悪い寝ぐせのように好き勝手な方向を向いていた。
「ぐちゃぐちゃスね。いや私がやったんデスけど」
「ゲーッ」
シキベの口角が少し緩んだのを見て、ガンドーは残りの冷えた濃いだけのコーヒーを啜った。彼がコーヒーを啜り終えると、シキベの手が、今度は乱れた羽並みを直すために延ばされた。
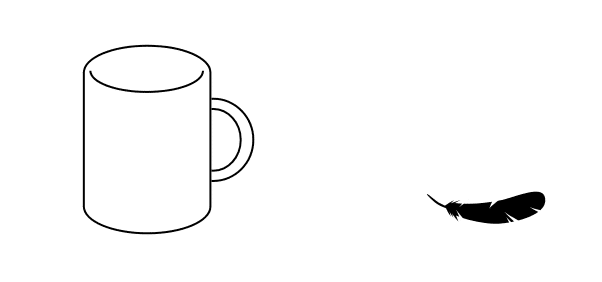
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
