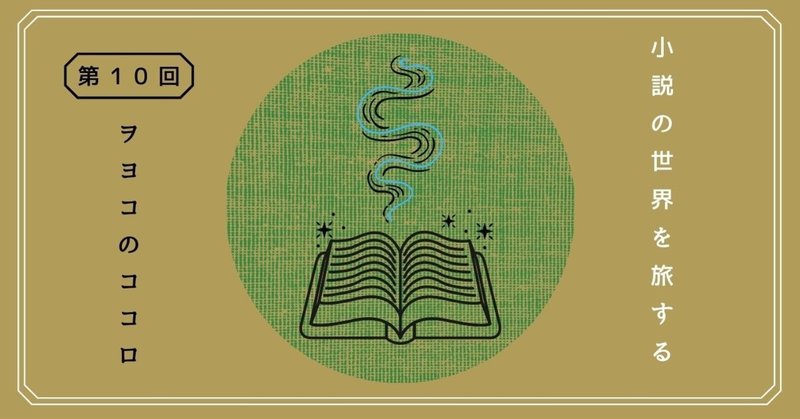
小説の世界を旅する
私がこの世で最も嫌いと言ってもよいであろう蝉共がやかましく朝を告げる季節が過ぎ、寝れない熱帯夜を過ごす日も少なくなってきた。そうかと思えば知らぬ間に夜風が心地良い9月も半ばに差し掛かろうとしている。葉月にまた一つ歳を重ねた私は近頃ひどく多忙を極め、拙文の執筆活動に費やす時間を設けることができずにいた。私の投稿を毎度待ちわびているという物好きの諸君にはまず初めに謝らねばならない。
特に何をしていて忙しかったというわけでもない。月並みに仕事をし、月並みに趣味に勤しんでいた。それでもうだるような暑さに何もかものやる気を吸い取られる毎日ではなくなったこの頃といえば、生誕祝として伯母が送ってくれた私が崇拝する作家、森見登美彦氏の小説全巻セットをぷかぷかと笑いながら読んだり、学生時代から続けている仏語学習にほとほと参ったり、あるいは近所の木工用品店で購入してきた木材を切り刻んでいつ使うやもわからぬ入れ物などを工作したりして、いつ終わるかもわからぬこの人生の限られた時間を徒に、それでも愉快痛快に過ごしているのである。
森見氏の小説に手を伸ばす少し前のこと、私は升形商店街の中にある古本屋で買った村上春樹氏の長編小説を読んでいた。長い小説を読むのが苦手な私にとってはあまりにも長く、同時にあまりに多くの時間を消費した。私がどれほど長い小説を読むことが苦手かというと、一番最後のページが何ページかを確認し、今何ページまで読んだかをそこから引き算し、あとどれくらい読めばこの本が終わるのかを章が変わるごとに確認してしまうほど苦手なのである。そのくせその小説の中にどっぷりとハマり込んでしまうと、あと数十ページで終わるというところまで来ているというのに、その話が終焉を迎えてしまうことがたまらなくなり読むのをやめてしまったりもする。私はこの現象を”閲読の反抗期”と呼んでいる。
そんなことはどうでもよいのだが、私が苦戦したその長編小説は、ある時点から、主人公が住む世界線が不意に変わってしまい、その謎めいた世界を3人の視点から見ていくという内容だった。あまりにも長い小説をたったの三行にしているのだからうまく伝わるはずもない。気になったらぜひ読んでみて欲しいし別に読まなくたって構わない。いずれにせよ物語の中では現実世界ではあり得なかったことが次々と起こっていくのだが、中でも私の目を一際引いたシーンはある日から夜空に浮かぶ月が二つになったという場面だった。いつもの見慣れた月の横に不気味な緑色をした小さな月が一つ、あたかも昔からそこにいるかのように浮かんでいるとのことだった。
何故だかよくわからなかったが私はこの日から毎晩月を見るようになった。もしや自分もある日突然住んでいる世界が変わってしまうかもしれないと思ったのか。はたまた緑色をした不気味な月がひょっこりと顔を出すかもしれないと本当に思ったのか。あり得るはずのない小説の中の作り話が万が一にも自分の生きている世界に起こったらと思うと、私はそこにある種の浪漫を感じ、あるいは病的な震慄すらも覚えた。それからというもの、ほとんど毎晩鴨川デルタに月を見に行くようになった私は、そこに向かうまでの道のりがまるで小説の中の世界のように思うようになり、遂にはその感覚がたまらなく好きになってしまった。月を眺めながら小説の中に何度も登場したヤナーチェックのシンフォニエッタを聞いた。つい先日葉書を出しに京都出町郵便局に行った時に、ひどい音質のラジオからシンフォニエッタが流れていたのを聞いた時はここが違う世界線への入り口なのではないかと震えたくらいだ。ますます私はこの話に登場した青豆や天吾が1Q84年を生きたように、私も2O2O年を生きているかのように錯覚した。2O2Oの語呂の悪さには吐き気すらも覚えたがそこはご愛敬とさせていただきたい。
この小説を読み終えてからしばらくして、熱りも冷めたのだろうか、私はパタリと月を見にいくことをしなくなった。それは月を見ることに甚だうんざりしたからという理由ではなく、単に新たな小説の世界への旅が始まったからである。要するに今は月どころではないのだ。
私が今旅をしている小説の舞台は京都だ。察しの良い方はお気づきだろうが森見氏の小説である。森見氏の小説を読んでいると私の愛おしい学生時代が思い出されて仕方がない。別に当時骨董屋でアルバイトをしていたわけでもなければ、下鴨納涼古本祭で劇的な恋愛をした過去などもない。名高き京大生でもなければ、ボロボロの四畳半の部屋に住むどころか私は新築の十二畳の豪邸賃貸に住んでいたのも紛れもない事実である。それでも京都で四年間の学生生活を送り、市内を自転車で東奔西走していたあの頃の私を、私は彼の描く小説の随所に重ねずにはいられないのだ。最も学生身分ではなくなり、社会の歯車へと成り下がったいまでも自転車で京都市内を東奔西走し、しこたま酒を飲んでは困窮する様などは学生時代のそれを下回る時もあるのだが。如何せんそうなると彼の描く小説への逃避行は、私のポンコツ頭にはちと難解過ぎた村上節と比較するといささか捗るわけである。楽しくて仕方がないのだ。
しかしここまで書いてきてなんだが、よくもまぁ“小説の世界を旅する”などと痛々しい題名で文が書けるものだと自分でも恐ろしく思う。読者諸君がこの筆者はさては痛い奴かと思うやもしれぬことは百も承知であるし、私がそれを百も承知と思っていることを諸君は百も承知なのであろう。言わずもがなそんなこと私は百も千も承知である。そもそも小説の世界に逃避行することなどは百歩譲って世間でも多くの人間がすることなのかもしれないが、そんなことをいちいち文章にしたためる奴はロクでもない奴だ。普段から本を読んで現実逃避をしている人間は現実逃避が日常なのだからそんなことを世界に大公開すべく書く必要もない。普段本を読まない奴こそこういうことをしたがるのだ。急にそんな卑屈になってどうしたのだと思うかもしれないがそう思ってしまったのだから仕方がない。
私のひねくれ小噺はこの辺にしておいて、どうして私が恥を忍んでまで今回こんなにも痛い文章を書いたのかというのは次回作につながる布石とするためである。今私の中では壮大なプロジェクトが動き始めている。それを上手に伝えるにはこんなにも恥ずかしい私の脳内を晒す必要があったのだ。どうかその部分を読者諸君には理解していただきたい。これは私にとってある種の挑戦であり、私の中では多くの大手新聞各社が取材に来るのではないかとも思わざるを得ない内容である。ぜひとも次回に期待して欲しいとここに書き残し、私は今夜も夜の逃避行に出かけることにする。それではまたそのうち。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
