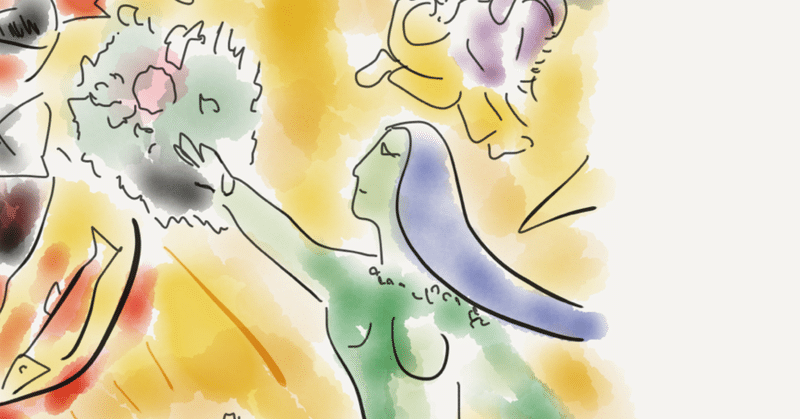
『ダンス・ダンス・ダンス』
村上春樹作品の書き下ろしは、『騎士団長殺し』を除いて、すべて発刊直後に購入し読んできた。中には出だしでつまずいてどうにもこうにも前に進まずいったん閉じて、売って、川面のはるか彼方まで跳ねながら飛んで行った小石のように、忘れた頃にまた買って読んだ作品もあったけど、その話についてはまた改めて。そのようにして読んできたけど、内容のほとんどはすでに忘れている。
読み終えページを閉じたそばから骨子なり潮流や抑揚なりが口に含んだ綿菓子のように消えていくのは、なにも村上作品に限ったことではないけれど、氏の小説ほど忘却率のよい作品は珍しい。
読んだ気がしない。
読んでもなにも残らない。
こうした類の評価も多く、作品を手に取ることを憚る読者も少なくないと聞く。
ノンジェネレーションと呼ばれた米文学の影響を受け、宙に浮かぶ蜃気楼のごとくの不確かな魂を、重みを持たない言葉でとらえたらこうなりました、といった典型を確立した作家の作品ではあるけれど、ふわり宙に浮かぶしゃぼん玉の非掌握性を好む人はのめり、好まざるは者は嫌悪した。
そういうことは、世の中にたくさんある。パクチーを避ける舌が、とことんエスニックを遠ざけるのと同義。
重みのない言葉は、重みのある言葉と違って、そう長く生きてはいられない。見た目が豊かでも中身が希薄な言葉は、生まれたそばから死んでいく運命にあった。
「お客さん、電車がきましたよ」通勤電車の入線と共に、生まれたばかりの言葉は次の瞬間に死んでいく(『街とその不確かな壁』より)。書いた本人もそのことをよくわきまえていた。
『ダンス・ダンス・ダンス』
読んだのに、雪に埋もれたセミの抜け殻みたいに、ガワだけが硬く湿気を帯びて残っている。重みをもたない言葉の成れの果ては、注いでも注いでも満たされない穴のあいた樽のように、読者という水をいつまでも求め続ける。止まると死んでしまう回遊魚のようにそれは蠢き、踊り止むと息を止めてしまう被生命体。
絵は、マルク・シャガールの『La danza』のラフ模写。Danzaはスペイン語で、意味はダンス。
シャガールの放ったタイトルに重みがなかったとはとうてい思えないが、邦題は『ダンスとサーカス』と名付けられた。翻訳者が画家の真意を取り損ねたか、描かれた絵に惑わされてしまったか。絵にしても本にしても、踊らされた末の結果がこれである。
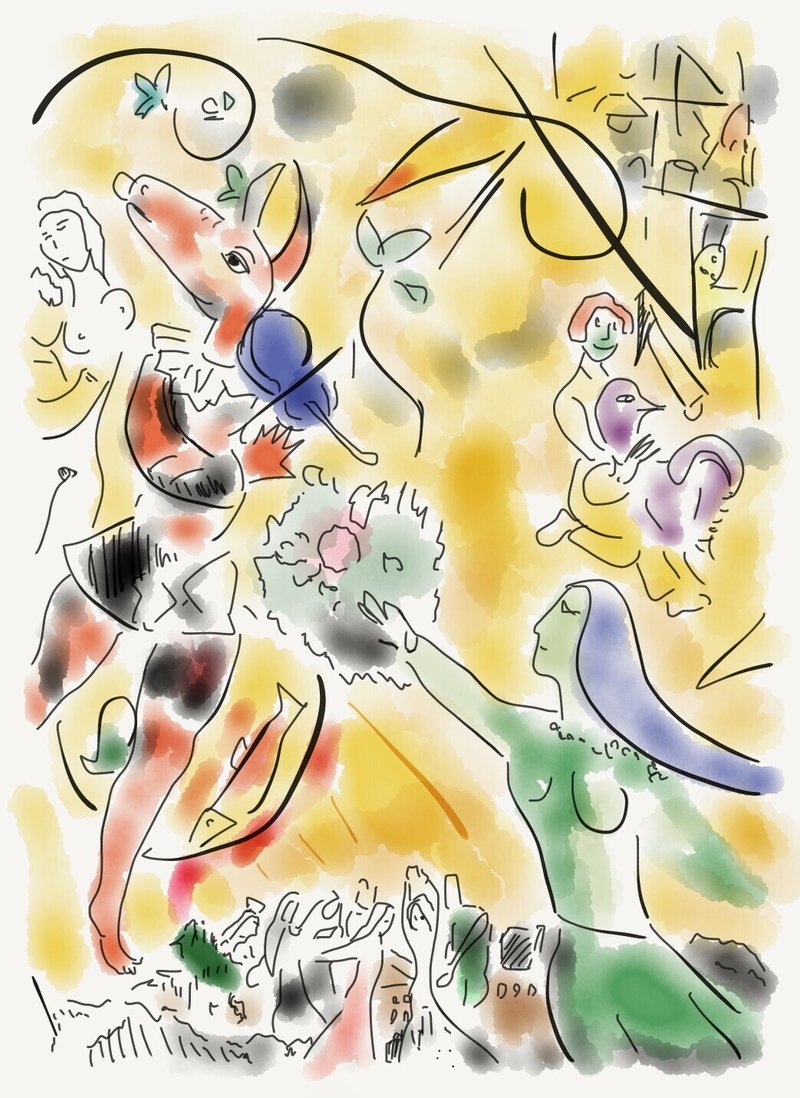
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
