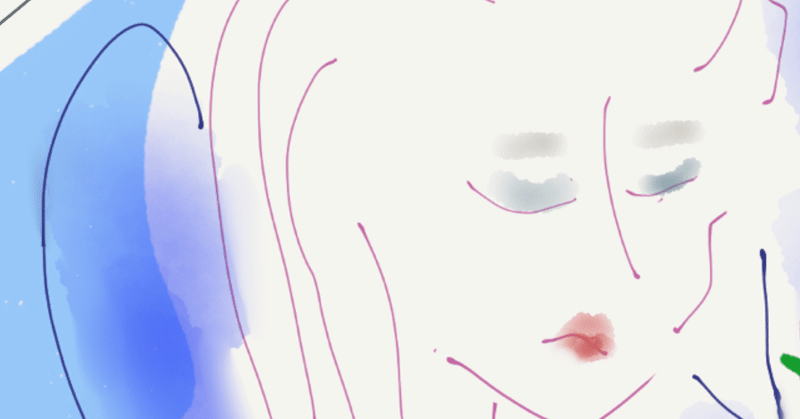
ラブアフェアは未完の絵画のように。
ラブアフェアはいけない娘のすることか。ふしだら男のなせるわざか。
純子は親から感動されてもなお、実らぬ恋を選ぶと決めた。
「それで幸せなんだよね」。10年ぶりに会った幼馴染は、笑うと切り立った峡谷さながらの深いエクボを刻んだ。10年前より深みを増したように思えたが、もともと華奢な体がやつれを纏い、辛苦の経験を身に刻んだことが関係しているのかもしれなかった。
孝徳の問いかけに純子は「ええ」と小さく肯定しただけだった。わざわざ声を大にしなくても、わかりきったことを答えるのに無益な争いはしないとでもいうような答え方だった。
実家を離れて四木山の中腹に借りたアパートは、無駄なものがなく、風の通りがいい。比呂世川は山の清流を引き継いで、今でも真夏に涼を運んでくる。アパートは安普請とまではいかないまでも品格とは無縁の質素さで、彼女の部屋に置かれた分不相応な高級ベッドが海に浮くブイのように異質に際立っていた。
すべてが綺麗に整えられている。それは自分のためにではなく、迎え入れる誰かさんのためにだと思うと、やるせなくなる。不倫男を一刀両断ばっさり切り捨てて、それを肥やしに家族を増やす選択肢もあっただろうに。
大人になった少女は、すでに港を離れ、自らの意志で後悔なき航海に旅立っていたのだ。他人がとやかく口を出すようなことではない。どこに向かったのかも、誰と同乗したのかも、他人ばかりでなく親も友もしばらくは知らずにいた。
いかにして発覚したかは、知らぬ男の腕に嬉々としてまとわり戯れる純子の目撃情報が散見されたことによる。周囲は最初、祝福への軌道だと勘違いした。ところが閉じた蓋が開いていくにつれ、送る笑顔が重い怒りに変わっていった。
「陽子は味方になってくれたわ」。頬を撫でていった風の尾を視線の端で捕まえて、純子は物憂げに言った。言葉で言い表すにはあまりに複雑に絡まりすぎた諸事情が、純子に覆いかぶさっていた。
親友は、純子の意志が揺らがないことをよく知っていた。諭しても聞かないのなら、せめて痛みに寄り添おうと決めたのだと思った。
あれからさらに10年が過ぎた。純子は相変わらず実ることのない男との関係を紡いでいた。彼女の仕事による上京で知った現実だった。
「今でも愛しているの?」と訊くと、控えめだけどキッパリとコクと頷いた。
「なによりだ」。それ以上は言えなかった。
旅は、出かける前がいちばん楽しいと言う。あれこれ浮かんでくる「ああしよう」「こうしたい」「どんなかな」が小さな不安をステップに好奇の味覚を刺激して、味わいの高みに昇っていく。その工程のなんと優雅で甘美なことよ。
ところが現実の旅程は残酷で、あれだけ膨らんでいた理想が次々とちんまりとした型にはめられていく。あんなに大きかったものが、見る間にシュリンクされていく。
純子は意志の強い夢みがちな少女だった。その彼女が「こう生きる」と意志を誇示したのだ。彼女も、旅の現実を知っていたのだと思う。旅に出てシュリンクされてちんまりまとまる愛よりも、もろく儚く霧のように消えてしまいそうだけど、いつまでも追いかけていられる右肩上がりの愛を選んだのだ。
こんなふうに思っていないと、誰も幸せになれない。
恋は、視界にパステルの絵の具を塗る。そうしたカラフルな絵画の中で生きようとする女がいる。夢と景色を描き続ける男がいる。すべては愛の序章。その愛でさえ、収まる愛と膨らみ続ける愛がある。
ラブアフェアは、モラルで縛られる世界とは別の次元で夢が営まれている。夢を描く絵画はいつまでも未完で、永遠にたどり着かないゴールを目指してしまう。現実に落とし込めない夢は蜜。心を右肩上がりで舞い上げて、恋心をそそのかし続ける。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
