アルーレン解説・実践編 (前編)
こんにちは、otabaです。前回の解説記事をたくさんの方に読んでいただくことができました。アルーレン自体の情報が少ないということもあって、意外な需要があると感じたので、アルーレンを使う方のために自分の知りうる限りのことを書いていきたいと思います。
また、前回のデッキとほぼ同じリストで100戦に到達したのでそれぞれのマッチアップごとの相性や立ち回りについても触れていきたいと思います。書いているうちに思いのほか長くなってしまったので、フェアを中心に取り上げる前編とアンフェアを中心とした後編に分けたいと思います。
アルーレンのテクニック
アルーレンを実際に使う際は、スタックのルールをしっかりと理解しておく必要がある。これは「魔の魅惑」下では、お互いのプレイヤーがインスタントタイミングでクリーチャーをプレイすることができるからである。
この性質から、アルーレンには「魔の魅惑」を利用したいくつかのテクニックが存在する。
〇単体除去をかわす
アルーレンコンボは「洞窟のハーピー」始動の場合、単体除去1枚では止めることができない。これは簡単な手順を踏む必要がある。ここではコンボの終点である「寄生的な大梟」の例を挙げる。
①「魔の魅惑」を設置する
②「洞窟のハーピー」を場に出し、開門能力(青か黒のクリーチャーを手札に戻す効果)をスタックに積む。
③開門能力の解決前に「寄生的な大梟」をプレイする。
④先にスタックに積んでおいた開門能力で「寄生的な大梟」を回収する。
Note用動画その②
— otb (@otb33291187) July 22, 2019
アルーレンの基本テクニック pic.twitter.com/en5mfXwehZ
これが基本の1ループとなる。この手順を踏むことで、「洞窟のハーピー」や「寄生的な大梟」に除去が飛んできても、「洞窟のハーピー」の1点ライフを払って手札に戻る効果を使うことで、除去に対応して「洞窟のハーピー」をプレイし直すことができる。
また、MOでこの操作を行うと、クリック回数を少なくして手間を減らすことができる。他にも様々な状況に応用が効くので、アルーレンを使う際は必須のテクニックとなる。
〇ドローステップにハンデス
「渦まく知識」や「思案」などでライブラリーの上にハンデスを積んでおけば、「断片無き工作員」で相手のドローステップにハンデスを叩き込むことができる。使う場面は多くないが、覚えておいて損のないテクニックである。
Note用動画⑤
— otb (@otb33291187) July 22, 2019
アルーレンの基本テクニック pic.twitter.com/dhYOSJTncs
〇後出しで駆け引きに勝つ
アルーレンは使用者が少ないため、相手取ることに慣れていないプレイヤーが多い。そのような相手の場合、プレイング次第で本来なら負けていた場面を勝ちに変えられることがある。その際に意識すべきなのが「後出し」である。
アルーレンは設置したものの、相手が対応札をもっていることが予想できる場面がある。その際は、本命となる「護衛募集員」を隠しておいて、「悪意の大梟」などのクリーチャーからプレイしていく。こうすることで相手のミスを誘うことが出来る。相手と対応札をたたきつけ合う、デス&タックス戦などでよくみられる光景で、慣れていない相手の場合、「悪意の大梟」に対応して「エーテル宣誓会の法学者」などをプレイしてくることもある。
また、それでもつられてこない場合は、設置した後に何もせずエンドステップまでターンを進め、相手の様子をうかがうことも有効である。手札にクリーチャーを抱えている場合は、返しで殴るためにプレイしてくる人が多い。そうして先にプレイさせ、後出して自分の本命を通していくことで、細い勝ち筋を手繰り寄せることができる。
Note用動画
— otb (@otb33291187) July 22, 2019
対オムニテル pic.twitter.com/tNkr7TSeXJ
今回ここに貼った動画はオムニテル(メイン戦)との駆け引きである。三ターン目に「実物提示教育」には、「全知」を警戒して「Force of Will」を当てている。「Force of Will」をカウンターさせ手札を2枚消費させた上で「魔の魅惑」を設置しようとする意図がある。できなくてもトップに「トレストの使者、レオヴォルド」がいるので、そのバックアップを受けながらコンボを決めに行く算段である。
また、相手のアクションに「護衛募集員」を合わせに行くことで、後出し勝利をしている。相手との駆け引きでは先に底を見せないことが重要である。
このように、「魔の魅惑」さえ設置してしまえばどのタイミングでも動くことができるため、リスクとリターンを天秤にかけて、コンボを仕掛ける最も有効なタイミングを見極めていく必要がある。
マッチアップ解説
Nic Fit Snow Alurenでリーグに参加し、100戦行った。最終的な結果は72/100で勝率72%と望外の高さであった。この記録を踏まえながらマッチアップごとの解説を行っていく。以下のデッキが現在回している最新のリストとなっている。

ホガーク等の墓地利用やリアニメイトが増えてきたのできたのでサイドに枠を設けるために「漁る軟泥」をメインに昇格している。このような構築にして勝率も上がり、以下のような結果になっている。MO上のメタに対しては最適化されているものと思われる。

対デルバー系各種
計20勝4敗
・UR Delver 6勝1敗
・Canadian Threshold 9勝2敗
・Grixis Delver 1勝0敗
・4C Delver 4勝1敗
今回の高勝率の原動力はデルバーの多さにある。現在のMOのメタは完全にデルバーに寄っていて、1リーグに1~2回は必ず当たるほどである。今回のデッキはどのデルバーに対しても有利に戦うことができている。アルーレンの対デルバー戦は序盤と中盤が全てである。
〇序盤
序盤はとにかく「不毛の大地」をかわすために基本土地を置きながら、「目くらまし」をかいくぐって壁となるクリーチャーを展開していくことを意識している。「陰謀団式療法」を撃つ場合は「目くらまし」か「もみ消し」を指定し、できるだけ早く3~4マナに到達できるようにしたい。
〇中盤
中盤に突入している場合は盤面を止められていることが多いため、「稲妻」による突然死を防ぐことに重きを置く。そうして長引かせてコンボをそろえることを目指すのがメイン戦の立ち回りとなる。そのため中盤以降の「陰謀団式療法」の表は「稲妻」を指定している。(コンボの前方確認の場合は異なる)
〇サイドボード後
サイド後は「魔の魅惑」の枚数を減らしてビートプランを中心に戦う。(劣勢でもワンチャンスを作りたいため0枚にはしない)「花の絨毯」で無茶苦茶な展開をできるため、サイド後はメインより楽な戦いとなる。
〇メインボードの要注意カード
「真の名の宿敵」
メイン戦で出されてしまうと対処不可能。壁を並べる戦術はとれなくなるため、速やかにコンボを決めなければならなくなる。

「もみ消し」
これを上手に当てられると負ける。撃たれても大丈夫なタイミングを図ってフェッチを使うか、土地をたくさん引くしかない。

〇サイド後要注意カード
特になし。「花の絨毯」で蹂躙しよう。
デス & タックス
・Death &Taxes 2勝1敗
レガシーの単色フェアデッキの代表であるデス&タックス。カウンターもなくクリーチャーのサイズも大きくないこの相手だが、アルーレンは苦戦を強いられる。
これはデス&タックスがアルーレンにとって厳しいカードを多く採用しているからである。
しかし、勝率としては低くなく、微有利といった印象である。
・Maverick 3勝1敗
類似デッキとしてマーヴェリックにもここで触れておく。マーヴェリックは骨太になったデス&タックスといった印象である。「緑の太陽の頂点」から「魔の魅惑」のプレイすら許さない「ガドックティーグ」が飛び出してくるため、さらに厄介な相手となる。今回は運よく勝ち越すことができているが、相手が対アルーレンになれれば慣れるほど勝率が下がっていくものと思われる。
〇メインボード
とにかくコンボを決めて勝つことを目指すことになる。そのためには「不毛の大地」と「リシャーダの港」に嵌められないことが重要である。「不毛の大地」は基本土地を置くことで回避可能だが、「リシャーダの都」はどうしようもない。フェッチを温存するなどしてささやかな抵抗を試みることとなる。もし複数枚置かれた場合は投了が見える。ここに「スレイベンの守護者、サリア」が合わさると完全に嵌められた状態となる。
逆に言えば、それさえなければコンボを阻害するものは少ないため、メインボードはあっさりコンボが決まる。
Note用動画③
— otb (@otb33291187) July 22, 2019
対デス&タックス(メイン) pic.twitter.com/dqWAYvDOAS
このような嵌めを回避するために、初手の「霊気の薬瓶」は「Force of Will」などで打ち消せるのならば消した方がよい。相手もマナを使って展開せざるを得なくなるので結果的にこっちへの妨害が少なくなりコンボへの道のりが近くなる。ちなみに「霊気の薬瓶」を通してしまうと消すカードがなくなり、ゲーム終了まで「Force of Will」が手札で腐り続けることになる。
〇メインボードの要注意カード
「スレイベンの守護者、サリア」
クリーチャー主体で構成されているアルーレンだが、他のデッキと同じようにサリアの影響を強く受ける。これは除去が「突然の衰微」しかないため重く、「渦巻く知識」などのドローソースも多く積まれているからである。また、2/1先制攻撃というスタッツ自体がアルーレンではなかなか止まらない。「Karakas」と合わさると、討ち取ることは実質不可能となる。

「梅澤の十手」「火と氷の剣」
「梅澤の十手」は、殴られれば殴られるほどコンボを決めることが困難になっていく。カウンターが4つ載ってしまうような状況はコンボを決めることがほぼ不可能になる。(2個くらいなら案外どうにかなる。)「火と氷の剣」は、実は「梅沢の十手」よりも苦手なカードである。装備されるとアルーレンに入っているクリーチャーではブロックがほぼ不可能となり、速やかにゲームが終わってしまう。メインの「突然の衰微」は主に「スレイベンの守護者、サリア」かこれらの装備品に使うことをお勧めする。


「リシャーダの港」
前述の通り

〇サイドボード
サイド後は相手の妨害がこれでもかと入ってくるためコンボを決めることは簡単ではない。しかし、コンボ以外で勝つのが難しいマッチアップであるため、「魔の魅惑」は減らさないようにしている。
全体除去を効果的に使ってヘイトベアーを受け流し、妨害が薄くなったタイミングでコンボを狙っていく。
〇サイドボード後の要注意カード
「ミラディンの十字軍」
コンボを阻害しないが着地してしまうと「毒の濁流」などの全体除去以外では触れなくなってしまう。2~3ターン生き残るとゲームが終わる。

「各種コンボを妨害する生物」
これらが飛び出してくるので、たくさんの手札を抱えるデス&タックス相手に「魔の魅惑」を設置するのは自殺行為である。ハンデスで前方確認をするか、準備を十分に整えて相手の息切れのタイミングを伺うこととなる。

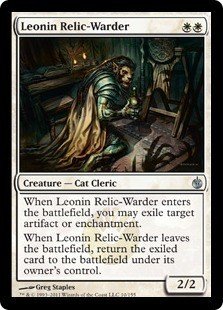
奇跡
・Miracles 3勝1敗
奇跡戦は「精神を刻む者、ジェイス」を置かれるかどうかが全てである。ジェイスを置かれて2ターンほど維持されるとほぼ負けなので、いかに出させない、もしくは出されても脅威にならない盤面を作るプレイングをするかが重要になる。こちらへの妨害はカウンターのみなので、コントロールデッキの中では比較的戦いやすい相手である。
常にクリーチャー2〜3体が場にいる状態を保ちながらゆっくり体勢を整え、「陰謀団式療法」でコンボを無理やり押し通していく戦いになる。勝ち越してはいるが、上手な相手には負けているので五分の勝負と思われる。
〇メインの要注意カード
「精神を刻む者、ジェイス」
着地されるとアルーレンの貧弱なクロックでは、ほぼ落とせない。置かれた返しは前方確認しながらコンボを決めたい。下はよくある負けパターン。

Note用動画④
— otb (@otb33291187) July 22, 2019
対奇跡のよくある負けパターン。プレイングもいまいち。 pic.twitter.com/blIN3rsn4x
〇サイドボード後の要注意カード
特になし。エンチャント破壊が入ってくるが、コンボ直前に「陰謀団式療法」で叩き落とそう。

多色ミッドレンジ・コントロール
多色ミッドレンジ
Grixis Midrange 4勝1敗
RUG Midrange 1勝0敗
Jund 1勝0敗
多色コントロール
Grixis Control 1勝1敗
4c Leovold 0勝1敗
4c Snow control 1勝0敗
多色のミッドレンジはアルーレンと同じ速度帯のデッキなので、基本的には得意な相手となる。しかし、互いにアドバンテージを獲得する手段が多くあるので、消耗戦になることも少なくない上、除去が豊富でビートプランで攻め切ることが難しい。手札が減りにくいアルーレンと言えど、よりアドバンテージに特化したデッキと正面から戦うのは厳しいので、コンボに頼る戦いになる。
ミッドレンジとコントロールの境界が曖昧であるので、同時に多色コントロールについても取り上げるが、こちらは一転して苦手な相手となっている。より防御的で妨害も多いので、さらに攻めるのが難しくなっているのが原因であると考えている。アルーレンが苦手とするカードがどれだけ積まれているかで相性はさらに変化してくる。
〇メインボードの注意すべきカード
「Hymn to Tourach」
これのせいで黒が混じる相手とは噛み合いが必要になる。「陰謀団式療法」で最序盤に指定するくらいには撃たれたくないカードである。撃たれても粘り強く戦おう。

「トレストの使者、レオヴォルド」
7500円の強さは1000円程度になった今でも健在。これが立っているだけでアルーレンは機能不全に陥る。「花の絨毯」は緑が絡んでいる場合は置いてはいけない。

「罰する火」
アルーレンに入っているクリーチャーのほとんどがただで焼かれてしまう。

「精神を刻む者、ジェイス」
奇跡の時と同様。
〇サイドボード後注意するカード
メインで十分厳しいのでそれよりつらいカードは少ない。強いて挙げるならばグリクシスコントロールが使う「血染めの月」だろうか。対策として「花の絨毯」を「老練の探険家」と入れ替えてサイドインしよう。

Nic Fit 系
Nic Fit Rector 1勝0敗
Nic Fit Neoform 1勝0敗
マナを伸ばして自分の好きなカードを叩きつけるNic Fit だが、アルーレンが確実に有利が付く相手である。マナを伸ばして重いクリーチャーを出してくるころには「魔の魅惑」で即死コンボを決めることが出来る。
〇注意すべきカード
特になし。すみやかにコンボを決めよう。
つづく
ここまでで前編を終えたいと思います。これだけ見るとかなり強そうに見えますが、比較的勝率の高いフェア相手を取り上げているからというのもあります。後編は苦手な相手が目白押しなのでそちらも合わせて読んでいただきたいと思います。
サイドの抜き差しには触れなかったのですが、興味がある方は前回のスプレッドシートをご覧になるか、Twitterで連絡をいただければ応えられる範囲でお答えしたいと思います。
それでは後編でまたお会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
