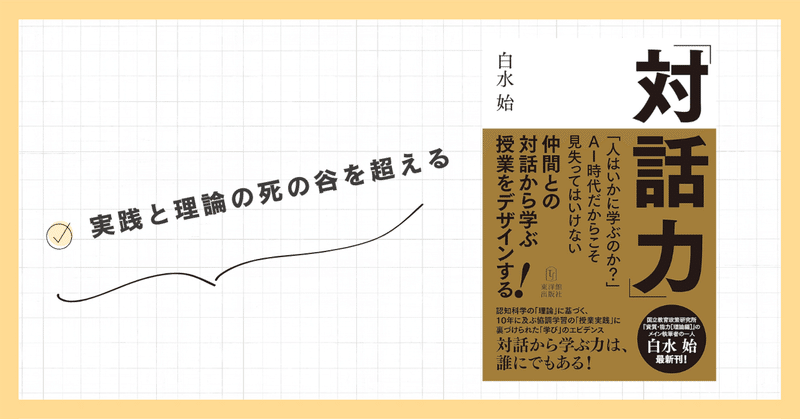
MBAで学ぶ理論を実践で役立てるための唯一の方法
こんにちは、秋山です。
今日は、積読解消シリーズです。残っていた「対話力」の後半をまとめていこうと思います!
さて、昨日XをみていたらMBA不要説をのツイートが流れてきました。引用元の動画では「MABを持っていても採用したパターンはあるが、MBAを持っているから採用したパターンはない」といったコメントがありました。
イーロン・マスクは候補者の中から「MBA」を意図的に "除外" しているらしい。その理由等をアメリカで26の会社を経営する起業家が語っています。これは個人的にもかなり共感できる。 pic.twitter.com/b4vfVpCqK8
— Brandon K. Hill | CEO of btrax 🇺🇸x🇯🇵/2 (@BrandonKHill) March 2, 2024
私も動画の内容は概ね賛成です。理論を頭に押しこんだだけでは、予測不能で一寸先は闇状態のリアルに対峙できるとは思いません。ですが、理論がまったく無意味だとも思いません。クルトレヴィンの言葉で「よい理論ほど実践的なものはない 」という一節があります。
良い理論ほど、現実の解像度をあげ、筋の良い打ち手を考えるサポートをしてくれます。ただし、理論を知った人はそれを世界の全てだと思い込み、あらゆる事象を理論で片付けようとしがちです。それが、理論と実践の間にある死の谷を作り出していると感じます。
実践と理論の架け橋
「対話力」の第4章には、この死の谷に橋をかける方法が紹介されています。その橋について解説する前に、実践と理論には即ちどんな違いがあるのかを触れておきます。
実践とは、経験から生まれた「経験則」「素朴理論」で成り立つ世界です。裏付けはなく、個人が経験する中で一定のパターンを見出し、経験のたびにパターンは強化または修正されていきます。本書の中では、ボールを蹴る幼児の例が紹介されていました。
自宅の居間で柔らかいボールを蹴って遊ぶ幼児は、これくらいの力加減で蹴るとこれくらい飛ぶんだな、という感覚を経験則で学んでいきます。さらに、屋外に出てボールを蹴ると居間で蹴る時に比べ、同じ距離飛ばすにはより強い力が必要なことを学びます。これが、経験則・持論の世界です。Xでいうところの、実践、リアルです。
さらに、この幼児が数年後小学校に入り物理を学ぶと、ものには「慣性の法則」が働き、力を加えると同じ方向に動き続ける、ことを学びました。これが理論の世界です。科学者が数十年、数百年かけて導き出した原理原則を情報として教師から教えられます。
しかしここで、理論が間違っていることに気が付きます。居間でも屋外でも、蹴ったボールは転がり続けるのではなく、いつの間にか止まっていました。慣性がはたらくのなら、一生動き続けるはずなのに….そこで幼児は自分の経験則と原理原則のズレを認識し、なぜだろうと考え、「摩擦」という理論を知ることになります。これこそが、理論と実践の間にある死の谷に橋をかける、方法です。
実践と理論、どちらか一方を正しいと思い込むのではなく「この状況でなぜ理論が当てはまらないのか、実は一部あてはまっているのか」と理論をつかって現実を眺めてみる。逆に、現実から新たな理論を考えてみる。これこそが、実践と理論に橋をかける方法です。
一人よりも複数人の方が橋をかけやすい
「対話力」の前半でも紹介した建設的相互作用(メインで問題に取り組む人と、アシストする人がいることでより本質的な課題解決や議論に発展すること)ですが、実践と理論を橋渡しする上でも大変役に立ちます。
一人で実践と理論を行き来するのではなく、誰かの経験を理論から紐解いてみたり、ある理論を自分の経験を踏まえて説明してみることで、実践と理論の間に丈夫な橋をかけることができ、忘れない知恵へと変換されていきます。
個人的感想
中原さんのブログに、対話力の挿絵と同じような図が載っていました。
こちらも、理論の抽象的な世界と実践の具体的な世界を対立構造として捉えるのではなく、間にブレンドされた世界があることを示しています(たぶんw)
理論を通して実践をみる、実践で理論を活用する。研究者と実務家が協働できる世界が一番ハッピーだなと思うのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
