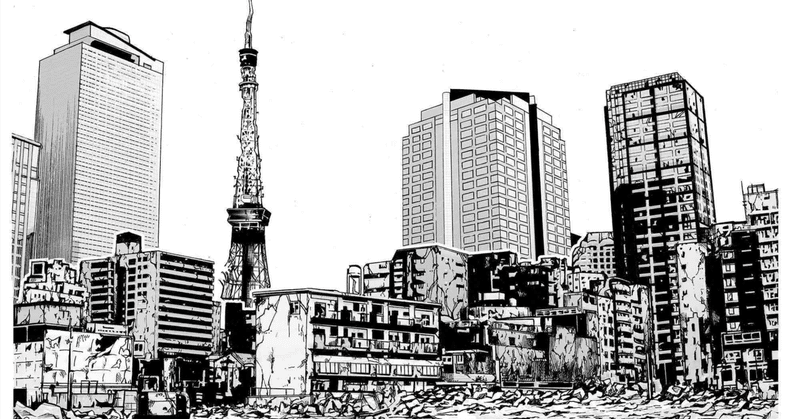
職場を越境する社会人学習のための理論的基盤の検討
こんにちは、秋山です。
今日は、ワークプレイスラーニング(以下、WPL)についての論文を読んでみました。
職場を越境する社会人学習のための理論的基盤の検討
― ワー クプ レイ ス ラーニ ング研究 の類 型化 と再考―
東京大学大学院情報学環 荒 木 淳 子
3行サマリー
これからは職場での有能な学習者=自らの学習ニーズを自発的に把握し、そのニーズに合うリソースを探し、自らの学習経験を組織化し、結果を評価することができる個人
WPLは職場での公開的な学習方法として注目されており、マネージャーのスキルの多くがインフォーマルなWPLによって獲得されている
WPLの4類型の中に越境学習があるが、越境する実践共同体への参加の実態を明らかにするようなものであり、仕事のための学習を効果的に行うためには、どのような介入が望まれるかという視点での研究は非常に少ない
WPLとは
WPLとは、「主に仕事での活動と文脈において生じる人間の変化と成長」と定義されます。
———Fenwick, T. 2001 Tides of Change: New themes and
questions in workplace learning. New Directions
for Adult and Continuing Educatkn. 92. 3-17.
さらに、WPLと業績との関係を強調する立場は、workPlace leaming&perfbrmanceと呼ばれる。研修等のフォーマルな学びか、教え合いといったインフォーマルな学びか問わずに、企業の経済活動に寄与することを重要視するのが、著者の立場です。それを踏まえて、以下の通りWPLを定義しています。
もの と見なす ことがで きる。従 って 本稿で は,WPLを,「 個人や組織 のパ フ ォーマ ンス を 改善する 目的で実施 され る学習その他 の介入 の統合的 な 方法」(中 原 ・荒木,2006;Rothwell&Sredl,2000)と 定 義する。
WPLをとりまく学習観
学習転移モデル
経験学習モデル
批判的学習モデル
正統的周辺参加モデル
WPLには、4つの学習観があります。
研修転移モデル
研修で習った知識を、現場で実行し、応用すること。
学習転移には、直属の上司や同僚のネットワークが有効であるとされています。
経験学習モデル
個人が自らの経験から独自の知見を紡ぎ出すこと。
批判的学習者モデル
学習者自身が、自分のあるべき姿を描くプロセスを重要視する。自分自身の状況を意識的に省察することを通じて、現状に対する問題視域を育むことを学習と捉えるモデル。
>>この論文では、経験学習と批判的学習者モデルをまとめて「経験による内省学習観」と呼ぶ。
内省 に よる学習 は,成 人教 育の分 野で も重視 され て いる(Cranton,1996;Mezirow,1991)。Mezirowは,経 験 に よる内省 を,(1)内 容の振 り返 り,(2)プ ロセスの振 り 返 り,(3)前 提の振 り返 りに分けている。そ して,個 人の 知覚,考 え,行 動やその効 果その ものに対する批判 的振 り返 りで ある 「前提 の振 り返 り」 を重要視 して い る (Mezirow,1991)。
正統的周辺参加モデル
学習を、個人の経験というよりも、ある社会的活動への参加と捉える。
>>この論文では、「参加学習観」と呼ぶ。社会的活動への参加を学習と捉える立場に、状況的学習論がある。
状況的学習論とは、学習者と周囲の人や道具、コンテクスト、環境との相互作用の中で行われる社会的活動として捉える。
「 認知的徒弟 制」 (Cognitive ApPrenticeship)と してモ デル化 した。認知 的徒 弟制 とは,熟 練 者が新 参者 に(1)仕事 をや ってみせ (modeling),(2)実 際 に教 え(coaching),(3)新 参者 が独 り立 ちで きるよ う助 け(scafolding),(4)次 第 に手 を引い てい く(fading)と い う一連の学習過程である。
Sfard(1998)は,共 同体へ の参加 を学習 と捉 える学 習観 を 「参加メ タファー」(participation metaphor)と 呼 び,従 来 の知識 獲 得 メ タフ ァー(acquisidon metaphor)と 対比 する(表1)。 参加メ タフ ァー では,学 習 とはある共 同体 に参加す ることであ り,学 び手 とは共同 体 に参加 し,共 同体の熟達者 とともに活動 し,対 話す る ことを通 じて学 んでい く。知る こととは,知 識 を持つ こ となのではな く,共 同体 に所属 し,参 加 し,そ こで他の メ ンバ ーとコミュニ ケーシ ョンを行 うことで ある

WPLの4類型
自分組織<>越境
経験学習<>参加型
で分類したのが、4つの類型です。

1.職場経験アプローチ
この領域の中でもいくつかに分けられる。
・経験から学ぶ個人の資質に着目したもの
・リーダーや熟達者の仕事経験に着目するもの
・経験から学ぶための組織的文脈によるもの
・職場での経験学習の支援に着目するもの
経験か ら学ぶ個 人の資 質につ いて,楠 見(1999)は, 社 会人 と大学生 に対す る調査 を行った。その結果,社 会 人の経、験か らの学習 を支 える態度 として 「挑戦性(責 任 や難易度 の高 い仕事 変化の大 きい職場 を好 む)」,「柔 軟性(新 しい考 え方や視点の切 り替 え,相 手 に応 じた対 処 をしようとす る)」 が重要 なことが明 らか となった。
Mitchen et al.(1999)は,「 計 画 され た偶 然 性 (plamed happenstance)」 理論 の中で 個人が遭遇す る 偶然 を活か しなが らキャリア発達 を遂 げてい くためのス キル として,(1)好 奇心:新 しい学習機 会を探索する こと, (2)粘り強 さ:失 敗 に挫 けず努力する こと,(3)柔 軟 性:態 度 と環境 を変えるこ と,(4)楽 観 性:新 しい機会 を可能で 到達 で きる ものだ とみなす こ と,(5)リ スク ・テ イキ ン グ:不 確実な結果 に直面 しても行動を とることを挙 げて い る。
資質 に着 目す る研究 に対 し,経 験 の 質や内容 に着 目 したのがMcCall(2002)で ある。McCallは,実 際の 企業経 営者に対す るイ ンタビューか ら,リ ーダーに必要 なスキルの形成を促す 「経験」が 変化 を生み出す仕事 や高 レベルの責任 を負 う仕事,タ スクフ ォース など 本 来の職務 ・役割 には規定 されていない非 公式 な活動であ ることを明 らかに した。
個人的感想
しか し,参 加 学習 アプ ローチ で は,学 習 が行 われ る 状況は分析で きて も,そ れ らの知見か ら,仕 事 を通 じて 個人が効果的 に学ぶために どのような学習環境 を整 えれ ば よいか という示唆 を得るこ とは難 しい(上 野 ・ソーヤ ー,2006)。 なぜ なら,参 加学習 アプローチでは,参 加 メンバーが そこで どの ような経験 をし,何 を学 んで いる かには,あ ま り注意が払 われないか らである。最近 は, 実践 共同体 にお ける個人の経験や学 びに着 目す る研究 も 行なわれているものの(Blaka & Fistad,2007),ご くわ ずかである。
以上の指摘にある通り、経験による内省学習観であれ参加学習観であれ、どんな経験がどんな学びを引き起こしているのか、を一番知りたい。
内省が大事というのはわかるが、どんなアサインメントをしてどんな葛藤を経れば、意図した学習を経験できるのか。ここがある程度カテゴライズできれば、それぞれのつまづきに応じてどんな仕事を割り振るべきか、どんな関わりをするべきか、自ずと見えてきそう。
まずは、Blaka, G. & Filstad, C. 2007 How does a newcomer construct identity? A socio-cultural approach to workplace learning. International Journal of Lifelong Education, 26, 59-73.を読んでみようと思います。
以上!
食中毒になったっぽくって、辛い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
