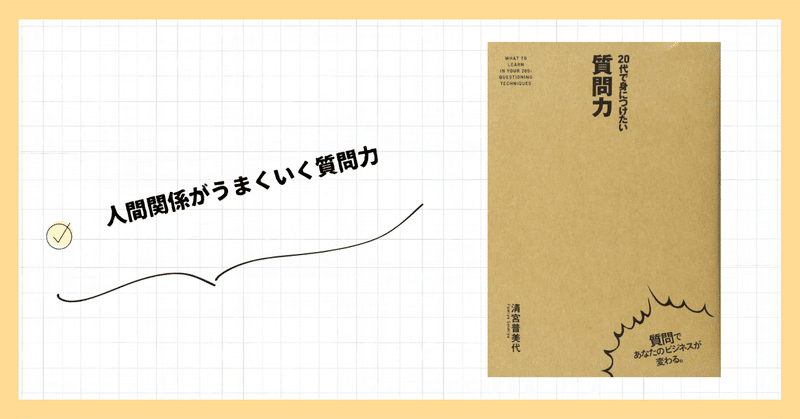
20代で身につけたい質問力
こんにちは、秋山です。
さて、今日は積読解消シリーズ。
今日の正解は明日の不正解。そんな今もとめられるのは、多くの知識よりも考える力です。そのスイッチをいれるのが、質問です。「〜か?」と問いかけられると人間の脳は作動せずに入られません。自分なりの答えを見つけ出します。
自分自身に質問すれば、思考力がアップ!
周りに質問すれば、考える機会を与え、気づきや新しい発想を促す!
そんなことを教えてくれるのが、マスター・オブクエスチョン清宮さんの著書「質問力」です。
質問の基本は、わからないことを聞くことですが、筆者は極めると4つの良いことがあると述べています。
人間関係がうまくいく
問題解決がうまくいく
人を動かすことができる
自己成長につながる
なんとも、全部魅力的なメリット!是非とも質問力を極めたいものです。
書籍自体は4章に分かれており、各章10前後のポイントが解説されています。今回は、各章で印象的だったものを、2-3絞って紹介していきます。それではいってみよう〜やってみよう〜
人間関係がうまくいく
質問は、相手への興味の表れです。効果的に質問すれば、相手に興味・好意があることが伝わり、人間関係が円滑になります。
🙄 今日研修で聞いたtipsで、上司が部下の強みに注目することが部下の生産性を最も高め、その次が弱み、最後が無関心だと言います。強みにも弱みにも着目しない、相手のパーソナリティを無視したコミュニケーションが、部下の生産性を下げるのです。逆に言えば、質問力をたかめ相手に興味があることが伝われば、部下の生産性もぐんぐんあがっていくでしょう!
力を与える質問をする
質問には「力を削ぐ質問」と「力を与える質問」があります。例えば「本当に大丈夫?」「ちゃんとやってる?」など相手を否定する、決めつけるような質問は、力を削ぐ方に当たります。
🙄ちゃんとやっていない、大丈夫ではない、ことを前提にコミュニケーションされたらそりゃ「うるせーな!」ってなりますね
同じことでも「何からだったら着手できそう?」「それをするにはどうしたらいいと思う?」といったできること、前に進めることを前提とした質問は、力を与える質問です。
💡力を与える質問をするには、自分の認識をフラットにすることがポイントです
沈黙を恐れない
質問して答えが返ってこないと、不安になってついついヒントを出したり、コメントを挟みたくなるものですが、相手はじっくり考えているだけかもしれません。
人は大きな決断をしたり、いい問いに応えるためには、時間がかかるものです。商談でも、沈黙が相手の決断を促す効果があります。沈黙は金、ですね。
問題解決がうまくいく
思い込みを打破する質問をする
多くの問題は、結果>原因>フレームワークの「結果」として現れます。例えば、結果=プロジェクトの遅延、原因=Aさんのプロセスで滞留が発生している、があるとします。シンプルな問題解決では、Aさんの滞留を解消すれば済みますが、そもそもAさんのところになぜ滞留が発生したのか、というフレームワーク・背景に疑問を持たなくては、また同じ問題が生じることになります。
このシンプルな問題解決をシングルループ学習、フレームワークまで踏み込んだ問題解決をダブルループ学習と言います。良い問いは、ダブルループを促す問いです。
レバレッジポイントを意識する
問題を繋げシステムのように繋げていくと、ボトルネックになっている部分、言い換えれば、解決することでレバレッジポイントになる部分が見えてきます。問題解決をスムーズに行うためには、このレバレッジポイントを抑えることが大切です。
レバレッジを可視化するためにも、質問を繰り返しもれなくシステム化・見える化することが必要です。
感情への質問がブレイクスルーを生み出す
論理<>感情、未来<>過去の2軸で4つの質問に分けることができます。会議や質問は論理的であれ、という思い込みが多いビジネス界ですが、実は感情を問うことで思わぬ促進力になることがあります。
たとえば、Aという商品がうれないときに「売っていて楽しい?」「いいえ楽しくないです」「どうしたら楽しくなるかな?」「Aが開発された意図を知らないので、意味もなく販売している感じがして楽しくないです。開発者のストーリーを聞いてみたいです」といったポジティブな議論に発展することがあります。
人を動かす
動かそうと思うと、人は動かない
人を動かしたければ、自分の頭を使って考えた意見を伝えるのではなく、相手に質問し自分自身で考えて導いた答えを持って動いてもらう、つまり本人の頭を動かしてもらうことが必要です。
例えば、Aさんの業務が遅延している時。「遅延しているよね?どうしたらおくれないの?」と質問のような意見の押し付けをするのではなく「何か問題は起きてる?どんな時におきてるの?」と本人が遅延を認識しているのかを確認し、本人から遅延の原因とネクストアクションが出てくるように問いかけることが適当です。
人間、自分の頭で考え、心から納得した時に、初めて自発的な行動を起こすものです。
されて嫌だった質問を思い出す
されて嫌だった質問を思い出し、力を与える質問に言い換える。このトレーニングの積み重ねが、つい考えたくなっちゃう・動きたくなっちゃう質問を生み出します。
嫌だった質問例 → 力を与える、気持ちの良い質問
どうしてできなかったの?>達成するには、何が必要?
どうしてやらないの?>どんなことから着手できそう?
やる気ないの?>何が妨げになってる?
誰が悪いの?>どんなサポートが必要?
〜すればいいと思ってない?>どうすればいいと思いますか?
自己成長につなげる
リフレクションを癖づける
一週間に一度や、プロジェクトの終わりに以下の質問を自分に投げかけてみましょう。リフレクションは、同じ失敗を回避したり、再現性もって成功パターンを繰り返すために必要なプロセスです。やらないと単純に成長スピードが落ちます。
①私はうまくやっているか?
②どうしたらもっとうまくやれるか?
③何を学んだか?
④何が今後に活かせるか?
質問日記をつける
多くの人が日記をつけたことがあるでしょう、そこにもう一工夫!質問形式で日記を書くと、思考のスイッチが入り、〇〇へいった、〇〇ができた、以上のリフレクションが可能となります。
個人的感想
自分はなぜこの本を読んだのか?(早速実践してみる
診断型コンサルテーション以外の武器が欲しいから。
コンサルタントとして、人事制度改革やリーダーシップ研修で介入する機会をもらっているが、いまいち彼・彼女たちを主役にできてない違和感がある。意見を吸い上げうまくまとめて、アプローチを提案し、クライアントがそれを選択していく。みたいな一辺倒な打ち手しかなくて、これでいいのか感が強くある。
コンサルとしてならそれでいいのかもしれないが、私はコンサルだけがしたいのではなく、組織の底力を上げるような関わりがしたいので、主役がクライアント組織になっていくための、質問力を高めたいと思っているのだと思う。
質問力あげるにはどうする?
その日の、よかった質問といまいちだった質問を2つ挙げて、リフレクションしてみる。なぜダメだったのか、なぜうまくいったのか自分の中のパターンを見つけて、しっくりくる落とし所を見つけたい。早速今日の日記から、質問を振り返ってみたいと思う。
以上!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
