
Vol.26「お葬式」
お葬式の歴史
人類はいつから「お葬式」をするようになったのか。
最古の「お葬式」と言われているのは、イラク北部のシャニダール洞窟遺跡にその跡が見られます。洞窟で見つかったネアンデルタール人の骨には埋葬された跡があり、たくさんの花粉や花弁が確認されました。死者のために花を供えたのか、それとも副葬品だったのか。このことを紹介したフランスの歴史学者フィリップ・アリエスは、著書の冒頭で次のように述べています。
かねてより信じられてきたように、人間はみずからが死にゆくことを知っている唯一の動物だ、ということは、確実ではありません。そのかわりたしかなことは、人間が死者を埋葬する唯一の動物だということです。
古墳時代が終焉したのは簡素化の影響だった
日本では旧石器時代(1万年〜3000年前)の遺跡から埋葬の跡が見つかっています。古墳時代(3〜7世紀)には権力者を埋葬する墳墓が巨大化します。現代にも残る古墳の数は全国で16万基以上といわれ、これは全国のコンビニ店舗数の約3倍にあたるそうです。
権力の象徴であった巨大古墳は『大化の改新』の時になくなります。葬儀や墳墓を縮小し、簡素化をはかる薄葬令(はくそうれい)が出されたためです。埋葬する場所(墓地)が制限され、副葬品も限定されました。これにより、古墳時代は終焉を迎えます。
火葬のはじまりと香典のはじまり
遺体を火葬した形跡は、縄文時代や弥生時代の遺跡からも確認されています。日本で初めて火葬されたと記録に残るのが、700年に亡くなった道昭という法相宗の僧侶です。仏教ではお釈迦様が火葬されたこともあって、火葬文化は仏教伝来とともに日本に伝わりました。703年には持統天皇が火葬されています。しかし、火葬はまだ一般的ではなく特権階級の間でのみ行われていました。庶民の墓は一定の場所に定められていて、そこに埋葬されていました。鎌倉幕府から遺体放置禁止令が出され、鎌倉仏教の布教活動とともに埋葬の習慣が少しづつ定着していきます。
室町時代の貴族や武士の葬儀の次第をまとめた書物には、北枕や入棺の儀式、喪服の裁縫や、棺は御車(牛車)に載せて火葬場まで運んだなどの風習が記されています。また、この頃から香典とみられる金銭のやり取りがあったと記録に残っています。
仏教葬儀が繁栄したのはキリスト教のおかげ
庶民の間に仏式の葬儀が広まったのは江戸時代に入ってからです。幕府はキリスト教を弾圧するために、いずれかの寺を菩提寺として登録する檀家制度を設けました。菩提寺が発行する寺請証文(てらうけしょうもん)はキリシタンから改宗したことを証明し、のちに旅行や就職の際に必要な身分証明書の代わりを果たしました。寺は信者家族の生死や婚姻を把握し、これが戸籍の元となりました。葬儀は菩提寺が執り行い、盆と彼岸の墓参りや追善回向が行事化したのもこの頃です。
パンデミックは繰り返される。
明治になって神仏分離令や戸籍法の制定により、檀家制度が意味をなくすものの葬式仏教は残りました。
明治28(1895)年にコレラが流行り、伝染病予防法が制定されて火葬が推奨されます。大正7(1918)年にパンデミック(感染爆発)を起こしたスペインかぜは全世界で6億人が感染し、5000万人が死亡。日本でも約40万人が死亡したとされています。結核も流行し、昭和10(1935)年からの15年間、死亡原因の1位となり「亡国病」と恐れられました。
戦争で亡くなった人に院号が多い理由。
太平洋戦争で亡くなった戦死者は「英霊」と称えられ、院号を授与するよう陸軍が仏教界に働きかけました。昭和39(1964)年には戦没者約68万人に対して叙位叙勲が行われ、この時に合わせて院号を下付したケースもあったようです。国のために若くして逝った「英霊」たちの親は、我が子より文字数が少なくならないよう戒名に高額なお金を払うことが一般化しました。
新生活運動と冠婚葬祭互助会
敗戦後、経済的に困窮していた社会の中で、冠婚葬祭を簡素化して費用を少なくする「新生活運動」が起こります。多くは廃れましたが、いまだに根強く残る地域もあり、祭壇価格の上限等、制限があるので注意が必要です。
葬儀と告別式を一時間で行うスタイルも戦後に確立しました。告別式用の装飾に組み立て式の祭壇がセット化され、販売されます。新生活運動を背景に、この祭壇や備品を加入者に安価な料金で提供する冠婚葬祭互助会が誕生します。
高度経済成長の祭壇文化の隆盛
高度経済成長からバブル期にかけて消費の高まりとともに、葬儀も華やかになります。豪華な祭壇を飾り、門前には樒や花輪を並べ、華やかに葬送を行いました。葬儀が社会儀礼と化し、企業の社員や取引先が総出で参列することもありました。不特定多数の会葬者に「お香典のお返しが大変だった」とおっしゃる方はこの時期に葬儀を経験された方かもしれません。町内会で受付や炊き出しの手伝いをし、町会長が葬儀委員長を務める。葬儀も派手になり、平成3年の葬儀の会葬者数は平均280人と最大になりました。
バブル崩壊後の葬儀の変化
バブル崩壊後、小規模で葬儀をあげたい場合に「密葬」という言葉を使うようになりました。平成8年に渥美清さんが「密葬」でされたことから広く認知されます。密葬とは本来、後日「本葬」や「お別れ会」を行うため近親者だけで葬儀を行うことを指しますが、家族で行う葬儀=「密葬」というイメージがつきます。
平成7年1月17日午前5時46分に発生した阪神・淡路大震災では、10日間で約4800体の遺体が火葬されたという記録が残っています。影響は大阪にもおよび、亡くなってから火葬まで10日ほどかかることもあったため、エンバーミングが普及しました。
平成8年に起こった堺市集団食中毒事件を機に、炊き出しが自粛されます。「隣組」と呼ばれた町内会は高齢化に伴いお互いに気を使うようになり、ご近所の力を借りずに家族だけで行う葬儀が増えます。自宅や近隣の寺、集会所を借りて行っていた葬儀場は、すべて整った葬儀専用式場を借りることが主流となります。
「家族葬」の時代
「家族葬」という言葉は、平成12(2000)年ごろから使われはじめたと言われています。家族葬は大衆に広く受け入れられ、葬儀の「個人化」「小型化」に拍車がかかります。「一日葬」や「火葬式」といった、よりコンパクトなスタイルの葬儀が登場しました。
そして未来はー。
内閣府の令和元年度版『高齢社会白書』によると、平成30(2018)年10月1日現在65歳以上人口は、3,558万人。総人口に占める65歳以上の人口の割合(高齢化率)は28.1%。高齢化率が21%を超えると「超高齢社会」と呼ばれますが、日本は平成19(2007)年に超高齢社会に突入しました。2023年には2人に1人が50歳以上、2065年には約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上になると予測されています。
ずいぶん未来の話ですが、
2065年、皆さんは何歳ですか?
その時の「お葬式」はどうなっていますか?
会場に幕を張り祭壇を組み、式場を設営する“職人”さんが中心だった「葬祭業」は、ここ数年で細やかな配慮を必要とする「葬祭サービス業」に変革を遂げました。
「葬祭サービス業」として何を提供するのか。
今日のお客様と明日のお客様は全然違います。
今日求められたものが明日も求められるとは限りません。
たいそうに言えば
「諸行無常」
世の中は常に変化します。
お客様も変わります。
お客様が求めるものも変わります。
「お葬式」はなくならない。
そんなことはありません。
焼くだけでいい。
それが「お葬式」と言えますか。
「お葬式」に遺族は何を求めているのでしょうか。
「お葬式」とは何なのでしょうか。
「ありがとう」と言ってもらえるように
「やってよかった」と言ってもらえるように
「またお願いね」と言ってもらえるように
「頼れるお葬式屋さん」を目指して
〜早い時期に小さな変化に気がつけば
やがて訪れる大きな変化にうまく対応できる〜
スペンサー・ジョンソン『チーズはどこへ消えた?』
このメルマガが、豆知識程度に役に立ったなら幸いです。
ご拝読ありがとうございました。
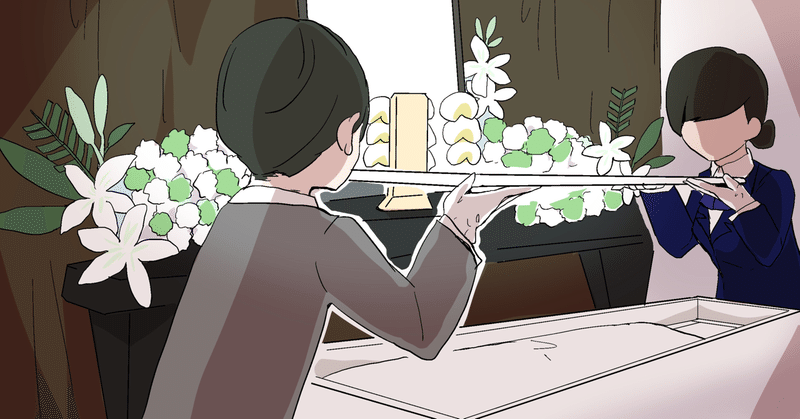
イラスト きむら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
