
◆読書日記.《土居健郎『精神分析』》
※本稿は某SNSに2020年6月30日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
土居健郎『精神分析』読了。
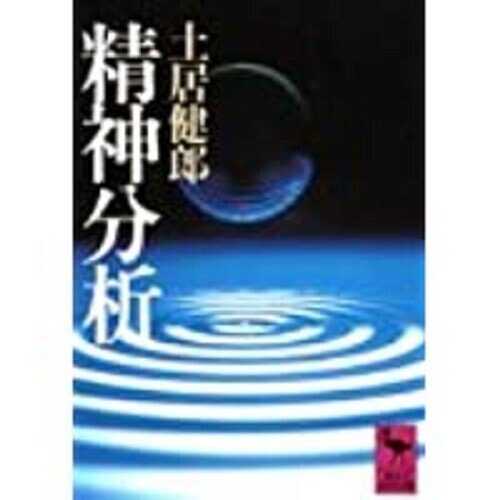
著者は、フロイトの下で直に精神分析を学んだ古沢平作博士の内弟子として正統派精神分析を学び、精神分析的日本人論『「甘え」の構造』によって海外にもその名を知られる精神科医。
その著者のデビュー作として精神分析の概要をまとめたのが本書というわけである。
◆◆◆
著者は本書で所謂古典的精神分析学の概要をメインに3部構成で精神分析の内容を解説している。
1)心理学としての精神分析
2)精神病理としての精神分析
3)精神分析と精神療法
以上のの三つである。このうち「1」と「2」については、フロイト理論の概要を敷衍しそれに対して著者が様々な批判的視点で解説をしている。
そして「3」については、「精神療法」としての精神分析を精神医療全体の中に位置づける内容となっている。
特に「2」と「3」はフロイトの正統的な古典的精神分析学の理論を踏まえて、それをさらに実践的な「医療」として解説している所が、今まで読んだ精神分析関連の本にはない部分であって興味深い内容であった。
という事で著者は終戦直後の日本で精神分析学研究の中核にいたメンバーとも言えるようで、その上実際に精神分析療法が盛んなアメリカで精神分析医療を学び、国際精神分析学会にも参加している超実践派の精神分析医であり、その著者が精神分析を学んでいる過程での疑問を露わに書いている所も本書の特徴と言えよう。
そういった経歴の著者が、精神分析学の基本的な知識を非常に丁寧に「日本語の表現に寄り添って」説明しているという特徴がある一方、著者自身が精神分析に抱いている疑問について、批判的アプローチによって吟味するという特徴をも持っている。
この著者の疑問が、ぼく自身、精神分析に対して疑問に思っていた部分にもリンクしてくるものがあったので、そういった批判的部分も含めて実にすっきりと精神分析学の概要についての考え方を整理する事ができた。
◆◆◆
フロイトの理論でも批判が多いのが「タナトス(死の本能)」だと言われているそうだ。
この点は特に、ぼく自身も疑問に思っていた所だったので「みんな疑問に思ってたんだ」と知れたのはありがたい所だった(笑)。
フロイト理論では、人間の情動には二種類あり、それが「生の本能」と「死の本能」だと言われている。
このフロイトの「生と死の本能」論というのは生物学の発想からヒントを得られたもののようで、そのために特に「死の本能」は生物学的な考え方に偏り過ぎているという印象があったのだ。
「死の本能」は通常「攻撃/破壊欲動」と説明されているが、フロイトはこの本能の正体を「自己破壊本能」と考えていた。
生物は自らの生を生き長らえさせようとする「生の本能」を持っている反面、最終的には自ら自然へと帰っていこう、即ち「最終的には個体の死を望んでいる」というのが「死の本能」の考え方であった。
つまり、フロイトからしてみれば人間でも生物でも「永遠に生きていよう」とは思っていないはずだと見ていたのだ。
人生とは、なかなか思う様にいかないものである。
個体としての人間は、厳しい自然環境に晒されているだけでなく、人間社会の中にあって常に厳しい競争にも晒されなければならない。
多くの他人と協調して生きていくという事は、自分が本当にしたいこと(本来的欲求)を実現する事もままならないという事なのだ。
絶対に病気にならないという事もなく、幾度となく事故や怪我で苦しい思いをしなければならない事もあるだろう。
人生とは、そういった厳しくも苦しい過程を過ごしていくという事で、それを未来永劫続けて行くなどとは想像もつかない苦痛に違いない、といった感じでフロイトは考えていたのである。
人間は誰しも「いつかは死にたい」と思っているはずだ、とフロイトは考えた。ただ「いまは、死にたくない」だけなのだ、と。
いつかは、自分の心の底から納得する死に方によって最期を迎えたいと思っているはずで、人生とは、その「自分の本当に納得する死に方」へ向かうための迂回路なのだと考えたのだ。
事実、フロイトの最期は「安楽死」という形で「自分で納得する死に方」を自ら選んでいる。
そういった「個体は最終的に自らの死を望んでいるものである」という捉え方が、フロイトの考えた「死の本能」の正体で、それが人間の情動の中で「攻撃/破壊欲動」として現れていると考えていたのである。
しかし、「自分で納得して死にたい」という本能が「攻撃/破壊欲動」というものに繋がるというのは、ぼくとしてはどうにもすんなり納得できなかったのである。
で、これはフロイト以後の様々な理論家が批判している部分でもあったようだ。これは、ぼくにとってもまさに「我が意を得たり」といった感じであった(笑)。
著者も次のように書いている。
「もし彼(フロイト)が、接触結合の欲求を代表する性本能に対して反発攻撃の欲求を代表する攻撃本能が存在するといっただけであるならば、問題はさしておこらなかっただろう。しかし「攻撃本能」を、本来的に自己破壊的な死の本能として理解したところに問題があるのである」
◆◆◆
このように本書では、フロイトが作り上げた古典的精神分析理論を丁寧に説明しながらも、その理論にべったりと寄り添うのではなく、その後のフロイト理論への批判的意見や、著者自身が感じていた疑問点などを開陳し、精神分析に対して突き放したような批判的アプローチをも試みている点が実に優れてると言えよう。
「だいたい、精神分析をやるということは精神分析を信ずるということではないのだ。なぜなら精神分析というものが本来一つの批判的方法だからである。であるから、既存の精神分析理論を鵜呑みにするより、それに批判的に対するほうが、より精神分析的であるとさえいえるほどである」とも著者は言っている。
これくらい精神分析について真摯に疑問を突き付けている著者であるからこそ、ぼく自身も以前は根強く抱いていた「精神分析学の科学性」への疑問というものにもしっかりとした言及がある。
果たして精神分析は科学的と言えるのか否か? これはヤスパースなどが精神分析をボロクソに批判する要の点でもある。
著者は「この問いに対して少なくとも現在のところは「否」と答えねばならない」としている。
何故なら現代の科学的吟味というものは「実験科学」をベースとして発展してきた経緯があり、実験的科学というのは「原則としてある現象に参与するすべての因子がコントロール可能でありかつ数量化されなければならない」からで、精神分析療法の基本的手法である「自由連想法」では、このような因子がコントロールできないからである。
何故かと言えばそもそも精神分析の扱う「無意識」というものが基本的にブラックボックス化しているものだからである。
このために現在の実証心理学などでは無意識は扱えないので「手を出さない」というスタンスを取る。
だが、実証実験的に扱う事の難しいものだからといって、それが「ない」と考えて無視するわけにもいかないのが現実の精神医療の現場なのである。
だからこそ精神分析療法の現場では「実験科学」的なアプローチは望むべくもないが、様々な仮説や理論的背景を踏まえてある種の基準をもって解釈を行っているのだ。
例えば著者が挙げているのがR・ダルビエにおける自由連想法の解釈基準であって、
1)喚起の基準
2)頻度の基準
3)類似の基準
4)集合の基準
5)立証の基準
の5点である。
但し、これによって完全に客観的な分析基準になるというわけではなく、その解釈の確度を上げるための基準でしかないのである。
つまり、無意識を扱う精神分析に、現代的な実験科学的な精密性を求めるのはどだい無理な話であって、その点で考えれば確かに精神分析は「科学ではない」と言えるだろう。
ただ、以前からぼくがフロイト理論に感じていたスタンスである「ガリレオ的(実証実験的)でなくアリストテレス的(観察/分析的)」だと言うのは半ば当たっていたようで、フロイトは大学在学中に薫陶を受けたフランツ・ブレンターノが再発見したアリストテレス思想について幾許かの影響を受けているようで、フロイトの著書の中には随所にアリストテレス的な考え方の影響を伺うことが出来るのだという。
(因みに、哲学者であり心理学者であるフランツ・ブレンターノは、フロイトだけでなくエトムント・フッサールにも多大な影響を与えていたようで、そういう影響関係から辿って行っても、精神分析理論と超越論的現象学の理論にはリンクする部分を見いだせそうな気もしている)
つまり、精神分析は「実験科学」的な科学性には疑問がつけられるものの、全くの非科学的な学問だとは言うことではなくて、むしろ方法論的には歴史科学や社会科学に近いのではないかというように言われているそうである。
だから(実験的な)科学ではないからといって、全くあてにならないものという事ではないのだ。
ぼくも以前から「精神分析は科学的ではない、という事は本当にあてになる理論なのだろうか?」という部分が強く疑問に思っていたので、この著者の意見を伺うことが出来て、長年の疑問に一応の決着をつける事ができた思いがした。
この点だけでも、本書を読んだ価値があったというものである。
◆◆◆
本書の後半では、より診療現場に近い「精神療法としての精神分析」について解説している。
これについても著者の批判的アプローチは一貫していて、精神分析療法は万能ではなくて、得意とする症状と適応できない症状とがある、という事も明確に指摘している。
精神分析学については現在、様々な学派に分かれているので、その学派間の違いによっても得意分野の差というのは存在しているのだが、基本的に精神分析は無意識を扱っており、そのため心因性の症状を対象としているという事。
つまりは神経症であれ精神病であれ、それが現実との軋轢を問題にしている場合は無効となる。
例えば、会社での過重労働によって心身共に疲弊した末での鬱病等は精神分析で扱う事はできない、という事だろう。
古典的精神分析学派の考え方では、現在問題となっている軋轢に関して、無意識に因を発するものを扱うのが精神分析の方法だと考えていいだろう。
つまりは現在の現実的な環境因子による精神的葛藤を対象としているのではなく、症状の原因が過去の環境因子によるものを対象としているのが古典的精神分析なのだという事である。
それが例えば「トラウマ」であったり「エディプス・コンプレックス」に因を発するものであったりするというわけである。
古典的精神分析療法がなぜ自由連想法を用いているのかと言えば、自由連想法によって患者の精神状態を一端幼児期(つまりは無意識)の状態まで退行させる事で、無意識における因子の解決を行うからである。
そして、更にこの方法に古典的精神分析療法の問題点も含まれていると言われている。
著者は、一般的な医療の理想として挙げられる条件として、
1)安全であること
2)短期間であること
3)経済的であること
の三点を挙げているのだが、精神分析療法についてはこの三点に抵触するものがあるのだという。
まず第一に精神分析の問題点は、かなりの長期間の治療期間が必要になるという点にある。
通常の精神分析療法に必要な期間は週に1時間以上のまとまった時間を数回、そしてそれを数年、長くて6年(!)という長期間、分析医との対話が必要になるのだそうだ。
これの問題は膨大な時間だけでなく、診療にかかる金額に関しても問題となる。患者は長期間に渡って継続的に診療費をかけねばならないのである。
しかも患者は、この療法によって自らの根幹に関わる無意識に抑圧していた欲望を分析医の前に曝け出して、その問題と真正面から向き合わなければならないという苦しい事態に追い込まれる事となるという。
精神分析療法とは、自分の無意識に対して外科手術を行うような苦痛を覚悟しなければならないのだそうだ。
斯様に精神分析療法というのは、患者としてはかなりリスキーな療法なのである。
「無意識」に関して精神医療には大いに貢献してはいるものの、診察の現場での精神分析療法がフロイト以後、なかなか発展していない理由と言うのが、どうもそういう所にありそうだ。
現在の精神医療が薬物療法と行動療法がメインになっているのもそういう事情があるのだろう。
◆◆◆
昨今の精神医療の主流である薬物療法は一回の診察でも短くて数分、長くても一時間以内には終わるし、一回の金額もさほどかかるわけではない。
しかし、そういった「効率的」な「三分診察」に問題がないわけではない。そういった大量の患者を効率よく捌いていくといった資本主義的なオートメーション医療にはそれなりの問題があるのだ。
薬物療法はとても「西洋医学的」であると思う。
薬物療法にある考え方というのは「精神病と言っても「精神」というのは、結局は脳の機能の一部なのだから、脳の異常を物理的に治療すればそれでいいのだ」といった新自由主義以降の世間の価値観である。問題解決の経済的効率化、単純化、といったものである。
この薬物療法の考え方はぼくが過去、何度か主張しているように「向精神薬によって"症状"自体は抑えられるかもしれないが、その症状を発症させるに至った"原因"が解決するわけではない」という問題を棚上げしてしまっているのである。
症状が抑えられたとしても、病因が取り除かれないので再発する可能性までは免れないのではないのか。
「西洋医学的」である薬物療法は、そういった複雑な人間精神を単純に「脳の物理的機能障害」として脳に還元してしまう。
効率的、物理的、還元主義的、数値還元的、エビデンス主義的……良くも悪くも、「科学的」な薬物療法にもそういう問題を孕んでいるのである。
精神病を発生させるものは何も物理的問題だけではなく、個人を取り巻く社会的問題であったり人間関係の問題であったり、またもや属人的内面的な問題であったりが複雑に絡んでくる多面的な要因をもっているのである。
現代の薬物療法の問題は、そういう精神病の複雑な要因が捉え難いからといって無かった事にして「物理的な脳機能の問題」に還元してしまうという点にある。
現代医療にはこういった問題を含んでいるからこそ「科学ではない」と言われながらも、現在に至るまで精神分析の知見が生き残っているのではなかろうか。
精神分析は既に科学界や思想界では「葬り去られた思想」だと言われているが、未だに精神分析学派は存在し、精神分析学派からの活発な言論が行われているのは何故なのか?
それは、現代大きな問題となっている精神病理の原因が、単なる「脳の機能的異常」の問題に還元しきれない問題を抱えているからに他ならないのではないのか。
そういった問題意識が、本書の最終章に紹介されている精神分析諸分派の学説にも現れている。
例えば「劣等感」という概念を有名にしたアドラー派は人間精神の社会性を重要視し、神経症の治療方針で重要なのは「個人をふたたび社会の一員とすること」だとした。
それに対してユング派は、患者の精神を癒すのに必要なのは、個人の人生観、宗教観であること――つまりは神経症の文化的/哲学的意義を重視したという。
また、ホルナイ派の考え方には社会批評の側面があって、患者の病因にどのような社会環境が影響しているかを理解する事でその調整を営むよう助ける事を目指した。
エーリッヒ・フロムのフロム学派も文化批評、文明批評、社会学批評の側面を持っている(マルクス的な疎外論の問題も絡んでくるかもしれない)。
このように見てみると、確かに精神分析学派は自然科学というよりかは、人文科学的な「厳密な数値には表せられない問題」に対して何とか切り込んで行こうという傾向があるのかもしれない。
そう考えると上述したように、精神分析学派は「方法論的には歴史科学や社会科学に近いのではないか」と言われるのも理解できる。
仕事のオートメーション化や効率化による自己疎外によって徐々に人生の意義を見失い、過重労働や先の見えない不景気の負担、そしてますます複雑化する人間関係の問題等を考えても、現代人にとって精神病の問題はますます重要性を増してくることはおそらく間違いないであろう。
そういう環境下にあって、ますます人間の価値を「数値」や「物理的なもの」に還元してしまう現代的医療に対抗する方法論として、「科学的ではない」という批判を浴びながらも、精神分析学派が生き続けてきた意義というものがあるのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
