
◆読書日記.《新宮一成『夢分析』》
※本稿は某SNSに2020年6月24日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
新宮一成『夢分析』読了。
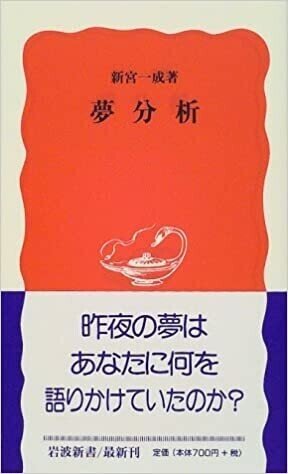
京大名誉教授にして精神科医、そしてラカン研究者である著者の代表的著作で、2000年にサントリー学芸賞を受賞した一冊。
本書ではそんな著名な精神分析家による夢の具体的分析方法とその機能について解説する。
ぼくの中で本書を読むに当たり、精神分析学派における『夢分析』の価値を計る指標を3つほど設定していた。
●1、フロイト『夢判断』は読むに値するか?
●2、夢分析は学ぶ値するだけの意義や価値があるか?
●3、現在の精神分析による夢分析の最新状況はどういった段階にあるか?
この3点である。
◆◆◆
正直、ぼくは精神分析学における夢分析にはこれまでかなり懐疑的だった。
まず第一に科学的なのかどうか?というのが疑問だった。
単なる解釈学であり、根拠が不明確なのではないのか?……解釈学であるにしても、その方法論が適切なものなのかどうか?……それが「夢」という不可解な現象の謎をどの程度解明できているのか?……解釈に恣意性は混じらないのか?
そのように、疑問点があまりに多いのだ。
「夢」については脳科学的にもまだ謎の部分が多い。
脳内の夢の活動領域をPETやfMRI等で観測する事は出来るだろうが、それが「何故"夢"を見るのか?」という疑問に直接対応できるような答えにはつながらない。
何故あのような不可解で非論理的な表象が内面で起こっているのか。
それに対する精神分析学派からのアプローチが、どれだけ有効な方法なのかというのが今までイマイチ確信できないでいた。
その疑問に対するフロイトの見解を知りたいと思っていたので、今回は本書の内容を踏まえたうえで、まず上述した指標の内の一つ目「フロイト『夢判断』は読むに値するか?」に対する疑問から考えて行こうと思う。
◆◆◆
フロイトの夢に関する学説は、フロイト自身が『夢判断』という著書を出版しているのでそれを読めば良いことなのだが、この本は上下巻2冊分もあってフロイトの著書の中でもダントツに長い論文なのだ。
積極的なモチベーションのないまま手を出そうとするには、ちょっと長すぎるのである。
という事でフロイトの『夢判断』は入手していはするものの、読むにあたっては躊躇していたのである。
という事で今回は、それよりかは手軽に手を出せる本書(新宮一成『夢分析』)の内容を見てフロイトの夢に関する学説の概要を理解して、その上で『夢判断』に手を出すかどうかを決めようと思ったのだ。
本書の著者はラカン研究者ではあるのものの、やはり「フロイトに還れ」と主張したラカン派であるだけにフロイトをちゃんと踏まえているらしく、幸い本書の見解の大部分はフロイト学説を下敷きに説明しているようであった。
本書を読んでいて最もありがたかったのは、夢に関する研究についても、フロイトはあくまで「神経症の治療の一環」として考えていたという事がわかったことだった。
つまりは、夢に関する学説も、他のフロイト学説と同じく「症例研究」であり、深層心理に関する「説明概念」であったという事だった。
フロイトは精神分析療法を行うにあたって自由連想法を採用していたのだが、患者が連想した事を語っていくとたびたび「夢の話」が出てきたのだそうだ。
「自由連想法」というのは、患者が頭に浮かんでくる想念を批判や否定する事なく自由に語り、思いのままに連想を働かせていく方法である。
自由連想法を行った際に連想されたイメージや言葉といったものに関して出てきた、昨晩の夢や、もっと前に見た夢の話など、夢の中に出てきたイメージが「なぜその時に連想されたのか」というのを、精神分析では重要視するのだという。
つまり、夢というのはその時の患者の精神状態や自分に対する態度や認識と、対応関係が成り立っているのだと。
ぼく的には夢が「無意識のもの」である事には概ね異論はない。
何しろ夢というのは、自分で見る/見ないを意識的に選択する事はできないし、見ている最中の夢の内容に関しても何らコントロールする事はできない。
自分の「意識」の力で左右する事が一切できない内面現象であるからこそ「無意識」の作用だと言える。
フロイト学説によれば「無意識」の領域の大半を占めるのは「快感原則」を司っている「エス」である。
という事は、フロイトとしては夢の作用というものを「エスの作用」であったと考えていたというのは自然な事なのかもしれない。「エス」には我々が幼い頃に持っていた認識や感覚というものが保管されている。
本書の著者は「夢を特徴づける性質は、夢が幼年期の記憶を再活性化させ、それを頼りにしながら、現在の思考を組み立てなおすということである」と書いている。
つまり「無意識」の領域である夢の世界は、まだリアルな世界の理屈が適応されていない幼年期の記憶や認識が幅を利かせているという事なのだろう。
そう考えると、夢の世界の混沌とした感じというものの正体の説明も何となくわかる気がしてくる。
おそらくその混沌感は、まだ何も知らない幼児期の視点から見た現実世界の分からなさを表しているという事なのだろうと思う。
フロイトのテーゼには「夢には覚醒時の精神活動が流れ込んでいる」というのがある。
夢というのは、そういった現在の精神活動と幼年期の記憶との対話の上で成り立っているのだ。
精神分析学では、どの学派も多かれ少なかれ夢には現在の当人の精神状態が組み込まれていると捉えている。
そのことがはっきりとは読み取りにくいのは、夢が「幼年期の認識」で成り立っているからだ、というのが、どうもフロイトの考え方だったらしい。
フロイトの考え方からすれば、幼年期の記憶や認識というものは、皆かなり似通った過程を通るという。それがつまりは、エディプス・コンプレックスを作り上げて崩壊するまでの子供の成長過程にあたるのだ、というのがフロイト学説の特徴的な考え方だ。
だから、人の夢に出て来る象徴的なエピソードというものにも、似通ったものが色々と出て来るのだと言うのがフロイトの主張らしい。
それがフロイトの主張する、いわゆる「類型夢」論である。
◆◆◆
フロイトは既に『夢判断』執筆時の段階で、人間が見る「様々な夢の類型」をカタログ化していたのだそうだ。
その「夢の類型」には、様々な幼児期の記憶や認識が紐づいているのだという。
例えば、という事で本書に上がっている「類型夢」が「空を飛ぶ夢」である。
「空を飛ぶ夢」というのはそのまんま字面のごとく、夢の中で自分が空を飛んでいる夢の事だ。
これはフロイトが『夢判断』をまとめた時期にはまだフロイトもこの夢の扱いを保留にしていたが、本書の著者に関しては、この夢は類型夢の中でも重要なものだとしている。
「空を飛ぶ夢」を見た時の、人の精神状態の特徴を著者は「新しい人生の段階にさしかかり、その段階にふさわしい言語活動に参入できるかどうかが不安になったとき」と説明している。
例えば、大学に進学してまだ間もない時期、新しい友人が出来て上手くやっていけるのかどうか、学業にはついていけるのかどうか、ちゃんと学費をきちんと払っていけるのかどうか……、例えば、新社会人になって、就職した会社で問題なくやっていけるかどうか、パワハラなど問題のある部署に配置されないかどうか……そういう不安な時などにこの夢を見るという。
こういう精神状態の時にこの夢は「かつて言葉を話せるようになったときの記憶が呼び戻される。そして、今度もまたうまく話せるようになるだろうと思えるようになるまで、夢は続けられる」のだそうだ。
つまり、夢は幼児期の成功体験の記憶を呼び戻し、現在の不安感を和らげて自信をもたせようと機能するのだという。
「空を飛ぶ夢」は、幼児期に「初めて言葉を喋って他者と意志疎通した成功体験」に紐づけられている。
それが何故「空を飛ぶ」という表象となって現れるのか?
著者によれば、幼児にとって「言語」は、自分の背丈よりも高い人間たち(=大人たち)が操る、自分には理解不能なコミュニケーションなのだという。
そんな幼児にとってみれば、自分の頭の上でやり取りされる「言語」を自分が習得するという事は「自分より上空でやり取りされていた価値観に追いつく」という認識となるのだそうだ。
つまり、その認識が幼児の中で「空中への上昇感覚」の観念連合が起こる由来となっているのだと。
フロイトは夢というのは本人の願望を充足させるために働く無意識の機能だと主張している。
子供の頃の夢というのはそういうものがストレートに表されていて、例えばケーキが食べたいのに両親がケーキを買ってくれなかった日の夜に、ケーキを食べる夢を見て夢の中だけで満足する、というような傾向が子供の夢にはあるのだそうだ。
それが大人になるにつれて意識の中に「現実原則」や「超自我」が組み込まれて行き、それがストレートな願望充足の夢の機能を歪ませる。
大人になると、無意識であり「エス」が幅を利かせている領域の「夢」に入る事で、かつての傍若無人だった頃の幼児期の記憶と認識を呼び覚ます。
そこで大人の精神は幼児期の記憶と対話を始める。
だからこそ夢の中では「幼児期の記憶と認識」に則った理屈でエピソードが展開し、現在の精神上の不安の解消や願望の充足を「エス」の仕事のやり方で行うのだという。
人間は「自分は何処から来て何処に行くのか?」と言ったような「自分のルーツ」に関する好奇心を満足させたいという願望を持っているのだそうだ。
著者は「フロイトが無意識の欲望と呼ぶのは、こうした問いへの答えを得ることである。すなわち我々は、自分で自分の生まれた時の姿を確認するのでなければ、どうしても気持ちがおさまらないという傾向をもっているのである。こうした欲望が自分の中にあることに、人はふつう気付かない。気づかないので、その欲望を軽く扱おうとする傾向がある。それに対し、その欲望は、夢の中で我々に向かって存在を主張してくるのである」と説明している。
夢の機能というのは、そういったように多かれ少なかれ「願望充足」のために働いているそうなのだ。
不安を解消したり、好奇心を満足させたりするのも、夢が行っている「願望充足」の仕事の内のひとつだというわけだ。
敷衍すれば、夢の機能と言うのは「幼児期の記憶や認識を使って、現在直面している願望を充足させる働き」なのだと言えるだろう。
これが本書で説明されている「夢の機能」である。
◆◆◆
さて、ここら辺でようやく一つ目の指標である「フロイト『夢判断』は読むに値するか?」には答えられそうだ。
このレベルで精神分析学の夢に関する学説の知識が手に入れば、フロイト『夢判断』を読む意義は限られてくる。この夢分析に関する学説が組み立てられてきたプロセスを学ぶという意義が出て来る。
これは夢や無意識の内容を分析する方法論を根底から学んでいくためには役に立つだろう。
また、それに加えてフロイトがカタログ化した「類型夢」を知る事もできるので「フロイト学説に従って見た夢を分析する」事も可能になるかもしれない。
だが、それでもまだ果たして夢分析を学ぶ意義があるのかどうかという疑問は残ってしまう。
つまりそれが二つ目の「夢分析は学ぶ値するだけの意義や価値があるか?」という指標の話となってくる。
本書で知った事の内で非常に重要だと思ったのは、フロイトの夢分析の方法はレヴィ=ストロースの神話分析に通じるものがあるという指摘だ。
高田明典『構造主義方法論入門』ではフロイトの無意識の理論もレヴィ=ストロースの神話分析の方法論と同じように構造主義的な手法を採用していると説明していた。
実際、フロイトとは別学派であるユング派も精神分析学の手法を応用して実際に神話分析や伝説や民話、昔話などの分析を行っている。
という事で考えれば応用範囲は広く適応できようであるようにも思える。
だが、それでも上述したように、まだぼくの中では「その解釈方法は恣意的なものなのではないか?」という疑念は捨てられずにある。
その疑念を持ったまま読むには、ちょっとフロイトの『夢判断』という本の分量は、多すぎるようにも思われて、そこが悩みどころでもある。
◆◆◆
最後に3つ目の指標「現在の精神分析による夢分析の最新状況はどういった段階にあるか?」だが、これについては本書はけっこう曖昧な所があったように思う。
本書の説明部分のどこがフロイトに準じていて、どこが最新の研究成果なのか、イマイチわかり辛い部分があった。
というのも、本書で実際に分析を試みている「サンプル夢」は、著者の研究室の学生が発表したものらしく、例えば学会ではどのような意見が出されているのか、他の学者の最新の研究ではどのような説が提唱されているのか、そういった言及がほぼなかったという点が惜しいという印象があったのだ。
3つ目の指標に関しては、ほぼ「著者の研究室内での研究事例」といった、どこか小ぢんまりとした範囲の研究成果しか提示されておらず、その点が不満の残る点ではあった。
が、そうは言うものの、本書の内容は精神分析学の夢に関する分析の方法論の一端をコンパクトに窺い知る事が出来、その点では大いに意義のある内容であったと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
