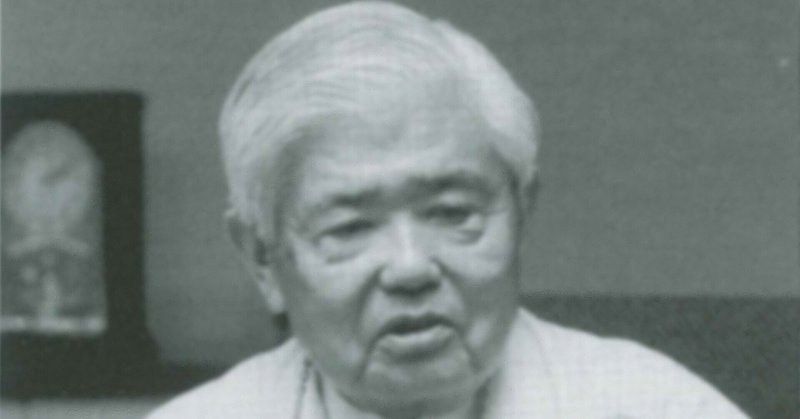
私の発言 晝馬 輝夫氏 光技術の行き着くところは,結局のところ健康問題だと思います。
浜松ホトニクス(株) 晝馬 輝夫
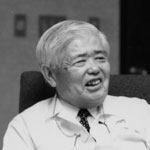
1926年生まれ。47年,浜松工業専門学校(現静岡大学工学部)機械科卒業。
53年,浜松テレビ株式会社設立と同時に取締役就任。64年,同社代表取締役専務就任。
78年,同社代表取締役社長就任(現任)。83年,浜松ホトニクス株式会社に社名変更,現在に至る。
84年,PhotonicsManagementCorp. (米国)社長就任。
90年,浜松商工会議所副会頭就任。91年,国立天文台評議員就任。
同年(財)しずおか産業創造機構理事就任。93年,光科学技術研究振興財団理事長就任。
94年,中国浙江大学教授就任。同年,(財)天文学振興財団理事就任。
96年,(株)磐田グランドホテル代表取締役会頭就任。98年,中国南開大学客員教授就任。
99年(株)光ケミカル研究所代表取締役社長就任。
2000年,(株)筑波研究コンソーシアム取締役社長就任。
01年,上海交通大学客員教授就任(現任)。02年,浜松医科大学運営諮問会議委員就任。
同年,日本経済団体連合会理事就任。同年,(財)浜松光医学財団理事就任。
1983年,第25回科学技術庁長官賞受賞。84年,紫綬褒章受章。
98年,浜松市市勢校了者として表彰。
カミオカンデ秘話
当時はまだ小さな会社でしたから,カミオカンデの話にしても私の決断でやったわけです。最近は,日常の注文をもらうというようなことには関与していませんが,あの当時は細かいことにまで口を出していました。
うちの会社は,人が知らないことやできないことをやれというのが方針なのです。ばかでかいことでなくていいから,これができるのは世界広しといえども俺しかいないとか,これを知っているのは俺だけだとかいうようなことをやりなさいと言っているのです。
そのような方針でやっていると,問題なのは,わけのわからないことをやったときに,これが果たして値打ちがあるのかないのかということなのです。そのようなときに社長や専務が良いと言ったとしておけば,うまく行かなかったときでも,まあなんとかなるかなということです。

しかし,おかしなもので長年やっていると「あの男がいいと言ったことは不思議と最後にはうまく行く」と,こういうふうになるのです。まあ,当たり前のものを当たり前に売るような話は私のところへはきませんがね。
それで,カミオカンデの話にしても,これまで8インチの光電子増倍管は作っていましたから,ガラス管を作ってくれれば20インチもなんとかなると思っていました。確かに,世界で初めて挑戦するわけですから開発にはいろいろと苦労しましたが,思ったよりもすんなりできてしまいました(写真1)。
どちらかというと,この時いちばんの大冒険は,お金をちゃんともらえるかどうかでした(笑)。小柴先生が,お金は絶対に作ってくるからということでやったわけですが,実は先生は,カミオカンデを造るのに国から予算をもらってやったのではなくて,いろいろなところからお金をかき集めてきて造ったのです。われわれとしては増倍管1個につき30万円は欲しかったのですが,先生にそんなことを言ってもだめだとわかっていましたから「できたら1個につき27万円は欲しい。まかり間違っても最低25万円は必要だ」と言ったのです。カミオカンデ用(写真2)には1200本の増倍管を作っていますから,1200 ナ 25万で3億円となります。ですから,そのくらいはくれと言ったのですが,もらったお金はその1割もなかった。そこがいちばん問題だった(笑)。

カミオカンデをいざ造るとなったら先生は「早く増倍管を作れ,作れ」とせかすのです(写真3)。それで,一生懸命1200本作ったのはいいのですが,穴を掘ったところでお金が尽きてしまったのです。しょうがないから,でき上がったものを工場の食堂に積んでおいたのですが,工場の方からは飯を食うのにも不便だから早く持って行ってくれと催促されるわけです。それで小柴先生に言いに行ったら「すまないけどお金ができないんだ」と言うのです。作ってしまった後にお金がないと言われても困ってしまうでしょう。といって,よそに持って行っても買ってくれるところはありはしませんからね。しょうがないから「じゃあ先生持ってけや」となったのです。ただし,3000万円で1200本を売るとなると1本2万5000円ぐらいの値段で納めなければなりませんから,その請求書だけは書きたくない。だから「100本分の請求書を書くからその分だけお金をくれればいい。残りははタダでくれてやるから持って行け」と言ったのです。今思えば,あの時「貸す」と言えばよかった(笑)。当時はそこまでの知恵はなかった。まあ,どっちみち小柴先生にはお金なんてありっこないんだから(笑)。
会社の成長とトヨタ自動車

われわれが事業を始めた頃は,光産業はまだ隅にいる脇役でしかありませんでした。ですから,浜松の田舎で職人を集めて好き勝手なことをやっていてもそれで良かったのです。しかし,光技術は昭和30年代の後半から徐々に時代の主役になっていきました。このような状況のなか,時代の流れに乗るには,やはり事業の拡大が必要になります。そこで,体力のある会社にしなければいかんということで,昭和59年に株式の店頭公開をしたのです。店頭公開するわけですから,当然,証券会社の方々が「主幹事は当社へお願いします」と何社も来られるわけです。当時私は,店頭公開のことをあまり知らなくて,来る会社来る会社に「はいよ」と返事をしておいたのです(笑)。これは後から知ったのですが,主幹事というのは株式の発行から売買まですべてを取り仕切る会社で1社だけなのです。この時は,いろいろな証券会社に「はいよ」と言ってましたから当然もめます(笑)。それで,実際に主幹事会社を決めるとなった時に各証券会社から「冗談じゃないよ」となったのです。そのときは,これはえらいことになったと思いました(笑)。なかには,「いまさら変なことをするなよ,いつも月夜の晩ばかりじゃないんだぜ」とすごんでいたのもいました(笑)。
そのようなことで困っていたのですが,当時トヨタ自動車の経理で大番頭をやっていた花井さんという方がいまして,その花井さんとは遠戚だった関係で,これは一つ相談してみるかということで相談に行ったのです。そうしたら「わかった」と言ってくれて,いろいろとしてくれたのです。どのようなことをしたのかわかりませんが,どこからも文句はこなくて,その時は「やはりトヨタ自動車の力というのは相当なものだ」と思って感謝したことがあります。
その後も花井さんにはいろいろとお世話になったのですが,ある時花井さんが「お前は店頭公開だなんて言っているけれど,いったいいくら欲しいのだ」と言うのです。当時の金額で「いや,せめて200億円もあればいいのだが」と答えると「なんだ子供の小遣いみたいだな」と言うわけですよ(笑)。トヨタの年間利益から見るとわずかなものですから。
それで,ああだこうだとやっているうちに,花井さんが「おまえ1回豊田英二さんに会え」と言うのです。12月のことでしたが,英二さんが海外に行くというので,その直前に東京本社に行って話をしたのです。その話のなかで,私は「うちの会社でやっていることは口ではなかなか説明しにくいから,豊田(愛知県)のほうにお帰りになるときにでも浜松に寄ってください」とお願いしたのです。そうしたら,確か1月の20日過ぎ頃だったと思うけれど,突然英二さんから電話がかかってきて「今から見に行くからな」と言われたのです。それで大あわてで,東名高速のインターまでお迎えに行き会社を案内したのです。

英二さんはあまりものを言わない人で,時々,にやにやっと笑っていたのを覚えています。それで,最後に研究所用に買ってあった土地に案内して「この土地を買ったのだけれども,建物を建てるお金がないんです」と言ったのです。でも出資してくれとは一言も言わなかった。
そのようなことがあってから2月の半ば過ぎになって突然連絡があったのです。第三者割り当て株の時価発行をしろと。トヨタで200万株を持ってやるというのです。それで,うちの経理がいそいでトヨタと交渉に行ったのです。そのおかげで中央研究所を建てることができました。
この時は条件がありまして,トヨタ側は経理経営にはいっさい口を出さないけれど,光技術で自動車に使えるものがあったらそのときは頼むぞというものでした。
スポーツホトニクス研究所
光技術の応用はいろいろ考えられますけれども,結局行き着くところは健康問題ではないかと思っています。それでは健康とはいったい何だろうかと考えて造ったのがスポーツホトニクス研究所なのです。

健康というテーマは決まったのですが,人間の健康とはどうやったらわかるのかという話から,ひょいと出てきたのがスポーツ選手なのです。スポーツ選手を計測すれば,ひょっとすると健康ということがわかるかもしれないということで,運動面から健康を研究する施設を造ることになったのです。
スポーツ選手を継続的に計測するとなるとやはり宿泊施設が必要となります。その時たまたま,静岡県にある磐田グランドホテルのめんどうを見ないかという話があって,ちょうどホテル内に空いている土地もあるということで,そこを借りることになったのです。
そうしたら,今度は磐田にはジュビロ磐田というサッカーのJリーグチームがあるわなという話になって,ジュビロ磐田の社長に「選手強化の測定をしてやるよ」と言ったら「お金がない」と言うのです。「お金はないけれども,浜ホトがスポンサーになって広告宣伝のボードを出してくれればその分を測定にまわせる」というのです。
それで測定することになったのですが,測定を開始したその年の前半戦でなんとジュビロ磐田は優勝したのです。それ見ろという話になったのだけれども,後半戦は負けてしまったのです。それで聞いてみると,前半戦で優勝したものだから,そんな測定はしなくてもいいから,もっと働けということで手を抜いていたのです(笑)。そのことを散々言ったら,「申しわけない,今度からちゃんとやる」ということで2002年は前半戦,後半戦ともジュビロ磐田が優勝しました。
こういったスポーツ選手以外にも一般の人を測ってみると,スポーツをやっている人とやっていない人の差は,その違いが歴然としています。例えば,同じ年寄りにしてもスポーツをしていない人は筋肉が脂だらけなのです。それでは歩けなくなって当たり前です。そのようなことが見えてくると「さあそれをどうしようか」ということで今考えています。
PETの開発

これまで話したことは,運動といった面から見た健康についてですが,それ以外にもPET(Positron Emission Tomography)と呼ばれる装置(写真4)を使って,ガンや痴呆症の早期発見をする研究をやっています。この研究は浜松市の医療センターとも提携しています。
ガンなどは種類にもよりますが,早期発見して治療ができれば大半は簡単になおってしまうのです。痴呆症の方を完全になおすことは,現在はまだ不可能ですが,早い段階でわかれば進行を止めることはできます。それに,病気の状態を詳しく測定することができれば治療薬だって作ることは可能だと思います。
このようにして,ボケない,ガンにならないということになれば,現在赤字になっている健康保険や年金を黒字にできるのではないかと思っています。それで黒字になれば,「儲けを半分よこせ」と言っても文句はあるまいと言っています(笑)。
従来のPETというのは,朝から晩まで1日中測定しっぱなしでも6人測るのが限界なのですが,うちで開発している装置は新しいディテクターを使っており,1日30人ぐらいは測定ができます。実際問題として,浜松地域だけで120万人の人間がいますから,最低でもそのくらいのペースで測定できなければ実用的ではありません。
ただ,誰も彼も放射性物質を注射してPETにかけるというのは乱暴すぎますから,予備検査などである程度対象者を絞るスクリーニング手法も開発しています。
この方法を使って,最初に社員のなかの希望者を300人ほど検査したら,これはあやしいという人間を30人ぐらい見つけたのです。この30人を実際にPETにかけたら3人に早期のガンが見つかりました。そこで,この3人のガンを完全に治療したのです。
これまでのいろいろな測定結果から,全体数の1%の人にガンがあることがわかっていますから,あやしいと思われる人をスクリーニングで2%ぐらいに絞ってやれば検査も効率よくできます。例えば,測定者が100万人いたとしたら,あやしい2万人を1日30人ずつPETにかけるようにすれば装置が2台あればなんとかなるかなと思っています。
この計画は,現在財団を設立し,検診センターを建てるということで進んでいます。実際に建物も今年3月ごろには完成する予定で,夏頃から測定を開始します。
私が,医療分野で光技術の応用を考えている理由の1つには,「死ぬまでボケないで健康に働く」という思いがあります。というのも,そのような社会にしないと医療費で国の財政がパンクしてしまうからです。今でさえ30兆円もかかっている医療費が15年もたつと60兆円になるというのです。それで政府は医療費の負担増とか言っているわけですが,病人から銭をふんだくってもしょうがありません。その上,介護保険だとか何だとか言ってるでしょう。これでは若い人はやってられないということになってしまう。そこのところを何とかする必要があると思うのです。
米作りと高出力半導体レーザー
日本の国内産業の発展における課題には,人件費の他にもエネルギーのコストが外国に比べてえらく高いということがあります。われわれは,大阪大学でやっているレーザー核融合研究にも協力しているのですが,国はエネルギー問題にもっと真剣に取り組む必要があるのではないかと感じます。
レーザー核融合の研究では,ストリークカメラをはじめとしていろいろな装置を開発しましたが,このレーザー核融合研究センター初代所長の山中千代衛先生も小柴先生に輪をかけたような先生でした(笑)。例えば,何か装置を作れと言われて,作って持って行くわけです。持って行くと,これでいいとは言わないのだけれど「持って来たか」となるわけです。それでお金を貰う段になると「お前高い,半分にまけろ」と言うのです。もう使っているのを半値にしろと言うのです。要するに,メーカーというのは,だいたい原価の倍で持ってくるものだと敵はちゃんと知っているのです(笑)。だから,それで儲かったことはないのだけれども新しいことはいろいろとやらされました。
実は,このいろいろとやらされたなかに,現在開発中の高出力半導体レーザーもあります。まだ研究室的に作製できた段階ではありますが,1~2年もすれば生産技術が確立できるところにはきています。
それで,この高出力半導体レーザーが数年前にできたときに,さて何をしようかと考えて,ふと思いついたのが1994年にあった米騒動です。考えてみたら,米作りなどの農業は産業とはいえません。お天道様しだいで生産量が変わるようでは産業とはとてもいえないのです。それなら,この半導体レーザーを使って米作りを産業にしてやろうじゃないかと考えたのです。それで,半導体レーザーを使って試験的に米を育ててみたら,なんと70日で米が収穫できたのです。70日だと単純計算で年5回米が獲れることになります。
それで,前会長の三輪大作さんが亡くなったときに,三輪さんの遺言は「葬式はまかりならん,偲ぶ会ならいい」というものだったので,「三輪さんが米を作った。だからこれは酒を造って俺に偲ぶ会をやれ」ということだなと思って,山田錦という酒米を半導体レーザーで作ってお酒を造ったのです。
開発スタッフは非常に苦労したみたいですけれども,なんとか無事できて,このあいだ,その酒をみんなに飲んでもらったのです。たくさんはできなかったのですが,大変おいしいお酒ができました。私も実際飲んでみて,これはうまいと思った。
農林水産省の技術の親方で,私が半導体レーザーで米をつくると言ったら「藁ならできるかもしれないが,米はできないよ」と言った方がいました。その人に「米ができたよ」と言ったら「なぜできたのか」と聞くので「それを見つけるのが農水省の仕事だ」と答えたのだけれども,その人にも飲んでもらったら「シャープだ,こんなうまい酒は飲んだことがない」と言ってました(笑)。
しかし,このお酒の原価計算をしてみると,直接材料のコストだけで,なんと1升30万円もかかっているのです。おいしいはずですよ(笑)。
といっても,50m2の試験場で作ったのですからしょうがありませんが。しかし,これを何町歩という田んぼでやり,コントロールもきちんとして,電気もむやみに使わないでやれば何とか安くできると思うのです。
それにプラスして,レーザー核融合による発電を実用化し,電気代をキロワットアワー3円50銭ぐらいにできれば,もっと安くすることができると思います。阪大の先生に言わせると「それは無理だ,8円だ」と言うのですが,私は「8円になるなら工業生産だから3円50銭ぐらいにはすぐなる。そんなことは大学の先生が心配せんでもいい」と言っています。
科学とサイエンス
私がつねづね言っていることは,科学とサイエンスは違うということです。
エンサイクロペディア・ブリタニカでは,サイエンスは「芸術,宗教又は哲学の如く,絶対真理を求める人の心の動き」とあります。つまりサイエンスと科学は同列ではなく,サイエンスの結果生まれた色々な知識を,科目別に分類したのが科学というのではないかと,私は言っているのです。
日本は開国して以来,知識,技術を一生懸命欧米先進国から教わってきました。しかしそれは,欧米から切り花を買ってきて,きれいだと喜んでいるようなものです。そこには,花はどのようにできたのか,また,実はどのようにしたらできるのかという,根っこにあたるサイエンスがないのです。このサイエンスを輸入してこなかったことが今の日本の産業の閉塞感につながっているのです。
サイエンスをやるというのは,ある意味宗教的なところもあります。つまり,ただひたすら信じるとか,祈るというような部分でです。例えば“真理の追求”といったことや職人の“カン”などがそれに近いかもしれません。職人のカンなどは“暗黙知”ともいえますが,今の日本の教育現場ではそのようなことを教えはしません。これはGHQによって憲法第20条ができたからです。しかし一方で,われわれ企業のほうは,暗黙知をみんな持っているのです。企業というのはどこも暗黙知を必ず持っているはずですから,それが自分の会社の宝だと気付けば,日本もまだまだ捨てたものではありません。
ただ1つ危惧するのは,現代の日本人には,良い意味で「無心に信ずる」とか「祈る」という心が無くなっていますから,サイエンスなどの奥深いところをやるには,これから大きな意識の変化が必要になります。それにはまず,国民一人ひとりが人類には知らないことできないことがいっぱいあるのだということを認識しなくてはなりません。そして,毎日の仕事を素朴な疑問をもって,全身全霊の力をこめて未知未踏を追求すれば,この閉塞感を打開するだけでなく,日本独自の新しい産業を創出できると信じます。
(O plus E 「私の発言」2003年2月号, 140~145ページ掲載。
ご所属などは掲載当時の情報です)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
