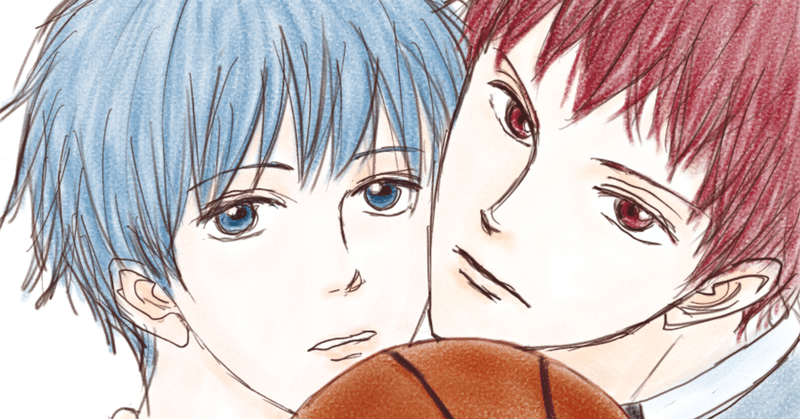
眠れないとき・ニ
黒子は自転車に乗っていた。風の気持ちよい日だった。
五月の風は自分には優しい気がする。黒子は頬を撫でる風に神経を研ぎ澄ます。
誰かに頬に触れられるよりも、こうした何気ない感覚が好きだった。曖昧で、確証など要らない自分だけのもの。人に説明する必要の無い大事な何か。世界に在って、祝福されていると実感できる言葉には出来ない想い。
仲間ありきではあるが、バスケはそれにちょっとだけ似ている。
赤司に自分の心を晒す真似をした事を後悔したが、どうせロクに憶えてやしないだろうと、並木道を過ぎた辺りで自転車を止めた。
彼が働く、近代的且つ豪華な建物が、道路を挟んだビル街から見えたからだ。自転車なんておよそ似合わない、高価なスーツに身を包んだ人たちの居る所。
少しだけ近くに乗り付け、道路の反対側からビルを眺めていた。
そのビルの玄関らしき大きなガラス張りの扉から、赤司が部下や同僚らしい人間を伴って現れた。
趣味がよく、瀟洒なスーツに身を包んだ赤司は、普段の鋭利な仮面を隠していた。
営業用ではあるだろうが、柔らかい面持ちで会話をし、誰が見ても御手本みたいな社会人と思うだろうと黒子は思った。自分とは間逆の人間だと改めて自覚した。あの様な笑顔は決して出来ないだろうと思った。
なんだって僕はこんな場所に来てしまったのか。黒子は自転車のハンドルを強く握る。赤司の顔なんてちっとも見たくなかったというのに。足を漕ぐに任せていただけだったというのに。自分から『しばらく連絡しないで下さい』と言った癖に。
面倒くさい、本当に赤司は面倒な人間なのだ、と黒子は道路を隔てた所から見える遠い横顔を睨み付けた。赤司を無視できない、面倒な自分にとてつもなく腹が立った。
途端、まるで判っていたみたいに赤司が黒子を見た。道路も、ビルも、仕切られた離れた空間を無いものみたいに、ここに、この瞬間に、黒子が自分を見ていることを知っていたみたいに、赤司の目は視線を彷徨わせる事無く、黒子を捉えた。
真田正一がこのところ考えてしまうのは冒涜というものについてだった。世の中には数え切れない程、数多の冒涜が存在する。人の尊厳を踏みにじる、歴史がそれを残すにしろなき物にしたにしろ、絶えた事の無い、人の持つ悪しき性(さが)だ。
冷酒を少しずつ味わっていた。嘗めるように。愛しむように。だが、調子のよい酔っ払いの手によって、静止する間も無く、安酒の熱燗をそれに注がれた。仕組んだ風にも思えるくらいの不味い温度、そして燗冷ましを飲んだ様な酷い後味になっている事だろう。
彼にとってだけでは無く、それは、日本酒に対する冒涜だった。
真田は、職場の飲み会の席で一人怒りに震えていた。無礼講などというレベルでは無い。ネクタイを頭に巻き、上司の席に酌に跳ね回るといった真似ならば許容範囲だ。視界から消し、飛んできた際には適当に流せばいいのだ。
しかし、一杯だけなら明日の仕事にも響かないだろう。そう思って味わっていた辛口大吟醸に、どうでもいい温い酒を混ぜられた日には勘弁ならない。
「…きみは、なんてことを」
わななく唇で、真田は部下を睨みつける。悪意が無いからと云って赦せる筈は無い。恣意的な悪意と、過失によるものとでは、受けた側が悪意と捉えればそれは同じでしかない。
三ヶ月ぶりの日本酒だった。半分も口にしておらず、真田は悪意についても熟考せざるを得なかった。
「へ?」
若い男は赤らんだ阿呆面を晒し、「ビールがよかったっすか?」と、真田に視線を合わせた。
にきび痕の残る、その顔面にぶっかけてやろうかと無意識に手が動いたが、「いや、きみが飲みたまえよ」と、突っ返すだけにとどめた。「僕はそろそろ失礼するから」
物腰の柔らかい、けれども冷静なハンサムというのが真田の職場での評判だった。それを損なうのはプラスでは無いという計算が瞬時に働いた。
「まだ一次会ですよ、補佐?宴はこれからですよー」
隣に陣取った女子社員が、てらてらと光る口元を笑みで象る。
馬鹿な男を庇ったわけではなく、その女子社員は何かと真田にアプローチをしてきていた女だった。婚期が近い所為もあったかもしれない。甘ったれた声音だった。
てんぷらの食べ過ぎにも見える、胃がもたれそうな唇から目を逸らすと、彼女の卓の前には確かに手のつけた茄子の揚げだしの器があった。
「大事な人を待たせているんでね、悪いけど」
真田は独身で三十歳になったばかりであり、もちろん離婚暦も無かった。
「えー!いい人がいたんすか、やっぱりー!」
「じゃあお先に」
お調子者の部下ににこりと片眉を上げて見せ、きびきびした態度で店を後にする。
帰宅し、真田は事の顛末を語った。
「だからさ、秘蔵のやつ。そうそう十四代。今日だけ一杯飲ませてよ、母さん」
渋る母親に拝み手をしてねだる。
「正ちゃんたら、いつまでも我儘ねえ。一杯だけよ?絶対よ?」
「わかってるよ。僕は約束はいつだって守るじゃないか」
「ふふ、そうだったわね」
真田正一は、幸せだった。
世間体もあるし、将来的には母に似た嫁を貰うのも悪くない、と時折は考えた。だが、彼にとって母以上の女など居る訳もなかった。
夫を亡くし、細腕で苦労しながらも一人で自分を育ててくれた母。彼女と共に暮らし、一生独身なのもまた一つの生き方であると胸を張るのだった。
自分をマザコンと呼ぶ者は、母を冒涜する言葉であると。
最高の女と暮らす事に、なんの後ろめたさがあるのだろうかと。性処理などは、風俗やら自慰で事足りる。
そんな真田に転機が訪れた。
営業先の社員、どうやら系列の財閥本社の幹部候補らしいーーーに一目惚れしたのだ。
表現として使い古されてはいるが、雷に打たれた様に、というのが最も適した心情だった。
柔らかな女では無い。おそらく、二十代の半ば過ぎにはなっているだろうと、凛々しい佇まいと、時折垣間見える貫禄を見て取る。
それは、どこから見ても完璧な美男子だった。
ほほ笑む口元は薔薇の蕾の如く。細い鼻梁は、天使が指で摘まんだような繊細さ。そして、椿の様な見事な色彩の艶やかな髪。
「ーーあの!この資料のご確認をお願い致します。」
通され、座る席近く、彼が通りかかった契機を真田は見逃さなかった。
彼に声をかけたい。四十分間の懊悩が実を結んだ。 立ち上がり、彼の手に封筒を押し付ける。
一瞬、驚きの表情を見せたが、すぐに頷いた。
そんな彼を追い、半ば無理やりに共にエレベーターに乗り込んだ。さっと、名刺を差しだす。
然程広い空間では無い。静かに、そして幾分厳かに、降下する機械音がする。本来の担当が追いかけて来ていたようだが、奴の戸惑いなど真田にはどうでもいい。
肩を叩いて彼を呼ぶ様な野暮はしたくはなかったし、別の社員が、「こちらの担当は彼ではありませんが?」とにこやかに口でも挟もうものなら、その者に殺意さえ抱く己がいると自己分析していた。
「ああ、B社の担当の方ですね。確かにお受け取りました」
微笑んだ顔のまま、彼は名刺を確認し、真田を見る。 彼の名刺は渡されなかったが、そんな事は些末時だ。
その赤色の瞳ーーそう、髪色と同じなのだーーは、光の屈折によって琥珀色にさえ見えた。切れ長の目元には確かな知性が宿っていた。そして、強い情熱みたいなものも、おそらく。
その場で抱きしめられたらどんなに幸せだろう、真田は深く息を吐き出した。
上役であろう、隣に立つ白髪の見事な老人と視線が交差した。疚しさを気取られたか、と咳ばらいをした真田だったが、それは勘違いであると直ぐに気付いた。
チン、という音と共に地上に辿り着く。
「赤司君?」
エレベーターを出て、ロビーを抜けて直ぐだった。白髪の男が戸惑った声を漏らす。
彼は他所を見ていた。時間が止まった様に微動だにせず、呼吸さえも忘れたかの様に。
驚いた上役が、足を止め、彼に呼びかけたのだ。
『赤司君』それが彼の名前であるのは間違い無かった。尋常な事態では無い事も予測できた。
彼の視界に映っているのは一体何なのか。真田は焦燥にも似た思いで、その向かう視線を追いかけた。
『それ』を自分の目で見る為に。
真田は、其処に向けられる、赤司の一直線上の視線をなぞった。
『それ』は自転車に跨った一人の男だった。極めて目立たなく、何度かその存在を確認した程だった。
水色の髪が風に揺れている。細身のジーンズを穿き、無地のブラウスを着た痩せた地味な男だった。どこにでも居るであろう、会った次の瞬間には顔さえ覚えていないような、風で吹き飛ぶように儚げな、多分は、凡庸な男だった。
凍ったように動かないその男は、こちらを、正確には赤司だけを見ていた。
二人の視線の交わりには何の意味があるのか。身動きが取れない程の奇跡の邂逅だとでも云うのだろうか。感動の再会でもしたと云うのだろうか。
真田は未だ固まっている赤司をちらと覗い、真横に寄った。できればその場を去りたくは無かった。
胸ポケットから小さな手鏡を取り出し、鏡の中の自分の顔を確認する。普段の顔つきより明らかに生気が漲っている。
「どうして僕じゃあないんだ」低く呟いた。
赤司の熱を帯びた瞳の中には、自分こそが居るべきだと真田は感じた。あの二人の関係などどうでもいい。自転車の男など誰だっていいのだ。
確かなのは、この自分が、初めて会った彼をとてつもなく欲しているという事だ。彼以外に、誰かにこれほど心惹かれる自分など想像すら出来ない。
我に帰った真田は、傍に既に赤司が居ない事に気づいた。
自分を置いていった彼に切なさが増した。
そして、自分を怪しげに見る白髪男に血へどを吐かせたくなった。
更には、直ぐさまにでも彼を追い掛けようという衝動を抑えてしまう自分に、とてつもなく苛立った。
「黒子、仕事中に何の用だい?まさか、わざわざ睨みつけに来たわけじゃないだろうね」
赤司は己の毒舌に辟易した。けれども、唇は勝手に動くのだ。
「上に後でどやされるのは俺なんだ。たかが系列会社だけどね、これでも高給取りなんだよ」
「…すぐに気づきましたね」
黒子は自転車から降りようともせず、赤司の言葉が耳に入っていないとでも云うように珍しく微笑んだ。
「は?」
「赤司君、僕がここに居ることを知ってたみたいに、こっち見ましたよね」
その言葉に赤司はかぁっと全身が熱くなった。自分が火箸にでもなったんじゃないかと思うくらいの熱さだった。
「それが、何だい。たまたまだろう。しかも、黒子。地味過ぎて、お前は自分が思っているよりずっと目立つ」
誤魔化すように饒舌になり、逃げるように歩きだした。行くべき方向では無かったが構わなかった。その後を、自転車から降り、手でそれを押す黒子がついてくる。
黒子の気配を、存在を、背中の全部で感じ取りながら、赤司は平静さを取り戻そうと何度も深呼吸を繰り返していた。
「僕、思い出したんです。色んな事」
その言葉に赤司は振り返る。
静かな、蒼い瞳で自分を見据える黒子が居る。
「赤司君が僕をからかったりした事は沢山あった。でも、そこに悪意みたいなものは全く無かった。そう、昔から」
「....それで?」
黒子は戸惑いながらも言う。
「僕にとって、赤司君は誰とも違う存在だっていう事を伝えたかった」
「人として?それとも、恋愛対象としても俺を受け入れるという意味で?」
「…それは、…前者の意味合いしかないと思いますけど」
俯く黒子は青ざめていた。自分が置かれた立場を初めて思い出したみたいに。
『こいつは結局、何も、わかろうとはしない』
赤司は呪文のように繰り返した。馬鹿な期待を持たずによかったと苦笑した。
後づけの理屈でしかないのかもしれないが、そもそも、告白こそが赤司の出した結論だった。二人が共に、前に進むものとして発された言葉では決して無かった。それが嫌と云うほどわかっていた。
願いが叶うことは絶対に無いのだと、きっと自ら言葉で線を引いたのだ。マジックペンでくっきりとした線を書いて、灰色の紙の上に、右と左の区切りをつけるように。
精神と肉体、その両方を求めるのは、謂わば、生と死の共存を選ぶにも似た心境ですらあった。
ふいに、黒子の視線が赤司の背後にずれたのに気づく。誰かが並木道をこちらに向かって走ってくる様だった。
視線の対象などはどうでもよくなり、不思議そうな顔で無防備さを晒している黒子を無理やりにでも抱きしめようかと、赤司は唇を噛む。断ち切れない未練によって、線はどうしたってぼやけてしまう。
「あ、赤司さん!」
名を呼ばれ、ちらと見た。突如現れたのはスーツ姿の人間だった。赤司にとっては記号ですら無いただの邪魔者として、のっぺらぼうとしてその姿は目に映った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
