
第1回 ラップから予想する宝塚記念(傾向編)
こんにちは!
いよいよ上半期総決算の宝塚記念が明後日に迫ってきました。みなさんも予想に頭を悩ませておられるのではないでしょうか?
宝塚記念らしい小頭数の出走となってしまいましたが…そのメンバーは個性豊か。重馬場の絶対女王・クロノジェネシスが連覇を達成するのか、コントレイル、グランを破った無敗の超新星・レイパパレがこれを阻むのか、最強のシルバーコレクター・カレンブーケドール悲願の初G1制覇か、などなど見所盛りだくさんの一戦です。
今回はそんな宝塚記念の予想をラップ的な観点から予想していこうと思います。「今までラップなんて気にしたことがない!」という方にも分かりやすい記事にしようと思っていますので是非ご一読ください。
【宝塚記念過去5年の傾向】

まず過去5年の宝塚記念のラップ推移をグラフにして表してみました。ちなみに濃い青色はかなりタフな馬場、青色はタフな馬場、緑色は標準馬場、橙色は普通の高速馬場、を表しています。
(※JRAの公式の馬場状態ではなく、実質的な馬場を考慮したものです。府中ではよくあることですが稍重発表でも実際は高速馬場ということは多々あるので注意しなければなりません。)
どの年も大体同じようなラップ推移を辿っていることが分かると思います。個人的には、宝塚記念のラップ推移の大きな傾向は以下の2つにあると考えています。
傾向①先行争い部分にあたる2F、3Fは11秒台前半から中盤のラップを維持しており小頭数になりがちな宝塚記念でも序盤はペースが流れ、ある程度のスピードが求められやすい(60秒前後)。
傾向②後半の最速ラップは過去5年でみても2019年に11秒台中盤を踏むことがあったくらいで、特にタフな馬場以上になると12秒台まで落ち込み各馬が消耗しがち。
ではなぜこのようなラップ推移傾向になるのでしょうか?大きくは以下の3つの要因が複合的に重なっていることが原因と考えています。
要因ア.上半期グランプリG1というレースの性質
古馬G1というレースの性質上、序盤は各馬が自分の取りたいポジションを取ろうと必死になることから先行争いは激しくなりますし、前哨戦特有の脚を図ろう、賞金加算の着拾いという騎手意識も存在しないことから仕掛けも強めになりやすいです。
要因イ.阪神芝2200mというコース形状
こちらはコースのイラストを見ると分かりやすいんですが…

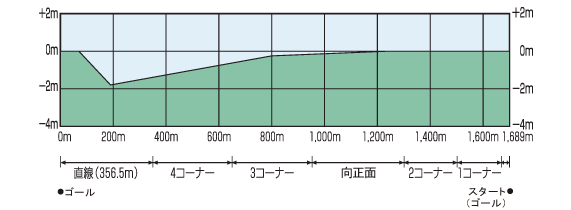
画像引用:https://www.jra.go.jp/facilities/race/hanshin/course/index.html
阪神芝2200は内回りと外回りの合流点にスタートが設けられており、1角までの距離が500m超と非常に長いんですよね。だからスピードにも乗りやすいし先行争いも長引きやすく、上のグラフでも2F、3F目は速いラップを踏んでいることが分かると思います。
さらに向正面から若干下りつつ3角の入り、4角へ向けてなだらかに下りが始まるのでこの下りに乗じてコーナーから加速していくことが多い。向こう正面は6F目、3角は7F目辺りからですが、同じく上のグラフでもここら辺から加速してることが多いことが分かると思います。
要因ウ.6月末の開催時期
6月といえば梅雨ですよね、例年この時期の開催は雨季と被ることが多いので馬場が非常に悪化しやすい。確かにここ5年でみても高速馬場で行われたかなというのはリスグラシューの年くらいでその他の年はほぼほぼ馬場が悪化した状態で行われています。
では、そんな悪化した馬場状態で、要因アや要因イで述べたような序盤の先行争い、コーナーからの早めの仕掛けが起きるとどうなるか?各馬が直線に向いた時にはほぼ余力は残っていません。超高速府中では余力十分、直線で1F10秒台前半の末脚を繰り出せるキレ自慢の馬がいたとしても、ドロドロ梅雨阪神ではそれを繰り出すことができないのです。上のグラフでも5F目以降に10秒台のラップを刻んだレースが一度もなくほとんどが12秒前後のラップしか踏めていないのはそういうことです。
※ただし、上で述べたようにリスグラシューの年は高速馬場気味ではあったので早めの仕掛けにはなったとはいえ、11.6-11.5-11.4-12.4とガチガチの消耗戦にはなりませんでした。それでもラストは12.4と消耗していますし10秒台までキレる脚が求められたわけではありません。
いったん整理しておくと…
要因ア+要因イ⇒傾向①
要因ア+要因イ+要因ウ⇒傾向②
こういう関係にあるのかなと思っています。
【宝塚記念2021は傾向があてはまるのか!?】
と、だんだんと宝塚記念の傾向がつかめてきた気がしますよねw?でも傾向が分かったからと言ってじゃあ今年もそうなるのかというのは全く別の話なので考えないといけません。
個人的には傾向①は今年も当てはまってくるんじゃないかなと考えています。傾向①を導き出す要因アや要因イは騎手の意識やコース形状からくるもので年によって変わるものではないからです。
問題は傾向②でこれは要因アや要因イだけではなく要因ウからも導き出されるものですから今年も当然に例年(2019年は除く)の傾向が当てはまるとは限らないわけです。
なので今年の宝塚記念の最大のポイントは…
後半のラスト5F目から4F目にかけての早仕掛けで消耗しきらず量的な者だけでなく質的なものを問われるか?それとも消耗しきって量的なものしかとわれないのか?
だ!!!
と大げさに言ってはみたのですがまあ要するに馬場がどうなるかということですハイ…( ;∀;)
とりあえず先週の馬場をみてみましょう…先週は金曜から土曜にかけて結構雨が降っていてダートも不良になるレベルだったんですよね、米子Sも1:35.0とこの時点ではかなりタフな馬場だったかなと。一転、日曜は晴れて乾いてきているのかなあと思っていて、マーメイドSの時計が2:00.4。
度々例に挙げている2019年のマーメイドSが2:00.3なんですよねー、レベルの問題はあれど結構1日で乾いたのかなという印象もあります。そもそも今年は変則開催で阪神はロングラン開催だったので路盤が固めに作られている可能性も十分あってすぐ乾いちゃうのかもしれない…加えて今週はパラパラと雨は降れど1週間通して夏日が続いていたのでふたを開けたら土曜は高速化していることもありえると個人的には思っています('_')
土日の開催中の天気予報もパッとしなくって、土曜は30~40%、日曜は70%の降水確率。仮に路盤が固ければ多少の雨は関係がなく馬場も悪化しにくいが…ここらへんはまず土曜をみてみないとなんともいえないですね。
なので収まりが悪いのですが、今年の宝塚記念は傾向②が当てはまらない可能性もある、というところでとどめておこうと思います。(ちなみに関西在住なのですがこれを書いてたら凄い雨がふってきましたwやっぱ例年通り消耗戦になるかも…w)
【中間結論(仮)】
中間結論(仮)として…
宝塚記念2021は序盤から流れてスピードが問われ(傾向①〇)、かつ、早めの仕掛けになり量だけでなく11秒台中盤のラップを踏みつづける後半の質も問われるレースになる(傾向②×)!(可能性がある)
ということです。
さて、だいぶ長くなってきてしまいました…( ;∀;)
今回はラップで予想する宝塚記念(傾向編)として、宝塚記念の過去の傾向を考えつつなぜそういう傾向になるのか?今年にもそれはあてはまるのか?、ということを探ってきました。
しかし、仮に今年のラップ推移が分かったからといって競馬の予想が完成するわけではありません。次のステップとして、予想されるレース質に強い馬を探りあてる、これをやって初めて競馬予想になるのです。
ということで次の記事では、過去の参考レース分析をするとともに今年の宝塚記念に適性が合致しそうな馬を探していきたいと思っています。
ここまでお読みいただきました方、長らくお付き合いありがとうございました。もしよろしければ次回の記事も読んでいただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
