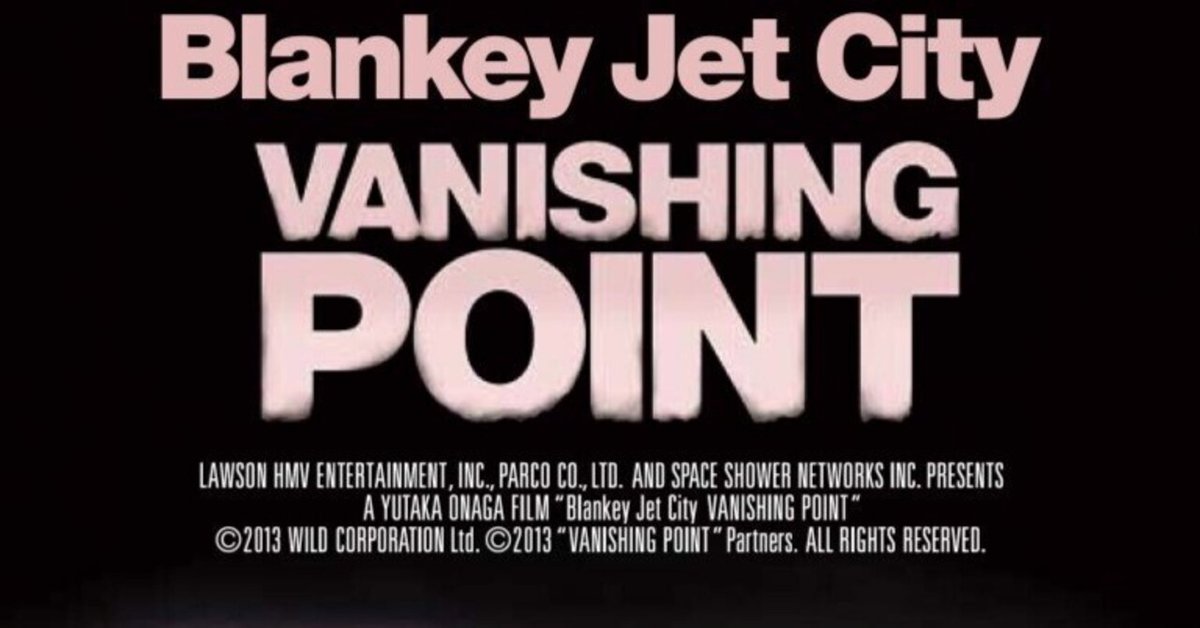
翁長裕監督インタビュー:ブランキー・ジェット・シティ『VANISHING POINT』を巡って
『LAST DANCE』一回限りの配信、アナログ盤発売、サブスクリプションサービス解禁などでにわかに盛り上がるブランキー・ジェット・シティ。
これは解散ツアー(2000年)の模様を追ったドキュメンタリー映画『VANISHING POINT』(2013年公開)の翁長裕監督のインタビューである。映画の劇場用パンフレットなどに一部を使用したが、これはその完全版だ。当初映画の公式Facebookに掲載されたが、今回の一連の再発プロジェクトにあわせ、ここに再掲する。初号試写の2日後の2011年11月14日に監督のアトリエでおこなわれたもので、映画完成直後の生々しい第一声が聞ける貴重なものである。
翁長監督は『VANISHING POINT』のほか、横浜アリーナでの解散ライヴの映像『LAST DANCE』始め、古くからブランキーの映像作品やMVなどの制作に携わってきた。解散の報を聞き、抱えていた仕事をすべてキャンセルして手弁当で解散ツアーに同行しカメラを回し始めた翁長氏に追って『LAST DANCE』のオファーがあり、という経緯もあって、いわば『LAST DANCE』の前日譚が『VANISHING POINT』、という側面もある。私は『VANISHING POINT』のスーパーバイザーという肩書きでスタッフの末席に名を連ねている。翁長氏にとっても、デビュー前から解散まで彼らの取材をやり続けた私にとっても、これはブランキーとの仕事の集大成であった。
同じタイミングで行ったブランキーのマネージャー、藤井努氏のインタビューと併せてお読みいただければ幸いだ。(小野島 大)
ーー難産ながら、こうやって完成したわけですが、今の心境はいかがですか。
「そうですね・・・なんでも作るときはそうですけど、まず自分が感動の当事者なわけで。観客のつもりで見るというか作るというか。この画を見たときにどんな感情が残るか、自分の中でシミュレーションしながらカットを繋いでいくわけですよね。おそらくその時の感覚が頼りだから、ピュアであろうとするし、音に対して一番センサーがたったような状態に自分を追い込んでいく。そうやって繋いでいったものに対して、第三者の意見が入った時に、ものすごく・・・心細くなるわけですよ。その時に自分が良いと思った感情がはたして正しかったのか。正しいという答えはないわけですから、どこまで客観的になれたか、どこまでファンの感覚になりきれていたのか、というところの試行錯誤なわけですね。今回の場合、最初の段階でけっこう厳しい駄目だしをされたりして、そこの自信が揺らいだりしてたんですね。自分が良いと思って繋いでいた頂上への道が、違う方向に向かっていたのかもしれない。一本道のつもりが、遠回りをしていたのかもしれない。遠回りしてまた元の道に戻ってきた。そんなことを繰り返してたわけです。それで最終的に登りつめた頂上が、結果的に、彼らを支持していた人たち、僕以上に愛していた人たちから、身に余るお言葉を頂戴して。ホッとしたというのが正直な気持ちですね」
ーー最初に粗編集して藤井さんに見せたわけですよね。その時のものと完成形は相当に違うものになったんですか?
「いや、基本的にその時の素材は本編にすべて入ってますね。特に(素材の選択が)間違っていたとは思わない。ただ、僕の中で常に補完しながらの粗編集だったわけです。音はもっと良くなるとか、いらないところは削るであろうとか。今回の場合、時系列はいじらないというのがあったんです。しかも結論も見えているわけですから。でも僕がやりたいと思ってたものが最初はなかなか理解されなくて。そこで頓挫しかけたんですけど。そこで急遽修正して編集したものを、最初の(小野島との)インタビューの時(2011年9月12日)にお見せしたんです。その時良かったのが、最初からずっと見ていたスタッフが、修正してかえってダメになったと言ってくれて。ああ、わかってくれてる人もいるんだと、ぎりぎり救われた気がしたんですけどね」
ーー最初にカメラを回してた時、完成形みたいなものは頭の片隅にあったんですか。
「僕はね、人間性の問題でしょうけど、あんまり先のことまで考えてないんですよ。そこはコントロールして行動できない。だいたい、変わっていくじゃないですか、モノを作る時って。当初の構想通り行かないのが普通で。だからこのドキュメントをどうしようとか、そんなに明確な目的はなく始まったんです。しかもそれは『LAST DANCE』の収録前のことですから、『LAST DANCE』をどうしようかっていうのが、まず僕の中で第一義的にあって。その補完素材的な意味合いもあったわけです。とはいえ、彼らのドキュメントを撮るのは初めてではないし、その流れという側面もある。でも最後だから明確なポリシーも必要。そこはまあ、撮りながら考えよう、ぐらいのものでしたね。これは映画にしたいねって話は、そのころからあったような、ないような。でも映画にするんだったら、これをオープニングにしたいなと思って隠し持ってたのが、冒頭の飛行機の画なんですね。あれは岡山に行く時かなあ。東京から僕ひとりで現場に向かう新幹線の窓から撮ったんです。いろんなものが重なったんですね。すごくシンボリックな映像だと思ったし、もし作品にするのであれば、あれをオープニングにしようと思ってたんです。なので今回映画化が決定するまで、誰にも見せずに封印していた。茶々入れられるのも嫌だったから。これは押し通そうと思ったんです」
ーーそこで「あの飛行機には何の意味があるのか」とお聞きするのは野暮ですが・・・。
「うん、あれはいろんな解釈があってもいいと思うんですけど、映画版とDVD版ではBGMが違うんですよ。当初は「ガードレールに座りながら」を、これしかないって感じでハメてたんですね。結果的に映画版では「古い灯台」にしたんですが、「ガードレールに座りながら」の歌詞と、飛んでる飛行機がものすごくシンクロして胸に刺さったんですね。ブランキーらしさがすごく表れてた。何の因果か、その後ベンジーがおもちゃの飛行機を取り出して眺めてるシーンが出てきますけど、この3つの合わさり方というのが、実はこの映画のテーマでもあるわけです。爆走しながら突き進んでいって、いろんなものがよぎりながら、どんどんスピードをあげていって、いつかは・・・その様を描くのかもしれないけど、まっすぐ飛んでいく様がね、ブランキーの3人のイメージと一番近かった」
ーー燃料が尽きれば落ちてしまう。
「うん。その後ね、9.11とかいろんな出来事があったけど、そういうのとは関係なく、生き様としてなにか、DNAに刻まれているような気もするわけですよ。ついでに話すと、途中で「皆殺しのトランペット」が出てくるでしょう。なぜあそこで出てくるかというと、あの歌詞で白頭鷲の話が出てくるじゃないですか。翼を切られた鷲の話。空が広がっているのに飛べない。その哀しさ。でも実は、翼はあるのに飛ばない人たちの愚かさとかね。それを歌いあげることで彼らの音楽の世界は出来上がったわけだけど・・今回の映画のテーマはそこなんですよね。言いたかったことはそれだったと自分で腑に落ちて」
ーー「ガードレールに座りながら」と「古い灯台」では、かなりイメージが違いますね。
「そうですね。ここで映画版とDVD版の違いを言っておくと、時間的にも違うし、見る人の熱意というか濃さも違う。なので映画版はある程度凝縮してエッセンスみたいにするのがいいだろうという判断が僕の中でありまして。映画で表現したいのは、ブランキーの爆走感というか疾走感というか、刹那感というか、そういうものをテーマにして編集したんです。なので「古い灯台」のほうがいいかなと。DVDの方は、買う人は映画より濃いだろうし、そういう人たちはもっと深く知りたい、見たいだろうし。時間的な制約もある程度緩やかなんで、DVDはブランキーと一緒に過ごす時間というか空間というか臨場感の方を大切にしたかったんですね。なので、当初の構想だった「ガードレール」がふさわしいだろうなと考えたんです。だからDVDはディレクターズ・カットといっても単なるおまけ映像的なものとはまったく違うものなんです。時系列は同じだし結論も同じだから、重なる部分もたくさんあるわけですけど、僕の表現しようとしている空気感はまったく違うんですね」
ーーDVDを見る人には、もう少し感傷に浸ってもらってもいい。
「うん、それでもいいかなと思うんですよね。あの曲かかった時点で泣いてもらってもいいかなと(笑)」
ーーDVDは部屋でひとりで見るだろうから、あれは泣きますね(笑)。ブランキーは本当にいろんな人の思いを呑み込んだバンドだと思うんですが、もちろんそこで翁長さんなりの思いもある。折り合いはどうやってつけましたか。
「そうですね・・・僕は、どれぐらいブランキーのファンなんだって問い詰められたら、おそらくそんな大したファンじゃないと思う。皆さんに比べればね。でも僕なりのスタンスがある。ブランキーはちょっと苦手だよなーという人の感覚も、なんとなくわかるんです。一方、ブランキーしかいないよ、という人の気持ちもわかる。そういう立ち位置だと思うんです。だからこそ描く時に、その匙加減、伝え方がわかる。ブランキーを世の中に伝えていくというか残していくという役割を僕が仰せつかったとするなら、あまりゴリゴリにしちゃうと、苦手な人をますます遠ざけてしまう危険性がある。でも自分がブランキーを苦手だったら、はなから「お仕事モード」になっちゃって、ロクなものは作れない。そういう意味では、自分の立場はわきまえているつもりなんですよ。で、それとは別に、個人的に好きなんですよ、人として。過去の仕事の中で出来上がった人間関係というのもあるでしょうし、彼らのキャラクターもあるでしょうし。裏表のある人間は好きじゃない。そういう付き合い方は苦手だし、めんどくさい。そういう形じゃなくて付き合える数少ない男たちなんですよ。だからあの人たちが凄いプレイヤーじゃなくてもいいんです。遊びに行ったり飲みに行ったりできればもっといいんでしょうけど、たまたまこういう形で出会えているから、お互いに精一杯やれることをやっているわけで。だからそういう意味で言えば、3人の、人としての記録映像を、僕の培ってきたノウハウをうまいこと活かして作品にまとめられる立場なので、こうやって3人のことを世にしらしめることができたっていうことだと思います。ラッキー・・・なんでしょうね」
ーー人としての彼らは映像そのものに表れてくる?
「そうでもないですね。一番そう思うようになったのは、『SKUNK』のロンドン・レコーディングに同行した時です。朝から晩までスタジオで一緒にいるわけですよね。彼らはミュージシャンで、僕は職業カメラマンとして撮っている。夜になって終われば一緒にメシを食ったり。で、何もやってない時、彼らは何をしてるかというと、ひたすら本を読んでいるわけです。けっこう小難しい本を。長丁場なんで、いっぱい日本から持ち込んで。それぞれ部屋はあるんだけど、リビングみたいなところでダラダラしながら読んでいる。僕はたまた精神世界に興味が湧いてきたころで、彼らもそういう本を読んでたんですよ。そこから深いところの話をするようになって。3人ともそんなに口数は多くないでしょ。でもそういう話を始めるとすごく饒舌になるんですよ。そういうことを考えてるのか、こういうことを表現したいのかって、なんとなくわかってきて。すごくピュアな人たちなんだなと。少年のまま大人になったんだろうなって。自分の中のそういう感覚ともシンクロして、深いところでお友達感覚になれた気がしたんですよ。あと、いつも「ありがとう、ありがとう」って言ってるんですよ、お互いに。今でもそうですけど。外でメシ食っても、何しても「ありがとう」。本当に礼儀正しいなと思った。すごくコワモテな連中がそういうことをやる、そのギャップにもやられたわけですよ。で、ステージになるとあんなじゃないですか(笑)」
ーーわかります(笑)。
「僕は彼らの代々木のフリーライヴの現場で死にかけたことがあったんです。『SKUNK』のレコーディングが終了して、そのプロモーションとして代々木公園のステージでフリーライヴをやったんですけど、それを収録してビデオで出そうという話になったんです(DVD『Are You Happy?』)。それを僕はステージのすぐ前で撮ってたんですよ。アルミの柵でブロックごとに囲って万全の態勢で臨んだはずだったんだけど、メンバーがステージに登場した途端に後ろからどーんと人が来て。そうしたらパキーンと音がしてアルミの柵が倒れて、弾みでカメラが前に飛んだんですよ。やっべーと思った瞬間に柵とコンクリートのステージの間に挟まれた。そこからはもうワケがわからない。とにかく自分の許容範囲を遥かに超える圧力なんですよ。こっちも渾身の力で押し返すんだけど、そんなものへのつっぱりにもならない。そうするうち波が少し弱まって一息つけるかと思ったら、すぐに第二波が来た、これが強力で、挟まれて押されて胃の中のものが全部噴水みたいに全部出て。苦しいやらびっくりするやら。ああ、こりゃもう終わりだなと。人生こんな風に終わるのか。一瞬だなあと。時間にしてどれぐらいだったのかな。すごく長く感じましたけど、実際は短かったんでしょうね。ステージ上では舞台監督とか僕の方を見て騒いでましたけど、そうなっちゃったら誰にも抑えがきかない。僕の足元にはアシスタントの女の子がうずくまってましたけど、下にいたから助かったんでしょうね。彼女が挟まれてたら死んでたでしょう。で、照ちゃんがちょうど僕の前にやってきて、これはもうメンバーが止めるしかないから、照ちゃんがなんか一言言ってくれるかと思って必死の思いで見てたら、照ちゃんもテンションあがりきってて、目がイッちゃってて。「ロックンロール!!!」って絶叫(爆笑)。・・・幸いそのあと波が少しひいて、なんとか抜け出せたんですけど。あとで医者に見てもらったら、肋骨が数本、折れてましたね(笑)。でもまあ、そんな凄い状況だから、凄い画が撮れてるのはわかってたし。もうそんな、自分の体がどうのなんて言ってられない。狂乱の状態だったけど、ベンジーの足元で、なんとかカメラを担いで撮りましたよ」
ーー私は後ろの方で見てましたけど、前の方ではそんな大変なことが起きてたんですね(笑)。
「小野島さんが押したんじゃないの?(笑)。あとで編集の時にじっくり見たんですけど、とにかくすべてのカメラがその時の凄い状況を克明に捉えている。凄い画が撮れてるんですよ。で、一番迫力の出るように編集して納品したんです。その時は自分のことなんて意識になかったですけど、何年かたって見返してみたら、バックショットで僕が挟まれて胃の中のものブワーッと吹きあげてる瞬間がちゃんと写ってた(笑)。ほかの画が凄いから、そんなとこに普通目が行かないんだけど。ああ、これが俺の遺作になってたのかもなあ、と思って」
ーーまさに命をかけた仕事だったんですね。
「だから、あの人たちの仕事で僕は一回人生を終わらせてるわけですよ。それ以降は本当におまけっていうか」
ーー一度は死んだ身であったと。
「そうそう。ほんとそんな感じですよ。だからゴリゴリのブランキー・ファンかといえば、そうではないけれども、自分の人生のなかではかなり重要な存在ではありますよね」
ーーなるほど。13年前に撮った素材を見返してみて、改めて気づいたことはありますか。
「今回ね、なぜ13年もかけたのか、とか、なぜ今なのか、とか、当初からあったんですよ、僕の中で。なぜ今なんだろうって。たまたま、ではあるんだろうけど、それでもなんらかの意味があるはずと思って今回のプロジェクトを始めたんですけど。もちろん、撮った当時は10年以上も寝かせることになるとは思ってないですよ。『LAST DANCE』と一緒のパッケージにするか、映画にするか。いずれにしろ近い時期にまとめてしかるべき素材だったんですけど、結果的に13年もたってしまった。それはみんな疑問に思うだろうし、僕もずっと自問自答してたんです。それでこの半年、いろいろ揉まれているうちに、答えがわかったんですよ。それは2つあって、一個は僕の変化なんです。実は13年前、『LAST DANCE』を納品した直後にドキュメントとして粗編集したものが残ってたんですよ。それを見返してみたんですけど、その時選び抜いた素材と、今回の映画で使った素材は、ほぼ重なるんですよ。だから重要な場面はそこですべて選ばれていた。でも全然違うものなんですよ。なぜかというと最初のヴァージョンは、『LAST DANCE』に頼ってるんですね。ドキュメントといっても、よりエンタテイメントに近いものを目指してたと思うんですよ、当時の僕だったら。それが手慣れてたし、エンタテイメントとしてのドキュメント・ライヴならお手の物だったから。それはそれで悪いものにはなってなかったと思うけど、あくまでもそれは『LAST DANCE』というものが骨格にあったから、それに花を添えるという意味でのドキュメントになっていたはずなんです。ところが僕もこの13年の間にいろいろ経験を積んでーーま、歳をとったということなんですけど。価値観が変わってきた。ひとりの男の視点として、3人の男と対峙しながら見てきたものを、地味だけど積み上げていって、最後はアリーナにたどり着くーーそこに至るまでに、僕の中ではこれだけの歳月が必要だったんですね」
ーーなるほど。
「もう一個の理由は、時代背景です。この映画の中で飛び跳ねている若い子たちも、今はもう家庭を持ち、あるいは社会の一員として存在してるわけじゃないですか。この時期の13年ってすごく大きいですよね。人生の大変革期なわけで。すると、その子たちの置かれてる状況って、天と地だと思うんですよ。ブランキーの音楽って、すごく聞き手を選ぶじゃないですか。すごいピュアな、無添加のクリームみたいなもので。不純物が一切ないから、こっち側に余計なものがあると沁みてこないっていうか。歌詞ひとつとっても、「なにそれ?」とか「ハア?」とか思っちゃったら、もう受け付けないような。でもこっちがちゃんと受け入れる態勢になれば、すごい深いところまで入ってきて、彼らが伝えたいことがわかる頃には、もう離れられなくなるんですよ。そんなアーティスト、いないからね。単に爆音でかっこいいと思って入ってきてる人も、そこまで意識しなくても、ほかのバンドとはどこか違うってことはわかってるはずなんですよ。今でもコンサートで盛り上がって、観客が一緒に歌うことってありますよね。でもそれは単に「合唱」なんですよ。アーティストと一緒に歌ってるだけ。でもブランキーのライヴでの光景は、歌ってるんじゃなくて叫んでるんですよ。叫び合って共鳴してる。そんなことをしてた連中が大人になって、ならざるをえなくなって、今どうだろうって想像するとね。今の世の中って、いろいろ妥協して我慢しないと生きていけない。つらいことが多いじゃないですか。ピュアであればあるほど。そんな子たちがね、あの時の自分をもう一回みて、なにかを得られれば。人それぞれ化学反応の仕方は違うと思うけど、絶対それは意味のあることだと思う。それは(解散から)2〜3年じゃダメだったと思うんですよ。それこそ干支が一回りするぐらいの時間が必要だったのかもしれないという気がしてるんです」
ーー子供が大人になるぐらいの。
「そう。青年が親になるぐらいのね。だから、こうやって仕上げて、妙に納得してる自分がいるわけで。なんか・・・ツイッターでこの情報を解禁した時に、誰かの書き込みで「生きてりゃいいこともあるな」みたいな書き込みがあって。思わずちょっと泣いちゃいましたけどね。・・・ノスタルジーで作ったわけじゃなくて、今必要なんじゃないかと。必要であって欲しいというか」
ーー翁長さん自身はこの13年間で、何が一番変わったと思います?
「僕はね・・・今の音楽マーケットとか、どう考えてもおかしいじゃないですか。今の世の中の音楽のありようって、明らかに商品なわけですよね。売れれば音楽の内容なんて関係なくて、逆に良い音楽は埋もれて多くの人に届かなくなってる。主流とそうでないものの差がーーもちろんあっていいんですけどーー激しすぎて、商売の道具になっちゃってる。一部だけが利権を持ってうまいことプロモーションして売ってる状況。そうでない音楽家はみんなに聴いてもらう機会さえない。僕は、昔は加害者側に加担してたわけですよ。売れ線のアーティストをずっとやってきたわけですから。でも今は被害者的な立場でもある。だからある種、贖罪の意味もある。マーケティングだなんだは関係なく、縁があって僕がさわれるものに関しては、良い物として残していきたい」
ーー今回の作品はまず第一に、誰に見てもらいたいですか。誰のために作りましたか。
「さっきも言ったように、あそこで飛び跳ねてた子供たちのためですよ。メンバーは、いいんですよ。今でも頑張ってるから。こんな映画のことなんて気にしなくていい。映画があろうがなかろうが死ぬまであのままで行くだろうし。まあ少しは力になってくれれば嬉しいけど。でも第一義的にはね、ちょっと疲れて出口が見えなくなってるところでうずくまってるような、かっての若者たちですよ。だってピュアな人たちだからね。自分を誤魔化せないわけだから。そりゃつらいですよ」
ーー誤魔化せないところでなんとかやりすごしてる。
「そういう人たちへの13年ぶりの差し入れってとこじゃないですか?」
ーー翁長さんも私も、ブランキーに出会った時にはもう30歳を超えていたから、そういう子たちと同じ気持ちにはなれないかもしれないけど、10代の時に会ってたら、きっと人生が変わっていたと思います。
「ブランキーの連中も、永遠の少年なわけないじゃないですか。体はどんどん老けていくし、気力も体力も衰えていく一方だけど、でも変わらずにあるものって、あるじゃないですか。そこは、頑張ってほしい。我々も我々のテリトリーで頑張るから。だから映画の最後は、あの人たちに向けてのエールなんですよね」(インタビュー・文:小野島 大)
よろしければサポートをしていただければ、今後の励みになります。よろしくお願いします。
