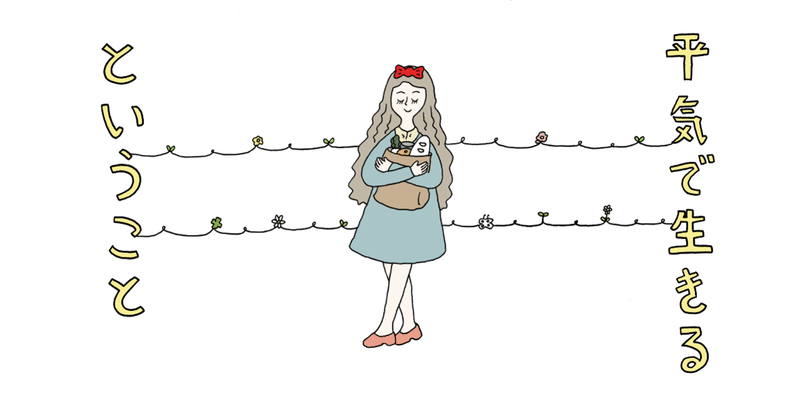
不機嫌な人が放置できないのは何故か?
これから数回にわたって、生まれ持った特徴、いわゆる個性として説明される「HSP(繊細な人)」という心のあり方について、それが本当に「わたし」と不可分のものであるのかについて問い直したい。
それに先立って、精神分析的な<わたし>と西洋哲学的な<わたし>の異質さに触れておく必要がある。というのも、「わたしは繊細である」ということ、そして「繊細はわたしの個性である」という言い方は、西洋哲学的な自我観を言外に踏襲しているからだ。
文化やフィクション、あるいは社会において「個性」がどのような人にもひとつずつ与えられた、どれひとつを取っても同じようなものがない、その人と不可分な、素晴らしく、否定できない要素として扱われているというのは珍しい光景ではない。そしてその「個性」はわたしの外見、性格、好みや習慣、信念といった諸要素と関連付けられて「不可侵」なものになっている、というのが一般的な民主主義社会の認識としてある。
この前提は言うまでもなく、裏を返せば、わたしが嫌っているわたしの諸要素、できるようになりたいのにできないこと、やめたいのにやめられないこと、そういった成長によって克服すべき部分まで含めて「個性」の中に取り込んでしまう。それは、わたしが「できない」ことを優しく容認してくれる代わりに、暗にそれらの要素が「わたし」と切り離せない要素であることを示唆し、「わたし」を成長や変化から遠ざける。
<繊細な人>というカテゴリはまさにその「わたし」と不可分な<個性>の一つとして存在している。HSPという言葉が提案される以前も、対人関係や生活に特殊なトラブルを抱えている人たちを総括して名付けようとする試みは常に行われてきた。これに類する「この人はこういう人である」という前置きに基づいた励ましは、「それがあなたなのだから、あなたはそのままでいい」と、欠点や克服したい部分を含んだ「わたし」を肯定してくれる。しかし、そのいっときの安心感が尽きると、やはり「わたし」の中に内包されている欠点、悪意、コンプレックスは依然として「わたし」を苦しめ、堂々巡りの中に閉じ込めようとする。
ここにある板ばさみ、つまり「わたし」を肯定しようとするとわたしの欠点や成長によって克服しなければならない点まで肯定されることになり、また何らかの点を成長によって克服しようとすれば「わたし」を否定することになるという矛盾は、自己と他者が断絶され、対立しているという西洋的な自我観にとってみればひとつの宿命といえる。
いっぽうで、仏教的な存在論では「わたし」というものは存在しない。仏教においては全てのものがそれ単体としてあるのではなく、他のものとの関係性で成り立っている(縁起)と考える。
実のところ、精神分析を理解するうえではこちらの考え方のほうが数段都合がよい。なぜなら、わたしが暴力的な衝動に悩まされているとき、西洋的な善悪の観念は「それは<わたし>の欲望である」と断じ、わたしが悪人だと糾弾する。しかし精神分析は「それは他の対象との関係の再現である」と疑う。すると、その衝動が幼児期に親に与えられた影響の反復であることがわかる。では、悪いのは親なのか、と問うと、今度はその親の行動もまた他の誰かの影響の反復であることが分かる。そうすると、もはや誰が「悪い」という責任の所在の感覚は成り立たなくなる。このようにして、他者に対して「この人を糾弾しても仕方がない」という感覚が身につくと、その感覚は自分自身にも向けられるようになる。「私が悪い、私は不出来だ」という自責の感情から逃れて、「なぜそうなっているのか」という外側の力学に着目することができる。
前提3: 自己犠牲的な人とは、自分の機嫌を取る責任を放棄して他人に奉仕する人である
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
