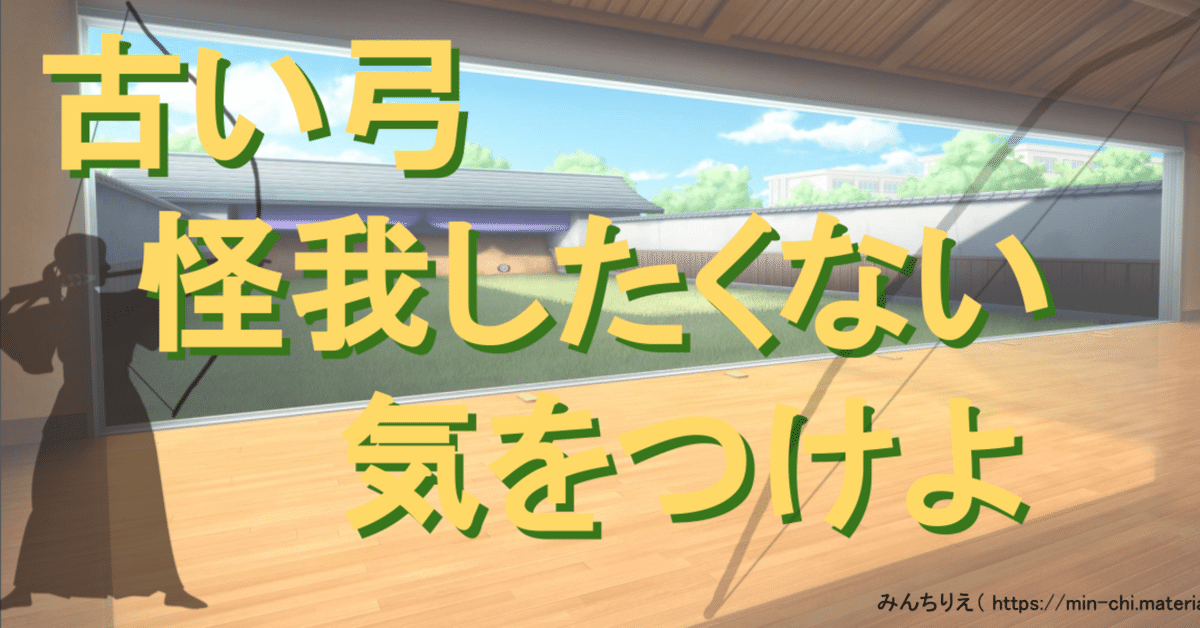
【コラム】古弓の注意点
掃除していたら倉庫から竹弓が出てきたー!
と喜んでる人がおります。
その気持ち、すっごくよく分かります!
私も古弓を貰ったときは同じような気持ちになります。
早く張りたい
どんな成りなんだろうか
引いてみたいなー
と期待に胸を踊らせています。
しかし、そう甘くはありません。
経験上で、的前での使用に耐えた弓は3割くらいでした。
7割の弓は途中で破損してしまったのです。
ほとんどが接着剤の経年劣化でした。
古弓は張る前に反りを落ち着けます
両弭を床につけて、
外竹を下にして、
握りをもってゆっくり押し込んでいきます
この時、内竹に加わった力に負けて内竹が剥がれることがあります
これを数回繰り返し、張れそうだと思ったら張ります。
裏反りが高い場合は切詰めと弦を紐で縛るといいです。
張る途中でも竹が剥がれる可能性はあります。
張ったあとは弦通りと成りのチェックです。
通常よりも極端に変になってる場合は、
竹が浮いているか、側木や芯材が破損している可能性があります。
小反→本弭、姫反→下弭の方向に押し込むようにしてみてください。
この時、関板が分離することがあります。
これが意外と多いです。
弦通りよし、成りより、じゃあ的前に行きましょう!とはいきません。
まずは巻藁をやりましょう。
いきなり矢束まで引くと破損する危険性があるので、最初は矢束の半分、徐々に引いていき、10射ほどで矢束まで引いてみてください。
そこで問題がなさそうであれば、ようやく的前にもっていくことができます。
慎重すぎるかもしれませんが、いろんな古弓を破損させてきた弓右衛門の危険回避術だと思って、参考にしてもらえたらと思います。
的前で引いて大丈夫だと思って常用していたら、
会で弓がバラバラになったり、
会で下から折れたり、
張った時に関板がとれたり、
急にトラブルが舞い込んできます。
引く弓がなくなった!?ということにならないように、メインの弓として使うことはさけて、射形改善用・勉強用として使いのがいいかもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
