
上等兵ズ覚書
2022年6月のゴールデンカムイ 上等兵について語るスペースのために調べた内容を備忘録として残します。
読みきれていない資料が多々あり、できれば追記したいと思っています。
参考資料は最後に記載しております。wikipedia多めです。ご容赦ください。
なるべく信頼できそうな資料を記しました。
不明点・間違いなどありましたら教えてください。
宇佐美時重
▶︎明治28年(1895年)時点で14歳(単行本23巻)、1881年2/25生まれ。
新潟県新発田出身?(新発田までも歩きで二時間はかかる農家、稲作メイン、水車を踏む描写)
宇佐美の言葉は、厳密には新発田の方言ではないらしい。新潟市方面ぽい?(twitterにて言及してい方がおられました)新発田より南なのでは。
▶︎おそらく長男、姉、弟、さらに下に弟か妹(宇佐美12歳の時点で赤ちゃん)がいる。仲のよい家族の描写。(妹ではなく姉なのは宇佐美のことを「時重」と呼び捨てにしているから。)
▶︎少なくとも12歳までは小学校に行っている
1886年(明治19年)4月9日 - 小学校令(第1次)の公布により尋常小学校(修業年限4年、義務教育)と高等小学校(修業年限4年)が設置された。
1890年(明治23年)10月7日 - 小学校令(第2次)の公布により、高等小学校の修業年限が2年、3年、または4年となる。※wikipedia
12歳まで行くとなると義務教育以上の高等小学校に通っている事になる
柔道を熱心にやっている。柔道は当時、階級を飛び越えて出世できる道の一つであった。二時間歩いた先の学校であることからも、教育熱心で向上心の高い家庭と思われます。
新発田藩について
東軍として戊辰戦争で敗北、そこまで知名度はなく、かつ周囲の藩が強かったのであまり大きな立場にはなかった。 1873年(明治6年)に廃城となった新発田城の跡地には第2師団(友人の高木智春の父親が所属、鶴見中尉も宇佐美との出会い時点で所属)仙台鎮台の所属部隊として1884年(明治17年)6月に新発田歩兵第16連隊が編成され、以降、明治から終戦までこの町は軍隊の町としての性格を強めた(これは戦後も陸上自衛隊新発田駐屯地として残り、現在に至っている。)。
袴は「馬に乗れる身分」の証し?士族に憧れているのでは? 馬を殺す描写が多く、食べるのが好き →憧れつつも士族が嫌いであると示唆している。出自にコンプレックス。向上心旺盛で、学問を後押しする家庭には恵まれているが、越えられない壁がある。
尾形百之助
▶︎宇佐美の少し年下(ファンブック)とあるので
1882年あたりの生まれか?1/22生まれ
▶︎東京府に生誕(浅草?)、茨城の海に近い地域で育つ。
幼少期に母が亡くなり、祖父母に育てられるが陸軍入隊直前に行方不明に。
祖父に銃の扱いを教えてもらう。
▶︎推定19-20歳ごろ時点で鶴見中尉とともに軍にいるので、自ら志願して(?)10代のうちに入隊したと思われる。その他生育環境不明。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ゴールデンカムイ開始時 作中1907年
宇佐美26歳、尾形25歳
最終巻で1908年となる
作中の細かな時系列について、こちらを参考にさせていただきました。
軍隊と上等兵について
徴兵制3年の時代
20歳以上で徴兵、3年の兵役。
日露戦争を除けばまだ大規模な戦争が起きておらず、徴兵も全員に課せられるものではなく成人男子対象者の1/4程度の人数だった。
上等兵の給料
月給一円50銭 住居費は無料
一等卒
月給一円20銭と上等兵と大差なし
上等兵のすぐ上の階級、伍長から職業軍人となり
月給4円程度となる(ただし住居費が一円25銭かかる)
お給料についてこちらを参考にさせていただきました。
ここからは特に記載がなければ、参考資料 「兵営の告白」をメインに参照します。(明治41年発行の、上等兵を目指した人物の手記)
※wikiなどでも上等兵についての記載があるが時代が不明であり、時代が下ると条件なども変わるので、ゴカムと同時代と思われるこちらを主軸にしました。
上等兵とは?
▶︎兵のうち、指揮監督するもの(下士官になると職業軍人なので別枠扱いとなる)
品行方正にして銃剣術や器械体操、学術科の優秀なるものだけがなれる。
▶︎品行が一番大事とある
古兵に誘惑されて遊里に足を踏み入れたことが公になり、上等兵候補者から除外された。また、妬み、過去の恨みによって上等兵になれなかった事例も。
ただし、術科のできるものが軍では必要とされる。学問のできるものを軍隊では排斥する傾向にある。
▶︎上等兵になると世界が一変するというようなことが書いてある。
「上等兵と言えば下級ながら軍隊の幹部である。班内における唯一の権力者〜上等兵には一人の従僕がつく〜上等兵にならざる間は一人前ではない」
▶︎満期除隊して民間の職場に復帰すると、上等兵ならば体力人格ともに優秀者とみなされ、在郷軍人会でも優遇される場合があった。※wikipedia 時代不明
兵について・上等兵になるには
下から二等卒、一等卒、上等兵に分かれていた。
(昭和6年以降一等卒→一等兵と呼び方が変わる)
明治期・大正期中頃までは二等卒のまま満期除隊する兵も存在した。
入隊したばかりの新兵は二等卒からはじまる。
上等兵になるには、まず修業兵となり、半年訓練を行い、試験に合格したもののみが上等兵になれる。
入営から約4か月経過して行われる第1期検閲が終了すると修業兵の選抜が始まる。
修業兵には二等卒からもなることができ、試験に合格したものは一等卒を経て上級兵に進級する。
修業兵の期間
▶︎練兵(兵の基本的な訓練?)以外にも、修業兵には「間稽古」という、朝晩の銃剣術や器械体操の稽古がある。(器械体操の絵には鉄棒が描かれているので、今と変わらず鉄棒や運動などを指すと思われる。)
朝起床ラッパ(おそらく6:00?)の鳴る前、未明に起きて上等兵や古兵の分まで物品の手入れをする。半年の間ずっとなのでかなりつらいとのこと。
兵には昼寝の時間があるが、修業兵はその時間も学科の勉強をする。
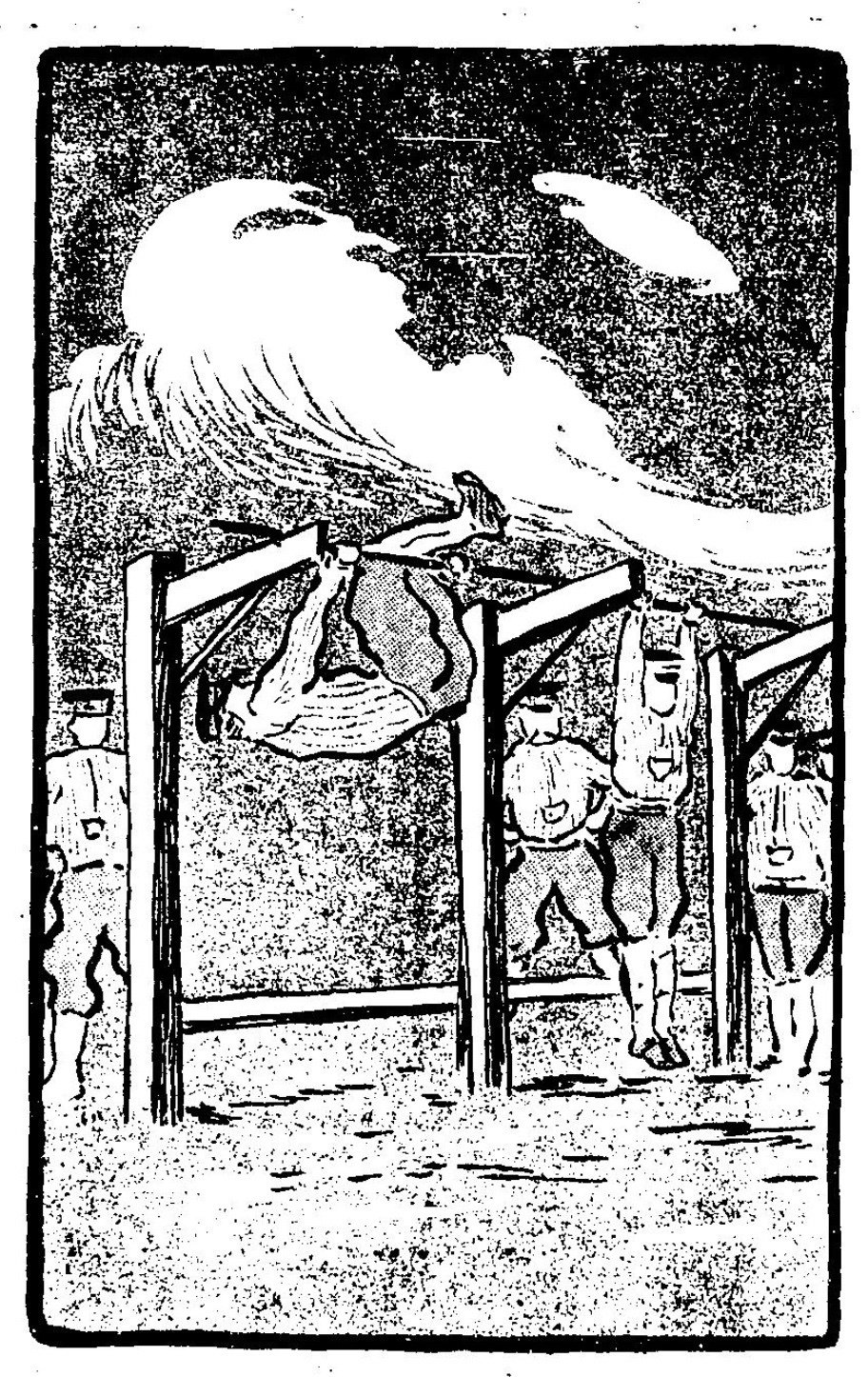
修業兵の試験
▶︎中学卒業以上の学力がないと合格しないと記載あり。(当時の中学は高校程度の年齢)10人中8-9人が 小学校の義務教育のみの時代だった。
▶︎試験が何回かあり、最後に終末試験
11月に発表があった(5月ごろに修業兵となる?)
優秀なものから順次採用、合格順でその後の扱いに差が出るので席順も重要。
修業兵の2/3が合格する。(修業兵の全体に対する比率については記載なし)
上等兵になれる者は,同年兵の4分の1程度といわれる。伍長勤務上等兵になると、多くても中隊に3人程度である(歩兵中隊の場合、平時は二年兵・初年兵ともにそれぞれ約60名程度)。そのため全ての初年兵にとって、上等兵は憧れの地位であり、入営から4か月後(時代によるが昭和初期までは3か月)、第1期検閲終了後に発表される上等兵候補者の発表は、最大の関心事であった。
↑二年兵などの記載から、昭和以降の内容であることがわかりますが、参考まで。
世界大戦以降の資料には、除隊時に記念的に上等兵になる例や、24歳で伍長になる例があり、明治よりも階級の重さが違うのではと想像しました。
▶︎試験や実技の成績だけで選ばれるわけではなく、上官に気に入られないと、修業兵の時点で落とされる事例があった。
軍隊で人間関係もうまくやれないと上等兵にはなれない、というような意味の記載あり。
「兵営の告白」筆者の上等兵への視点
▶︎学力においては青年将校(陸士出身の年若い将校)に一歩譲るが、軍隊における経験と常識においては上等兵が勝ると記載あり。
今で言うキャリアと叩き上げ。
▶︎上等兵の仕事は新兵の教育係、もしくは古兵の担当をする、新兵担当になると偉そうに振る舞えるので良い、とある。
青年将校も新兵の教育係となることがあり、同一の業務を行うことがあったらしい。
▶︎兵営内での上等兵の居丈高な振る舞いの記載あり。兵たちに厳しく接していた。上等兵が嫌われているとの描写あり。
▶︎満期兵(上等兵に上がれないが年嵩の人たち)からの妬み、いじめなどがあった
「如何に階級が上でも二年の上等兵は三年の満期兵に勝たぬ」
満期兵が皿を隠す、お椀を隠すなどの嫌がらせをすると、管理する上等兵の責任になる。
上等兵側はその満期兵に 仕事の割り振りの際に嫌な役目を押し付けるなど、表に見えない戦いがあった。
▶︎上等兵は兵営内の権力者なので、事前に誰にとりいるか調べておき、機嫌をとるために朝から靴とボタンを磨いて待つ新兵がいた。従者になりたがるものもあった。

上等兵の上司
▶︎「兵営の告白」にも特務曹長、伍長などが登場するので、このような階級の人も、兵卒にとって身近な存在だったように思われる。特務曹長は主に人事を担う、10年以上の在籍経験のある人物。
文中にリンクのない参考資料
▶︎兵営の告白
▶︎軍人になるには
▶︎当時の小学校と義務教育について
以下、ゴールデンカムイの上等兵ズに関しての妄想と想像
▶︎上司とうまくやれないと修業兵になることもできないので、宇佐美はともかく尾形もそれなりに上司とうまくやっていたのだろうなと思いました。
棒鱈を彷彿とさせます。
▶︎器械体操をする宇佐美は想像できるけど、尾形は体が硬そうだなと思いました。
でも猫だから柔らかいのでしょうか。。
鉄棒をする上等兵いいですね。
▶︎兵隊さんたち、真夏でも、詰襟の長袖シャツ(襦袢、と記載ありますが、今でいうシャツの形)を着ているようです。
明治時代、上半身の下着は存在しないのかもしれません。
▶︎宇佐美は二階堂とタメ口で話してますが、尾形は二階堂・谷垣・有子に丁寧語を使われている、さらに谷垣・有子にはやや恐れられている雰囲気だったので、怖い部類の上等兵だったように想像されます。
▶︎上等兵には従者がついていた・・ので尾形・宇佐美にもいたことになります。
かなり近しい関係で、プライベートなところまで(下女であり下男であり子守でありと記載あり)奉公するとのこと。
顔つきの小綺麗な動作の敏捷なるものが選を受ける、とあります🤔
どんな関係のモブがいたのかなと気になります。
▶︎上等兵は中隊で数人とあるので、実際には上等兵ズがつるんだりはあまりできなかったのではないかと思います。
▶︎徴兵時の年齢はかなり差がある様子。
兵営の告白の著者は30歳程度で入隊(長く学問に携わっていたことを示唆する記載あり)しているが、同室は志願兵のまだ子供のような新兵だったので話が合わなかった、とあります。
宇佐美・尾形が上等兵になったのは、比較的若いほうなのでは?(入隊が早いので)
▶︎243話上等兵たち
表紙の宇佐美と 走る中尉と尾形が描かれる
この二人は出会うことはない(宇佐美の頬にペンで描いた時に)と中尉が語っている。宇佐美は中尉と尾形を引き裂くための行動を一貫してとっているのでは?と想像される。
▶︎旅順での宇佐美の言葉「勇作どのが消えれば百之助が父上から寵愛を受け・・」のくだりは、宇佐美が勝手に考えた嘘で、尾形と中尉の間を引き裂くために言った嘘では?
もしくは中尉と結託して、尾形を騙し花沢勇作を消し、尾形をも消す予定だった?
宇佐美視点でも、中尉視点でも、とても本気の言葉とは思えません。
また、尾形が師団長宅で花沢中将を殺したあと、馬車の中で中尉が尾形を褒めますが、宇佐美の目の前でのそのような言動は危険であることを中尉はわかっていたはず?スパイとしての活動から、尾形を消す予定だったのではと想像しました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
