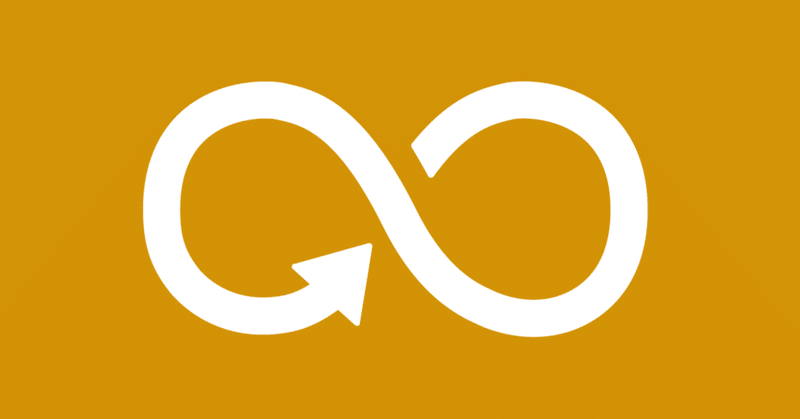
化学産業とSDGs「12.つくる責任つかう責任」
日化協SDGsタスクフォース資料の「関連する化学産業の活動」
レスポンシブル・ケア全般が本目標に関連している。SAICM&GPSにより、製品ライフサイクルにおいて化学物質を管理している。機能性素材・技術により、環境に負荷の少ないプロセスや 省資源プロセスを開発している。廃棄物の再利用や資源化技術により、廃棄物の削減に貢献して いる。
化学物質管理の基本的考え方である「レスポンシブル・ケア」に関連したSDGs目標になります。SDGsの中でも化学産業の責任が問われる面が大きい分野といえるでしょう。
SAICM&GPSについては別のnoteにまとめております。
目標12の具体的なターゲットは以下の11項目です。
12.1 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じる。
12.2 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。
12.3 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、 収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。
12.4 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。
12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。
12.6 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。
12.7 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。
12.8 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフ スタイルに関する情報と意識を持つようにする。
12.a 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援する。
12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。
12.c 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境 への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する化石燃料に対する非効率な補助金を合理化する。
化学産業においては、12.4の「製品ライフサイクルを通じた化学物質や廃棄物の管理」、12.5の「廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用による廃棄物の大幅削減」に真剣に取り組んでいます。
プラスチックごみの行方
皆さんの住んでいる街でもプラスチックの分別収集が行われていると思います。ここで集められたプラスチックごみはどのように処理されているのでしょうか。わかりやすいレポートがありましたので、ご紹介します。これは立川市のプラごみ収集のレポートで、集められたプラごみはポリバケツなどに加工されているとのことですので、「廃プラスチックを原料に別のプラスチック製品を製造する」、すなわちマテリアルリサイクルに該当します。
廃プラスチックのケミカルリサイクル
日本では廃プラスチックはどのように処理されているのでしょうか。日本のプラスチック有効利用率は2019年の実績で「85%」とされていますが、そのうち60%分は「サーマルリサイクル」、すなわち廃プラを燃やして熱エネルギーとして回収しています。燃やすことは二酸化炭素の発生につながるので、世界的にはサーマルリサイクルは好ましくない方法とされ、リサイクルとは見なされない国もあります。

TBSのレポートで紹介されていた「マテリアルリサイクル」は、ポリバケツやプランターなど別のプラ製品に変換する方法ですが、食品容器には使えません。元のプラスチックに戻す「ケミカルリサイクル」はマテリアルリサイクルと異なりバージン品と同じ品質のプラスチックが製造できるので食品容器にも利用できます。欧州では続々とケミカルリサイクルのプラントが建設されています。ドイツのBASFは、2019年、廃プラスチックを熱分解して得られた生成油を商用運転している石油化学コンビナート(スチームクラッカー)に1%の濃度で混入して実証テストを行いました。BASFはこのリサイクルをChemCyclingと称して、サステナビリティ経営の優先順位の高いものに位置付けて推進しています。
住友化学のPMMAケミカルリサイクル
BASFの方法は廃プラスチックをナフサクラッカーのレベルまで戻してしまう方法ですが、樹脂によってはモノマーに戻して再び重合することができます。ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ナイロン6、ポリチレンテレフタレート(PET)、ポリスチレン(PS)などのプラスチックは無酸素条件下の熱分解により解重合してモノマーに分解します。2021年9月、住友化学はアクリル樹脂PMMAのケミカルリサイクル実証設備を愛媛工場に新設しました。22年秋に実証試験に着手し、翌23年にサンプル提供を始める予定とのことです。実証設備では、アクリル樹脂を熱分解してMMAモノマーとして再生します。得られたMMAモノマーを再重合することで、再生アクリル樹脂を製造できます。再生アクリル樹脂の透明性と強度は、化石資源から生成したMMAモノマーを原料とするものと「同水準」(同社)とのことです。
三菱ケミカルの熱分解PMMAリサイクル
三菱ケミカルも、独自の熱分解技術を持つ米国Agilyx社との協業を進めており、オレゴン州にあるAgilyx社のパイロットプラントでアクリル樹脂の解重合技術の実証に成功したことを2021年12月に発表しました。
三菱ケミカルのマイクロ波分解PMMAリサイクル
三菱ケミカルは熱分解にかわる新たなテクノロジーであるマイクロ波分解にも挑戦しています。マイクロ波化学株式会社は三菱ケミカルと協業し、PMMAのケミカルリサイクルの事業化に向け、マイクロ波化学大阪事業所に実証プラントを建設することを2021年5月に発表しました。三菱ケミカルでは2024年の稼働を視野に検討を進めるとのことです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
