
子供の頃を思い出して
昭和8年6月の早朝6時ごろ、私は、京都市上京区の西陣のすこし南側の商家で生れました。家は、帯締めを中心に和装小物の仲卸業を営んでいました。父正一・母やへの四男三女の末っ子です。一番上の姉(すが)とは19歳違いで、私は遅く生まれた子供でした。私の名前は、父が尊敬していた渋沢栄一から、借用して名付けてくれました。
京都の町家の家屋はウナギの寝床と言われますが、私の実家も、確か間口が3間半ほど、奥行きの深い町家でした。二階建てで、一階の間取りは、表通りに面した店の間、中庭のある内玄関、中の間、台所、奥座敷、その奥に、家の外に奥庭と便所がありました。各部屋の横には建物全体を通る通り庭があり、大部分は明かりとりのために吹き抜けとなっていました。二階は、ほぼ一階と同じ間取りでした。便所は家の外でしたので、小さな時には、夜、一人で便所に行くのが怖く感じました。

父・正一

母・やへ

店で仕事をする母 昭和20年代?に撮影
母は、43歳で、自宅の奥座敷で私を出産したそうです。かなり高齢出産でした。父は兵庫県氷上郡市島町喜多の出、母は兵庫県氷上郡春日部村小多利(現春日町)の出で、父母は、明治44年11月に結婚し、大正2年に夫婦で、京都の西陣の南で腰紐、伊達巻などの組紐業を創業し、創業当時はかなり苦労をしたそうですが、その後商売は順調に伸び、帯などの扱い商品も増やし業績も好調で、数人の使用人を使い、私が生まれたころは比較的余裕のある生活ぶりでした。母も商品の仕上げの仕事が忙しく、夜も夜なべの仕事をしていて、家事や育児は女中さんに任せていました。だが私は、夜寝るときは母の布団の中で一緒に寝ていたのをよく覚えています。老舗の和菓子屋の若狭屋さんがよく見本を持って御用聞きにきていました。大好きなビロードの服を好んで着ていました。どうも末っ子で、甘やかされて、なんの不自由なく育てられたようです。毎年夏になると、1ヶ月ほど丹後由良海岸海水浴場に、民家の2階を借り切って、家族で夏を過ごすのが常でした。特に二人の姉からは、大変かわいがってもらいました。

丹後由良海水浴場にて、左から兄(3男)、私、母、姉(3女)、姉(次女)です。
幼稚園は1年間でしたが、北野神社の近くの北野幼稚園に通っていました。紅葉組で粂田正子先生のクラスでお世話になりました。虫を捕ろうとして急に飛び出しブランコに頭をあてられ、何針かぬう怪我をした事件のことはよく覚えています。

小学校入学記念写真 昭和15年(1940年)4月ごろ
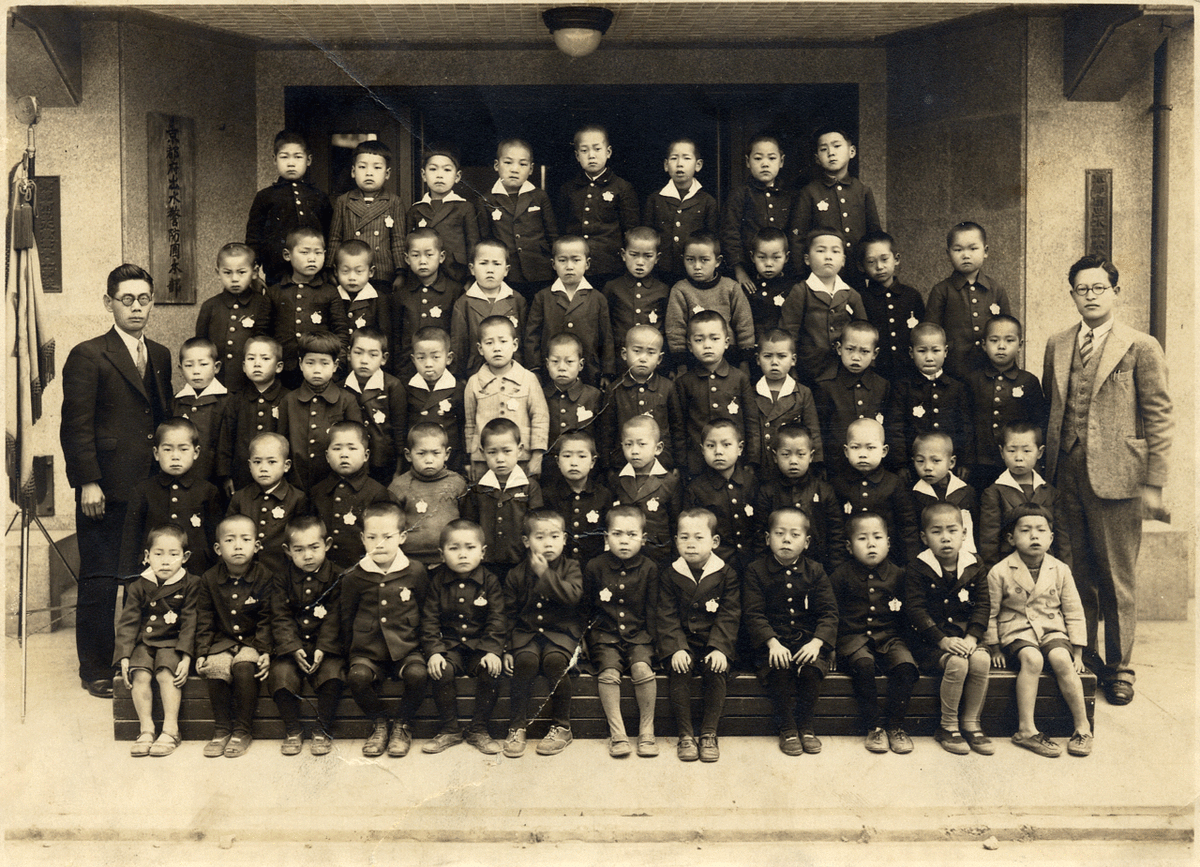
出水小学校1年生のクラスメートとの記念写真
昭和15年4月に地域の尋常小学校(出水小学校)に入学しました。当時は、男子3クラス、女子3クラスの男女別のクラス分けでした。すぐに翌年の昭和16年4月からは国民学校令が出て国民学校に変わりました。同年12月には太平洋戦争に突入しました。子供もみんな国民服を着せられ、カーキ色の帽子をかぶっていました。富国強兵のための軍国主義教育となりました。教育勅語も暗記させられました。また天皇制護持で、神武天皇から昭和天皇まで歴代の天皇の名前を暗記させられました。「鬼畜米英」のスローガンを、よく見かけました。だが放課後は、隣近所の子供達でよく遊んでいました。メンコ、ビー玉、トンボとり、かくれんぼなどで遊んでいたことをよく覚えています。よく近くの広場の池に来るトンボを網で追いかけていました。ときには二条城までトンボとりに出かけていました。5年生から森木滋先生が担任になられました。国語が専門でした。森木先生には、終戦後も卒業の時まで担当して頂き、卒業後も同窓会などで、長いお付き合いを頂きました。ずーと後のことですが、一度森木先生が、三鷹の私の家まで訪ねて下さったこともありました。当時、私は、週に一回、下立売通り日暮通り(?)角にあるお寺に、習字を習いに行っていました。戦争が激しくなり、習字は2年間ほどで、残念ながら続けることが出来ませんでした。段々お菓子がなくなり、甘いものとしては、干しバナナを一時期よく食べていた記憶があります。それも長くは続かなかったようです。食べ盛りの子供にとっては、厳しい状況でした。

父と兄弟 前列左から父、と私4男。後列左から長男、3男、次男。撮影は、昭和17年ごろと推定。

小学校5年生ごろの私 昭和18年ごろと推定。

姉・次女・美代子 昭和17年ごろと推定

姉・3女・禮子 昭和17年ごろと推定
昭和19年には、長女(すが)と次女(美代子)はすでに結婚していましたので、京都には住んでいませんでした。また長男正次朗と次男敏郎は徴用でそれぞれ舞鶴と能登で勤務のため京都を離れていました。3男徳雄は兵役で中国大陸を転戦していました。京都に住んでいたのは、父母と3女禮子と私だけでした。段々と戦況が悪くなり、本土空襲の危険が増したため、昭和20年、6年生になる直前の3月31日に小学生の集団疎開が始まり、私は京都府宮津市の如願寺に学童疎開をしました。担任の森木滋先生が引率して、宮津まで汽車で移動しました。そこから半年の間、宮津小学校に徒歩で通学しました。食料事情が悪く、ひもじく厳しい日々でした。

疎開先の如願寺の山門
7月30日昼頃、お寺のすぐ近くを何度も敵機が低空から機銃掃射をしてきました。すごい音で、生きた心地はしませんでした。終戦の詔勅は、集団疎開先の宮津市のお寺(仏性寺)に集められ、みんなで聴きました。暑い夏の日でした。戦争が終わってもすぐには京都に帰れず、秋になってから集団疎開先の宮津からから京都に帰ってきました。

小学校6年生の卒業記念写真 昭和21年(1946年)3月撮影
戦争がおわりますと、長男正次朗は、すぐに舞鶴から帰って来ました。次いで3男徳雄が大陸から復員し、しばらくして次男敏郎も能登から帰って来ました。兄弟3人で、戦前の組紐の商売を復活しました。もの不足の時代なのでよく売れて、よく儲かりました。私は、翌昭和21年4月旧制の京都府立第3中学校(現山城高校)に進学しました。旧制の中学校は、府立中学校、府立高等女学校、私立高等女学校、市立商業学校、工業工業学校からなっていました。出水小学校の同じクラスでは府立中学校に進学できたのは私一人だけでした。昭和22年(1947年)GHQの命令で、大きな学制改革があり、633制に成りました。昭和23年(1948年)4月から現在の高等学校が発足しました。高校3原則(男女共学、総合制、学区制)が実施され、また新制中学の校舎が足りず、半年ほどの間、午前午後の二部制となり、同じ学校を二つの新制高校が使用しました。学校により、授業は午前だけや、午後だけとなり、とても変則な状況でした。
私は、昭和23年(10948年)秋には、新制の朱雀高校併設中学3年に編入されました。朱雀高校は、元の京都府立第2高等女学校の校舎を使っていました。位置は二条城のすぐ西側にありました。これまで旧制高等女学校だつたので、丁寧に使われ、古のですが、綺麗な木造の校舎でしたが、みるみる汚くなりました。また生徒用の男子トイレが設置されていず、しばらくは校舎の横に並べられた肥桶で用をたすという今では考えられないことが行われていました。しかも男女共学となり、いろいろな部活動などが活発に行われ、自由な雰囲気でした。授業の内容も大きく変わりました。ホームルームが導入され、クラスが集まり話し合う場でした。

当時、家業の株式会社安達商店で、なんとかかき集めて野球チームをつくって、みんなで一緒に野球に汗を流しました。野球場として御所の中の広い通りが一般に開放されていました。

修学旅行の四国で撮影 右端に私
高等学校では、私は親の勧めで商業過程の科目も一部とり、簿記を選択しました。急な改革で、すこし混乱し気味な雰囲気の時期でした。秋には全国共通の「大学進学適正試験」が実施され、国公立大学を受験するものは一定のレベル以上の成績をとることが要求されていました。朱雀高校は、当時現役の京大合格者が40名ほどと多く出ていて、レベルは高い学校でした。幸い私も高校3年生最後の1年間は、猛勉強をした結果、なんとか「大学進学適正試験」では、受験できる成績をとっていたので、親からも経済学部ならよいと云われ京都大学経済学部を受験をしました。我々の年度から初めて修学旅行も実施され、2泊3日で、四国の金比羅宮に出かけることができました。そして無事朱雀高校の第4期卒業生となれました。また、好運にも京都大学経済学部の入学試験に合格しました。

昭和27年(1952年)4月京都大学入学記念
家業の安達商店の70年のあゆみをまとめたものがありますので、添付します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
