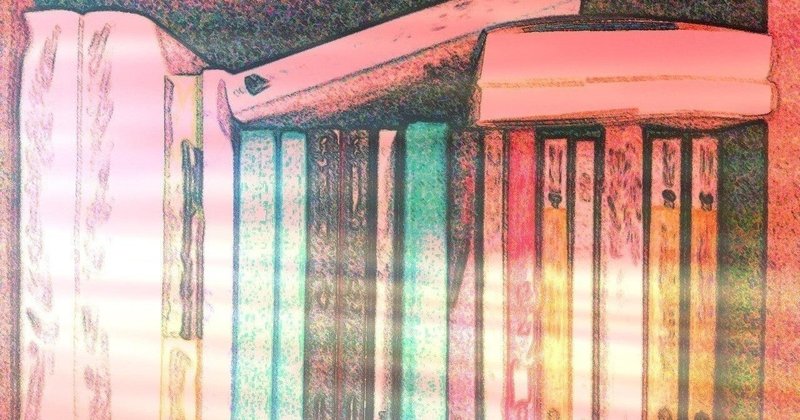
関口安義著 評伝・松岡譲 の検証3
前回は『評伝・松岡譲』の的外れな久米批判について検証してみた。
今回は、久米に関する記述も含めて不自然だと思う点について指摘してゆこうと思う。
10年の忍耐の沈黙という欺瞞
まず、松岡が結婚後10年の沈黙を誓ったという内容の記述。まずこれが守られていない。法城を護る人々は結婚後5年目程で書かれている。この発言を、久米に対するものだとする意見もあるようだ。何を言われても我慢、結婚後10年は忍耐を重ねたというものだ。しかし松岡は自著の中で長女が『あんな悪い人の子供と遊んではいけない』と言われて目の前で連れ去られことがあり、それは久米の破船のせいだと妄信する。そしていつか自分も自分側からの目線で書こうと思った、と書いている。
久米が破船を書いたのが松岡が結婚して4年後。この時、長女は2歳だ。長女が目の前で連れ去られたのが5歳だったというから3年後のことになる。
この時点で、結婚後7年。この時点で憂鬱な愛人を書く決意をする。準備期間を入れると、長女の件があってからほぼすぐに執筆の構想を練ったと考えてよいだろう。憂鬱な愛人が発表されたのがたまたま結婚後10年だったというだけで、別段松岡はその人格の高さから忍耐と沈黙を続けたわけではないのだ。
モデル小説であるという紛れもない事実
次に、この憂鬱な愛人の宣伝方法で雑誌社と揉めたという点。
モデル小説と言われることを嫌った。宣伝に妻筆子の写真まで使われたことに怒ったとある。確かに勝手に写真まで使うのは感心しないが、久米の破船に対抗して書いた以上、モデル小説と言われるのが嫌だというのはおかしな話だ。だったら書かなければよかったというより他無い。松岡はこの件の関して『自分の結婚問題に取材はするが、あくまで実話ではなく文学作品として書くつもりだ』と話したという。これもまた後の随筆と矛盾する。松岡は長女が友人と遊ばせて貰えないことを久米のせいだと盲信し、『いつか自分の側から見たこの事件を書いてやろうと思った。』と記述している。つまりはモデル小説に他ならない。要するに、久米に仕返しはしたいけれど、そういう俗悪な自分を受け入れられないのだ。筆子との結婚時、親友であった久米との対話から逃げた松岡は、ここでもまた自分と向き合うことから逃げてしまう。
それにしても、関口氏の主張は不自然だ。この松岡がモデル小説と扱われるのを嫌ったとしつつも、その僅か数ページ後に、『いうまでもなく漱石山房を舞台とした恋愛小説である』とモデル小説であることを認めているのだ。この人物は、持論の一貫性のなさへの自覚はあるのだろうか?
憂鬱な愛人と後の記述の矛盾点
そしてこの憂鬱な愛人の内容がまたきな臭いものがある。松岡は晩年の随筆で『久米が一方的に筆子にのぼせ上っていた。しかし筆子が愛しているのは自分だと知らされた』と書いている。まるで、自分は筆子には何も魅力を感じていなかったかのような書き方だ。そしてそれを後押しするかのように、筆子もまた、娘である半藤茉莉子氏に『私からお父さんを好きになったの。好きで結婚してもらったの。』と語り続けたという。この『松岡にとっては筆子は恩師の娘で雲の上の女性であり、久米は身の程知らずにのぼせ上った。しかし筆子は松岡を愛していた。』という筋書きを押し通そうとしている。しかしこの、憂鬱な愛人によると久米から筆子への恋愛感情を相談されたとたんに、自分もまた筆子を異性として意識し恋したとある。
いう事がまるで違うのだ。おそらく、憂鬱な愛人で正直に書いてしまったために世間の顰蹙を買ったのだろう。松岡は親友の婚約者を横取りした男。筆子は婚約者の親友に乗り換えた女。それを打ち消すために話を作り替えてしまった。そういう所でのこの夫婦の協力体制は凄い。いかに『自分たちを被害者ポジションにするか』という事にだけは非常に長けているのだ。
余談だが、その後、松岡は長女を知人にあづけて久米に合わせるという事をしている。長女10歳頃のことだという。久米はその時の事を随筆に書き、長女が『私がだれだか分かってきているのかと思ったが、分からないようだった』とあいまいな書き方をしている。これは、破船で長女が傷ついた(と松岡が思い込み吹聴している)ことを指すのではないか。松岡は、この事を読売新聞で語っている。つまり久米がこの件を知っているという前提で、あえて長女だけを久米に会わせた。子供を使った嫌がらせ、仕返しだ。それを受けて久米は、(かつての門下生の先輩たちに誘われたにも関わらず)漱石の20回忌に行くことができない。
『われわれは先生が一番嫌がる事をしたのだ』と綴っている。久米一人が責を負う事ではないはずだが、子供まで巻き込んでしまったことに深い悲しみを覚えたようだ。なお、久米が破船を書いた理由については後日考察する。
焼いたはずの手紙の謎
松岡の言動できな臭い点はまだある。前回、久米を中傷する手紙が夏目家に届いたという件は書いた。破船にもその描写があるが、松岡はどさくさに紛れてその手紙を預かる。松岡は晩年この手紙の主はYという作家であるとし、この手紙は焼き捨てたと明記した。しかし関口氏はこの手紙は筆子が保管しており、実際に読んだと明記しているのである。つまり、焼き捨てたというのは嘘なのだ。もともと、この手紙に関する松岡の記述は疑問点が多い。Yという作家としているが、その作家は夏目門下生ではない。久米と筆子の婚約の件は夏目家の親族とその門下生しか知らない事であり、蚊帳の外であったYは知る由もなかったはずだ。もし知っていたというのならば、共通の知人が意図的に話したことになる。また、この中傷の手紙は門下生の先輩たちにも同じものが数通来ていたそうだ。Yが、そこまで夏目門下生の動向や住所まで把握していたとは考えにくい。
そして、この嘘である。
松岡の言動には一貫性がない。関口氏は骨太の作家とひたすら持ち上げているが、果たしてそれほどの人物かどうかは疑問が残る。尚、前回書いた『久米が筆子の同級生の名を騙って松岡を中傷する手紙を書いた』という件で、現物が残っていないのおかしいと指摘したのはこの件に由来する。
芥川、漱石との関わり
また、関口氏は松岡の芥川評を持ち上げているが、これは芥川理解の一助にもならない。芥川理解には、天才の誉の影で抱えた孤独と苦悩への理解が必須だが、松岡にはそれがなく、芥川を超然としていたと表するのみである。この、芥川の内面に全く切り込まない一文のどこに称賛のポイントがあるのだろうか。
松岡には夏目漱石の名を冠した著作が多い。それもまたべた褒めに褒めている。しかし私に言わせれば、生前ほとんど交流の無かった義父の名を借りて商売しているに過ぎない。義父の名を借りなければ、随筆集一つ出せない作家なのだ。義母である鏡子から聞き取って書いた『夏目漱石の思い出』は漱石門下生の猛反発をくらったが、当然だろう。ここには、漱石から鏡子へのDVが書かれている。漱石の遺産で自著の人気を偽装しただけでは飽き足らず、今度は証拠もない中傷をするのかー。門下生先輩たちからの反発は、単に恩師漱石の醜聞を広められたからだけではないように思える。(なお、久米はかつては筆子との婚約を門下生先輩たちに猛反対されたが、この時期に謝罪を受けており、対照的だ。)
松岡の『漱石の遺産食い』はこれに留まらない。一時期、金銭的に窮した松岡は得意の書を売って生活の足しにしたという。しかしそれは『松岡譲の書』だから売れたのではない。市場に出回っている松岡の書を見たが、漱石の漢詩だった。つまり『夏目漱石の漢詩』だから売れたのだ。漱石の著作権を受け取り、徹底的に義父の遺産を食った娘婿だったのだ。
また昭和6年に出た『明治大正文学全集41』に松岡作品が収録されていることに触れ、発行元の春陽堂が生前の漱石と深い仲であったため、娘婿である松岡を無視できなかったと記述している。つまり松岡は作家としての実力ではなく、義父の恩恵を預かる形で採用されたのだ。
第一書房閉鎖を絶賛する事への疑問
松岡はその著書全てを、第一書房という出版社から出版していた。ここを運営していた長谷川が、突然出版社を閉鎖したという。投資者はおろか、長年一緒に仕事をして来た松岡にも、他の社員にも一切の断りが無かったという。関口氏はこの件を英断と絶讚しているが、果たしてそうであろうか。ずっと第一書房から出版していた松岡は、出版先を失う。戦後、多くの人が活字に飢えた中なら松岡の作品も出せば売れたかもしれないが、それが出来ない。結果、松岡一家は疎開先の長岡で雨漏りのするような家に転がり込むことになる。それでも家があるならまだマシで、戦後の住宅難の中で立ち退きを迫られ、家財道具を放り出されたことさえあるのだという。それでもこの人物は松岡に手を差し伸べることはなかった。それが、『死後も友情が続いた』と美談にするには無理があるのではないだろうか。関口氏は松岡作品が残らなかった事を延々と久米が悪いと書き続けている。久米が松岡を文壇から抹殺しようとしたかのようだ、とまで書いている。しかし真に松岡を文壇から抹殺したのは、この長谷川では無かったか。最も、松岡が認められなかったのは一重に作家としての力量に問題があったと言わざる得ない。松岡作品については、後日検証する。
この本は評伝と言えないのではないか?
その他にも、筆子を芯の強い女性であると非常に行数を割いて描いている割には、具体的なエピソードがない。鏡子は肉親が誉めるからいい人だと断定する。松岡への批判的な批評は、その内容を検討することもせずにピント外れと断罪するなど、評伝としては非常に不完全な面が多い事を指摘しておこうと思う。関口氏は『久米の失恋小説には理解を示したが、漱石山房の書斎に納まった松岡には嫉視と反感以外のものは持ち得なかった』と語る。しかしそれは単に、久米が作家としての力量が抜きん出いたから評価されただけに過ぎない。松岡が義父の名を借りただけの作家であることは、既に述べた。関口氏がここまで松岡に執着する理由が理解できない。関口氏は多くの著書が有りながら、評価は低い。そんな自身を、松岡に重ねているのだろうか。この『評伝』は巧妙に隠された、関口氏の劣等感の投影ではないか。これをもって評伝と呼ぶにはあまりに無理がある。内容が片寄りすぎている。人が文章を書く際、自らの深層心理から逃げることは出来ないのは無理からぬ事だ。そこに文芸の面白さと怖さがある。
尚、鏡子夫人に関しては別に論じられるべきであろう。
参考文献
評伝・松岡譲 関口安義著 株式会社小沢書店
漱石の印税帳 松岡譲著
夏目家の糠みそ 半藤茉莉子著
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
