
BCPを一人で作れるのか
BCPの策定で悩まれている方は多くおられることでしょう
ひな形を基に作り上げることができるのか…
策定だけならまだしも、運用とか研修とか言われても…
そもそも、事業主や担当者だけで何とかなるのだろうか…
…などなどの悩みがあろうかと思います
その先には、"自分だけでBCPを作り上げられるのか?" でしょう
今回は、BCPの策定や運用を "一人だけでできるのか" についてお話します
■ 一人だけでもできます
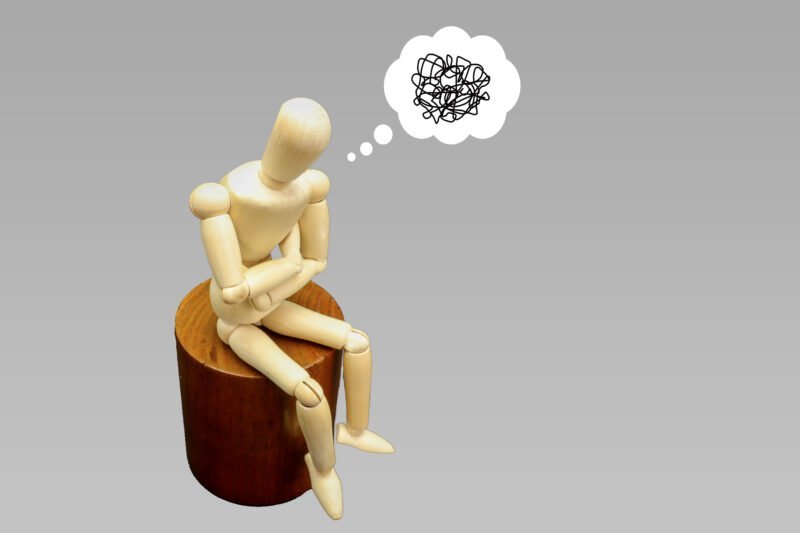
結論として、条件が整っていれば一人でも作り上げられます
その条件とは、次のいずれかの場合となります
① 非常事態の経験と教訓があり、現在の事業に反映できている場合
事業の経営・継続の方針が明確で、行うべき事項が平素の業務に浸透・定着している状態
⇒ 現在の運営・経営戦略や行っている施策を書面化するだけです
② 自分らの事業の運営や経営、危機管理について精通している場合
事業の経営・継続の方針が明確で、BCPの策定に必要な情報や知識が十分にある状態
⇒ 事業体質や脅威リスクなどの分析、施策導出の作業を経て書面化する
③ 非常事態発生で受ける影響を理解し、初期の対処態勢はとりあえずできている場合
災害等の発生当初には対応できるが、その後の対処は臨機応変としている状態
⇒ 初期対処の方針や要領が中心に書き込まれた "単なる防災計画" として書面化
④ 計画書としての形式・体裁さえ整っていれば良い場合
事業の経営・継続の方針がなく、情報や知識もない・乏しい状態
⇒ ひな形を入手して、空欄に記載する事項を考えて書き込むことで完成
①②と③④は、非常事態における事業継続の計画として、次のような特性となりがちです
事業継続のために何をすべきかの指針・参考となるもの
使える・使うBCP=①②事業継続の計画書という形だけのもの
使えない・使わないBCP=③④
上記のいずれかとなります
極端と思われそうですが、この2種類しかありません
結論として、一人だけでもBCPを作り上げることは可能です
ですが、どちらのBCPを作りたいかは、みなさんの考え方次第です
■ やっぱり複数で
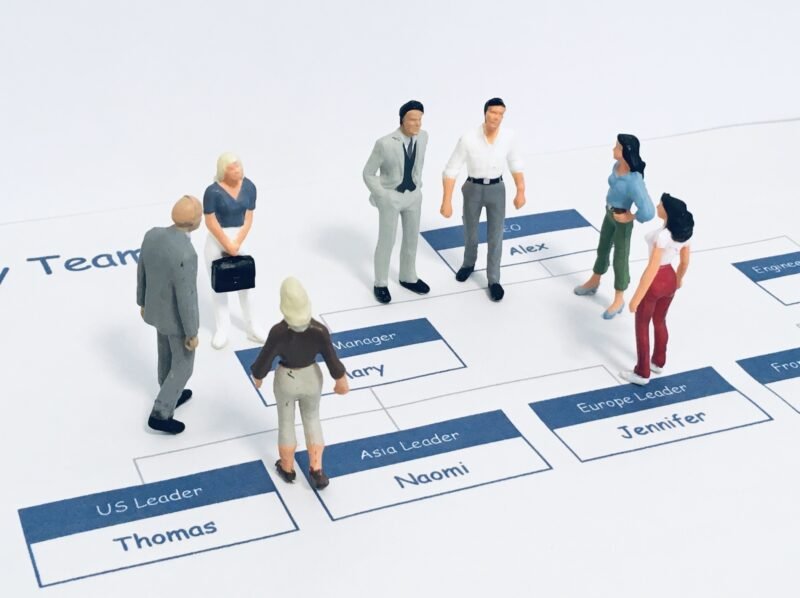
一人でもBCPを "作成" することはできます
でも、"策定" となると、それなりに使える・頼りになる内容が必要です
非常時の事業の運営・経営は、事業主が責任を負いますが、非常時に所在しているとは限りません
場合によっては、職員だけで物事を判断して重要な業務を継続させる必要が出てきます
そんな時の参考・より所となるのがBCPですが
事業に携わる人々が見て、何をすればよいかが分かる内容である必要があります
ということは、事業主や担当者だけの目線で策定された内容だと不足・不十が生起します
例えば…
現状・実情とかけ離れた内容
業務処理上の細かな注意点などが欠落
重要業務を支える資器材の細かな種類や数量が不明確知らないリスクやアイデア
事業の脅威となるリスクが限定されることによる対策不足
もっと良いアイデアがあるのに、わざわざ効果が小さな施策を選ぶ内容や用語が分からない
策定を担当した人にしか理解できていない内容や用語そもそも、必要性が感じられない
BCPの存在意義(目的、目標など)が全員に伝わっていない
BCPの存在すら浸透しない・忘れ去られる
BCPは、一人でも作れます
ですが、事業に携わる全員が使えるBCPにするには、全員の知見や経験が必要です
"三人集まれば文殊の知恵" のとおり、やっぱり複数でBCPを策定するのが良策です
策定と作成の作業を分担することもできますので、時間と労力の効率化も図れます
そして、"非常時の事業継続" という戦略や方針を策定作業を通じて皆で共有できます
また、事業主・担当者だけに業務負担が集中するのも避けることができます
やっぱり複数名で、可能が限り、全員の知見や経験を加味することが良いでしょう
■ 限られる人数と労力で

日頃の業務で忙しく、BCPの策定という新たな業務を行う時間と労力がないかもしれません
更に、職員・従業員の人数や能力、勤務時間上の制約もあることでしょう
そうなれば、できる範囲で・できることから進めるしかありません
そこで活用するのが "ひな形" です
ひな形には、BCPを機能させるために必要となる事項が列挙されています
既に骨組みができていますので、肉付け作業をするだけです
事業主さんのほか、ナンバー2の人、現場のリーダー的な人の3名だけだったとしても
・今週は、ひな形の中のこの項目を、それぞれに考えてみて
・来週末までに、Aさんは〇〇、Bさんは□□を考えてみて
などと、共同・分担で作業を繰り返します
その後、3名のほか、他の職員を集めた会議を行って内容を精査するようにします
完ぺきではなくても、それなりに使える内容が作れるかと思います
人数などが限られるなら、策定作業の項目を細かくし、時間、人数又は労力で分割して進める方が効率的でしょう
一人でやるよりは複数名が効果的、複数名でも時間、人数又は労力で分ければ個人への負荷が分散できます
■ BCPにも共助の考え

障害福祉サービス事業や介護事業は、法人として組織化されています
また、虐待防止委員会や感染対策委員会などの設置が義務付けされています
ということは、事業の運営・経営には、事業主以外に主要なメンバーが参画しています
また、事業所によっては、部外のメンバー(顧問や弁護士など)も参画しているでしょう
それらの主要メンバーをBCPの策定と運用の支援者として加えることもアリでしょう
加えて、提携先や取引先などの密接な関係にある事業者との協力・協同も考えておくと良いでしょう
災害事態下で事業継続に必須の資材の優先納入などに関する取引業者との非常時契約の締結
自分らの事業施設を福祉避難所として運用する旨の行政との協定の締結
緊急避難行動を他の事業所と共同して行う旨の申し合わせ
報酬請求業務を委託している業者との間の災害時業務の申し合わせ
非常事態の発生に備え、自分らの活動のほか、他事業者との連携・協同は非常に有効な手段です
防災の対策・対処における "自助・共助・公助" の概念でいうところの "共助" に当たります
平素からの関係や仕組みを作っておくことも、事業継続のための恒常業務と捉える方が良いでしょう
■ まとめ

事業主・担当者一人だけでBCPを作れるか
→ 作ることは可能であるが、容易ではない
→ 形式的なBCPでは、非常事態下では使いものにならない
★やっぱり、複数名で作り上げる方が "使えるBCP” を効率よく作れる
他事業者や行政との平素からの関係作りも事業継続のために必要な活動
防災における "共助" の概念をBCPにも取り入れる方が良い
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
