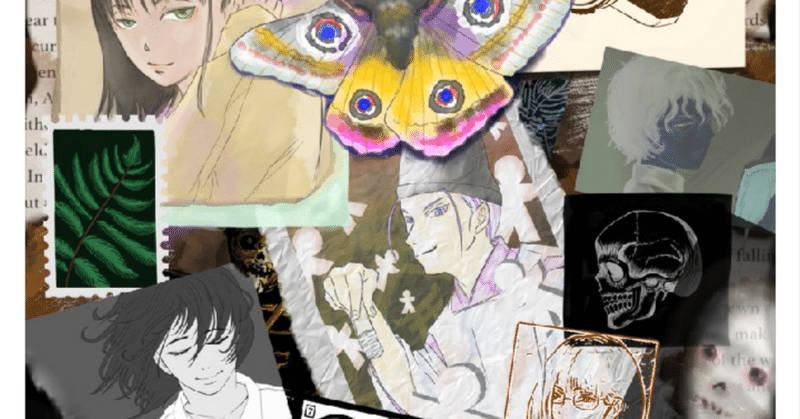
オカルテット5 回顧
主要登場人物



五 回顧
「あんたと初めて会ったのは、舞狗市の商店街の一角にある空きガレージだったわね。廃校になった小学校の椅子と机並べて、表に『町の便利屋』って手作り感が満載の看板が立ってて」
「おうよ。えーっと、保志さん⸺」
「星冶で構いませんよ。お二人のほうが年上ですし、さん付けは無しで。鵜ノ目さんも」
「じゃあ、私のことも冴歌って呼んでちょうだい」
三人は今やすっかり打ち解けている。
「なんか、小学生のガキが初めて会って、『お友達になろうよ』みたいなノリだな」
「そうですね!」
「え? 何それ?」
星冶が賛同して、冴歌が首をかしげる。
「あぁ、そうか。オマエは学生時代、ずっとボッチだったんだっけ?」
意地を突くような言い方をされ、「私には一人でいる時間のほうが性に合ってたの!」と答える。半分は本当で、半分は嘘だ。
ふーんと、何か裏があるのではと探るような相槌を打つと、大和は星冶に話を振る。
「さっき言いかけたのは、星冶はオレの昔話に興味があるのかってことなんだけど」
「はい! ものすごく興味があります」 精一杯の元気を見せるその顔色はまずまずだ。
「まず、オレは中卒だ。オレには学ってやつがなかったからな。入学したのは俗に言う底辺校で、ヤンキーどもの集まりだった。んで、オレは入学して間もなくタバコを吸い始めた。顔だけはイカついからな、いわゆる顔パスってやつだ」
「こいつ、すごくタバコ臭いでしょ? そこからはもうヘビースモーカーまっしぐらよ」
「それがオトナだって思ってたからな」
意外にも、冴歌に食って掛からない。
「入学早々、『一年坊主のくせにタバコなんて生意気だ』って親玉だった三年に絡まれたが、返り討ちにしてやったんだ」
「空手とか何か武道はやってたんですか?」
「いや。習い事なんてモンはしたことねぇな。喧嘩も自己流だ」
左頬を撫でるように触れる姿を、冴歌はしかと見た。
「また癖が出てる……」「あ? なんか言ったか?」
「いえ。どうぞ続けて」と先を促す。
「ダチや後輩たちを連れて夜な夜な遊びに繰り出していたが、卒業と同時に足を洗った」
「何かきっかけがあったんですか?」
「それ! 私も興味あるわ! あんたなら、今頃どっかの暴走族の総長でもやってそうなのに」
テーブルに肘をついてカフェオレを飲みつつ聞いていた冴歌が、大和に体を向ける。アイコンタクトはなく、目線は首のあたり。
敢えて暴走族や総長という言葉を出してみたが、今日も彼はきまりが悪そうに押し黙るだけだ。冴歌は首を左右に振り、ため息をついた。
「ヤンキーは平気なのに、暴走族だとか総長って言うといつも黙るわよね? まあ、誰だって言いたくないことの一つや二つはあるでしょうから、これ以上は突っ込まないけど」
冴歌はまたテーブルに肘をつくと、話題を変えることにした。
「髪色の呼ばれ方にこだわりがあって、ピンクパープルって言わないと怒りだすのよ。なんでも、中学校に上がる頃からずっとこの色らしいし」
「行きつけの美容院があるんだよ。ダチの母ちゃんがやってる」
「さすがに大和さんみたいな髪にする勇気はないですけど、金髪も目立つからって理由で、僕なんかせいぜい明るめの茶髪ですよ」
「いいんじゃねーか? それぞれ、表現したいものが違っても」
「あら。名言のつもり?」
返事をしたのは大和のお腹の音だった。
「テキトーに昼飯済ませたから、食い足りねぇって」
何か作りましょうかと、立ち上がる星冶を大和は制する。
「俺の昔話をざっくり言うと、不良の道から足を洗って、罪滅ぼしに町の便利屋を名乗るようになったってことだ」
「かなりざっくりね」
「で? オマエは星冶に話したのか?」
「昔話? そういえばしてなかったわね。私は、二十云年来から『超常現象さあくる』を利用していたのよ。今ほどマメにチェックしてたわけじゃないけど」
「昔のことは詳しくは知らねーけど、今のコイツは、下手すりゃ『超常現象さあくる』に一日じゅう張りついてるんだとよ」
「おかげさまで、星冶くんに会うまでほぼ引きこもりだったわ」
「いや。出会う前からすでに引きこもりだっただろうが」
「はいはい、いちいち茶々入れないで。長くなるから端折るけど、十五年前、『超常現象さあくる』を介して、とある女性の刑事さんに出会ったの。紆余曲折あって、私はその刑事さんから捜査ファイルを託された」
「刑事さんから捜査ファイルを!? 親御さんが警察関係の人とか?」
「残念ながら、私の両親は物心がつく頃に亡くなってるわ」
刹那、重たい空気が流れる。
「知らなかったとはいえ、すみません……」
「気にしないで。それから私は、ちょっと……いえ、だいぶ変わり者の弁護士の事務所にお世話になったの。その弁護士先生が里親を見つけてくれたのよ」
「その里親ってのがすげー金持ちなんだよな?」
「ええ。ビル一棟を生前贈与してくれたくらいには」
星冶は目を丸くして、「す、すごい……」とつぶやいた。
「子どもがいなかったこともあってか、私が何一つ不自由なく暮らしていけるようにしてくれたけど、それがかえって申し訳なくてね」
冴歌の目に宿る憂い。
「微々たるものだけど、十三歳から始めた新聞配達のバイト代も『冴歌の好きなように使いなさい』って一切受け取らなかった。大学にまで通わせてくれて、卒業してからはそのビルを生活拠点にさせているわ。ま、こんなとこかしら。星冶くんは?」
「僕ですか……。普通に大学生してますけど」
「たしか、彼女さんがいるって言ってたわよね?」
「お、リア充かよ。ま、モテそうではあるもんな。顔もそうだけど、どっちかっつーと行動でモテるタイプ」
そう言うと、大和はカフェオレを呷った。
「そうね。あんたと違ってね。というか、お酒じゃあるまいし、もっと味わって飲みなさいよ」
「ちびちび飲むのは性に合わねーんだよ。そう言うオマエだって、交際の経験で言えば、オマエだってゼロだろうが!」
「はいはい、そうでした。話を中断させちゃったわね。先を続けて?」
「高校に入ってわりとすぐに交際し始めたんです。でも、こっちに越してきてからは遠くなったので、一か月に三回程度会うくらいですけど。そのほかは、取り立ててお話しするようなこともないかなぁ」
「今後もその彼女さんとうまくいくといいわね」
「ありがとうございます、冴歌さん」
「さてと。いつまでもここで厄介になるわけにいかねーし、そろそろ行かねぇと」
「あ! それじゃあ、これどうぞ」と星冶が差し出したのは、依頼の報酬であるバナナうなぎ餅のセットだった。
驚いたのは冴歌だ。
「けっきょく原因を解明できなかったのに受け取れないわ!」
垂涎の的には違いないが、きっぱり断る。
「……バナナうなぎ餅に釣られたのか、オマエ。バナナうなぎ餅ホイホイじゃねーか」ため息まじりの大和に対し、
「だって、報酬にファミリーサイズ一箱をお願いしたら、商店街の福引で十箱当たったって言うから……。星冶くん、甘いものが苦手で困ってるって言ってたし」
と、言い訳がましくモジモジしながら答える。
「こちらが義務を果たしていない以上、それは受け取れないわ。だから……。代わりにどうぞ」
冴歌が手渡したのは一枚のメモ。
「ここ、私の事務所っていうか、活動拠点にしているビルの住所。何かあったらいつでも来てね。本当は電話番号も教えたいんだけど……」
そこで、冴歌はちらりと大和の胸元に視線を送る。
「こいつは機械音痴で、扱えるのはノートパソコンと、じいちゃんとの思い出だっつーゴツくて古めかしいカメラくらいなんだよ。だから、これはオレの電話番号」
冴歌の視線に気がついた大和が助け舟を出す。
「お二人とも、今日は本当にありがとうございました!」
星冶は深々とお辞儀をする。
「星冶くん。この案件、絶対に解決してみせるから!」
「オレも冴歌と同じ思いだ。だから、一人で抱え込むなよ?」
「長居しちゃってごめんなさいね。行きましょう、大和。お邪魔しました」
「その……部屋に入るなり、胸ぐらつかんで悪かったな。あ、脱ぎっぱの服くれねぇか?」
大和は受け取ったずぶ濡れの服をきれいにたたみ、大きめのレジ袋に入れた。
「あんたってガサツに見えて、意外とそういうところはしっかりしてるわよね」
三和土で靴のつま先をトントン言わせながら冴歌が言うと、
「ふふん。オレさまはそんじょそこらの男どもとは違うからな!」誇ったような声が返ってくる。
「まーた、すぐ調子に乗るんだから」
「星冶、近いうちにジャージを返しに行くから。それからいつでも連絡寄越せよ? コイツ共々いろいろ世話になったな」
星冶のお礼の言葉を背中に、二人は土砂降りの雨の中を歩いていく。
「はぁ。まさかオマエと相合傘をするハメになるとはな」
「嫌なら、また濡れねずみにでもなる?」
「そりゃ勘弁だな」と苦笑いの大和。
「絶対に解決してみせるって言い切ったものの、どうしたものかしら……」
「ふふん! ここでオレの出番だな。三上神社はオマエも知ってるだろ?」
「もちろん。それがどうしたの?」
「そこに霊視、幽霊が視えるっていう神主がいるっつー話があるんだよ」
「それこそガセネタじゃないの?」
冴歌は渋い顔をする。
「まぁ、オレも実際にソイツに会って確かめたわけじゃねーけどさ。星冶の案件が行き詰まってる今、ソイツに賭けてみねーか?」
黙り込んでいると、
「いいのか? オマエの大好物三百個が懸かってるんだぜ?」
と大和が意地悪く笑うものだから、言葉を詰まらせてしまう。
「今から行くの?」
「バカ言え。こんな悪天候の中、あんな奥深い森に行けるかよ。……んーと、あさってなら晴れるみてーだな」
スマホをいじっている大和の横で、冴歌は昔のことを思い出していた。
自分は四歳くらいで、まだ祖父が病床に臥す前の話だ。
「おじいちゃん……。たしか、こう言ってわ。『冴歌。お前はこれからたくさんいろんなことを見たり聞いたりしていくだろうけど、目に見えるものだけがすべてじゃないんだよ』って」
大和には聞こえず、大雨にかき消されていく言葉たちを冴歌は一人噛みしめる。当時こそ、その意味は解らなかった。だが、大人になった今なら解る。
大和の言うように、星冶の案件が壁にぶつかっているのも確かだ。一か八か、賭けてみてもいいかもしれない。
「わかったわ。これから事務所に戻って、少し調べてみましょう。あんたも来るわよね?」
「もちろんだ」
「じゃあ急がないと!」そう言って駆け出す冴歌。
「待て、またオレを濡れねずみにさせる気か!」
彼女の後ろ姿を、大雨に負けないくらいの大和の声が追う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
