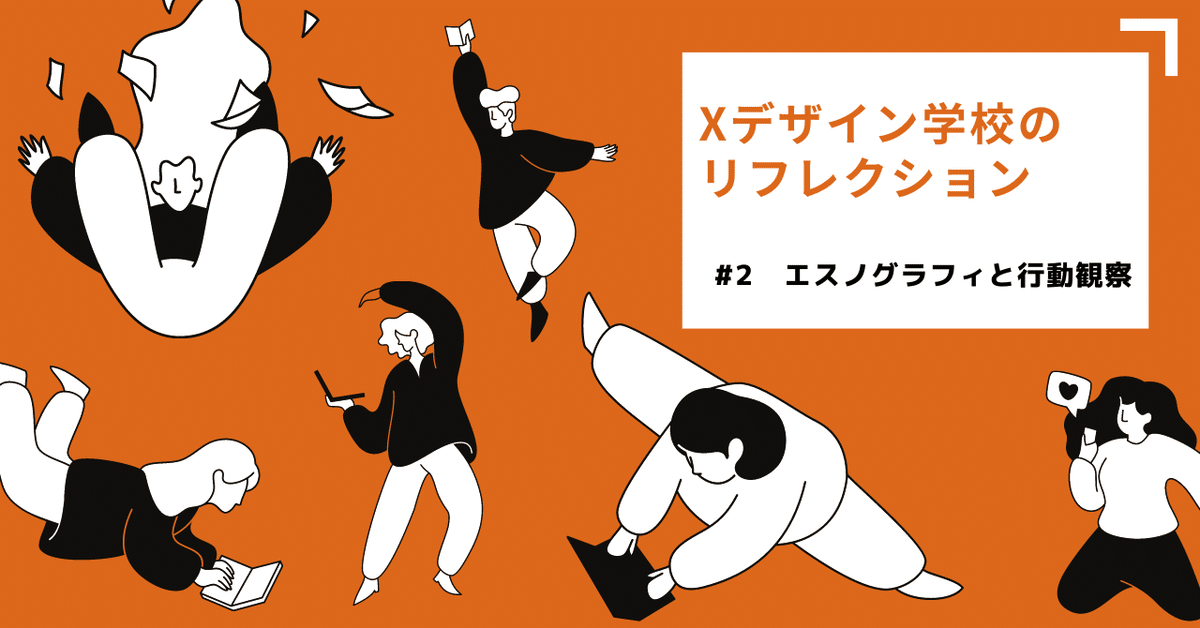
Xデザイン学校のリフレクションNo,2
はじめに
先月の授業からはや1か月
2023年6月10日の第2回では、エスノグラフィと行動観察の授業でした。
時間が経つと回顧型になり、最適化されてしまう!とのことでしたので早めに今回もリフレクションを残します。
リサーチとは調査ではなく、研究である
「UXリサーチャー」はここ近年、よく聞く職種ですし、私の会社にも専門のカンパニーがあるので、調査に長けている人材だと思っていましたが、研究することが重要であるとのことでした。
先日の授業でもありましたが、省察をして概念化することで価値があるということです。
例で挙げてくださったのが、IK○Aのエスノグラフィの話を他社にお話しをした時のことでした。調査結果を受けて、「個人が団欒する時代はもう過ぎた」という感想だけにとどまらず、「では自社ではその状況に対してどのように生かすのか」を考え、「では大型テレビの流行は過ぎたので個人が家のどこでもテレビを楽しめるような小型TVを開発しよう」みたいな発想ができないとダメだよね、ということです。
おっしゃる通りで、以前新規サービス開発の際に、調査結果(その時はインタビューでした)を受けて現状のサービスでは需要も限られ、収支が回らなさそう・・で私の思考は止まってしまったのですが、チームに情報を持ち帰り、検討したところビジネスモデルの再考でビジネスの広がりが生まれ収支も見当がつきそうであるという道筋が見えました。
ここまでの考察を持って帰ってこそリサーチャーとしての仕事になるので、調査手法の習得に目がいきますが分析を行なって概念化する思考訓練こそが重要だと感じました。
定性調査と定量調査
定性調査と定量調査は、数えられるものとそうでないもので対局にあるものだと思っていたのですが、世の中は定性が大半であり、定性の中に数で測れる定量があるとお伺いして驚きでした。
特に定性調査の中でも、一次情報を取得することができる質的調査を行うことが重要であるとのことでした。一次情報ではない二次情報では最適化され、情報の正確性が削がれる可能性があるため、新しいビジネスモデルを開発する際には、エスノグラフィは必須になるとのことです。
実際に必要性は理解できたのですが、前職でいた時にもエスノグラフィや行動観察の重要性を理解いただいたり、時間を避けることがPJとして難しかったのでどうしたものか・・・と思っていたら、有名な企業にお勤めの方でもPJ内で行うことは難しく、先生からも実際は普段の日常生活で行うしかないとお話があったので、「やはりそうですよね」と思いました。と、同時に日頃から行うためには外に出るときにスマホばかり見てないで人々の行動観察をするようにしようと思いました。
ビジネスモデルキャンパス
ビジネスモデルキャンパス、前職のPJで使ってました・・もうすでに古いフレームワークということでまた衝撃でした。
時代と共にフレームワークは変化していくので、まさに学び続けるということをしないとお仕事できなくなっちゃうなと痛感しました。
ビジネスモデルキャンパスは二次元的なものなのでプラットフォームビジネスを表現できないとのことでした、食べチョクをもとにビジネスモデルキャンパスに書き起こせないのか今度実践したみようと思います。
ワークショップ
プラットフォームビジネスを見つけて、PDUピラミッドとフレームワークに併せて記述するというものでした。
自分がプラットフォームだと挙げたサービスとして、メルカリを上げたのですがプラットフォームの理解が合っていてホッとしました。
短い時間でしたが、みんなでさまざまなビジネスについて共有するのはとても楽しかったです。ビックデータ・個票データ・欲しいデータを洗い出すのが私たちのチームでは苦戦しました。
私は前職で「ピクト図解」を用いて、サービスのお金の流れや仕組みを見える化して整理していたので今回発表した「食べチョク」でも自分で見える化して整理をしてみたいと思いました。
一方で、発表時に浅野先生から良いことも悪いことも発表できるようにすることとアドバイスをいただき、今後の授業だけではなく実務の際にも気をつけようと思いました。多様な視点で考えることで、物事の理解が進むとともに相手への説得力も増すのだと思います。
また、フードテックを捉えるときに農家の背景や歴史を知らなかったので正しく全容の把握ができていませんでした。さまざまな分野の教養としての知識を学び続けなくてはいけないと思いました。
働く時のマインド
最後にですが、今回のXデザイン学校で学んでいるサービスデザインなどを、会社で周りに理解されないことを悲観したり上司に訴えるのではなく、今のうちに静かに爪を研いで時折アピールしつつ、時を待つというお話があってとても勉強になりました。笑
爪を研ぎ続けられる環境を作っていきたいので、次年度以降の課題にしたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
