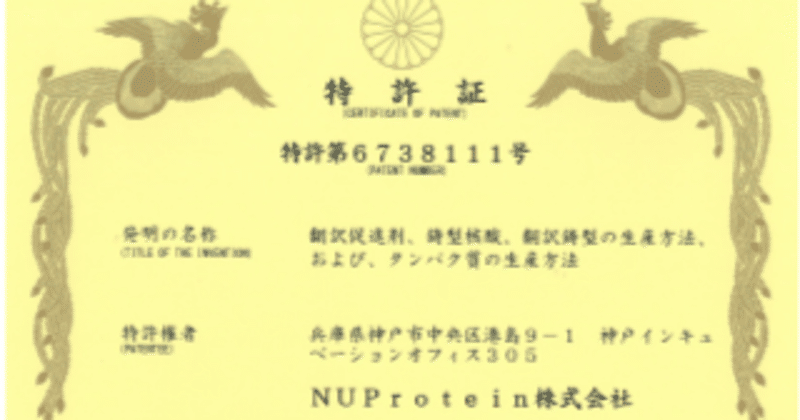
[NUProtein 南 #003] 特許 -1-
松下電器では技術本部・PC開発部に配属されました。技術本部だったからかどうか不明ですが、研修の一つとして、非常に詳細な発明・特許明細書作成に関する研修がありました。今では弁理士の先生に明細書を書いて貰っていますが、昔は基本自身で明細書を起案し詳細は弁理士さんに修正頂いておりました。
対外的な仕事が多くなると、知財の処分(ライセンスプール、ライセンスイン・アウト)に関わることがより多くなりました。また、特に米国でCVCを行っていた経験から、ベンチャー企業が特許出願中なので内容は開示できない、と主張する場合でも、VC側が第3者の知財コンサルを雇って、出願内容を評価させ、その結果だけをVCが知ることで、コンタミを回避しつつ、回避が難しい良い特許か、成立も見込めないようなダメ出願なのか等を評価していました。
そんな経験を持つため、特許について非常に強いこだわりがあります。そこで、経営学修士の研究は、”大学発ベンチャーの資金調達ならびに特許によるIPOへの影響に関する実証分析" を行いました。
具体的には、当時ジャパンベンチャーリサーチ社で得られた481社のベンチャー企業を母集団として、調達資金、時期およびPantent Integration社による各社の特許スコアを統計的に処理し、イグジットとどのような相関があるかを調べました。
イグジットを目的変数、説明変数として、調達額、出願数、共願数、特許の引用数、Patent Integration社特有のPI値(テキストマイニング技術を用いて、請求範囲が広い・メンテナンスされている・異議申立て等の他社アクションがある、等で高得点)等を用いて分析しました。
先に述べた母集団中のバイオテクノロジー企業であって、2002年以後に設立されたバイオ企業に関して言えば、88%の確率でイグジットするかどうかを判別できるとする結果が下記のように得られました。
(観測値として125社の11社がイグジットしたデータを分析した結果です。)

当社特許のPI値がでるまでもう少し時間が必要ですが、なぜ特許を重視しているかがご理解頂ければと思います。
また、2016年のNUProtein社起業前の論文で未発表ですが、古く発表機会もなくなっていますので、ご参考まで本稿に貼り付けておきます。
(追記:論文では、バイオベンチャーは資金入手できれば特許ポートフォリオが拡大できイグジットに至る確率が非常に高まる、と読めるかもしれませんが、相関と因果は別で、そのような仮説を立てた場合に他の対立仮説よりも有意に論じることができるかを示しています。また、因果関係は判断できずとも目的変数の予測は可能です)
今回も駄文をお読み頂きありがとうございました。
なお、イークラウドさんで株式投資型クラウドファンディングを2023年1月7日から開始です。是非ご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
