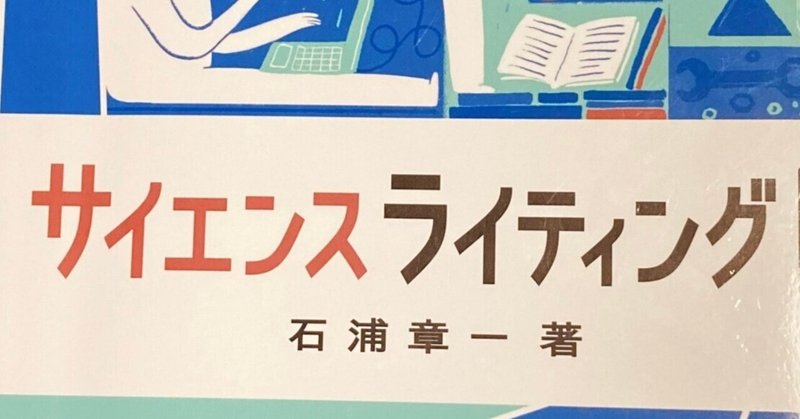
石浦章一著 サイエンスライティング超入門(東京化学同人)
まぐねたさんから書籍をいただいたので感想を書いていく。
いち薬剤師なので、院卒の理系大学院生とは感想が異なるかもしれない。
またまだ2週しかしていないので、内容を適切に受け取っているとは限らないことを前提にしてほしい。


文章術といっても、この本で述べられているものは通常の文才とは異なる。科学的知識や研究結果などを他者へ伝える目的だからだ。そこには正確性を保ちつつわかりやすさと面白さが求められる。
「ただ正確な知識をグダグダ述べるのはダメですよ.わかりやすくしかも魅力的に伝えないといけないんです.」
この著者の考えは一貫している。本文に口語調の言葉がでてきたり、時事ネタを取り入れたり。ただノウハウを紹介する教科書的な記述ではなく、例示が身近で、問いかけなど臨場感のある読んでいて楽しい一冊である。
目次
1 サイエンスライティングで身につくこと
2 誰を対象に何を書くか
3 文章の構造と型
4 各項目の書き方のコツ
5 マップを使って内容を練る
6 タイトルのつけ方
7 文章の要約
8 データの信頼性を読み取る
9 スライドのつくり方(初級編)
10 スライドのつくり方(上級編)
11 話し方は大切
以下、各項目での感想を箇条書きとする。
1 サイエンスライティングで身につくこと
ただ正確な知識をグダグダ述べるのはダメですよ。わかりやすくしかも魅力的に伝えないといけないんです。(p1)
サイエンスライティングに肝心なことは文字だけで理解してもらう必要があることと、読み手の力に左右されるので誤解のないように書かないといけない,(p2)
ただし、[1・5基本事項]はコラム的な内容。
2 誰を対象に何を書くか
2~7章までの作りとして、例文を読み、演習しながら理解できる。この構成がわかりやすく、オススメしたい点である。
対象年齢によって言いたいことをかき分けるのが大切とあるが、そのかき分け方(どういった内容にするか)は書かれていない。
一方、かき分けるときに、専門用語や文の長さを調節するなどは具体的に書かれいてよい。
コラムの主語と述語不一致は、とてもよく見る内容。かなり面白い。これをコラムにしておくのはもったいない。
3 文章の構造と型
「知らせたいことは、この研究が何に役立つか、という点です。「理解が深まる」だけでは、何のことかわかりませんね。」(p22)というのは身に染みる。
私自身、興味のある分野であれば、理解が深まることそれ自体が面白く、応用の先を提示しなくても十分だ。という甘えがあった。
題材が面白い……の「面白さ」に触れてない。このテーマならこうすれば面白いという個別のことは書かれているが、一般にこういう内容がウケるなどはない。
もちろん言われなくてもなんとなくわかる「面白さ」なのだが、自分とは違う畑のテーマを紹介する際、何をもとに選ぶのが妥当かがわからなくなる(これは自分の問題なのかも? リサーチ不足?)
→本書で「面白さ」に触れているであろう部分をピックアップした(後述)。
4 各項目の書き方のコツ
各項目=リード文、本文(科学的な文章)、結論。文章を読みながら解いていく、実践的な内容。
科学的な文章で、正しさを伝えるための技術が書かれている。
耳が痛いのは、専門用語を使って、その内容の説明を省いてしまっていることが不適切と書かれている。これは推敲の段階で使えるマインドだ。
「これくらいなら(高校で習ったし)わかるよね」「あらためて説明するのめんどくさいし、文字数増えてしまうし」と思って専門用語を使ってしまう。反省。
最後の「ちょっと難問」の回答。それが「面白さ」の例になっている。
5 マップを使って内容を練る
大学生に書いてもらったマップ3例が挙げられているが、それに対するコメントが意外と少ない。
(c)の矢印がよいというコメントはあったが(a)や(b)とはあまり比較していない。
私個人的に「PowerPointや付箋で考えをまとめる」というのをよくやっていた。小さな枠の中で考えをまとめて、後で順番を入れ替えられるから。思考の整理になる。これもマップと似たようなものなのだろう。
6 タイトルのつけ方
[6・4キャッチ―なタイトルの付け方]がよい。例示し、いくつか候補を挙げて後に取捨選択する。この思考を追体験するのが勉強になる。
タイトルの付け方、公式とともに上手な例示をしている。
7 文章の要約
要約トーナメント。
要約トレーニングに海外の童話は不適なのでは? 内容がブレてしまっているので(本書でも指摘されているが)。
結論の「よく知っていると思っている話でも、実は頭の中には違うストーリーが入っている」というのは、内容のブレ(出版の過程で)のものなのか否か、はたまた子供のころの記憶なのであやふやなのか、現在のスキルとは関係ないのではないか とも思う。
ただトレーニングとして童話などみなが知っているもので行うのは、見せ合うことができよい。
8 データの信頼性を読み取る
基本的な信頼性の話だった。
図や実験の内容から確からしさや妥当性を判断する内容ではない→かと思ったらコラムがそうだった。
本文よりコラムのほうが好き。
9 スライドのつくり方(初級編)
基本的なスライド作成の話、詳細は他書に譲ってもよいかも。
私個人としてはじーにょさんのPowerPointr Re-Masterが同人ではあるが内容が素晴らしくバイブルとしている。http://wimdac.com/c96/
10 スライドのつくり方(上級編)
学会発表や授業を考えると、こういった内容はありがたい。
一般のスライド作成の書籍にはない例が挙げられている。
11 話し方は大切
むしろ一番大切なのではないか? と個人的に思うテーマ。
コミュ障理系にはこういった内容とてもありがたい。
この本では面白さについてたびたび述べられてはいるが、それをまとめている記述はない。
というか言語化するのが当たり前だったり、それか別のスキルだったりするのだろうか。
とりあえずピックアップしただけだが、なにか包括できるものが見えればいいが……。
(p24)3・2文章の中身 無臭の匂いが判断を支配する
題材が面白い。本能を科学的に説明できるのではないか、と期待できる。
(p30)3・2文章の中身 表3・2 ある研究者が発表した論文題名
論文の内容が面白い。が、タイトルの付け方にコメントしている。
(p40)4・5ちょっと難問
論文の内容が面白い。知らない分野で、何をもって判定しているのか、どこまで調査しているのかといった内容に意外性がある。
(p58)6・1タイトルのインパクト性 店頭に並ばなかった和歌山みかん
タイトルが面白い。書かれている対象はわかるが、結果が想像できない、もしくは想像と異なるのではないかという予感。
(p59)6・1タイトルのインパクト性 スプレーひと吹きでがん細胞が見える!?
タイトルが面白い。対象や結果はタイトルに書かれているが、その過程を知りたい。
(p62~66)6・4キャッチなタイトルの付け方 図6・2キャッチ―なタイトル一般公式
しかし、p66で挙げている「黄金比とアイドル」は中身がわからないが見てみたくなる面白さがある。
一見無関係なものに関係性があった、と予測できさらに内容を知りたくなる。
例文や例題を用いて演習しながらの理解ができる。他人の文章でないとダメなところがわからなかったりするし、自分で書いているときは「こんなに悩んで出した文章」という我が子可愛さがあってつい甘えた校閲になる。
スライド以降のページはカラー折なのか、きれいな図が多い。読むのが疲れてくる後半でも続けて読めて楽しい。
論文・レポート以外で科学的な内容を伝える、といった状況はかなり多くなっている。見てもらうための、読んでいてわかりやすい、あくまで正しい情報を伝えるといった工夫が身に付けられる。
全体としてこのような感想だ。とてもよい書籍だった。
書籍は何冊何でもいい。様々な本を横断して知識を蓄えていってほしい。
自分が文章を書くうえで参考にしている書籍
野矢 茂樹 論理トレーニング101題
接続詞の使い方を中心に実践形式でトレーニングを行える
一般社団法人共同通信社 記者ハンドブック 第14版: 新聞用字用語集
文字のユレの基準として
高橋 佑磨 ほか 伝わるデザインの基本
スライドデザインとして
北原 保雄 問題な日本語―どこがおかしい?何がおかしい?
慣用句の誤りを未然に防ぐために
