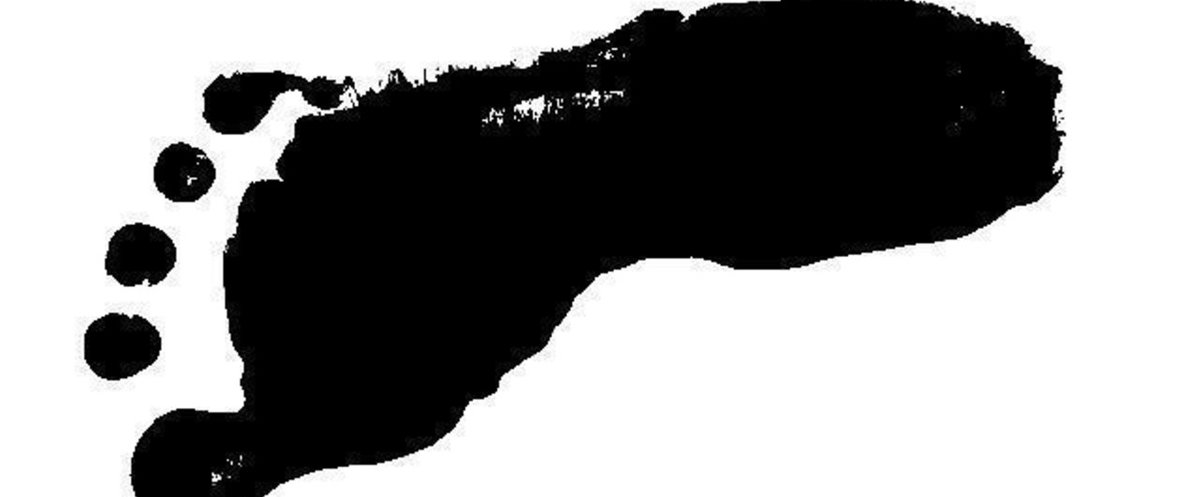
【戊己の怪】足跡を辿る
昨晩から降ったりやんだりの雨。
どうにも天気がつかみにくいので、自転車を諦め、徒歩で買い物に行くことに決めた。
スマホに入れたお気に入りの音楽を聴きながら、テクテクと目的地を目指す。
天気が不安定なせいか、道行く人は少ない。
せっかく持ってきたのに出番のない傘をブラブラさせつつ、のんびりと歩行者用のグリーンレーンを歩いて行く。
ふと視線を落とせば、白線の上に泥だらけの足跡が残っていた。
(きれいに靴跡が残るもんだな。普段はアスファルトだから目立たないだけか。『ゲソ痕発見!』なんちゃって)
下らない事を脳内で呟きながら、白線に残った靴跡を辿って歩く。
はっきりとした靴底の跡に混じって、形の違う足跡を見つけた。
土踏まずの部分がない、指の形までしっかりと分かる、裸足の足跡。
どうみても大人のモノだ。
(なんでこんな所を裸足で?)
スニーカーの特徴的な靴跡の隙間に残る、裸足の足跡。
しかも進むにつれて乾いた泥から、徐々に濡れた泥へと変化していく。
周りの足跡は乾いているのに。
(どこまで続いていくんだろう?)
私はその奇妙な足跡から視線を外せなくなっていった。
最初に裸足の足跡を見つけてから200メートルほど。
十字路になっている横断歩道の手前で、足跡は途切れていた。
ぬかるみから抜け出てきたばかりだと言わんばかりに湿っている。
戻っていく足跡はひとつもない。
そこで足跡はふっつりと途切れていた。
この足跡の主は一体どこへ行ったのだろう?
私の耳に音楽を流し込んでいたヘッドフォンの奥で、小さな「ガリガリ」というノイズが走った気がした。
横断歩道を渡り、先を進む。
聴こえてくる音楽に「ふっ、ふっ」と息遣いのような音が混じる。
目の奥からじんわりと痛みが湧き、首の付根から肩にかけてズンと重くなった。
肩コリからくる酷い頭痛の前触れだ。
「ヤバイな、痛み止め持ってきてないや」
早く買い物を済ませて帰ろう。
そう思って足を早めた時、前方にある小さな畑から、じっと私の方を見つめている老人がいる事に気がついた。
中腰になり、畑作業で使っていたのだろう鎌を桶に溜めた雨水で洗っている。
何か物言いたげな表情で私を見ているが、知っている人物ではない。
刃物を持ってこちらの様子を伺っているなど、気持ちのいいものではない。
私は目を合わさないようにしながら、老人のいる畑の前を横切ろうとした。
そんな事はあり得ないと分かっていても、背後から鎌で斬りつけられるイメージが頭から離れない。
頭痛がどんどん酷くなる。
たまらず、ヘッドフォンをむしり取った。
怖い、怖い、怖い。
痛い、痛い、痛い。
気持ちが悪い、気分が悪い、気味が悪い。
重くなる足を引きずるように、私は歩を進める。
痛みで目がチカチカする。
「おい……おい!」
ハッハッと短い呼吸をしながら、私は声の方へようやくの事で視線を動かす。
ただそれだけなのに、痛みが増す。
私に声をかけたのは、先程からこっちを見ていた老人だ。
右手に光る鎌を構え、柵を越えてこちらへやってくる。
なぜだか強烈な恐怖に襲われ、衝動的にもつれる足で1歩退る。
「ガシャン」と音がして、背中が道沿いのフェンスにぶつかる。
これ以上退がれない事を知って、私はパニックになった。
「く、来るな……」
震える手で傘を握り締め、身構えようとする。
そんな私を見て、老人は深くため息をついた。
「あんた、なんてモンを憑けてるんだ」
(は? 何を言ってるんだ?)
ダメだ、頭が痛い。
思考が痛みで塗りつぶされていく。
「動くなよ、じっとしているんだ」
何をする、と言いかけて私は動きを止めた。
老人が私に向かって鎌を大きく振りかぶっていたからだ。
まさか、こんな往来で!?
ギュッと目を閉じ、首をすくめた私の頭上で、ヒュンと刃が空を切る音が響いた。
同時にベチャッ、ともグチャッともつかない、気持ちの悪い湿った音が耳に届く。
それ以上何も起こらず、恐る恐る目を開けると、鎌を振るった老人が難しい顔をして私を見ていた。
「あ、あの……?」
「あんたな、余計な事ばっかり考えていると、妙な連中に付け込まれるぞ。見えもしねぇ奴の事なんざ、無視だ、無視」
そう言うと、老人は「せっかく綺麗に洗ったって言うのによ」とブツブツ呟きながら畑へ戻っていった。
反射的に老人の手にしている鎌に目をやると、先程までは確かに鉄色に光っていた刃は泥に突き刺したかのように汚れていた。
何か言わなくてはと思ったが、すでに私に対する興味など失ったようで、老人は水桶に鎌を浸して洗い始めた。
どうにも言葉が出なく、私は老人に深く頭を下げると、急ぎ足でその場を後にした。
気がつけば、目を開けているのさえ辛かった頭痛が、嘘のように治まっている。
まったくもって事態が飲み込めないまま、とりあえず急いで用事を済ませ、再びその場所を通る頃には既に畑に老人の姿はなかった。
だが私が立っていたと思しきフェンスのそばには、まるで大きな泥団子をぶちまけたように、一面に湿った泥がへばりついていた。
改めて背筋が寒くなり、ほとんどかけ足のような歩調で家路を急ぐ。
「ただいま!」
息を切らしながら玄関に飛び込んだ私の様子に、留守番をしていた息子が目を見開いた。
「あ、お、おかえり」
ドアに鍵をかけ、ようやく人心地がついたのか、私は大きく深呼吸した。
その背中に息子が声をかける。
「何、それ? どうしたの?」
気味悪そうに私の背中を指差す息子。
慌てて着ていたコートを脱ぐと、黒い生地の肩と背中の部分にはベッタリと泥だらけの手形と足形がついていた。
まるで……誰かが私の背中にしがみついていたかのように。
了
