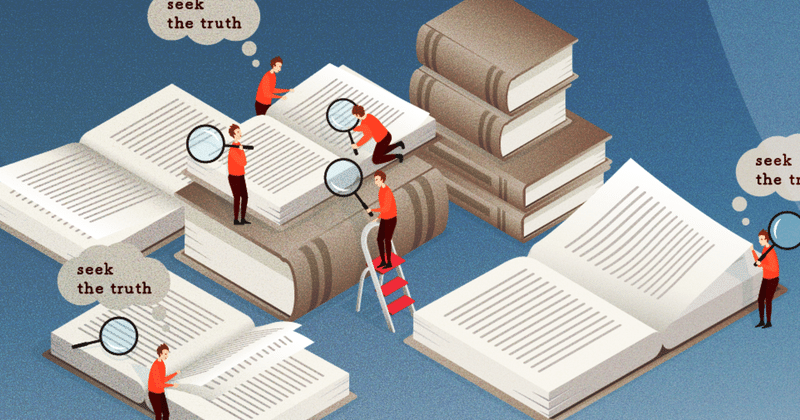
story seeker(っていうとかっこいい)
いちはらさん
「ググれ」という表現,確かに最近はあまり見かけなくなった気がします。でも,自分の端末で好きな時に調べものができるって,改めて考えてみるとすごいことですね。
そして
gugure
とローマ字入力をして変換すれば
ググれ
と一発変換されるわたしのATOKに,少しの申し訳なさを覚えます。
***
「わからないことを調べずに人にたずねること」よりも、「本当はわからないことをわかった気になって、あるいはわからないままでもよしとして、ググらずに突き進んでしまうこと」のほうが問題になっているなあと思うことはあります。
いただいたお手紙の,ここを読んで思い出したのは,今の仕事に就いて1年ほど経った頃のこと。
当時,数人がかりで,ちょっと大きい翻訳書を作っていました。
(この文章,なんだか意味が取れない……1時間くらい調べてるけど,原文を読んでもよくわからない……あぁでも今日中にこの章を終えなければ……)
そんな状況に遭遇したヒヨッコのわたしは,どうしたものかと悩んだのち「理解できないのは自分が専門家じゃないからだ」「きっと読み手たちの世界では,こういう言い回しをする/用語を使うもんなんだ」と勝手に物語を作り上げ,この文章を許容・スルーして印刷所に入稿。
そうして出来上がった初校ゲラをチェックしていた上司に,案の定「ここ,文意とれないんだけど(君はどうなの)」と件の文章を指摘されます。
「いやその,微妙にわかんないですけど。でも医師ならわかるのかな,と思って……」
そうモゴモゴと言い訳をしましたら,それはもう,はちゃめちゃにひっぱたかれ(比喩)ました。随分前のことですが,傷跡は今もときおり痛みます。
そんな経験の甲斐もあり,昨今ではそれはもうググりまくっておりますが,検索結果がチラホラと”既読”の紫色になっている
(イメージ図)
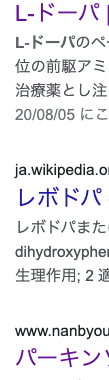
のを見るにつけ,「検索は 甘え」という気持ちが芽生えなくもありません。
***
人間の大脳が獲得した最も偉大な能力はストーリーテリング能力だ。
目の前で起こっていることのどれとどれが有機的につながっていくかを、「あたかもそうであるかのように」結びつけていく能力がキワだって高い。
ずいぶん前に拝聴した『いんよう!』で,たしか循環器系の「定説」とされていた事象が「新発見でひっくり返った」という話を,せんぱいが紹介されたときのことを,ふと思い出しました。
おふたりとも,その新発見そのものに驚いておられましたが,と同時に
「いっけん,ぜんぜん効率的じゃないように思える,意味わかんない」
「でも,きっと何か,そうじゃなきゃいけない理由があるんだろうな‥‥」
そうおっしゃって,背後にある「ストーリー」に思いを馳せておられましたね。
そのまま番組を拝聴しつつ,
「科学」とは事象を解き明かすことではあるけれど,「ひとつの物語を探求する営み」とも言えるのかもしれないなあ。
そんなふうに思ったら,なんだか美しいものをみたあとのような,とても豊かな気持ちになったのでした。
いつも素敵な番組をありがとうございます。
***
そういえば,「いま経験している物事を,評価せず,ただじぃっと見つめる」,いわば「物語化をしない」という過程は「マインドフルネス」と呼ばれるものだったでしょうか。
ストーリーから外れて,あるいはストーリー性をもたずに,眼前の出来事を捉える。
……んん?
AIはそもそも、「どうしてその結論に到ったのか」に興味がないと思う。
AI内部で行われている複雑な計算にはストーリー性がない。
うーん,どことなく”AI的思考” に通じる部分があるような…… ”AI” って言葉,だいぶマインドレスっぽいですけども……
……などと妄想にまかせて物語っていると専門家にひっぱたかれそう(比喩)なので,つづきはもう少し調べてからにします。
追伸:遅くなりましたが「脳旅」の再開,まことにおめでとうございます。
(2020.8.7 西野→市原)
