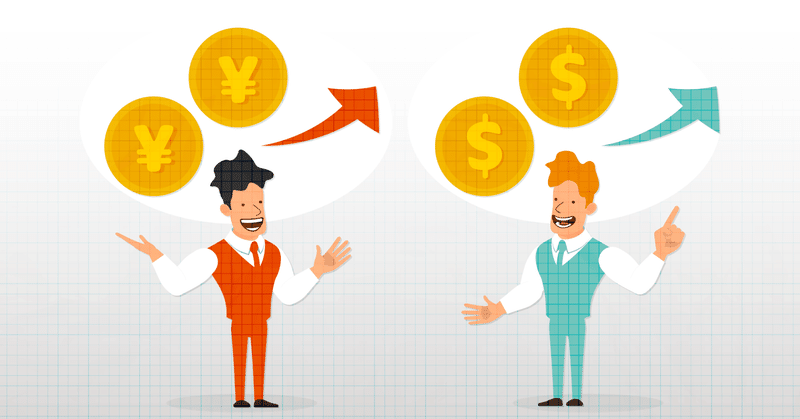
円安雑感~「悪い円安」などあるのか?~
この1か月で円安ドル高が10円程度進行した。この数年長らく続いたベタ凪の状態に慣れてしまっていたせいか、加速度としては比較的大きく感じる。そのためか、世間は大騒ぎである。「悪い円安」「国力が落ちた」など、情緒的な表現が乱舞している。
しかし、そもそも為替は相場物であり、変動相場制という荒波に飛び込んだ時点からこのような不安定性に心中することは織り込み済みではなかったのだろうか。
為替の方向がいずれに触れるにしても、それぞれメリット・デメリットがあるはずである。ほんの10年前は1ドル80円を割り込む騒ぎになったときは、「六重苦」だとか言って騒いでいた。あれはいったい何だったのだろうか。そもそもその円高への反省として、いわゆるアベノミクス、つまり円安誘導を行ったはずなのだ。あまりにも一貫性がなく物忘れが激しすぎるのではないだろうか。副作用というあいまいな言葉でごまかさないでほしい。
極めて単純に腑分けすると、円高は輸入に有利で消費者にメリットがあり、円安は輸出に有利で労働者にメリットがある。その単純な事実を忘れて熱に浮かされすぎである。この円安を前にして、雇用環境が大企業に限定されているとはいえ、遅まきながら改善しているのも事実である。
この記事にもあるように、この直前まで日本国内の給与水準は下落していた。それはプラザ合意以来の円高の影響で、いわゆる30年デフレが進行していたからである。つまり、消費者が長きにわたって労働者を搾取していたわけだ。
ツッコミどころは満載だが、単純に整理すると円高は消費者にやさしく、労働者には過酷である。円安は労働者にやさしく、消費者には過酷である。
ここまで単純に書くと違和感を持つ方も多いだろうが、町の家具屋をなぎ倒してきた円高の成功者であるニトリの華々しい成長神話が終わろうとしていることなど踏まえれば、ピンと来ないだろうか。
私たちは今、パンデミックや戦争を契機として、世界は大きな転換点にある。数十年単位の巨視的な視点が必要である。為替はその一つの表れにすぎない。
円高を駆使して世界中から安いものを仕入れて転売するという、ビジネスモデルが終わろうとしているのだ。その背景にあるものは何だろうか。その点を何回かに分けて連載して書いていきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
