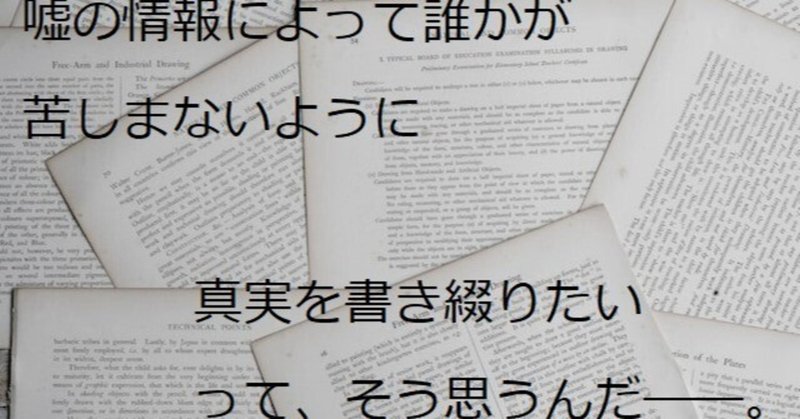
[短編小説]Leave the Truth
A案
――虎の子も、また虎だ。
彼以上にこの言葉が相応しい人を、知らない。
誰もが知るような有名企業を最前線で率いていた社長が、ある日辞任した。その後を引き継いだのは、彼の息子だった。
初めての経験というものは、誰だって四苦八苦するものだ。特に大企業の社長という立場になって、多くの従業員の人生を背負うことを考えれば、常人であれば気が触れてもおかしくはない。しかし、彼はまるで日常の延長線かの如く、難なく社長業をこなした。しかも、特筆すべきは、就任一年目から業績を上げたことだ。
元々備わっている才気が開花したのか、もしくは順応するスピードが桁外れなのか。彼の場合、両方だった。
業績を上げたことで、彼は更に自信を持ったのか、今まで手を出さなかった未知の領域に臆することなく挑戦するようになった。現状に甘んじようとする社員の反対の声も上がったが、彼は勇猛果敢に周囲の声を振り払った。
その挑戦が功を奏し、多岐にわたって会社の名前が知れ渡るようになった。
まさしく前社長が取った選択が、正しかったことが証明された。
どんな人生を歩めば、彼のようにプレッシャーに負けず、人を導けるようになるのだろうか。
その答えは、この一冊の本を読み終えた後に自ずと分かるようになっているはずだ。
B案
――人の顔は、表と裏で異なっている。
父親でもある前社長からその役職を引き継いだ彼は、今や知らない人はいないほどに敏腕社長として有名になった。メディアへの露出も高い彼は、多くの人に知られている。
普通の人生を送っていては浮かばないような経営戦略を惜しみなく展開することで、彼が社長を担う前よりも業績はうなぎ上りとなった。
しかし、上に立てば立つほど、苦労や心労は増えていく。人付き合いというものも、難しくなって来るというものだ。
それは、彼も例外ではなかった。
事業が忙しくなればなるほど、彼の指示は曖昧なものになっていく。曖昧になっていくだけなら未だしも、荒々しい横柄とした言動でもって、社員と接することもあった。
それでも、部下は彼の指示を聞き入れ、百パーセントの力で応えた。
周りに支えてくれる人がいるというのは、かけがえのないことだ。彼には類稀な経営の能力だけではなく、周りに好かれる能力も備わっていた。
一見すると誰もが近寄りがたい敏腕社長というイメージを持たれそうだが、彼にも人間らしい一面があった。その人間らしい姿を持ちながらも、すでに一流企業だった会社を、どのようにして更なる飛躍をさせたのか。
そこには彼だからこそ成せる技巧が隠されていた。
***
徳井正彰は嘘が吐けない人間だった。
彼は駆け出しのライターであり、出来るだけ事実に基づいた内容を書こうと常に心がけている。もちろん、文章を盛り上げるために脚色を加えることは時折あるが、嘘を交えたことは一度もなかった。
真実であってこそ記録として残す価値があり、虚偽は時間と共に記憶から薄れていくもの。だから、真実な文章を書き記したい――。
大学を卒業してから年月はそんなに経過はしていないが、正彰の胸中にはずっと理念があった。
しかし、現実はと言えば。
「いやぁ、鎚里さんの文章は素晴らしい!」
正彰の倍近くの年を重ねている鎚里晧也を、重厚そうな声を上げて褒め称えるのは、今回の依頼主である金盛社長だった。
金盛は前社長でもある父親からそのまま地位を引き継いだ、いわゆる二代目社長だ。金盛が社長を任されるようになってから、様々に紆余曲折があったのだが、その武勇伝を本にしたいという募集があり、正彰は早速応募した。金盛の部下による厳選な抽選により、正彰と鎚里が最終候補に選ばれることになった。
どちらに執筆を任せるか判断するために、序章部分を正彰と鎚里に書かせて提出させた。しかも、金盛社長が出した条件は、金盛の名前を出さずにどれだけ人となりを表現できるのか、というものだった。
事実に基づいた内容を書きたかった正彰は、迷惑だと分かりながらも金盛に頼み込んで、一週間ほど後ろについて仕事ぶりを観察した。金盛は「まるで有名人になった気分だよ」と豪快に笑って受け入れて、自分の武勇伝を惜しみなく伝えていた。
正彰は、金盛の言葉と金盛の行動を、忠実に自叙伝として書いたつもりだった。
その結果発表がまさに今なされているのだが、仕事を勝ち得たのは先ほどの金盛の言葉通り、正彰の競争相手であった鎚里だった。
「いやぁ。僕なりに金盛社長の素晴らしいところを、ふんだんに書かせてもらったのですが、お気に召したようで何よりです」
媚びへつらうように鎚里は言う。四十半ばだというのに、鎚里にとって自分のプライドを捨てるのは容易いことだ。鎚里の言葉に気を良くした金盛は、満足気にうんうんと頷いて、
「今回の執筆は、鎚里さんに任せるよ」
「ありがとうございます」
正彰をおいて、とんとん拍子に話が進んでいく。
「あの、おれ、……っと、僕は」
いたたまれなくなった正彰は、ついに自分からおずおずと問いかけた。すると、「ああ、徳井さんね」金盛はまるで今存在を認めたかのように、正彰に目を向けた。けれど、その瞳は、路傍に置かれている石を見るかのように熱が伴っていなかった。一週間ほど一緒に過ごしたはずなのに、と正彰は少しだけショックを受ける。
「君の文章は面白味がないんだよね。確かに事実を書いてほしいとは言ったけどさ、学生みたいに人の言葉を真に受けないで少しは忖度してほしかったわけ。大人になるためには必要な能力だよ?」
「は、はぁ」
「その点、鎚里さんは素晴らしい。やはり伊達に年齢を重ねているわけではない」
「へへ、もったいない言葉です」
鎚里と金盛のやり取りを、正彰はどこか冷静に眺めていた。
「では、今日すべき話は済んだので、二人にはお暇願いましょう。鎚里さん、後日また連絡いたします。徳井さん、また機会があればお会いしましょう」
「へい、失礼します」
「あ、ありがとうございました」
社会人らしい形式的な挨拶を受けると、正彰も鎚里も頭を下げて、金盛社長の部屋を後にした。
そして、そのまま自社ビルを出るとすぐに――、
「おたくさぁ、もうちょっと要領よく出来ないの?」
今まで媚びるような話し方をしていた鎚里が、まるで人が変わったかのように正彰に話しかけて来た。その豹変ぶりに、「え、え」と正彰は言葉を詰まらせる。正彰の反応に、更に鎚里は溜め息を吐いた。
「この世界に何を期待しているかは知らんけどさ。たとえ事実を書いたとしても、クライアントの意向を削ぐような文章書いたら受け入れて貰えないなんて、ガキでも分かるだろ。金盛社長の私生活なんて、とても文章として残せる代物じゃないし、どこに需要があるんだよ」
一週間金盛に付き添いをしていたが、鎚里の言う通りだった。経営は上手いのかもしれないが、人に対する敬意はなかった。部下に対しては荒い口調だったし、公共施設などを使う際のマナーも傲慢な態度で、付き添いをしながら恥ずかしい思いをすることが正彰には何度かあった。
金盛の私生活を書くべきかは正彰も確かに迷ったが、自叙伝として書き上げるためには隠すものではないと判断し、事実を書いたのだった。
何が楽しいのか、鎚里は卑屈な笑い声を漏らす。
「この世界で生き残るには、自分のプライドなんてゴミみたいなもんだぜ。事実を変えてでも人の興味を惹きつけなければならないし、特定の誰かを傷つけてでも不特定の誰かの気に入るように文章を書く必要だってあるし、なんなら自分の苗字とか名前を変えてでもしがみつかなければいけない時だってある。何のために書いてるんだっけ……、あぁ生活するために書いてるんだって思えるようになってこそ、プロのライターになるんだ」
鎚里の意見も一理あるものかもしれない。けれど、その結果が死んだような目をして媚びへつらうことになるのなら、正彰は願い下げだった。「はぁ、そうなんですか」、と受け流す。
しかし、正彰の言葉を肯定的に受け止めたのか、鎚里は親指と人差し指をくっつけて、口元に近付けると、
「どうだい、これから一杯やってくかい? 俺の処世術、安く売るぜ?」
「いえ、結構です」
二回しか顔を合わせていない人間――しかも、商売敵である人間と、一緒に食卓を囲むことは考えられなかった。即答した正彰に、鎚里は大袈裟に肩をすくめた。
「これだから、最近の若者はつまらねぇ。今回の報酬で、最初の一杯くらいなら奢ってやろうと思ったのに。あぁ、俺の特ダネを聞く機会を捨てるなんて、後悔しても知らねぇからな」
そう捨て台詞を残して、鎚里は去っていった。
「つまらねぇ大人なのは、どっちだよ」
去り行く鎚里の背中を見つめながら、正彰は誰にも聞こえないくらいの声量で呟いた。
そして、正彰は鎚里とは反対方向に向かって歩き出すと、いつもの習慣でカフェに入っていった。常日頃利用しているカウンター席に腰を掛けて、ホットコーヒーを頼む。コーヒーが出てくるまでの間、パソコンを立ち上げ、書類の束を並べた。書類の内容は、先ほどの金盛についてまとめたものだった。誤字脱字を見つけようとしたところで、
「いや、意味ないんだったわ……」
正彰は自分の行動の無意味さを悟って、机の横に置いた。今更確認したところで、これが仕事に繋がるわけでもない。
同時、店のマスターがコーヒーを机に置いたので、正彰は軽く会釈をしてコーヒーを口につける。ブラックコーヒー独特の苦味が、失望した正彰の心を更に刺々しくさせた。
「社長の私生活を、ちゃんと書いただけだったのにな」
もちろん好みなんて人それぞれだ。鎚里が書いた文章をちらりと見たけれど、金盛のことを敏腕社長かのように扱って綴られていた。確かに金盛にはそういう一面もあったが、いいところだけを切り取ってその人の本性を隠した文章を、果たして自叙伝として扱ってもよいのだろうか。
それとも、正彰の意見はただの理想論に値してしまうのか。
考えても仕方のないことに、正彰は思考を費やしていた。
「切り替えよう」
グイっとホットコーヒーを呷ると、正彰は次の仕事に向けてキーボードを叩き始めた。と言っても、内容はどこかのサイトで小さく取り扱われるウェブ記事だ。そのせいか、一向に考えがまとまらず、いつの間にキーボードを叩く指も止まってしまった。
ぼやける頭で考えていると、いつの間にかウトウトと睡魔が襲い掛かって来た。
誰かがカウンターの隣の席に座った気がしたが、正彰を目覚めさせるまでには至らない。
そのまま世界が闇に包まれて。正彰が微睡みから戻ったのは、
「これ、君が書いたのかい?」
とハッキリと正彰に対して声を掛けられた時だった。
***
真実な出来事であってこそ、後世に引き継がれ、人々の心を震わせることが出来る。
正彰は常日頃からそう思っていた。
地球上の歴史だって、真実だからこそ全人類の共通認識となっている。
だから、正彰でも真実な文章を書けば形として残せる、そう信じてやまなかった。
もちろん、そこまで影響を与えられるような文章を書けるだなんて正彰自身も思っていなかったが、理想は高ければ高いほどいい。
正彰は真実を文章に落とし込もうと、常日頃から意識していた。
しかし、真実というのは、誰かにとって都合の悪いものになる可能性もある。
今回、金盛の自叙伝を書いて欲しいという依頼があった時も、正彰は事実を書こうとした。敏腕な二代目社長として世間に知れ渡っている金盛だったが、それは表向きだけであって、裏では人に対する敬意はなかった。その真実を踏襲して自叙伝を書こうとした正彰だったが、イメージダウンを畏れた金盛は正彰から手を切った。自叙伝は、嘘で塗り固めた文章を綴る鎚里の手によって書かれることになった。
真実が持つ影響力を誰もが知っているからこそ、だった。真っ当に生きている人間であれば気にも留めないことでも、何か疚しいことを感じながら生きている人間にとって、真実とは不都合以外の何物でもないのだ。
それゆえ、正彰が仕事を逃したことは、金盛の件に限ったことではなかった。
実際のところ、金盛以外の相手からも、似たような旨を伝えられたことがある。だから、正彰は自分には文章の才能がないと感じ始めていた。もしくは、世間一般が求めているものと正彰が書きたいものには、絶対的な違いが生じていると認め始めていた。
正彰は細々としたウェブの記事でしか、仕事を達成したことがなかった。
文章が好きで自分も何か残したいという思いだけで始めたライターだったが、結果も満足に出せない今、畳み時ではないかと思い始めていた。
そんな最中――、
「よく金盛社長のことを書けているね。ここまで書けることは凄いことだ」
突如現れた初老の人物は、正彰のことを手放しに褒めてくれたこともあって、まさに神のように思えた。
しかし、ここは現実だ。普通のカフェにいる正彰の前に、いきなり神が現れるわけもなく。
「……なんで」
まとまらない頭で、必死に疑問を紡ぎ出す。
僅かな時間とはいえ仮眠していたのだから、まだハッキリと頭は働かなかった。正彰がぼんやりとしていることを察したのか、正彰の隣に座る初老の人物はマスターに対して指を一本立てた。すると、マスターはすぐにホットコーヒーを淹れて、正彰の前に置いた。
初老の意図を汲み取ることが出来なかった正彰は、
「これは……?」
「私の奢りだよ。もし良かったら飲んでくれ」
無理強いをしない奢り方だったから、名前も知らない初対面の初老の厚意に甘えることにした。「ありがとうございます」と、コーヒーをゆっくりと口に含んでいく。二杯目のホットコーヒーは、正彰の頭がフル回転するための手伝いをしてくれる。少しだけ頭も冴えて来た。
「えっと、どうして俺が書いた文章が金盛社長について書いているって分かったんですか? 名前は書いていなかったはずなのに」
正彰が一番聞きたいことだった。
「金盛くんが社長になる以前だが、かつて個人的に交友があってね。それでこの文章を読んだ時に、真っ先に彼の姿が思い浮かんだんだ。君の文章には、正確に人となりを記す力があるみたいだね。私と交友があった時と、全く変わっていないようだ」
初老の人物は、正彰をおいて一人で楽しそうに笑っている。
正彰の頭に疑問がグルグルと回っていく。金盛をまるで赤子のように懐古するこの人物は、一体何者なのだろう。
「あぁ、一人で盛り上がってしまったね。実は私はこういうものなんだ」
そう言うと、初老の男は丁寧な挙動で名刺を渡して来た。そこには「トゥルースランド株式会社 社長 真田倫幸」と書かれていた。
「え」
正彰は純粋に驚きを隠し切れず、素っ頓狂な声を上げた。隣にいる初老――真田の顔と名刺に書かれた情報を、何度も何度も見比べてしまった。
トゥルースランド株式会社と言えば、日本で有名な会社だ。誰もが一度は間接的にお世話になったことがあるほど影響力の強い会社の社長が、どうしてここに。一度は冴えたはずの正彰の頭だったが、あまりにも予期せぬ大きな出来事に、またしても頭を悩ませることになった。
真田は微笑を漏らすと、「君について教えて貰えると嬉しいのだけど」と遠慮気味に正彰に問いかけて来た。「は、はいっ」と、正彰は胸ポケットにしまっていた名刺入れから名刺を取り出した。
真田は興味深げに名刺を見ると、「徳井くん、ね」と正彰の苗字を口にしてから、名刺をしまった。
「徳井くんに執筆の仕事を正式に依頼したい」
「はい?」
突然の真田の発言に、正彰は疑問符を口から漏らす。
微睡みから醒めて真田と出会って以降、正彰の心はずっと動揺しっぱなしだった。
「私ももうそろそろ社長を引退しようとしていてね。その前に、自叙伝を残しておきたいと思っていたんだ。ここで出会えたのも何かの縁だということで、是非依頼したい」
「で、でも俺は、金盛社長からも仕事を断わられたような人間ですよ……。ガキみたいな文章しか書けないです」
思わず自己否定をするような言葉が出てしまった。しかし、それは事実だ。真実を取り入れたいと願う正彰の文章は、金盛だけでなく、会う人会う人から否定され続けた。信じ続けた理想と正彰を結んでいるのは、糸のようにか細いプライドだけだ。
仕事をやんわりと断わろうとした正彰に対して、全てを受け入れるかのような、柔らかい笑みを真田は浮かべた。
「確かに、徳井くんの文章は幼く拙いかもしれない。けれど、それをカバー出来るような魅力が、君の文章にある。私は君の人となりを正確に記す力に惚れ込んでしまったんだ。私が全ての責任を取るから、是非お願いしたい」
「そ、そうですか」
まさかそこまで褒められるとは思ってもいなかった正彰は、照れ臭さを感じてしまい、真田と顔を合わせることが出来なかった。
辞退の言葉を紡がなくなった正彰を肯定的に捉えたのか、「では、受け入れてくれるということでいいね」と真田は言った。真田みたいな大きな業界人に褒められて断わる人はいないだろう。無論、正彰も例外ではなく、「あ、はい」と首を縦に振った。
真田は重厚かつ柔らかい笑みを浮かべると、
「必要な情報は何かあるかい? 徳井くんが望むものなら、全て用意するが……」
顎に手を触れながら、正彰に訊ねた。正彰は瞬間考えたが、迷う必要がないことに気が付いた。真実を伝えたい、という想いは、相手が誰であろうと変わらない。
「あ、と。そしたら、真田社長について行ってもいいですか?」
「え?」
正彰の言葉は真田の想像していた言葉を超えていた。ここに来て、素の声が初めて真田の口から漏れた。
「俺、書くならその人のことを分かって、正確に書きたいんです。裏も表も、全部余すことなく、真実を伝えたい。そのために、真田社長について詳しく知りたいんです。だから、暫くの間でいいので、可能な限り俺を近くに置いてください」
正彰の言葉に、真田は言葉を返すことなく、真顔で見つめていた。その振る舞いに、正彰は出過ぎた真似をしてしまったことを悟った。当然だ。相手は、日本を支えるような会社の社長なのだ。ここで会って仕事を貰えたことさえも、信じられないほどの奇跡なくらいだ。
しかし今、考えなしに自分の主張を貫いたことで、その奇跡を自ら壊そうとしている。
「す、すみません。冗談なので気にしないでください」
正彰は今までにないくらい頭を深く下げた。
けれど、真田の返答は、正彰の想像を超えるものだった。
「謝る必要はないよ。むしろ、私も同じ気持ちだった」
「え?」
「私のことを正しく知ってくれる人に、正確な文章を書いてほしいと思っていたんだ」
これまで真実を残そうとしたら、否定されて来た。
当たり障りのない文章を、誰もが求めているのだと思っていた。
なのに、正彰と同じ想いを抱いている人がいるなんて。しかも、相手は高い地位を築き上げている、日本を誇る大企業の社長だ。
正彰の心を奮わせるには十分だった。
伸ばされた真田の手を、正彰は握る。真田の手は大きかった。
「では、早速だけど、これから約束があってね。一緒に着いて来てもらってもいいかな?」
「はい、もちろんです」
そして、真田は何も言わずに伝票を手にすると、正彰が自分で頼んだ最初のコーヒー含めて、すべての会計を払ってしまった。
真田の器も、また大きかった。
***
正彰が真田について書いた自叙伝が発売されるのは、奇しくも鎚里が記した金盛の自叙伝が発売された翌週だった。
金盛の自叙伝の売れ筋は好調で、週間ベストセラーにランクインするほどだった。
人の過去を面白く、また楽しく読ませられるのは、鎚里の手腕だろう。金盛の自叙伝を、多くの人が手に取って読むのも分かる。しかし、そこに金盛本人の姿はいなかった。金盛という同じ苗字をしたフィクションの中のヒーローが活躍しているだけ――、実際に読んだ正彰は、そんな感想を抱いた。
大手書店に、金盛の自叙伝の隣に真田の自叙伝が並べられていた。金盛の方は既に何冊何十冊も減っていて、パッと見ただけでは真田の自叙伝は売れ残っているように見える。一週間のタイムラグがあるのだから、ある意味当然の話ではある。
けれど、本棚の陰に身を潜めて、売れ行きを見守っていた正彰と真田の胸中は穏やかではなかった。特に、真田の自叙伝を執筆した正彰は、より一層焦っていた。
「もし売れなかったら俺の責任です」
真田の人生には、人を動かす力がある。ここ数か月の間、一番近くで真田と接した正彰だからこそ、胸を張ってそう言えた。
なのに、その真田の人生を記した自叙伝が売れ残りでもしたら、それは正彰に人を惹きつける文章力がなかったからに他ない。
そもそもの話、正彰が一冊の本を書き上げたのは、今回が初めてだ。何度も推敲したし、真田もその部下達も目を通して、「良い文章だね」と誰もが声を掛けてくれた。直接的に褒められた経験がなかった正彰は、その言葉を信じ、励みとした。しかし、実情はといえば、身内に褒められているだけであって、正彰の文章の拙さが露見されている可能性だってあるのだ。
一向に減らない積み上げられた本を見て、正彰はぎゅっと強く拳を握った。
「言っただろう? 全責任は私が取る、と。徳井くんは果たすべき責任を全部果たしたんだ。私も読んだが、君に任せて正解だった、と確信しているよ」
「……でも」
「正直どちらでもいいんだよ。売れたら確かに嬉しいが、一人でも多くの人に私のことを正確に知ってもらえることが何より喜ばしい」
トゥルースランド株式会社という大企業を背負う――それは一般人の想像を遥かに超えた重圧だ。
実際、あることないこと問わず多くの風評被害を受けたという話を、真田の口から聞いた。改善の余地のあるクレームなら大歓迎だと豪語していたが、ただ真田の地位を貶めようという敵意に満ちた悪評について触れる時は、真田の顔も流石に曇っていた。一度世に広まってしまえば、いくら風評被害とはいえ完全に解くことは難しく、誤解したまま真田を揶揄する者も未だ少なくないという。
真田みたいな苦労人かつ人格者が不当に攻撃されるという現実を、正彰は許せなかった。
だから、真実の言葉を詰め込んだ文章を世間へと投じたのだが、手に取られて届かなければ意味がない。
真田は気遣ってくれているが、正彰の胸中を満たすのは申し訳のなさだった。
「さて、私も次の仕事がある。名残惜しいが、そろそろ行くとしようか」
真田の背中を追うため、正彰は書店を後にする。少しだけ寂しそうに見えた真田の背中を見つめながら、正彰は爪が食い込むくらい両拳をギュッと握った。
正しく真実を伝えられて、読んだ人の心を掴むような影響力があれば、目の前にいる人物に悲しい想いをさせずに済んだのに。
そう自分の不甲斐なさに辟易するだけだった。
しかし、正彰の想いとは裏腹に事態が動いたのは、思ったよりも早いその日の夕方だった。
きっかけは、ネットの感想。
『真田社長の自叙伝、超感動した! 華々しいシーンだけじゃなくて、苦労話も失敗談もふんだんに書かれてたから、親近感湧いた!』
そう言った旨の書き込みが、ネットに多数広がった。冷静に考えれば、一般からの反応がその日の夕方になるのは当然だ。一冊の本を数時間足らずで読み上げて、感想を投稿する人物なんて早々いない。
多くの投稿に目を通しながら、正彰は胸を打たれていた。
もちろん本当に凄いのは、真田自身だ。真田から聞いた話に感銘を受けた正彰は、仕事云々はおいて真田の話をせがんだし、聞いた内容を誤解なく伝えられるように詳細に書き綴った。そのおかげで、真田のことを父親と思えるほど深く知ることが出来たし、親しくなることが出来た。
真田の自叙伝を読んだ人は、真田に対する認識を改めて、より一層尊敬出来るようになるだろう。やる気に満ち溢れている人は、第二の真田を目指そうと、今から努力するかもしれない。
それほど真田倫幸の生き様には、影響力がある。
真田自身も、「自分の生き方が、誰かの道しるべになるくらい影響を与えることが出来たら、心の底から誇らしいことだ」と明言していたことがある。
真田の想いの影の立役者になれたということが、正彰にとって、どれほど喜ばしく誇らしいことだろうか。
それから、ネットの一言を皮切りにして、閉店を待たずして各書店で売り切れが続出した。
一方、皮肉なものではあるが、金盛の自叙伝の売れ行きは急激に下がった。これまたネットの書き込みではあるが、
『真田社長の自叙伝読んだ後だから分かるけど、金盛社長のは話が嘘っぽい』
『ぶっちゃけ金盛の人柄が全く見えなくて違和感しかなかった』
『ただのフィクションとしての読み物としてだけなら満足かもだけど、ちょっとねー』
と手のひら返しのように、金盛の自叙伝に対する評価は下降する一方だった。
「――だから言っただろう。徳井くんには人を惹きつける力がある、と」
発売翌日の朝、社長室に呼ばれた正彰は、ご機嫌に笑顔を見せている真田と対面していた。この人を失望させたままにならないで良かった、と正彰は思った。
「徳井くんのおかげで、私の自叙伝を最高の本として完成させることが出来て、多くの人に読んでもらえた。私が思い描いていた以上の結果だよ」
「あ、いえ」
正彰にはもったいないくらいの真田による賛辞に、思わず謙遜してしまう。そんな正彰に対して、真田は口角をニヤリと上げると、
「そこで、だ。徳井くんは何が欲しいんだい?」
突然の提案に、「え?」と正彰はつい声を漏らした。
「君が欲しいものは、全て用意すると言っただろう?」
行きつけのカフェで真田から仕事の依頼を受けた時、確かにそう言われた。しかし、その時は、真田に対する参考資料という意味だったはずだ。
どうやら、完成後の報酬も含めて、ということだったらしい。
「幸い、私は社長という立場だ。大抵のことは、用意できるはずだが……あ、土地とかは勘弁しておくれよ」
こうして接するようになるまでは、硬派なイメージが強かった真田だったが、意外と冗談好きなところがあると分かった。馴れ馴れしくすることが失礼に値するのではないか、なんて正彰はもう思わない。
「えっと」
正彰は考える。欲しいものは何だろう――、そう自分に問いかけた時、正彰の中に明確な答えが見えた。
そして、それは――。
「真実を綴った文章を必ず残すんだって、今まで思ってました。けど、上手く行かなくて、挫折しかけてた時、真田社長に会ったんです」
浮かぶ答えが『言葉』に至るまで、丁寧に丁寧に、声を紡いでく。声にする度、正彰は今までの人生が無駄ではなかったと腑に落ちていく。
「俺が欲しいものは、もう十分すぎるほどに貰いました。あなたの自叙伝が語り継がれることは、俺の夢がずっと語り継がれることなんだから」
だから、もうこれ以上なんて要らない。
真実を伝えられること以上に欲しいものなんて、何もなかった。
<――終わり>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
